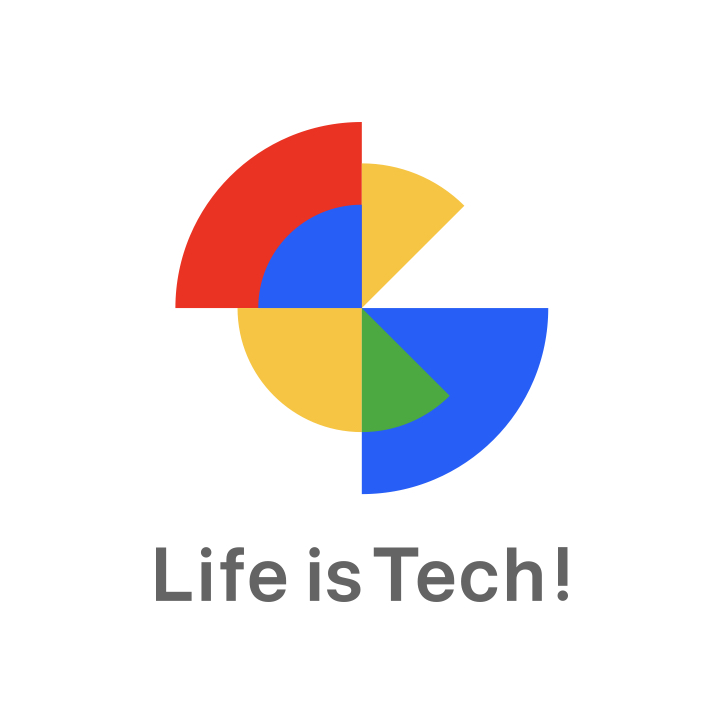「中高生ひとり一人の可能性を一人でも多く、最大限伸ばす」をミッションに掲げ、2010年の創業から次世代デジタル人材育成を手がけるEdTech企業、ライフイズテック。ひとり一人の「より豊かな今と未来をつくる力」を育み、その多様な力を地域や社会へと届けるためのさまざまなプロダクトやサービスを開発・提供しています。今回は自治体とタッグを組んで未来への架け橋をつくる事業に取り組む坪井祥太さんにお話を伺いました。
Profile
坪井祥太(Shota Tsuboi)事業開発事業部 公民事業共創グループ 部長
新卒で、三菱重工に入社。アジア各国に電力を届ける国家レベルでの発電プロジェクトに携わる。キャリアの後半ではJICAのプログラムでミャンマーへ長期派遣。IOTやAIの活用を通じて電力オペレーションの改革に取り組んだ。帰国後、外資系コンサルティングファームに転職。ユーザーを起点とした新規プロダクトやサービス開発を経験する。2024年9月、ライフイズテック株式会社に入社。公民共創による新規事業開発や、ソーシャルインパクトをもたらすデジタルイノベーター育成のエコシステム創り等を手掛けている。
![]()
新しいチャレンジの度に新しい学びを貪欲に
──これまでのキャリアについて教えていただけますか?
大学卒業後、新卒として入社したのは三菱重工です。タイやミャンマーなどアジアの新興国/途上国に電力を通わせる国家プロジェクトに関わりセールスや事業開発を担当していました。数百人単位で遂行するプロジェクトには、設計、開発、調達や建設といった様々なプロジェクトメンバーに加え商社や金融機関、現地パートナーといった、多くの社内外のステークホルダーと共に社会の根幹にあたる国のインフラを創る、とてもやりがいのある仕事でした。
もともと大学では経済学部で開発経済を専攻していました。また高校時代はサッカー、大学では体育会男子ラクロスというスポーツを通じてチームワークの素晴らしさにも魅了されていました。こうしたバックボーンもあり、同志と共に力をあわせて新興国や途上国の支援をする三菱重工の仕事はまさに望み通りの充実感を味わえるものでした。
ターニングポイントとなったのはJICAのプログラムでミャンマーに長期派遣された時のことです。当時のミャンマーの電化率は約30%でしたが、電気が通っていない環境でも子どもたちが一生懸命生きている姿を目の当たりにして、国のインフラをつくるという自分たちの仕事は果たしてその価値を生活する一人ひとりにまで行き渡らせることはできているのか?という思いに駆られたんですね。
一方、そんなミャンマーでも多くの人々がスマホを活用するなど、デジタルテクノロジーが一足飛びで導入されています。私自身のアサインメントもIOTやAIを活用した電力オペレーションやマネジメントの改善がJICAのテーマだったこともあり、テクノロジーを通じて途上国の生活者をダイレクトに変えてゆける、そのポテンシャルに強く惹かれるものがありました。
![]()
その後、ミャンマーのプロジェクトを終えたタイミングで、よりデジタルの力を用いて生活者にダイレクトに価値を届けられる環境に転身することにしました。
──それがコンサルティングファームへの転職だったわけですね?
はい、その後、外資系のコンサルティングファームにジョインし、ユーザーのインサイトや体験価値を起点に、デザイナーやエンジニアと一緒に新しいデジタルプロダクトやサービスデザインをする事業に取り組むようになります。それまではBtoBひと筋でしたが、初めてBtoCのビジネスに携わり、多種多様な産業セクターのプロジェクトをこなしながら、スピード感をもって事業をローンチさせてゆく仕事のやり方に魅力を感じるようになりました。
ただし最初は苦戦しました。ビジネス畑一辺倒で生きてきた私にとって、クリエイターやデザイナー、エンジニアたちと共創しながら事業を創るやり方に戸惑うことがあったのも事実です。そこで彼らと同じ目線で仕事を創るためにも学びを得ようと、多摩美術大学のクリエイティブリーダーシッププログラムを受講しました。ビジネスパーソンが美意識やデザインを学ぶカリキュラムですね。
実は三菱重工時代にも同じようなことがありました。新規事業部門に移ったときに自分の能力不足を痛感し、一念発起してMBAを取ったんです。振り返ると新しいチャレンジと新しい学びがセットになっているのが私の基本スタイルと言えるように思います。面白そうだと思う方向に飛び込んでみると、知らないこと、判らないことが次々と出てきます。だからこそ新しい学びを見つけにゆく。そういう意味では、ずっと私は学び続けているとも言えるのかもしれません。
![]()
社会課題を解決する人材が連鎖していく面白さ
──ライフイズテックとの出会いはいつ、どういったものでしたか?
前職の外資系のコンサルティングファームには5年ほど在籍しました。その間、並行して国際協力NPOやソーシャルビジネスにも関わりながら社会インパクトを創る仕事に志をもって携わってきたのですが、これからの人生では、こういった社会インパクトを創る人材が、日本から輩出されてゆく仕組みを創る仕事をしてゆきたいなと思うようになりました。そんな想いもあって、まずは社会課題解決の周辺を探りました。
私がライフイズテックを知ったのは、実はインパクトスタートアップがきっかけでした。元々国際協力の視点から認識はしていたのですが、そこに「教育✕ソーシャルインパクト」という領域があることを知り、一度話を聞いてみたいと思いコンタクトを取りました。それが最初ですね。
選考の過程ではかなりたくさんのライフイズテックの人と関わりを持つことができて、いろんな声を聴き、様々な思いに触れました。そしてライフイズテックで働く人の熱量を感じながら、何のために事業に取り組んでいるのかを自分なりに解釈していきました。
選考終盤で「ライフイズテックってどんな場所だと思う?」と問われたことがあったんです。考えたのちに「次世代のイノベーション人材を創り育ててゆく場ですかね」と答えた記憶があります。選考中の多くの社員の方と接点を持てたことで導き出された返答だったのですが、内示を頂けた事で志が一致しているのかなと自分なりの納得感を得られました。入社前から時間をかけて自分がこれから先の人生でやりたいことの方向性と会社の目指すビジョンをすり合わせることができて良かったように思います。
──今のお仕事について聞かせてください
多くの自治体や民間企業、スタートアップの方々とお話をさせて頂きながら、地域における教育のあり方などを一緒に考えるところから始まる仕事です。デジタルやAI等のテクノロジーを使って社会課題を解決するイノベーティブな人材をいかに育成していくか。仕事の面白みを感じるのは関係する人たちが実に多岐にわたっている点です。例えば自治体の中には未来の人材育成を扱う方もいれば、中小企業振興を担当する方、観光や企業誘致、産業政策等に携わる方もいらっしゃいます。そういった方々と教育という共通言語で一体となりながら、地域社会全体でデジタル人材を育成するプラットフォームを作っていく事を目指します。
![]()
予めパッケージ化された商品を提案するのではなくて、地域から社会を変える未来の人材を育成するためには何が必要か議論し、事業を一緒につくっていくんです。きっかけは私たちからアプローチして課題のヒアリングを起点に企画提案というケースもあれば、逆に知事さんや部局の方からお声がけ頂くこともあります。このあたりはライフイズテックがEdTechのリーディングカンパニーとしての知名度があるおかげですね。
わかりやすい事例でいうと山梨県の取組みがひとつあげられます。ライフイズテックと県、そこに地域の大学や商工会議所とも連携し「人材育成エコシステム創出事業」を立ち上げました。私たちのプログラムを経験した山梨県内の大学生が、中高生の子どもたちにデジタルによる課題解決の教え手となって育成しつつ、その大学生が県内の中小企業が抱える課題をデジタルで解決する為のファシリテーションをするという、社会の課題を解決できる関係人口を地域全体でつないでいく営みです。こういう取り組みが地域単位で増えていけば日本は必ず良い方向に変わっていくと思います。
もちろん山梨県の例はひとつのケーススタディであって、他の地域ではまるで異なる取り組みになる可能性もあります。それぞれ自治体によって課題の粒度や優先順位が違いますので、多様なやり方があるべきと思います。ただ、山梨県のようにいくつかの成功事例が様々な地域で生まれてくる事で社会実装されていくスピードは更に上がっていくと思います。課題解決できる人材を次世代人材として育成し、地域の振興をよりサステナブルなものにするということは共通するテーマですからね。
![]()
新しい価値の提供で固定観念をほぐす
──やりがいのありそうな仕事のようですが、逆に難しい面は?
自治体相手のビジネスというと、難易度が高そうに思われるかもしれませんが、実感値としては制約が違うだけで民間企業相手でも同じだと思っています。例えば自治体だと年に一回の予算のタイミングに合わせて調整を進めていく必要があります。それが整ってはじめて次の年度から事業として動かせるようになる。
これを難しいと捉えるか、特徴と捉えるか。与えられた制約の中でどんなことができるかを一緒に考えていく方が建設的だと思うんですよね。民間企業とのビジネスは意思決定のスピードや事業の回転の早さなどはありますが、でもそれはそういう環境と条件というだけなのかなと。
逆に取り組みをはじめてからの新しい発見が、この地域を変えていくんだという意志のある方々が自治体の中にたくさんいらっしゃるということです。民間企業と同じか、あるいはそれ以上に熱い思いと行動力を持った方がいるんです。そういう方々と一緒にチームを組んで事を成していく……これが社会にインパクトを創ってゆく仕事の一番の醍醐味と言えるのではないでしょうか。
たとえば財源不足が叫ばれている自治体も少なくありません。でもそこで止まっていても何も進まない。私たちの方から新しいアイデアを構想し提起する事で価値を提供したり、そもそもビジネスのやり方を変えたらお金が回るかもしれないという提案ができます。また新しいファイナンスのソリューションを組み合わせたり、民間企業や大学とのコラボレーションなどを通じてこれまでにないアプローチを取る事だってできると思います。社会を変えたい、未来の子ども達に道を創ってゆきたい、そういった意志があれば動きが変わるんではないかなと思います。
![]()
既存の枠組みに閉じていたらそれだけのビジネスしかできないと思います。いろんなところで壁にぶつかったりボトルネックが発生しますが、それを打開できるアイデアやアプローチを持ち寄って、みんなを巻き込んで突破する。事業を開発するシーンではそういう本質があるんだと思います。民間をつなぐとか産官学でやるとか、新しいプレイヤーを巻き込むことでお金の流れも実現のスケールもより大きくなるでしょう。
私の原体験にチームスポーツがあるという話は冒頭でしましたが、一社だけでできることには限りがあります。コレクティブにインパクトを出すべきだし、足りないピースがあれば一緒につくっていけばいい。だから私たちと一緒になってインパクトを出していきたい。そういう非常にシンプルな提案なんです。
ライフイズテックで働くようになって感じる特徴の1つに意思決定のスピードが早いことがあります。失敗しても次に活かすまでの速度が早い。私はまだジョインして日が浅いのですが戦略も組織も生き物のように変化しています。学びを届ける私たちだからこそ、自分たちが常に学んで進化し続けないといけない。学習サイクルが自ずとできているんです。
──日々の業務の成果はどうやって測っていますか?
業務ごとのKPIはもちろん設定していますが、上位概念として「どういう状態になれば社会課題が解決したり未来の人材育成ができたといえるのか」という視座をもつようにしています。私たちにはイノベーション人材を120万人つくるという目標があります。そこから逆算してどのタイミングまでにどれぐらいの地域でどれぐらいの人材が育っていれば達成するのかという事を常日頃考えています。手前の数字を追うことはもちろんですが、その先にそれによって何が成し遂げられたかが大事だと思うんですね。
![]()
教育はあらゆる産業、あらゆる志と接続される
──ライフイズテックのカルチャーを象徴するエピソードはありますか?
私のチーム内では日々仮説検証サイクルを回しています。何をやるかを決めて、どんなことがありえるかの仮説を立てる。その仮説に基づいてその日の実行プランを遂行し、その結果をその日のうちに投稿するというものです。これは本当に学びがあります。仮説の思考のプロセスを知ることや対話を通して、自分たちがいかに早く”変革の兆し”に向き合えるか。これがライフイズテックには文化として根付いていると思います。
チームの構成はプロジェクトごと、フェーズによって増減します。企画や検討の段階では人数も少ないですが、実際に動かすとなるとマネジメント層や異なる部署の方も巻き込むことも。スタートアップならではの機動力あるメンバーが揃っているからこそ実現できているんだと思います。みんなでチームを組成して一緒にやっていこうという文化ですから、部署を問わず困ったら手を差し伸べてくれるし、スポットだけの対応もしてくれます。そういう意味でも非常に仕事がしやすい環境といえますね。
![]()
──転職先として選ぶ上でのベネフィットは?
教育という概念はどんな産業とも結びつきます。つまり過去にやってきたことはもちろん、やりたかったこと、やれなかったことにもリーチできる。いろんな可能性と機会に満ちています。しかもAIやテクノロジーの活用という面では最先端の一丁目一番地の領域に携わることができる。このトレンドを追い風にさらに可能性も機会も広がってゆきます。
私たちも教えるばかりではなく、大学生や子どもたちからたくさんのことを教えてもらっています。教え教わるフラットな関係性は開発途上国支援の場面でもよく目にすることですが、スタンダードな学びの在り方になるかもしれません。そういった事に日々触れながら自らを成長させられることこそ何よりのベネフィットではないでしょうか。
──坪井さんの今後のキャリアビジョンを聞かせてください
極めてパーソナルなビジョンになりますが、「志の教育」に取り組みたいというのが私が思っている事です。社会起業家やアントレプレナーたちの志はどうやって形成されたのか。どんな意味付けがそこにあったのか。どんな内省や対話のプロセスを経たのか。その人の心の変容がどのように行われていったのかを追いかけていきたいです。
ちなみにいまライフイズテックの仕事に合わせて、大学院にも通って教育心理学・人間性心理学といった、人間の内面についての学びを得ています。いまの仕事も、これまでのキャリアからみると、また新しいチャレンジです。そして教育というフィールドについて、共に働く仲間のみんなほど豊富な経験を有しているわけでもありません。まだまだ学ぶことの多い領域です。ただ、私にとっては学び続けることが何よりの生きがいですから、とても充実した日々を過ごせていますね。
新たに仲間として加わってくれる方に求めたいのは、教育に熱い思いを持っている人、そして自らも新しさのある学びを楽しいと思える人、そんな方にはぜひジョインしてほしいですね。様々なタイプの志をもつ仲間同士それぞれが、尊重し合いながら既存の枠組みを変えていく。機会を生み、可能性を拡げていく。そんな集団がライフイズテックですから。
![]()
▶︎事業開発事業部 公民事業共創グループの求人