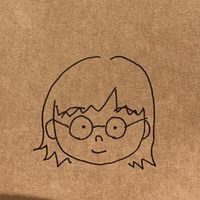- 高校生への伴走担当/学校連携
- 10職種以上で積極採用中
- 法人営業・コーディネーター
- Other occupations (18)
- Business
- Other
-カタリバ入職以前は、民間企業4社で広告企画やプロモーション業務に携わってきました。カタリバに転職をしたのは、どのような思いからだったのでしょう?
複数の企業で広報やプロジェクトの立ち上げを経験してきましたが、一貫して軸に置いていたのは、「自分の身近な誰かの生活が少しでも良くなるような仕事に携わりたい」という思いです。
そこに「子ども」という目線が加わったのは、出産と子育てがきっかけでした。家族の仕事で赴任した南アフリカで、子どもを出産し育てました。出産というライフイベント、そして外から日本を見るという経験をしたことで、「この国がどう変わっていくのか」「子どもたちが安心して育っていける社会とは?」という問いが、心の中に強く根づいていったんです。
子どもの幸せに直結する事業に携わりたいと思うようになり、そうした活動をしている転職先を探し始めました。
-民間の事業会社からNPOへの転身で、ギャップはありませんでしたか?
待遇面について、以前はビジネスセクターと比べるとギャップを感じる部分もあったと聞いていますが、現在は生活面での豊かさも確保しながら働ける環境になってきています。その上で、カタリバには、他の場所では得られない価値もあると感じています。
それは「社会貢献」といったことだけではなく、自分自身にとっての学びや気づきといった、かなり実感のある価値です。たとえば、カタリバでは不登校の子どもたちを支援するいくつかの事業に取り組んでいますが、広報に携わる中で、不登校についても日々状況が変化し、取れる選択肢も移り変わっている現状を目にしています。
日本の教育が向かっていく先や、子育てと教育現場のリアルを知り、その環境を良い方向に変えることに携わっているということ。これは逆にお金を出しても得られない経験です。そういった面で、給与や待遇では得ることのできない価値を日々実感できています。
-カタリバでは、広報部の立ち上げから関わられています。これまでと現在の取り組みについて教えてください
2020年に私が入職した際、カタリバでは既に外部メディアやSNS、オウンドメディアでの発信をしていました。ただそれは、主にメディアから取材依頼が来たら対応する、事業部の依頼を受けて発信する、といったスタイルでした。
そこで、広報部を立ち上げるにあたり、まずは「カタリバをどのように認知してもらうか」を企画しながら発信することを考えました。つまり、受け身のスタイルから、“攻めの広報”にしていこうと思ったのです。その方針は今も変わっていません。

-「攻めの広報」について、もう少し詳しく教えてください。
社会で注目を集めているテーマと、カタリバの取り組みを掛け合わせた発信を意識しています。そうすることで、より多くの人にカタリバの活動に対して興味を持ってもらえると思うからです。
たとえば「不登校」や「ヤングケアラー」など、注目が高まっているトピックがあるときには、事業部と連携してタイミングよくプレスリリースを出すなど、より届きやすい形で伝える工夫も大切にしています。
-これまで企業広報に携わってきた中で、NPOでの広報にはどんな特徴や違いがあると感じていますか?
企業広報では、自社の商品やサービスの価値を伝え、売上や利益につなげていくことが主な目的です。私自身もこれまでそうした仕事をしてきましたし、それも大切な役割です。
一方、NPO広報には、社会にまだ知られていない課題そのものを伝えるという大きな役割があると感じています。「今、子どもたちを取り巻く環境にはこんな課題がある。だからこそ、こうした支援が必要なんだ」ということを伝えていく。その“気づき”を社会に届けて世論を動かし、世の中の制度や仕組みを動かすきっかけになる――それがNPO広報の1つの意義だと思います。
実際、カタリバでは「支援の現場で得た知見」をもとに、国や自治体と連携して教育制度そのものに働きかけるような実証事業も進めています。社会の課題に光を当て、その解決の糸口を示す。それが現状を変える一歩になると信じて、広報の仕事に向き合っています。
-「攻めの広報」の取り組みによって、カタリバと社会との接点を広げてきました。現在、どのような手応えを感じていますか?
やはり、チームメンバーの成長を実感できるのが一番の手応えですね。メンバーの成長とともに、広報部としてできることの幅がどんどん広がっていて、私ひとりでは絶対にできないような新たなチャレンジに取り組めているのもすごくうれしい。
また、事業に携わるメンバーとの関係性にも変化が生まれてきました。いろいろな広報事例が生まれたことによって、今では「こういうことを発信できませんか?」だったり「どんな発信ができるか一緒に考えたい」といった相談をもらえる機会が増えました。
「一緒に広報をつくっている」という感覚が広がってきたことは、大きなやりがいの1つです。カタリバメンバー全員が広報パーソンとなり「誰もがカタリバを語れるようにすること」。これは、私が広報で大切にしている視点でもあります。
-「誰もがカタリバを語れるようにする」という考えについて、もう少し詳しく聞かせてください。
カタリバは創業24年という歴史があり、全国で20近い事業を展開していて、その内容はとても多様です。ひと言で「こんな団体です」と伝えるのが難しいからこそ、現場で子どもたちと向き合っている職員も含めて、メンバー一人ひとりが正しく自分の言葉で語れることも大切だと考えています。
カタリバを知っている人が、カタリバのことを語ってくれるようになることで、さらに手が届く子どもたちが増えるかもしれない。そのような想いから、広報部だけが情報を発信するのではなく、カタリバに関わるすべてのメンバーが“広報パーソン”になれるよう、ツールや仕組みを整備しています。

-今後、広報リーダーとして目指していきたいことを教えてください。
これまでは「子どもたちを取り巻く環境や社会課題を世の中に知ってもらう」ことや「現場の声を社会に届ける」ことに注力してきましたが、今後は、支援現場で得た知見やノウハウをもとに教育や社会の“仕組み”にアプローチしている側面ももっと知ってもらいたいです。
広報としてその意義をしっかりと伝えていき、「そういうことが大事だよね」と共感してくれる仲間が増えていくことが、これから子どもたちが生きる未来をより良いものにすることにつながると考えています。
「カタリバのカタリかた」を再度問い直すこのフェーズにおいて、カタリバが描く未来をより多くの人と共有し、広報の力で新たな仲間とつながっていけるように取り組んでいきたいです。