今回は人事や採用といった「人」に関わる業務である「HR」の仕事をご紹介します。
HRメンバーのお二人に、さまざまな観点からHRの仕事について語りつくしていただきました。前後編の長編となりますが、ぜひご覧ください。
【参加者】
野家 慶子さん 人事・採用・広報グループマネージャー
村松美奈子さん 人事・採用・広報グループ
目次
自己紹介
HRの魅力
HRの役割とは
HRならではのやりがい
justInCaseTechnologiesの組織としての魅力
自己紹介
司会:最初に、自己紹介から始めたいと思います。まずは、野家さんからお願いできますか?
野家:私は当社に入社してから丸3年が経過して、今4年目に突入しました。 人事に関わる全体を見ており、分かりやすいところですと評価制度を半期に一度回しながらアップデートしたり、人事制度や全体フローをどうしていくかなどを主に担っています。そのほかに日々発生する課題に対応しています。それらとともにマネージャーという役割もいただいているので、採用業務のマネージャーと広報のマネージャーも兼務しています。
司会:HR職としては何年目になりますか?
野家:前職は採用と採用広報を中心としたHR、その前はHRを含めた管理業務全般という時期もあり、そこまで含めると10年近くになるかなというところです。
司会:ありがとうございます。そう考えると、社会人としてのキャリアのかなり長い期間をHRとして過ごしていらっしゃるんですね。
野家:そうですね。気づいたらそうなってました。
司会:ありがとうございます。では、村松さんお願いします。
村松:はい。私は2023年の8月に当社に入社したので、あと数か月で丸2年になります。主に中途採用をメインで担当しております。採用ポジションとしては、エンジニアやBiz職、直近ではHRの採用もしていますのでバックオフィスも担当しています。人事グループにも所属(兼務)しており、人事の部分は野家さんにリードいただきつつ、ご支援させていただくこともあります。
司会:村松さんは、HR歴は何年になりますか?
村松:今、野家さんの話を聞いて、自分でも振り返ってみましたが、前職では人事総務の業務を担当しており、HR+総務労務の経験でいうと、多分6-7年ぐらいですね。
HRの魅力
司会:キャリアとしてのHR職の魅はどういうところにあるとお考えでしょうか?
野家:やっぱり人事って裏方ですけど、企業の土台を後ろや下側から積み上げて支える役割だと思っているので、そうした寄与の形は結構面白いと思います。
もちろんどんなアサインであるか、会社規模や事業フェーズによっても、やるべきこと、得られる情報、相対する社内のステークホルダーって全然違うと思うんですが。HRに関する課題を解決するために、代表含むレイヤーの高い方々の意向や意思、事業の進む方向を理解して、HRとしてどう支援、先回りできるかを考える形になるので、裏側からではありますが、事業推進に比較的ダイレクトに関わり、支援できる実感があります。やや唐突かつゲームをする人にしか伝わらない例えですが、前線で戦う方々や守るべき全体に向けて補助魔法を使うイメージかもしれません。一方で、採用に関しては攻めの側面も持っていたりもするので、そんな多面的なところが面白さかなと。
あとはキャリアの特徴としては、管理部門全体にも言えることですが、HRはどの会社にも必ずある機能なので、全ての会社が自分のフィールドになりえるというのもあります。
司会:攻めもあり、守りもあり、かつ全業種・業界に必要とされる職種というのは魅力的ですね。
野家:もちろん会社によって必要な機能は違いますが、夫に「よく考えてみたら、人事ってどこでも働けるの強い!」って言われたことがあって、確かにそうだなと。

村松:私も友達に言われたことあります(笑)
司会:村松さんはいかがですか?
村松:そうですね。 私も野家さんと近しい意見ですが、そもそもどの業界、どの会社でも必要とされる存在ではあるかなと思っています。HRにしかできないことの観点で言うと、人を対象にしている点が大きいと思います。HRは、人の感情に寄り添いながら、ポジティブな変化を促す役割を担っていると思っています。HRが発信する企画や制度は、どれもメンバーの安心感や働きやすさに本来繋がるはずのものであり、結果的にそれが組織のバリューやカルチャーを後押ししていくと考えています。で、そういった制度や仕組みをつくるときは、会社にいるメンバーの特性と会社の未来の両軸に向けて考えるので、言ってみれば“会社の性格”をつくっているようなものなんですよね。そこに正面から向き合えるのはHRならではの役割なのかなと思います。
司会:会社の性格をつくるっていう観点、面白いですね。ひとりひとりに寄り添いながら、導きながらというところは、確かにそうだなと思います。
HRの役割とは
司会:では次に、今のお話にも多少あったんですけれども、HRはどういう役割を担っているのかっていうところを伺いたいと思います。村松さん、いかがですか?
村松:私は前職でデザイン会社にいたのですが、そこで出会った松下電器(現在のパナソニック)の創業者の松下幸之助さんの「ものをつくるまえに人をつくる」という言葉が印象に残っています。当時HRという仕事を始めたばかりで「とにかく人を採用しなければ」という意識ばかりが先行し、正直なところ採用や人事の施策がどう事業に貢献しているのかについてあまり実感がありませんでした。ですが、この言葉に出会った事で自分のやっていることの意味に気付けたんです。
人が育ち、組織がしっかりと根を張ることで、事業は推進力を増し、持続的に成長していけるーこれはどんな事業においても本質だと思います。HRの仕事はまさに、その土台をつくる役割なのだと、今は実感しています。その土台作りを、今、野家さんが推進してくださっていますが、今の会社の状況を客観的に捉え、短期的・長期的にどういう組織にしていきたいか、そしてそれはどのような仕組みがあれば達成できるかを考えることがHRの役割なのかなと思ったりしています。

司会:ありがとうございます。確かに、どんな組織も「人」でできていますから、HRの役割は重要ですね。では、野家さん、お願いします。
野家:HRの役割は、経営戦略を実現するための「人」の部分を担保することだと考えます。その構成要素として、我々の会社の構想や事業に共感し、一緒にやるという人を場に集めることが、HRの機能の一つです。つまり採用ですね。これが1つ目。
2つ目は、一緒にやると言ってくれる方々がちゃんと働き続けられる環境を整備し、そして経営戦略の実行に必要な考えや価値観を共有・理解していただくことですね。大きい会社だと、環境の維持や価値観の伝達にたくさんの人と労力を割けられると思うんですが、我々のようなスタートアップでは、そもそも道がない場合もあり、荒野を少しずつ開拓して道を作っていくのが人事の仕事になるのかなと。前より少しずつでも良くしていくことに重点をおいて。また、評価の観点では、各人のアウトプットの振り返りと可視化だけに留まることなく、人の育成の支援・価値観の可視化やインプットというのもHRの役割だと思います。ここは現時点で実行できていない部分も多分にあり、自分へプレッシャーもかけています(笑)
司会:ちなみに、当社の場合、中途採用の方で構成されているわけですが、異なるバックグラウンドを持った方々に「この会社ではこうしてください」「こういうルールです」って伝えるのは難しい気がしてしまうのですがいかがですか?
野家:おっしゃる通りで、当社は評価について一定の形まで出来ているという自負はあるものの、今現在は良くも悪くもガチガチの基準はめこんだ評価はしていませんし、アンチパターンも明確に出しているわけではありません。
とある他社さんの例で、ちょっといいなと思ったのが「アンラーン(unlearn)」も評価するという考え方です。「過去のインプットにおいて当社で不要と思ったことをきちんと手放せるならそれも評価する」という会社さんで、前向きなアンラーンなら素晴らしいし、その代わりにこれをインプットしてねという要素をしっかり提示している作り込みも素晴らしいなと。
当社の場合は、そうした明示的なパッケージはまだないので、まだ道半ばだと思っています。当社に参画いただいたことによって、その方個人と当社の両方にとってプラスの効果が生まれるのがあるべき状態とは思っているので、そのあたりを促せる要素の明文化や、指標の可視化、より適切なフィードバックができる環境づくりなどはしていきたいですね。
司会:常に動きながら、すり合わせをしながら制度を進化させてくださっていますよね。
HRならではのやりがい
司会:お話を伺っていても、HRは非常に難易度の高い仕事だと感じますが、やりがいを感じるときというのはどんな時でしょうか?
村松:そうですね。私は採用という観点でお話ししますと、当たり前かもしれませんが、やはり人を採用できた時、特に自分からアプローチした(スカウトを送った)方が、最後に当社に決めてくれたときはやっぱり嬉しいですし、その方が当社で活躍している姿を見ると、「この人を採用してよかったな」って素直に思えます。あとは、当社のメンバーは、すごく採用に協力的だと思っていて。ここでは、結果的に採用に至らなかったとしても、現場のメンバーと試行錯誤しながら最後までやりきった、という一体感や高揚感があって、お互いの士気が高まっている状態を楽しいなと感じています。
司会:そういう風にメンバー採用を進めているチームの方と二人三脚で進められると、採用活動自体の質が上がるような気がしますね。
村松:そうですね。こういう人が欲しい、こういう人とこういう課題を解決したい、みたいな目線が合っていると、お互いにすごくやりやすいですし、効率的に採用が進められると思います。
司会:いいですね。では野家さんはいかがですか?
野家:はい。私も今の村松さんの話を「そうそう、採用の醍醐味はそこ!」と100%共感して聞いていました。採用に関しては村松さんがフロントでガンガンに回してくださっており少しずつ着実に採用できている状態なので、私はほぼ見守っているだけなんですが。その立場の私ですら、決まったという話を聞くと後ろで「わーい!」って思っていたりするので。まさに醍醐味だなと思いながら聞いていました。
村松:いつも野家さんはしっかりリアクションしてくれますよね(笑)
野家:じゃあ私のやりがいは何かと言いますと、私個人の性格かもしれませんが、粒々の話で「これはやりがいだった」とはあまり思わないような気がします。半年や一年、二年単位ぐらいで振り返った時に「やってきたことで、良い変化があったな」みたいなものを見て「(少しは)やれたかも」という心境になるのは、前職から変わっていません。
前職では主に採用を担当していましたが、やっている時はある意味で夢中だったというか、1回1回の小規模な嬉しさ無念さはありましたけど、まとめてどうだったという意義や価値ってそこそこ長期的なスパンで見ないとあまり実感できなかったんですよね。
そんな自分が感じるやりがいを言語化すると、私が相対している人事的な課題の中には、ステークホルダーが多かったり、レイヤーが高かったり、まとめに至るまで難度が高い大玉課題みたいなものが時々出てくるんですけど、しかるべきことを順にやっていくと、思いのほか綺麗に整って、今までガタガタしていたものがきれいに着地できた時にはやりがいを感じます。
司会:人事施策というのは、分かりやすいゴールがあるわけではなく、一歩一歩、山登りのような感じで登っていて、たまに見晴らしの良い場所に出たときに「ここまで登って来たか」って思うようなイメージなのかもしれませんね。
野家:そんな感じです。人事の仕事はずっと続くし、施策の効果も、もちろん従業員アンケート等は実施しつつも、単純な数値化が極めて難しい。さらにいうと、 人事課題って、ともすると「やった気になれてしまう」という危機感も持っていて、だからこそ「それは本当に当社の事業にとってプラスなのか?」とか「そもそも課題って本当にそれなのか?」は常に考えないといけないなと。村松さんから見ていて、もしそうなっていたら遠慮なく教えてください。
村松:野家さんは人事の重要なタスクを担っているわけですが、経営陣から発信されるさまざまなお題に対して、解決したい課題の本質部分を言語化をしてくださっていて、経営陣と目線を合わせにいく姿勢を持ちつつも、本質とズレることやメンバーの納得が得られそうにないと判断した際に「それは違う、なぜならば〜」と従業員を守れる強さを持っていると思っています。
野家:ありがたいお言葉です。 言わせてる感が無いか心配になりますね(笑)

justInCaseTechnologiesの組織としての魅力
司会:では次の質問に移ります。今度は少し視点が変わるんですけれども、お2人が考える当社の組織として良いところはどのあたりにあると思われますか?
野家:当社に関して良いなと思うところの一つは、代表の畑さんが、常に複数存在する重要度合の高い課題に関して、それがなぜ重要かという理解は必要とした上で、適切に関心を持というとしてくれることですかね。メンバーが重要だと考える課題について提案すれば耳を傾けてくれますし、判断についても、無闇に先延ばしはされません。また、畑さん自身が「じゃあ僕はこう動いた方がいいですね」と必要があれば行動してくれることもありがたいですね。さっき村松さんのお話にもありましたが、畑さんをはじめ、ボードメンバーの皆さんが課題に対して真摯に向き合ってくださるので、そこはすごくいいなと思っていたりします。
司会:確かに、ボードメンバーは皆さんフラットに話を聞いてくれる印象がありますね。話しやすさが組織の風通しのよさにもつながっているのかもしれませんね。村松さんはいかがですか?
村松:私が一年半くらい前に転職活動を始めたときに、会社を選ぶ軸がいくつかあり、そのうちの一つが「その会社が積極的に情報発信しているか」という点でした。ブログとかイベントの登壇とか、なんでも良いのですが、情報発信が活発な会社って勢いがあるというか、組織として強いんだろうなという印象があります。
今も畑さんが様々なイベントで登壇されていますし、ブログ記事としても紹介されていて、それらが会社のブランディングにもなっていると思います。事業を継続する上で、共感性は結構大事だなと思っていて、メンバーの共感を得るためには、経営陣の発信力や、熱量が重要なポイントになってくるんじゃないかなと思っているので、そこはこの会社のいいなと思っているところです。
野家:私もそこは一般論として良い組織の要素の一つだと思っています。 当社はリモートワークが中心なので、そういった熱量であったりとか、みんなが暗黙知として知っているようなことを伝播する力は出社が基本の組織に比べて弱いところだと思うんですね。だからこそ、積極的な情報発信は必要だし、メンバーにもキャッチしてもらえたらと思います。
司会:ありがとうございます。お二人の組織に対する考え方、とても興味深かったです。
※後編ではHRならではのメンバーとの向き合い方や採用活動で意識しているポイントなどを伺っていきます。後編もお見逃しなく!


/assets/images/19636006/original/e755afc6-ab61-4e4f-970d-7b313f2b6db8?1730888349)

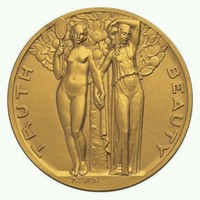



/assets/images/19636006/original/e755afc6-ab61-4e4f-970d-7b313f2b6db8?1730888349)

