- 新卒(総合職)
- 総合職(新卒)
- kintoneに関わる業務
- Other occupations (2)
- Development
- Other
【業界理解が深まる!IT業界・生成AI“学びの宝庫”】SI・AI講義〜M-SOLUTIONS株式会社 植草さん〜|25卒新人研修
こんにちは!新入社員の内村です。
ジョイゾーでは、新人研修の一環として、外部講師をお招きしさまざまな講義を受ける機会があります。
今回はその第1弾としてM-SOLUTIONS株式会社の植草学さんをお迎えし、「SI・AI講義」を実施していただきました。
本講義は、SI事業を展開するジョイゾーの一員として必要な業界知識やプロジェクトマネジメントの基本的な考え方を学ぶこと、そして現在kintoneとの連携も進み、注目を集めている生成AIについて理解を深めることを目的として開催されました。
SI事業のタイプやビジネスモデルの特徴、プロジェクトにおける計画の立て方、生成AIを活用するための適切なプロンプト(指示文)の書き方など、実際の現場で求められる視点やスキルが詰まった内容となっています。
ジョイゾーで働くことに興味がある方だけでなく、SI業界・生成AIに関心のある方にとっても学びの多い講義となっていますので、ぜひご覧ください!
講師:M-SOLUTIONS株式会社 植草さん
植草さんは、2000年にM-SOLUTIONS株式会社に入社後、会社の立ち上げやSmart atなど複数のサービスの立ち上げを経験されました。そして2019年、M-SOLUTIONS株式会社代表取締役社長CEOに就任されました。
では早速、植草さんによる講義で学んだことをお伝えします。

目次
講師:M-SOLUTIONS株式会社 植草さん
1. SI
(1)SIのタイプ
(2)SIのビジネスモデル
(3)kintone SIの拡大
2. プロジェクト・マネジメント
(1)プロジェクト・マネジメントを知る
(2)プロジェクトの流れ
(3)プロジェクトの計画「WBS」
3. 生成AI
(1)生成AIを知る
(2)プロンプト作成のコツ
(3)ChatGPT × kintone
まとめ
1. SI
はじめに、「SI」について講義していただきました。
SIとは、「システムインテグレーション(System Integration)」の略で、企業の情報システムの構築を請け負うITサービスのことです。
具体的には、顧客の要望に応じて、要件定義(何を作るか?)から始まり→設計(どう作るか?)→開発→納品といった一連のプロセスを担います。
また、このようなSIを提供する企業は、「Sler」(エスアイヤー)と呼ばれ、ジョイゾーもその企業の一つです。
(1)SIのタイプ
そして、SIには、主に「①SES」と「②請負開発」という2つのタイプが存在します。
①SES(システムエンジニアリングサービス)
1つ目の「SES」は、エンジニアのスキル単価 × 労働時間に基づいて月次で精算される契約形態です。
この契約では、成果物の完成責任は負わず、作業の遂行そのものが契約の目的となります。
以下は、SESにおけるリソース管理表です。
この表は、プロジェクトや業務において、誰が、いつ、どの仕事に、どれだけの時間を使っているか(または使う予定か)を管理するためのものです。

表の通り、SESのプロジェクトは通常、複数のメンバーによるグループ体制で数ヶ月にわたって遂行されますが、メンバーそれぞれのスキルレベルや労働時間によって報酬が個別に算出されるため、月ごとの合計請求金額は毎月異なります。
②請負開発
2つ目の「請負開発」は、納品物の完成に対して報酬が支払われ、納品・検収後に精算される契約形態です。
この契約では、成果に対する責任を負い、納品物の完成そのものが契約の目的となります。
以下は、請負開発におけるリソース管理表です。

表の通り、SESの場合とは異なり、報酬は個別ではなく、プロジェクト単位で設定されます。
そのため、納品・検収が完了した月にプロジェクトごとの報酬が一括で計上され、大きな金額が動くのが特徴です。
(2段目の表を参照。1行が1プロジェクトを表しており、検収が完了する月に報酬が記入されています。)
そして、請負開発においては、顧客と共に「目的」と「手段」を明確化することが極めて重要です。
以下の図は、顧客が自身の要求を正確に伝えられなかったり、社内外の複数の関係者を経由して開発が進められたりする中で認識の齟齬が生じ、結果として本来のニーズから乖離した成果物が出来上がってしまう状況を示しています。

そのため、このような事態を避けるためには、担当者が「なぜそのシステムを導入したいのか」という根本的な目的を丁寧にヒアリングし、顧客と完成形のイメージを共有した上で開発を進めていくことが求められます。
(2)SIのビジネスモデル
次に、SIのビジネスモデルについて学びました。
SIでは、多くの場合、以下の図に示すように、「顧客-プライム-サブコン」という契約構造が見られます。

「プライム」は顧客と直接契約を結ぶ「元請け企業」、「サブコン」はプライムと契約し間接的に顧客のシステム構築を担う「下請け企業」を指します。
さらに、同じプロジェクト内でサブコンが業務の一部を別の企業に再委託することで、二次請け、三次請けといった下請け企業が連鎖的に増え、多重下請け構造が形成されることもあります。
(3)kintone SIの拡大
そして、kintone SIの拡大イメージについても解説がありました。
これまで説明したモデルにおいて、SESでは、自分たちが工夫して開発効率を上げても、労働時間が減るため、かえって売上は減少してしまいます。
一方、請負開発では、開発効率を上げることで1案件あたりの稼働時間を短縮でき、その分多くの案件を同時に扱えるようになるため、結果的に売上を伸ばすことが可能です。報酬の回収は検収後となるものの、このメリットは大きいと言えるでしょう。
ただし、すべての請負開発が「提供価値に基づいた対価」であるとは限りません。SESのように「人月 × 単価」で金額を算出するケースも存在しており、SESと本質的に大きな違いがない形で運用されている場合もあります。
そうした中で近年注目されているのが、kintoneのようなノーコード開発の普及に伴う、「開発作業量」ではなく「顧客にとっての価値」を基準に報酬を決めるモデルへのシフトです。
これは請負開発の中でもさらに一段階進んだ考え方であり、開発にかかる手間よりも、顧客にもたらす効果や解決する課題の大きさを基準に価値を評価するアプローチです。
つまり、今後のSIビジネスにおいては、「どれだけ作業したか」ではなく、「顧客にとってどれだけの価値を提供したか」に重きを置いたモデルへの転換が、重要な鍵を握っていくということです。
2. プロジェクト・マネジメント
SIの仕組みや開発の進め方を学んだ後は、プロジェクトを円滑に進めるための「プロジェクト・マネジメント」について講義していただきました。
(1)プロジェクト・マネジメントを知る
プロジェクトとは
「プロジェクト」とは、独自性のあるプロダクト・サービスを創造するために実施される、有期的(開始・終了が明確)な業務のことを指します。(例:新製品の開発・セミナーの企画など)
プロジェクト・マネージャーとは
各プロジェクトには、その進行を管理する「プロジェクト・マネージャー」という役割の人が存在し、プロジェクトに割り当てられたリソース(人・モノ・金)を最大限に活かして目標を達成し、プロジェクトを最後まで遂行する責任を持ちます。
具体的には、主に以下のような業務を行います。
- 要求事項の特定
- 明確で達成可能な目標を確立
- 品質・スコープ・タイム・コストなど競合する要求のバランスを取る
- 各種ステークホルダーの異なる関心と期待に対して仕様・計画・取り組み方法を適用させる
この「ステークホルダー」とは「利害関係者」とも呼ばれ、プロジェクトの成功に影響を与えたり、逆にプロジェクトから影響を受けたりする全ての人々を指します。プロジェクトメンバーはもちろんのこと、スポンサー(出資者)、顧客などもこれに含まれます。

プロジェクト・マネージャーにとって、これらの多様なステークホルダーを正確に把握し、それぞれと円滑なコミュニケーションを取りながらプロジェクトを推進することは、最も重要な任務の一つと言えます。
(2)プロジェクトの流れ
プロジェクトの流れには、主に「①予測型」と「②適応型」という2つの型が存在します。
①予測型(ウォーターフォール)
1つ目の「予測型」は、開発プロセスを明確な段階に分割し、前の段階が完了してから次の段階へ進む、直線的な進め方です。「要件定義 → 設計 → 開発 → テスト → 展開」といった各工程を順に進めます。
- 利点:進捗管理がしやすく品質を保ちやすい。
- 欠点:途中の変更に対応しにくく、柔軟性に欠ける。
②適応型(アジャイル)
2つ目の「適応型」は、短い期間での開発とテストを繰り返し(反復的)、少しずつシステムを完成させていく(漸進的)進め方です。顧客からのフィードバックを頻繁に取り入れながら、柔軟に開発を進めていきます。
- 利点:変化への対応力が高く顧客ニーズに迅速に応えられる。
- 欠点:全体計画が初期には不明確な場合があり、進捗管理が複雑になることもある。
このように、予測型と適応型はそれぞれ異なるメリット・デメリットを持つため、プロジェクトの特性や状況に応じて最適なアプローチを選択することが重要です。

(3)プロジェクトの計画「WBS」
プロジェクトの流れについて学んだ後、特に予測型で計画を立てる際の基礎となる、「WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)」について説明がありました。
WBSとは、プロジェクトで達成すべき主要な成果物を明確にするために、その成果物を構成する具体的な作業要素を、管理可能なレベルまで分解し、階層的なツリー構造で整理したものです。

また、このWBSを作成する際には、「段階的詳細化」というアプローチが用いられることも教えていただきました。プロジェクトの初期段階では大まかに全体像を把握し、プロジェクトの進行とともに情報が明確になるにつれて、WBSの各要素を徐々に詳細化していくという考え方です。
最初から完璧を求めるのではなく、状況に応じて柔軟にWBSを具体化していくことも重要だと分かりました。
実際にWBSを体験!
WBSの基本を学んだところで、実際に「カレーライスを作る」というテーマのもと、新人それぞれがWBSを作成しました!
↓ 作成中...

↓ 完成!(上:戀塚 作・下:内村 作)

実際にWBSの作成に取り組んでみて、私たち新人の間でも、作業の捉え方や分解の仕方に違いがあることを実感しました。この経験を通じて、6月に予定している新人セミナーなど、今後2人で企画していくプロジェクトでは、それぞれの視点を活かし合うことで、抜け漏れの少ない、より精度の高い計画を立てられるようにしていきたいと考えました。
また、植草さんからは「WBSをどこまで細かく分解するかに唯一の正解はなく、指示を出す相手のタイプや状況によって調整することが重要である」という貴重なアドバイスもいただき、大変参考になりました。
3. 生成AI
プロジェクト・マネジメントの重要なポイントや計画の立て方を学んだ後は、「生成AI」について講義していただきました。
(1)生成AIを知る
生成AIとは
生成AIとは、人工知能の一種であり、テキスト、画像、動画などの新しいコンテンツを生成する能力を持つ技術です。例えば、以下の画像のような種類が存在します。(とてもたくさん...!)

従来のAIの多くは、マシンラーニング(機械学習)という手法を用いて人間が与えたデータを学習し、その範囲内で、判定や予測といった決められたタスクを自動化するものでした。
これに対し、生成AIは、マシンラーニングの中でも特に高度なディープラーニング(深層学習)という手法を用います。AI自身が膨大なデータから自律的に学習を重ね、データに潜む複雑な特徴や関係性を新たな知識として獲得し、その知識を基に全く新しいコンテンツを創り出す能力を備えています。
つまり、従来のAIが「学習データの中から最適な答えを選ぶ・予測する」ことに主眼を置いていたのに対し、生成AIは「学習した内容を応用して、新しいものを創造する」という点で、その能力と役割が大きく異なるのです。

(2)プロンプト作成のコツ
このような生成AIを効果的に活用するためには、「プロンプト」と呼ばれる指示文をAIに与える必要があります。プロンプトとは、いわばAIに対する「お願い」や「質問」のことです。
この点について、植草さんからは「AIに対して適切な問いかけ(プロンプト)をしなければ、質の高い回答は得られない」という、プロンプト作成の核心を突くアドバイスを頂きました。
では、「良いプロンプト」とは具体的にどのようなものでしょうか。
それは、AIに対して「何をしてほしいのか(目的)」、「どのような状況で(前提条件)」、そして「どのような形で答えてほしいのか(出力形式)」といった情報を、できる限り具体的に伝えることが重要です。
以下は、その良いプロンプトのサンプルです。

具体例で見てみましょう。
以下に、改善の余地があるプロンプト(左側)と、効果的なプロンプト(右側)の例を示します。

左側の「ChatGPT初心者向けのセミナー案を教えて」という指示だけでは、AIはどのようなセミナー案を具体的に求めているのか把握できません。
一方、右側のプロンプトのように、セミナーの目的、内容や参加者像といった前提条件、そして回答してほしい形式まで細かく指定することで、AIからの回答もより具体的で、実際に役立つ質の高いものになる可能性が高まります。
このように、プロンプトの質が生成AIの回答の質を大きく左右するのです。
(3)ChatGPT × kintone
最後に、M-SOLUTIONS株式会社が提供している、kintoneとChatGPTなどの生成AIを連携させるサービス「Smart at AI」の活用方法についてご紹介がありました。

「Smart at AI」の最大の特徴は、「ノーコードかつノープロンプト」を実現している点にあります。
これは、専門的なプログラミング知識が不要(ノーコード)なだけでなく、生成AIへの指示(プロンプト)も、あらかじめシステムに設定しておくことができるという画期的な仕組みです。
これにより、例えば情報システム部など専門知識のある担当者があらかじめ設定しておけば、その他の利用者はkintoneアプリ内で必要な項目を入力するだけで、その都度複雑なプロンプトを作成・入力する手間なく、生成AIによる様々な文章作成や分析といった作業を自動化できます。
例えば、営業活動におけるセールストーク案の作成シーンを見てみましょう。

画像のように、「Smart at AI」を使えば、kintoneアプリにお客様の企業名、担当者名、提案したいサービス、そして想定される質問といった情報を入力するだけで、AIがこれらの情報を基に、状況に応じた効果的なセールストークスクリプトを自動で作成します。
その他にも、日報やメール文章の作成、議事録の要約、さらには営業案件の確度分析といった、ビジネスにおける様々なシーンで生成AIは活躍します。 これまで時間を要していた作業をAIに任せることで、業務の生産性を飛躍的に向上させることが期待できるとのことで、非常に魅力的なお話でした。
まとめ
今回の研修を通して、これからジョイゾーでSIerとして働く上で、自社の立ち位置だけでなく、SI業界に存在する様々な開発タイプやビジネスモデルについて理解を深めることができ、大変勉強になりました。
また、ジョイゾーでは「プロジェクト型」の業務に携わる機会も多いため、今回プロジェクト・マネジメントの基礎を学び、物事を抜け漏れなく計画的に進めることの重要性を改めて認識できたことは、今後の業務において大きな糧になると感じています。
生成AIについても、研修前はほとんど知識がない状態でしたが、基礎から具体的な活用事例、そしてプロンプト作成の重要性まで体系的に学び、理解を深めることができました。
さらに、講師の植草さんからは、最後に「何事もポジティブな姿勢と笑顔で取り組むことが大切」という、心に響くメッセージをいただきました。植草さんご自身がまさにその言葉を体現されていることは、初めてお会いした瞬間から強く感じられ、ぜひ見習わせていただきたいと思いました。
これから仕事をしていく中で、様々な困難に直面することもあると思いますが、どのような状況であっても、常に前向きな気持ちと笑顔を忘れず、一つひとつの課題に真摯に取り組んでいきたいと思います。
/assets/images/5796153/original/1b6f44a1-d3c1-4a97-b485-30e0e6f1e3bf?1605749904)

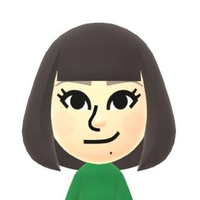
/assets/images/5796153/original/1b6f44a1-d3c1-4a97-b485-30e0e6f1e3bf?1605749904)


/assets/images/5796153/original/1b6f44a1-d3c1-4a97-b485-30e0e6f1e3bf?1605749904)



/assets/images/5796153/original/1b6f44a1-d3c1-4a97-b485-30e0e6f1e3bf?1605749904)

