- Web Engineer
- ECサイト構築
- 上場企業のCS
- Other occupations (21)
- Development
- Business
- Other
株式会社イノベーションは、『「働く」を変える』というミッションのもと、BtoB営業の変革を起点にIT・金融など多岐にわたる領域でDX推進を図ってきました。上場後はホールディングス化を進め、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)によるスタートアップ投資、新規事業の立ち上げなどを次々と実行。
同社が最も大切にしているのは、単に事業を拡大するだけでなく、ビジネスパーソン一人ひとりが「働く」を有意義なものに、そして楽しめる環境をつくること。その背景には、代表取締役社長・富田の原体験に根差した「もっとイキイキ働ける社会を作りたい」という強い思いがあります。
本記事では、なぜ今「働く」を変える必要があるのか、そしてその実現を支える「起業家精神」や個々の強みを生かす組織づくりとはどのようなものか──富田のキャリアやエピソードを交えながら語ってもらいました。
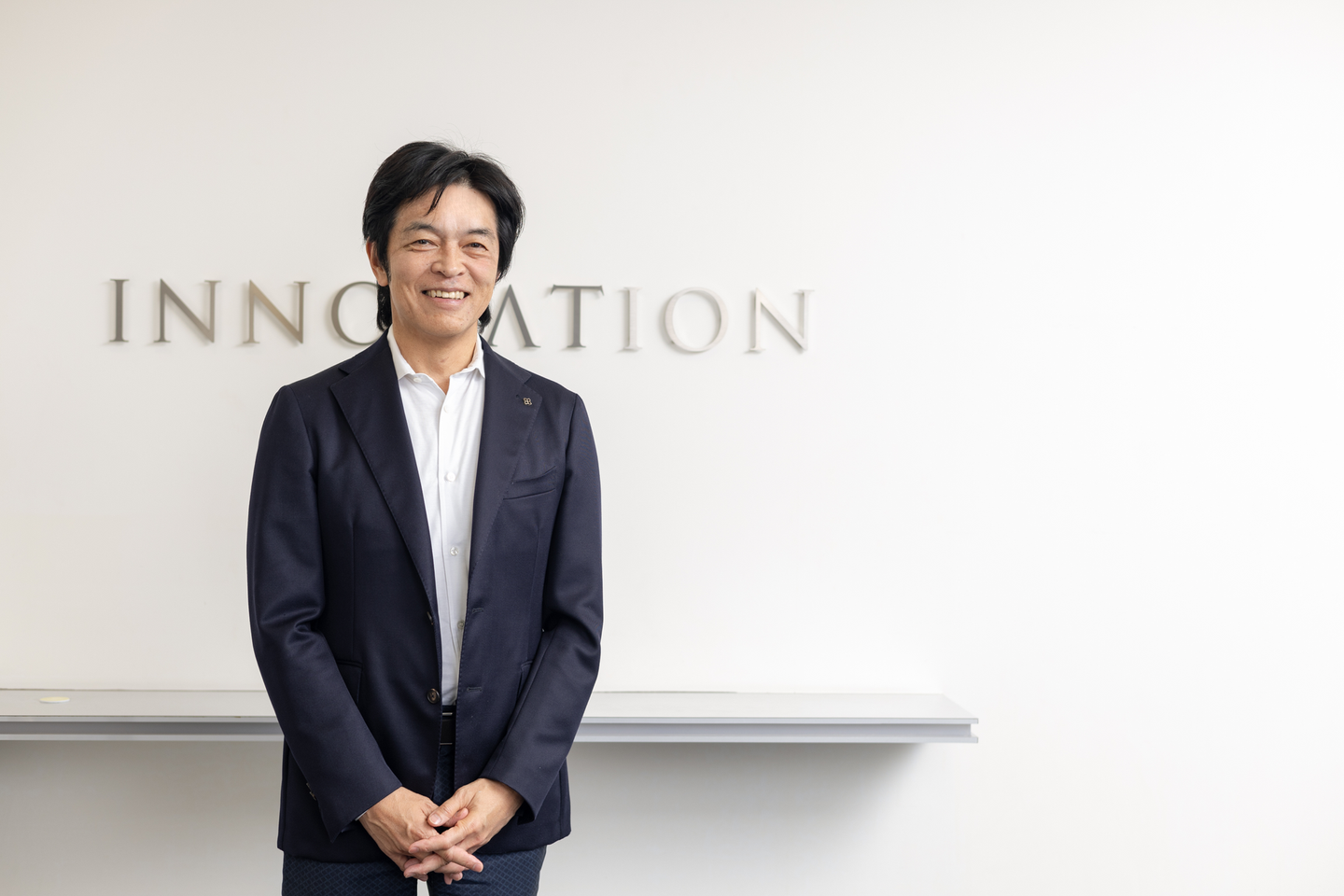
富田 直人/株式会社イノベーション 代表取締役社長
静岡県浜松市出身。実家が電気工事会社を経営していたこともあり、大学は横浜国立大学工学部電気工学科に進む。卒業後、父の会社を継ぐ前に社会勉強をしようとリクルートに入社。新規開拓営業を経験した後、2000年にイノベーションを設立。法人営業の新しいスタイルを創造すべく、IT業界を中心にインターネットマーケティング支援事業をおこなう。2016年12月、東証マザーズ上場を果たす。ホールディングス化・CVC設立・金融領域進出など改革を続けており、ミッション「働く」を変えるを拡げるため、多様な新規事業やM&A、スタートアップ支援を積極的に推進中。
原点は「非効率を変えたい」という想い──「働く」を変えるミッションが生まれた背景

ーーまずは、イノベーションが掲げるミッション『「働く」を変える』の原点から教えてください。
私がリクルートで新規事業の営業を担当していた頃、IT企業でさえ「集めた名刺を誰も活用しない」「アポを取らない」など、とても非効率だと感じていたんです。そこで「営業を変革すれば、企業も個人ももっと成長できるのに」と強く思うようになりました。独立した当初は「法人営業を変革する」べくBtoB営業支援を始めましたが、事業を進めるほど「営業を変えるだけではなく“働く”の捉え方を変えたほうがいいのでは?」という想いが芽生えたんです。人は人生の多くを仕事に費やすわけです。であれば、その時間をもっと活き活き過ごせる社会を作りたい。そうして生まれたのが「働く」を変えるというミッションです。
ーー大きなミッションですね。具体的には、どんな社会を目指されているのでしょうか?
私たちが目指しているのは、“個々人の働く意義が最大化される社会” です。非効率の排除やDXによる生産性向上は通過点であって、本質は「働くことってとても尊い」「自分が社会を動かしていると実感できる」状態を作ること。だから、既存事業に加えて新規事業やCVCなど、多様なチャレンジを仕掛けています。ITトレンドでBtoB営業のDXを進める一方、金融のIFA支援で証券営業を試みたり、M&A領域での新たな仕組み作りなど。「こういう新しい価値を提供すれば、業界や経済がもっとよくなるかも」という発想がベースにあります。
ーーそこに“起業家精神”が必要になる理由は何でしょう?
大きく分けて2つあって、一つは“業界ごと変革する”くらいの力を出すには、挑戦するマインドセットが欠かせないこと。もう一つは、変化のスピードが速い時代に適応し続けるには、一人ひとりが主体的に動く必要があることです。「働く」を変えるは、言い換えれば「業界の当たり前や慣習を壊す」ことでもあります。そこには反発や困難がつきものですが、起業家精神がある人ほど“どうすれば新しい価値を生み出せるか”と前向きに考え行動ができます。そういう人たちが増えれば、企業や業界の変革速度も格段に上がります。ただし、必ずしも起業する必要もなく社内であっても起業家のように行動する精神が大事だと伝えています。
ーー独立や起業をしなくても「働く」を変えるは可能、ということですね。
そうですね。むしろ、起業するよりも会社というリソースを活かし、自分の強みを発揮して変革を起こすほうが実現性も高くスピードも早いこともあるでしょう。私自身、リクルート時代に「それおかしくないですか?」と上司に直談判して周囲を困らせていましたが(笑)、あれも一種の起業家精神だと思います。“今あるルールを疑う”という勇気こそが、「働く」を変える原動力になるんじゃないでしょうか。
組織崩壊を乗り越えて得た気づき

ーー富田さんのリクルート時代のお話、もう少し詳しく伺えますか? “営業の非効率”に気づいたきっかけは何だったのでしょう。
リクルートでは新規事業の新規営業ばかり経験していたので、自分で道を切り開くしかないような状態でした。最初は全然売れずに苦しみましたが、量をこなしているうちにノウハウも溜まり成果が出せるようになりました。その過程でIT企業に訪問してわかったのが、「どんなに名刺や見込み客を集めてもアクションしない」という現実でした。経営者も営業も「それが当たり前」と考えている。私は「いや、やってみたらめちゃくちゃ伸びるかもしれないのに……もったいない」とずっと思っていました。これが独立の大きな動機ですね。「だったら自分が営業支援サービスを作って、お客様に結果を出してもらおう」と考えたわけです。
ーー独立後はすぐに軌道に乗ったのでしょうか?
起業当初はテレマーケティングやリスティング広告を軸に伸ばし、5年ほどで売上は10億円を超えました。しかし、どちらも労働集約型のビジネスであり、利益率が低く採用がネックになったりなどで……常に課題が絶えませんでした。それを打開するために始めたのがITトレンド、BtoBのプラットフォームです。当時のIT業界では成果に応じた広告が珍しく、初めは苦労しましたが、多くの企業に支援されるプロダクトになりました。そこから会社も一気に成長し上場を目指せるほど成長したんですが、上場後には組織崩壊の危機があったんです。
ーー組織崩壊の危機とは、具体的にどういう状況だったのでしょう?
かなり無理のあるIPOとはわかっていましたが、上場審査の多くのプロセスの中で組織は疲弊して上場後に多くの社員が去っていきました。私自身、とっても辛い思いをする中で「そもそも私は何をしたかったのだろう?」と自分に向き合うきっかけとなりました。そして私自身の使命が徐々に見えてきました。それは自分自身が「本物の起業家」であり挑戦し続けること。そして多くの起業家精神を持ったリーダーを生み出すことが私の使命なんだと確信しました。そこでグループ経営に転換して、多くのビジネスリーダーを増やすべく権限を渡す形へシフトしました。それにより現場から多様なアイデアや挑戦が生まれやすくなったり、私一人に依存しない体制が整ってきたのです。
「起業家精神」×「個々の強みを生かす」──多様な人材が挑戦できる組織へ

ーー多様な個性をどうやって把握し、活かしているのですか?
私たちは適性診断を活用して社内で結果を共有し、「この人は新規開拓が得意」「この人は管理業務が得意」といった強み・弱みをオープンにしています。たとえば、私自身の診断結果は“経営幹部やアントレプレナー型”で、新しいことを生み出すのは得意だけど、運用や細かい管理業務を地道に続けるのは苦手。だからこそ、そこを得意とするメンバーにしっかり任せるようにしています。重要なのは、強みを起点に役割を決めることで、成果が大きく変わり、自信がつき、働くモチベーションが向上するということ。「自分が得意なことで会社に貢献し、それが新しい価値やイノベーションにつながる」と実感できたら、働きがいも格段に高まるはずです。ピーター・ドラッカーは「組織の目的は人の強みを爆発させ、弱みをなくすこと」と説いています。まさにこの考え方が、私たちの組織のあり方に直結しています。
ーー守りや安定が好きな人も、起業家精神を発揮できるんでしょうか?
もちろんできます。起業家精神って「新規事業を立ち上げる」「大きな変革を起こす」ことだけを指すわけではありません。例えば「事務処理でミスを大幅に削減する」「セキュリティレベルを向上する」など小さな改善や改良を積み重ねていく、これらも起業家精神がなければ実現し続けられないと考えています。ただの作業ではなく、「業務を徹底的に改善して効率化する」「自分の専門性を発揮して事業を支える」──ここにも新しい価値創造があります。大きな社会変革も目前の改善から始まるのです。
ーー起業家精神を実践するには、どんなマインドセットが欠かせないのでしょう?
「ルールだから仕方ない」と思わずに、「そのルールって本当に正しいの?」「こう考えられないの?」と現状を疑ってみる姿勢が重要かなと思います。世の中のあらゆる非効率や負は、全てそこからがスタートだと思います。「働く」を変えるというミッションは、言い換えれば「これまでのルールや常識をどれだけアップデートできるか」です。そこで起業家精神を発揮する人が増えれば、自然と多くの問題は改善され、“もっと働くのが楽しい”状態に近づくはずです。
ーーでは、イノベーションの組織としての強みは、まさに「多様な人材が自分の得意分野で挑戦できる」体制づくりなんですね。
そう思います。ホールディングス化もその一環で、各事業会社やグループ会社にリーダーを置き、挑戦できる仕組みを整えました。私がすべてを統括するよりも、各領域で専門性を発揮できる人が“起業家精神”をもって動いたほうが、事業の成長スピードも速いし、働きがいも高まります。加えてCVCによってスタートアップとも連携できるので、「自分の強みを生かして外部の経営者を支援する」「そこで新しいノウハウを得る」といった循環が生まれやすいです。結果的に、「働く」を変えるというミッションに向けた新規事業の可能性も広がると考えています。
「働く」を変えるために、あなたができること

ーー今後、イノベーションが狙う事業領域や計画について教えてください。
私たちは引き続き強みの源泉であるITトレンドを軸にしながら、IT・金融・M&Aなど、働き方を大きく変えられる領域への挑戦を進めます。具体的には、DX化支援、証券・金融営業のDX化、M&Aプラットフォーム、HR領域などグループ各社が連携して企業の課題解決をトータルでサポートする仕組みづくりを構想中です。さらにCVCを通じて外部のスタートアップと協力し、共に新規事業を立ち上げることも考えています。こうしたオープンイノベーションを活用することで、自分たちだけでは届かない顧客層や業界を巻き込み、「働くの在り方」を変えるインパクトをより広げていきたいですね。
ーー将来的にはどんな世界を目指しているのでしょうか?
「働く」ことは人生を豊かにするものと思っています。人によって強みや価値観は違うけれど、その違いを活かした協力関係が成り立つことで、組織や業界がどんどんアップデートされていく。“会社員”や“フリーランス”といった枠組みを超えて、「自分がワクワクできる仕事にどう関われるか」が一番大切になる時代はすぐそこまで来ています。だからこそ、「働く」を変える取り組みを続けるうちに、気づいたら社会全体が“挑戦的で楽しい場所”になっている──そんな未来を期待しています。
ーーここまでお話を聞いた方の中には「面白そう!」と思う方も多いはずです。どんな人に仲間になってほしいですか?
“自分の強みを活かして何かを変えたい”と考えている方、そして「働く」という概念をもっと良くしたい方は大歓迎ですね。たとえばバリバリ新規事業を作りたい人だけでなく、管理部門や専門職でも「こうすれば現場の負担が激減するから、もっと攻められる」と提案できる人がいれば、起業家精神をもって働けると思います。あとはやはり「自分で現状を変えてやる」という意識がある人でしょうか。私自身、リクルート時代から理不尽さを感じたらすぐ行動してしまう性格で(笑)共感される方とはぜひお会いしたいですね。
ーー最後に、この記事を読んで興味を持った方へメッセージをお願いします。
「働く」を変えるというミッションに共感したら、気軽にコンタクトを取ってください。私たちが進めている事業やCVCの動き、グループ経営のリアルな部分も、いろいろお話できると思います。
“起業家精神”というと大きく聞こえるかもしれませんが、要は「疑問を持ったら動き出す」「自分の得意を磨いて周囲に貢献する」という姿勢です。誰だってその種は持っていますし、それを開花させる場所がイノベーションやグループ各社にあるなら、こんなに面白いことはない。私たちと一緒に、まずは一度話してみませんか? その一歩が「働く」を変える未来を、そしてあなた自身の未来を変えるきっかけになるかもしれません。
/assets/images/515210/original/94a08ec5-a702-43c7-89c9-aeb3c09dce5f?1538733802)
/assets/images/515210/original/94a08ec5-a702-43c7-89c9-aeb3c09dce5f?1538733802)



