“存在しない構造”を耕す組織
——まず、ALTURA Xはどんな会社なのでしょうか?
簡単に言うと、医療業界の中でも健診を起点に、業務やデータの非効率を解消するSaaSをつくっている会社です。でも、やっていること以上に「なぜやっているか」がこの会社の肝です。ALTURA Xは、今まだ社会に存在していない構造を、静かに、でも着実に耕していく会社です。
「インフラ」というと大げさに聞こえるかもしれませんが、ぼくらがやろうとしているのはまさにその“基盤”づくりです。
価値が乗る器、可能性が育つ土台。それは社会の裏側で静かに整っていくものであり、一度できれば、そこからいくつもの芽が生まれていく。
今は「ない」構造をつくるということは、言い換えれば「まだない選択肢を、人と社会に渡していく」ということでもあるんですよね。
でも正直、、、本当にもうダメかもしれないと思った瞬間があった。
2022年。藤田医科大学との共同開発の話が出たのが、2月の終わり頃でした。そこからまだ日本では実例のない国際標準規格HL7FHIRを活用したプロダクトを「2022年7月に出したい!」と急展開。仕様や要件も決まっておらず、日本での活用方法も事例がない状態であった。
その頃の僕は、
これまで医療業界にシステムやサービスを届けてきた経験を振り返りながら、こんな問いを抱えていた。
「このやり方で本当に医療や健康を通して世の中を変えられるのだろうか?」
医療業界特有の商慣習や制度の複雑さ。なぜ多くのスタートアップが医療領域でうまくいかないのか──そうした背景がようやく腑に落ちてきた時期でもありました。
それでも、藤田医科大学との共同研究のコアでもあったHL7FHIRを活用したデータ連携には、過去の海外経験から強い可能性を感じていました。さらに、健診領域から始めることに価値を見出していた藤田医科大学の存在も決断を後押ししてくれました。
「もしかしたら化けるかもしれない!海外での実例のように世の中の基盤を作れるかもしれない!」
そう信じて、夜な夜なリサーチやシミュレーションをしていた過去を今でも思い出します。

意思決定をしてからは怒涛でした。
日本では実例のない規格のキャッチアップはもちろんのこと、構造が複雑でパターンが無数にもある健診業務の詳細把握、さらには藤田医科大学が日本で一番病床数の多い医科大学でもあり、一番最初のお客様がエンタープライズでもありました。
しかしながら、我々はスタートアップです。どうなったら社会にインパクトを起こせるか?さらには上手く資本を活用できるか?を考える必要がありました。しかもキャッシュ(事業資金)が尽きる前に。
開発費用は当初の想定でも膨大で、毎月2,000万円ほどのキャッシュが必要な状態でした。どう見積もっても、開発期間は最短で1年半。初期投資だけでも、およそ3億円近くが必要であるとわかっていました。
正直言って、当初はすぐに資金調達できると思っていました。しかし、50社以上を超えるVCと面談し、最初は可能性を全くといっても見出してもらえなかったのも事実。
今思えば、これが大きな分岐点でした。
何度も壁打ちをしてもらい、どうすればこの資本主義社会で世の中にインパクトを起こせるか?を考え続けていましたが、どんどんキャッシュのタイムリミットが近づいてくる。毎日のように「これ以上は無理かもしれない」と思っていました。
それでも、開発はやめなかった。
藤田医科大学と一緒に取り組んでいるし、日本で初めて国際標準を見据えた構想と実現も進めている。
正直、やめようと思えばやめられた。けど、やめなかったんです。
なぜか根拠のない自信というか、、、社会が変わる!という無限大の可能性を感じていたんです。
そして2023年1月。約11ヶ月ほどの期間を経て資金調達も決まり、無事にALTURA Xを新たに立ち上げ、今の事業が確立した。
ずっと、投資をやめなかった。
普通はやめると思うんですよ。「できる範囲でやろう!」とか、「まずは目先の売上を安定させよう」とか。でも僕らは、そうしなかった。むしろ逆でした。
安定や成功が保証されていなくても、社会を変えるチャンスとその可能性に死にそうながらワクワクしていた(今でも思い返すとドキドキしますね 笑)。仲間と問いを立て続け、動き続け、学び続けた。その中で見えた、作り上げた今の基盤が、ALTURA Xの事業・組織そのものです。
ALTURA Xの原点は、“死ぬ一瞬まで、粘りきったこと”、“必ずやる!やれると信じたこと”にあると思います。どれだけ状況が厳しくても、簡単にやめない。自分たちが信じる「医療健康の未来」社会が変わる可能性に、向き合い続ける。
誰にでもできることじゃないと思っています。でもだからこそ、ハングリースピリッツが宿るALTURA Xという組織に意味があると思っています。

違和感が種になった原体験
—医療に向き合うようになったきっかけは何だったのでしょうか?
僕はもともと、スポーツトレーナー・セラピストとして国内外で活動していました。クリニックと提携したり、ストリートで施術したり、アスリートの子どもたちに関わったり。だけどどのような手段や技術を活用してもしても、うまくいくときといかないときがある。
その差は“構造”だと気づいたんです。関節の可動域、骨格、筋肉量、生活習慣。全部バラバラな人に同じアプローチは効かない。だからこそ定量的に前提条件を整理し、分析して、その人に合った手法を見つける必要があると思った。
医療データや身体のデータに着目している中で、海外と日本の医療IT、特にデータ基盤のギャップに衝撃を受けました。日本では、健康データが個人に帰属せず、情報もバラバラで活用されていない。「これは現場じゃなくて、社会の構造を変えないと無理だ」と感じたんです。
また同じようなタイミングで、「自分の人生を何に使うか」を考えるようになりました。目の前の人を救うだけでは、社会は変わらない。だからフリーランスを辞めて、ALTURA Xの前身となる組織を立ち上げたんです。
一見バラバラに見える出来事も、あとから振り返ると1本の線でつながっていた。ALTURA Xは、その延長線上にあるように感じています。
なぜ健診から始めるのか?
——現在は健診領域を中心にサービスを展開されていますが、それはなぜでしょう?
健康診断は体調に異常がない方でも自分自身の身体を見える化できる、医療との“はじまりの接点”です。
ところが、健康診断データは個人のもの(もっというと資産になるべき)であるはずなのに、現在はその活用が極めて限定的です。診療情報は病院間で共有されつつある一方で、健康診断データは紙で結果が返ってくる文化や制度、仕組み、デジタル化へのハードルがまだまだ残っており、自由に活用ができる状態にはなっていません。
転職や退職を経験した方、あるいは学生時代の健康診断データを思い出してみてください。ほとんどの人が手元に残っていないはずです。
僕らがまず取り組むのは、そうした「健康診断にまつわる業務」の徹底的な構造改善と、健康診断データの個人への帰属・活用です。個人が自分の健康診断データを保有し、必要なときに共有、活用できる状態になれば、不要な再検査の重複を無くし医療費を適正化。さらには放射線被ばくを減らしたりと、個人と社会の両方に大きなメリットが生まれます。
健診の仕組みを変えることは、医療健康データの流動性を高め、日本の医療構造全体のアップデートにもつながる。
だからこそ、ALTURA Xは「健診」という“入り口”から、社会の仕組みに本気で挑んでいます。
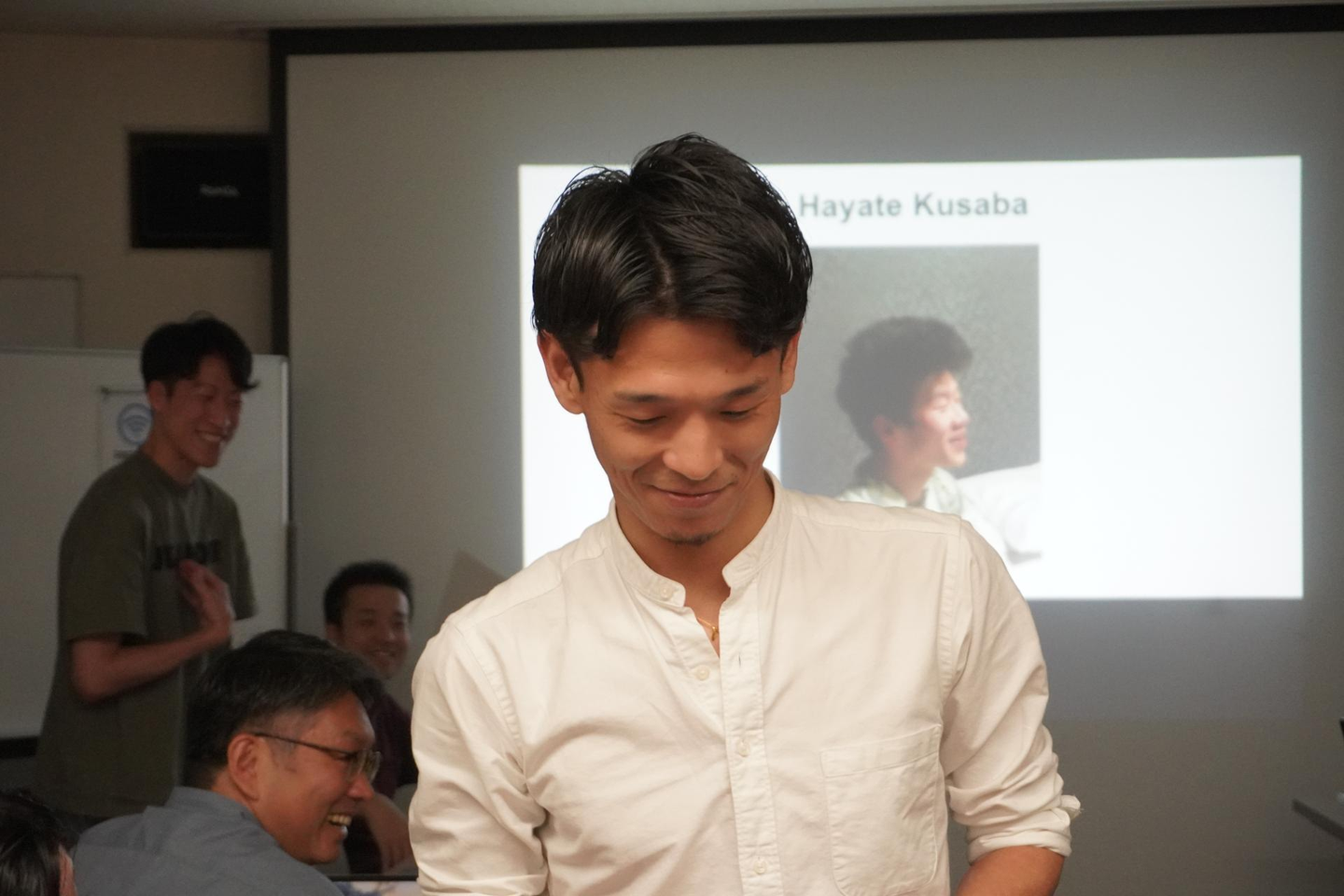
「スタートアップ」の定義が、少し違う
——ALTURA Xが考える“スタートアップらしさ”とは?
よく世の中でイメージされている「自由でフラットでエモい」みたいなスタートアップ像と、ぼくらは少し距離を取っています。
「スタートアップは資本をフル活用して、世の中をより良くすることに没頭している・楽しんでいる人たちの集合体。」
だと考えているからです。
なので、組織カルチャーや組織内部の定義というよりも、「誰の・何の課題を解決するのか」「その結果、社会がどう変わり良くしていくのか?」の定義の方が重要で、、、
本当に社会を変えようとするなら、本当に勝てる仕組み・環境を作らないといけない。構造を把握し、見える化、さらにはきちんと役割に責任を持つ。そのうえでの自由や柔らかさじゃないと、続いていかないんですよね。
「熱量に任せて突き進むだけでは、本当に社会を変えることはできないと考えています。だからこそALTURA Xは、構造にメスを入れていくための“冷静さ”と“責任”を持ったチームでありたいと考えています。」
正解を提示しない組織・正解を共に創っていく組織でありたい
——御社の組織やカルチャーについても教えてください。
ALTURA Xは、社会を良くするために、目の前の人々を良くするために「自分の頭で考えて、自分の言葉で問いを立てられる人」が集まる組織にしたいと思っています。
つまり、「組織としての正解」をあえて強固に作らず、向かう方向性だけを明確に定めているようなイメージです。
「XXXを目指すためには、今の現状だと◾️◾️が最重要で、まずは△△を確実に達成しながら、〇〇はあえてしないのもいいのではないか?だけど、▶︎▶︎は今から種植えしよう!」みたいな。
僕らは、「ALTURA Xは〇〇です」と組織が一方的に定義するのではなく、その“〇〇”を関わる一人ひとりが自由に見つけていいと思っています。
そして、その〇〇が根づき、育っていけるような地盤や気流を整えること、それがALTURA Xとしての存在意義です。
もちろん、確固たる方針やミッション、ルールはあります。でも、「自分がこの組織に対してどう関わるか」「どういう構造を耕したいか」は、自分で決めてほしいし、決められる場にしたい。
だからこそ、いろんな解釈が共存できるように、余白を残したいんですよね。

しなやかに・したたかに・どこまでも高みを目指し続ける
——最後に、これからALTURA Xで実現したいことを教えてください。
僕が大切にしていることは
「しなやかに・したたかに・どこまでも高みを目指し続ける基盤や環境」を創る
ことです。
誰かが、自分なりの問いを持ったとき。まだ社会にはない仕組みをつくろうとしたとき。ALTURA Xが、その人の根を支える「地盤」としてありたいと思っています。
ぼくらがやっていることって、すぐに華やかな成果が出るような仕事じゃないんです。でも、確実に社会の何かを変えていく。そんな「名前のない未来」の、少し手前を耕していくのが、ぼくらの役割なんじゃないかなって思っています。
プロダクトは変わるし、サービスの形も進化していくかもしれない。でも、構造を支える基盤を創る本質的な仕組みや創り方は同じ。
ALTURA Xは、100年後の社会にも必要とされる“地盤づくり”の会社でありたいと思っています。
そのために、いまからちゃんと種をまいて、研究開発に投資して、長く耕し続けられるような設計をしていきたいです。



/assets/images/21018083/original/6c21fddb-2608-4ff9-9bc8-302577204839?1746058152)


/assets/images/21018083/original/6c21fddb-2608-4ff9-9bc8-302577204839?1746058152)



/assets/images/21870659/original/6c21fddb-2608-4ff9-9bc8-302577204839?1755762595)

