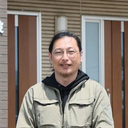みなさんはじめまして!
北海道の浦河で「神馬建設」という工務店の社長をしている神馬充匡(じんば みつまさ)です!
【プロフィール】
代表取締役6年目になる、今年47歳。 学生時代から17年間土木を学んだ後、 実家の工務店にもどり、建築14年目を迎える三代目です。 やらない後悔より、やって後悔。 一度きりの人生。楽しくやりきろうって思っています。
「就職氷河期って結局、ただの不景気でしょ?」
「リーマンショックのときだって、みんな大変だったじゃん?」
そんな風に思っている方も多いかもしれません。
でも実は、「就職氷河期」が社会に与えた影響は、単なる不況の一言では片づけられない、深くて長い爪痕を残しているんです。
この言葉が指すのは、1990年代から2000年代前半にかけて、新卒で社会に出ようとした若者たちが、異常なまでの採用難に直面した時代のこと。
「仕事がない」のではなく、「新卒でなければ雇わない」という日本独特の仕組みの中で、チャンスを完全に閉ざされた世代がいたのです。
そしてその影響は今も続いています。
正社員として働く機会を失い、非正規雇用や無業状態から抜け出せないまま中年を迎えている人も多く、まさに社会構造そのものに深い影を落とした世代。
本記事では、
- なぜ就職氷河期は起こったのか
- リーマンショックとどう違うのか
- そして私たちがこの歴史から何を学ぶべきなのか
を、わかりやすく解説していきます。
一人ひとりがこの背景を知ることで、「あの世代は甘えてるんじゃないの?」という誤解も、少しずつ解けていくはずです。
第1章:そもそも「就職氷河期」とは?

いつのこと?(主に1993年〜2005年)
「就職氷河期」とは、1993年から2005年ごろまでの長期にわたる就職難の時代を指します。
この期間に大学・高校などを卒業し、社会に出ようとした若者たちは、極端な採用縮小の波に直面しました。
景気の悪化により企業が新卒採用を大幅に控えたため、「卒業しても就職できない」という状態が続きました。特に1997年のアジア通貨危機以降は、採用数がさらに絞られ、若年層の多くが就職先を見つけられずに社会に取り残されたのです。
「就職できない時代」と言われる理由
「就職氷河期」が特別に深刻だった理由は、単に不景気だったからではありません。
根本的な原因は、日本社会に深く根付いた「新卒一括採用」という仕組みにあります。
この仕組みでは、「新卒での就職」こそが正社員への唯一の入り口であり、一度そのチャンスを逃すと、正社員としてのキャリアに戻ることが極めて難しくなります。
つまり、景気が回復した後であっても、一度「新卒切符」を失った人たちは、採用対象として見なされにくくなってしまうのです。
これが、他の景気後退期とは一線を画す「構造的な問題」として、就職氷河期をより深刻なものにしているポイントです。
「新卒一括採用」の日本特有の仕組みと影響
日本の企業文化では、長期雇用を前提とした「ポテンシャル採用(将来性重視)」が主流であり、育成前提の新卒採用に集中しています。
そのため、中途採用は即戦力が前提であり、「スキルのない若者」は対象外になりがちです。
つまり、新卒で就職できなかった若者は、その後どれだけ努力しても、企業にとっては「経験不足な中途」として評価されにくく、正社員の座が遠のいてしまうのです。
結果として、多くの人が非正規雇用に流れ、低収入やキャリア不安定のスパイラルに陥りました。
これは、単なる「一時的な不況」ではなく、日本の雇用慣行がもたらした“社会的排除”とも言えます。
コア世代(1970年代後半〜1980年代前半生まれ)
就職氷河期世代の中でも、特に深刻な影響を受けたのが1975年〜1985年ごろに生まれた「コア世代」です。
この世代は、大学卒業時に超売り手市場から一転、企業の採用抑制のピークに直撃されました。
さらに、正社員経験がないまま30代、40代を迎えた人も多く、現在でも生活基盤が不安定なまま、再チャレンジの機会が与えられにくい状況にあります。
第2章:就職氷河期はなぜ起こったのか?

「就職氷河期」は、単なる一時的な不況ではありませんでした。いくつもの要因が重なり、構造的かつ長期的な問題として社会全体に深刻な影響を及ぼしました。ここでは、主な原因を4つに分けて解説します。
バブル経済の崩壊(1991年〜)
就職氷河期の発端は、1991年の「バブル経済崩壊」にあります。
1980年代後半、日本は空前の好景気に沸き、不動産や株式などの資産価格が高騰。しかし、それは実体経済とはかけ離れた“虚構の成長”であり、1991年に崩壊を迎えます。
バブル崩壊後、企業の業績は急速に悪化し、リストラや人員削減が進みました。新卒採用も大幅に縮小され、学生たちにとって極めて厳しい就職環境が始まったのです。
企業の採用抑制と新卒至上主義
バブル崩壊後、多くの企業が「守り」に入り、採用数を削減しました。特に若年層の雇用が大きく削られ、「就職先がない」「面接すら受けられない」状況が広がりました。
一方で、日本企業には「新卒一括採用」が根強く残っており、「既卒=評価対象外」という風潮が一般的でした。そのため、卒業時に就職できなかった人は、翌年以降も正社員として採用されにくい構造になっていたのです。
これは「第二新卒」や「既卒」に対する評価基準が不明確だったことも拍車をかけています。結果として、多くの若者が“最初のレール”に乗れず、長期的なキャリア形成に苦しむことになりました。
経済全体の長期停滞(失われた10年)
1990年代の日本は、いわゆる「失われた10年」と呼ばれる経済停滞の時代でした。
金融機関の不良債権問題や、デフレ傾向が続き、企業の投資意欲も冷え込んでいました。雇用を拡大する余裕のない企業が多く、結果的に新卒採用は低迷し続けました。
2000年代に入っても状況は大きく改善せず、就職氷河期は10年以上続く長期的な問題へと発展しました。
構造的な雇用制度の問題
日本特有の「年功序列」や「終身雇用」も、就職氷河期を長引かせた要因の一つです。これらの制度のもとでは、「途中から入ってくる人」よりも、「最初から会社にいる人」が優遇されやすく、転職市場や中途採用の流動性が極めて低くなります。
また、正社員と非正規雇用との待遇格差も顕著であり、一度非正規に入ってしまうと、正社員への道が閉ざされるケースも多くありました。
このように、雇用制度の硬直性が、氷河期世代の“再チャレンジ”を困難にし、社会的な孤立や経済的困窮を生み出していったのです。
第3章:リーマンショックとの違いとは?

「就職氷河期」と「リーマンショック」は、どちらも日本の雇用や経済に深刻な打撃を与えましたが、その発生原因・影響対象・回復過程は大きく異なります。この章では、それぞれの特徴を比較しながら、なぜ「就職氷河期」の方が長期的・深刻な問題となったのかを解説します。
リーマンショックとは何だったのか?(2008年)
リーマンショックとは、2008年9月にアメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻したことをきっかけに、世界的な金融危機へと発展した出来事です。株式市場は暴落し、世界中の金融機関や企業が連鎖的にダメージを受けました。
日本でも、輸出産業を中心に大きな打撃を受け、多くの企業が派遣社員や契約社員の契約を打ち切り、雇用不安が一気に拡大しました。
就職氷河期との主な違い
発生時期と期間
- 就職氷河期:1993年頃から2005年頃まで、約10年以上にわたって続いた長期的な現象。
- リーマンショック:2008年に発生し、その後2~3年で一定の経済回復が見られた短期的な影響。
就職氷河期は「慢性的な採用抑制」によって長期間続いたのに対し、リーマンショックは突発的な金融危機による「一時的な雇用ショック」と言えます。
影響を受けた雇用層の違い
- 就職氷河期:最も打撃を受けたのは「新卒者」。特に、大学・高校卒業時に職に就けなかったことで、その後のキャリア形成に大きな支障が生じました。
- リーマンショック:主に影響を受けたのは「中途採用者」や「非正規雇用者」。派遣切りや雇止めといった形で雇用が不安定化しましたが、新卒採用そのものは完全に止まることはありませんでした。
回復スピードの違い
- 就職氷河期:10年以上にわたる長期的な影響が続き、多くの人がキャリアのスタートを失い、その後も挽回する機会に恵まれませんでした。
- リーマンショック:金融政策や景気刺激策などにより、比較的早期に経済回復が進み、企業の採用も徐々に戻りました。
被害世代の年齢層とキャリアへの影響
- 就職氷河期世代:1970年代後半〜1980年代前半生まれの「キャリア初期段階」で打撃を受けた層。職歴が乏しく、非正規雇用を転々とする中で、現在も生活が不安定な人が多くいます。
- リーマン世代:30〜40代の働き盛りの層が主に影響を受けましたが、すでにある程度の職歴やスキルを持っていたため、比較的早く再就職できた人も多いのが特徴です。
第4章:就職氷河期が残した社会的な影響

「就職できなかった」という一点が、人生全体にこれほど大きな影響を与えることがあるのか——。
就職氷河期世代が背負った課題は、単なる“就職の失敗”にとどまりません。ここでは、その後の社会全体にどのような影響を及ぼしたのかを見ていきます。
非正規雇用の拡大とキャリアの断絶
就職氷河期世代の多くは、当初から正社員の門戸が狭く、非正規雇用を選ばざるを得ませんでした。
しかし、非正規の仕事はスキルの蓄積やキャリア形成の機会が限られており、その後の「正社員転換」が困難な構造にありました。
その結果、仕事を通じた自己実現や昇進、転職などの道が閉ざされ、「働いているのに将来が見えない」状態に。
さらに、年齢が上がるにつれて企業側の「即戦力志向」が強まり、ますます正社員への転職が難しくなるという悪循環が生まれました。
結婚・出産などライフイベントの遅れ
安定した職と収入が得られないことは、人生設計そのものにも影を落とします。
特に大きいのが、結婚や出産といったライフイベントの遅れや断念です。
経済的な余裕がない中で結婚に踏み切れず、出産や育児のタイミングも先延ばしになる人が続出しました。
その結果、未婚率の上昇や出生数の減少にもつながり、社会全体としての少子化が加速しています。
社会的孤立や貧困
非正規雇用による経済的困難、職場での疎外感、将来への不安。
それらが重なり、孤立感や自己否定感を強く抱く人も少なくありません。
また、年齢を重ねる中で再挑戦のチャンスも減り、「自分にはもう無理だ」と諦めてしまう人が多いのも現実です。
このような背景から、引きこもりや生活困窮、貧困状態に陥る人も一定数存在しており、自治体や社会福祉が介入しなければならないケースも出ています。
日本全体の生産性や少子高齢化への影響
就職氷河期世代は、もっとも働き盛りとなるはずの世代です。
しかし、キャリア形成が妨げられたことで、本来持っていたはずの力を社会に十分に還元できなかったという側面もあります。
その結果、日本全体の生産性向上の足かせとなり、労働力不足・経済成長の鈍化に影響していると見る専門家もいます。
さらに、この世代の結婚・出産の遅れや断念が少子化を加速させ、将来的な社会保障制度への圧力も強まっています。
第5章:就職氷河期から何を学ぶべきか?

就職氷河期は単なる「時代の運」ではなく、社会全体の構造的な問題が重なった結果として起こった現象です。
ここでは、あの時代から現代社会が学ぶべき教訓を整理し、今後同じ過ちを繰り返さないための視点を提案します。
同じ過ちを繰り返さないために
就職氷河期世代の多くが「個人の努力ではどうにもならない壁」に直面しました。
つまり、努力や能力以前に、制度そのものが人を受け入れる準備がなかったのです。
景気後退や企業の採用控えは、いつの時代も起こり得ます。
その時、再び「若者が社会に出られない構造」が出来上がってしまわないように、制度や企業のあり方を問い直す必要があります。
多様な採用形態・中途採用の整備
最大の課題は、新卒一括採用に依存しすぎた日本の採用文化です。
新卒でレールを外れると、再起のチャンスが極端に少なくなる社会構造では、柔軟なキャリア設計はできません。
これからの時代は、以下のような改革が求められます:
- 中途採用の拡充:年齢や過去の経歴に関係なく、スキルや適性で評価する採用制度
- 通年採用・ポテンシャル採用:一時的な就職失敗で人生が決まらない設計
- ジョブ型雇用の推進:職務とスキルに基づいた配置転換と評価制度の導入
キャリア形成の柔軟性
人生100年時代、キャリアは一度決めたら終わりではありません。
複数の職を経験したり、途中で学び直したりすることを前提とした**「柔軟なキャリア構築」**が重要です。
そのためには:
- リスキリング(学び直し)制度の整備
- 社会人向け教育・資格取得支援の拡充
- 副業・パラレルワークの容認・推奨
といった柔軟な働き方を支えるインフラが必要です。
政策的支援と企業の姿勢
最後に忘れてはならないのが、「制度をつくる側」の責任です。
政府や企業は、氷河期世代のような“取り残された人”を出さないよう、以下のような取り組みを加速すべきです。
- セーフティネットの拡充(職業訓練、失業給付、再就職支援など)
- 公的機関と民間企業の連携支援
- 企業に対する雇用促進インセンティブの強化
そして、企業側も「即戦力」ばかりを求めず、未経験者を育てる土壌づくりが社会的責任として問われています。
第6章:浦河で「自分らしい生き方」を見つける。神馬建設のサポート体制とは?
ということでここまでは、就職氷河期やリーマンショックの話をしてきましたが、この記事を読んでくださっている方の中には、実際に就職氷河期にあたる方がいるかも知れません。(私もその世代です。)
そんな方へ向けたメッセージを、ここでお話しさせてください。
「働くこと」と「生きること」。どちらか一方を優先するのではなく、どちらも大切にしながら自分らしい暮らしを実現する。そんな理想を、浦河で叶えるために、神馬建設は“あなたに合った働き方”を用意しています。
「田舎でエッセンシャルワーカーとして働く」という選択肢を考えるなら、仕事だけでなく、その人自身の生き方に寄り添うことも大切です。そこで今回は、神馬建設がどのように社員一人ひとりの生き方をサポートしているのかについてお伝えします。
4-1. 3つの働き方から、自分に合うスタイルを選べる

私たちは、一人ひとりが理想のライフスタイルを実現できるように、3つの働き方を用意しています。
- もっともっと成長コース
仕事を通して自らの成長を最優先に考えたい人を対象にしています。仕事における目標設定のウエイトを少し高くしています。 - 着実コース
仕事を着実にこなしながらも、プライベートも充実させたいと考える方を対象にしています。ワークライフバランスのとれた生活スタイルを望む方にふさわしいコースです。 - ゆっくりコース
自らの人生を豊かにするために、仕事に必要な能力を着実に高め、他者や会社の役に立ちたいと望む方に最適なコースです。
私たちは、ただ働く場所を提供するだけではなく、一人ひとりのライフスタイルに寄り添った働き方をサポートします。就労時間の柔軟性もその一つ。ライフステージに応じた働き方の変更も可能です。
4-2. 就労時間が比較的短くライフ重視の生活が可能

また、勤務時間も非常に特徴的で、比較的就労時間が短く残業もないので、プライベートや休息の時間もゆっくり取ってもらえるようになっています。
▼(4/1〜9/30)
勤務時間:7:45〜17:00(実働:6.75時間)
休憩時間(2時間)
am 10:00~10:30
pm 12:00~13:00
pm 15:00~15:30
▼(10/1〜3/31)
勤務時間:7:45〜16:30(実働:6.75時間)
休憩時間(1.5時間)
am 10:00~10:30
pm 12:00~13:00
4-3. あなたの人生に寄り添う、柔軟な福利厚生制度

働く上で欠かせないのが、「ライフイベントに寄り添う制度」です。たとえば、一般的な育児休暇に加え、次のような柔軟な休暇制度を取り入れることを考えています。
①介護休暇
親の介護が必要になったとき、仕事との両立は容易ではありません。だからこそ、介護と仕事を両立できる仕組みを整備し、サポートしていきます。
②パートナーケア休暇
もし大切な人が病気になったら——
例えば、パートナーが癌を患い、支えが必要になったとき。
そんなときに、「一緒にいる時間を確保できる制度」があればどうでしょうか?単なる「仕事の休み」ではなく、大切な人のために使える時間をつくる。私たちは、そんなサポートを企業として提供していきたいと考えています。
その他福利厚生の面に関しては、下記の記事でもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
5.浦河の魅力──小さな幸せと、消えゆく日本の四季を感じる暮らし
都会には、物質的な豊かさが揃っています。高層ビルが立ち並び、どこへ行ってもコンビニやスーパーがあり、少し歩けばスターバックスやおしゃれなカフェが見つかる。
一方で、浦河のような田舎には、そういった便利な環境はありません。最寄りのスターバックスまで車で2時間。札幌までは、移動に4時間かかる。
でも、そんな浦河だからこそ、都会では決して味わえない魅力が詰まっています。今回は、浦河での暮らしを豊かにする2つの大きなポイントをご紹介します。
5-1. 小さな幸せをたくさん感じられる場所

浦河には、最新の商業施設や派手な娯楽施設はありません。
しかし、その代わりに、何気ない日常の中に溢れる小さな幸せがあります。
たとえば、
- 車で1時間走れば、まだ人間の手が入っていない大自然が広がる。
- 「こんな花がこの時期に咲くんだ」と、季節の移ろいを肌で感じる。
- 「こんな鳥がいるんだな」と、今まで見たことのない野生動物に出会う。
都会にいると、どうしても日々の忙しさに追われて、こういったささやかな発見に気づくことが難しいものです。浦河では、自然の中に身を置くことで、五感が研ぎ澄まされ、心が豊かになる瞬間を何度も味わえます。
5-2. 日本から消えゆく四季を、間近で感じられる
地球温暖化の影響で、日本の四季は徐々に変わりつつあります。
都市部では、春と秋が短くなり、冬の寒さも昔ほど厳しくありません。
しかし、浦河には、まだはっきりとした「四季」が残っています。
春──生命が芽吹く季節

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
浦河の春は、桜が咲き乱れ、子馬たちが立ち上がる美しい季節。
まだ冷たい空気の中で、新しい命が次々と生まれ、
「春が来た」と実感することができます。
夏──爽やかな風が吹く季節

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
都会の夏は蒸し暑く、エアコンが欠かせませんが、
浦河の夏は、海辺に昆布が干され、涼しい風が吹く過ごしやすい季節。
汗をかくほどの暑さが少なく、自然の風が心地よく感じられます。
秋──色彩が変わる季節

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
木々が燃えるように紅く色づき、
鮭が川を上る姿を見ることができる浦河の秋。
ただの景色ではなく、生き物たちの営みの中で季節が巡ることを実感できます。
冬──静かで穏やかな季節

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
本州のような豪雪地帯とは違い、浦河の冬は雪が少なく、穏やか。
しかし、海辺ではオオワシやオジロワシが羽を広げる姿が見られ、
冬の厳しさの中にも、生命の力強さを感じられる特別な季節です。
5-3. 都会にはない、浦河ならではの豊かさ

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
「物がたくさんあること=豊かさ」ではない。浦河の暮らしは、そう気づかせてくれます。
日々の何気ない発見、季節の変化をじっくり味わう時間、都会では気づかなかった小さな幸せが、ここにはたくさんあります。
「浦河での暮らし、ちょっと気になるかも…」
そう思ったら、一度訪れてみてください。きっと、都会では味わえない「本当の豊かさ」に出会えるはずです。
【まとめ】

「就職氷河期」は、単なる一時的な景気悪化ではなく、日本特有の「新卒一括採用」や「終身雇用」といった雇用制度の硬直性が大きな原因でした。
その結果、当時の若者たちは長期間にわたり不安定な雇用とキャリアの断絶に苦しむこととなりました。
一方で、「リーマンショック」は金融危機による突発的な経済ショックであり、主に中途採用層や非正規雇用者に大きな打撃を与えたもの。影響の範囲や回復スピードは、就職氷河期とは明確に異なります。
私たちがこの歴史から学ぶべきことは、「一度社会から外れた人を救う手段が十分でなかった」という事実です。
今後は、柔軟な採用制度、キャリアの再構築支援、そして何度でも挑戦できる社会の設計が必要です。
就職氷河期の教訓を、未来の働き方と雇用制度に活かしていくことこそが、次の世代への責任だといえるでしょう。


/assets/images/4861760/original/28144748-d770-45d9-bc7a-c44efc7f127e?1586147985)
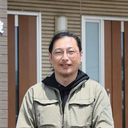
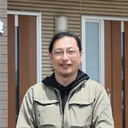
/assets/images/4861760/original/28144748-d770-45d9-bc7a-c44efc7f127e?1586147985)
/assets/images/4861760/original/28144748-d770-45d9-bc7a-c44efc7f127e?1586147985)