2025年に入社し、現在、統括責任者として活躍中の中島 海夢さんにインタビューしました。
統括責任者 中島 海夢さん
ホテル業、サービス業の経験を経て、リーフラス株式会社に入社を決める。現在は、担当する小学校4校の統括責任者として、部活動の運営を担っている。
「なぜ、この道を選んだのか」- 現在に至るまでのパーソナルストーリーを教えてください。
「子どもと関わる仕事がしたい」
それは、ずっと心のどこかにあった想いでした。
でも、現実はそう甘くなかったんです。
前職はホテル業。サービス業として人と接する楽しさはありましたが、「このままでいいのかな」と、ふと立ち止まることもありました。
教員免許を取ろうか、保育の道を目指そうか、そう考えたこともありましたが、時間もお金もかかる。気づけば、また一歩を踏み出せずにいました。
そんなときに出会ったのが、リーフラスでした。
「資格がなくても、子どもと向き合える場所がある」
そう知った瞬間、心がパッと明るくなったのを覚えています。
ただ「関わる」だけじゃない。
日々、子どもたちの変化や成長を感じられる。悩んでいる姿、笑っている顔、少しずつ前に進んでいく背中。
そんな瞬間に立ち会えることが、自分にとってどれだけ嬉しく、やりがいになっているかは、言葉にしきれません。
自分の「好き」が、誰かの「成長」に繋がっている
今はそんな日々を過ごしています。
もし、あなたにも「本当はこうしたかった」という気持ちがあるなら。
それを一歩、形にできる場所がここにあります。
「“部活動の未来”を創る」- 事業のやりがいについて教えてください。

入社してまだ間もないのですが、毎日が発見と学びの連続です。
子どもとどう接するか、大人の方とどう信頼関係を築くか、そして目の前の子どもが今、何を求めているのか。
そんなことを常に考えながら、悩んだり、試してみたり、失敗したり…まさに試行錯誤の日々です。
でも、そうやって少しずつ距離が縮まって、やっと心を開いてくれた瞬間や、笑顔を見せてくれたときの喜びは、何にも代えがたいものがあります。
「やっと向き合えた」と感じるその一瞬に、やりがいがギュッと詰まっているんです。
まだまだこれから、きっといろんな壁にぶつかると思います。
でも、その壁を乗り越えることで、自分自身も確実に成長できるし、子どもたちの未来にも何かしらのプラスを与えられる。
そう思うと、これからが本当に楽しみでなりません。
「子どもたちの笑顔のために、自分も前に進む」
そんな日々にやりがいを感じています。
「“未経験からプロ”へ」- 入社後のリアルと成長環境について教えてください。

子どもって、一人ひとり全く違うんですよね。
当たり前のようで、実はすごく深いことだなと日々感じています。
同じように話しかけても、笑ってくれる子もいれば、黙ってしまう子もいる。
だからこそ、「ただコミュニケーションを取る」だけでは足りません。
今、この子はどんな気持ちなんだろう?何を感じて、何を伝えたいんだろう?
言葉にできない思いやサインを、こちらが汲み取ろうとする姿勢が本当に大切なんだと実感しています。
でもそれって簡単なことではなくて、一人ひとりの個性を理解し、大切にするには時間も根気も必要です。
正直、大変だと感じることもあります。
それでも、「この子のこと、ちょっとわかってきたかも」と思える瞬間があると、それまでの苦労が全部報われるような気がするんです。
だからこそ、これからもっと子どもたちを理解できるよう、自分の関わり方も深めていきたい。
そのために必要な努力は、惜しまないつもりです。
「今後のビジョン」‐これからやりたいことについて教えてください。

将来的には、名古屋市だけでなく、自分の地元を含め、もっと多くの地域にリーフラスの活動を広げていきたいと考えています。
私は愛知県の岡崎市で育ちました。学生時代、部活動の指導は学校の先生方が行ってくださっていて、限られた時間や環境の中で、私たち生徒のために本当に一生懸命取り組んでくれていたことを今でも覚えています。
ただ、先生方は授業や校務なども抱えている中で、すべての競技に精通するのはとても難しいことだとも感じていました。
だからこそ、専門的な経験や知識を持つ指導者が学校外から関わることで、先生方の想いをさらに後押しできるのではないか。
そして子どもたち一人ひとりの可能性を、もっと広げることができるのではないか、そう思うようになりました。
リーフラスには、子どもたちの「ココロに体力を。」という指導理念があります。
ただ競技の技術を教えるだけでなく、その子の個性に寄り添い、心の成長を支える。そんな関わりが、これからの教育の新しい選択肢になっていくと信じています。
私自身、まずは今目の前にいる子どもたちと丁寧に向き合いながら、経験を積み、視野を広げていきたい。そしていつか、自分の地元を含むさまざまな地域で、子どもたちがもっとのびのびと成長できる場をつくっていくのが、私の目標です。
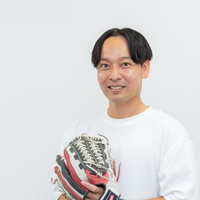
/assets/images/21544578/original/94d1112e-25f9-4e34-b73d-3fc390714bf2?1752035238)




