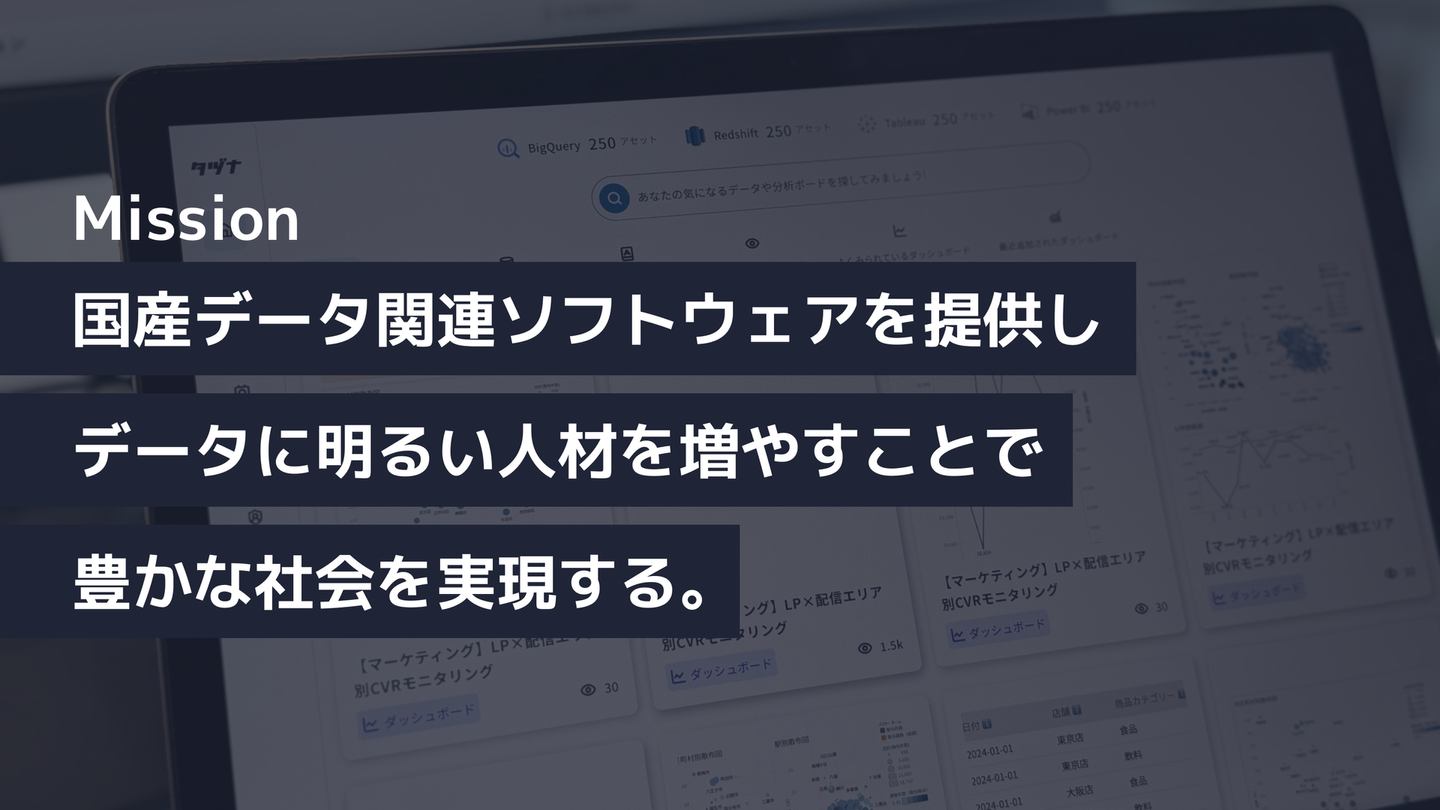未上場企業である私たちがコーポレートサイトにIRコンテンツを作成する理由 | 株式会社パタンナー
みなさんと信頼を育んでいくためにこんにちは。株式会社パタンナーです。弊社代表の深野は、会社を設立してからずっと「ひとり全社会議」という取り組みを続けてきました。会社を立ち上げたばかりの頃、深野が...
https://www.wantedly.com/companies/company_3237417/post_articles/956604
株式会社パタンナーの創業者である深野になぜ創業したのか。その前後にどんなことがあったのか。自社プロダクトのデータカタログ「タヅナ」を作るまでのストーリーを聞いてみました!
◼︎代表の深野について
北海道札幌市出身。
大学卒業後、船井総合研究所に新卒入社。経営コンサルタントとして業務に従事。エムスリーキャリアにてWebエンジニアの実務経験を経て、AIベンチャーにてデータサイエンス業務に従事。
国内大手企業のAI開発・分析基盤構築・データ分析組織構築などのプロジェクトに携わる。社内データサイエンティストを1名から12名まで拡大。執行役員、開発部マネージャを経験し独立。
2021年3月にパタンナーを創業。
最初の独立のときは、「このまま会社員のまま年を取っていく自分が想像できなかった」というのが大きな理由です。
当時はコンサルタントとして非常に多忙な日々を送っていて、プライベートの時間を取ることも難しい状況でした。同期の中には最年少でマネージャーに昇進するような人もいて、自分も知らず知らずのうちに出世競争に巻き込まれていたと思います。ただ、その働き方を続けていく中で、「もし家族や身近な人に何かあったとき、自分の意志で柔軟に動けないのはつらいな」と感じるようになりました。
そうした違和感が積み重なり、もっと自分らしく働ける道を模索したくなったのが、独立を考えるきっかけになりました。
その後、赤坂見附にあったYahoo! JAPANのコワーキングスペースで、起業予定だった仲間と一緒にプログラミングをしながら準備を進めていました。
勢いで会社を立ち上げたものの、資金がすぐに枯渇してしまい……やむを得ず、いったんは解散することになりました。
最初は、自分がよく関わっていた「データ戦略部(いわゆる“デー戦”)」の現場で使えそうなツールを開発したのですが、今振り返ると、自分の作りたいものを先行させてしまい、マーケットのニーズや製品のポジショニングをきちんと見定めずに進めてしまっていました。
結果として、製品カテゴリが曖昧で、誰のどんな課題を解決するものなのかが明確に伝わらず、まったく売れませんでした。その反省をもとに、
「自分が本当に作りたいものは何か」「市場に求められているのはどんなプロダクトか」
をゼロから見直しました。
そこで気づいたのが、自分の構想していたものは、すでに「データカタログ」という明確なカテゴリに存在しているということです。さらに、既存のデータカタログ製品を調査・比較してみると、ほとんどが海外製で、日本の企業にとっては使いにくいものが多かった。それなら、「日本の企業にフィットするものを、自分の手で作ろう」と決めました。
その背景には、これまで自分がWebアプリケーション開発に実際に携わってきたことや、スタートアップでプロダクトマネージャーとして仕様設計・機能定義・UI設計などを担ってきた経験があります。
つまり、ビジネス側と開発側の両方を理解した上で、プロダクト全体を“設計できる力”があるのが、自分の強みだと思っています。だからこそ、タヅナでは「現場で本当に使いやすいこと」を前提に、細かい設計や体験設計にもこだわって作り込んでいます。
実務に根ざしたプロダクトであることが、結果的に「使ってみて違いがわかるプロダクト」につながっていると思います。
けれどその一方で、現場では「どのデータを信じればいいのか分からない」という声が、今もなお飛び交っています。私自身、エンジニアとビジネス職の間に立ってデータマネジメントをしていた経験があります。
誰かが作ったExcel、更新されていないダッシュボード、担当者不明のテーブル定義……。現場の混乱やモヤモヤを、何度も目の当たりにしてきました。そんなときにいつも思うんです。
「もしここに、信頼できる“たったひとつの情報源”があれば、どれだけ多くの人が救われるだろう」
って。
AIの進化で、私たちは“人がルールを書く”時代から、“データがルールを生む”時代へと突入しました。
つまり、良い判断は、良いデータからしか生まれない。
どれだけ高度なモデルやアルゴリズムを用いても、元になるデータが曖昧だったり信頼できなければ、その判断には自信が持てません。加えて、今の現場では、データを活用しようと挑戦している人ほど、リスクの矢面に立たされています。営業やマーケ、企画の現場で、スピードを求められる中で手探りでデータを使っている。彼らは「信じていいデータが欲しい」だけなんです。だからこそ、挑戦する人たちを“仕組み”で守りたい。それが、僕がデータカタログ「タヅナ」をつくった理由です。
データカタログは、単なる業務効率化ツールではありません。
「この数字は大丈夫」「そのデータはこういう背景がある」――そう言える状態をつくることが、企業全体の自信になる。今後ますます、AIが意思決定に関わる時代になっていきます。けれど、何が正しいかを判断し、説明責任を果たすのは、やはり“人”の仕事です。間違ったデータが使われれば、たとえ悪意がなくても誰かが傷つくかもしれない。
Googleや大企業で起きたデータやAIに関するトラブルや事件も、そのほとんどが「挑戦しようとした人たち」が責められてしまう構図でした。だから僕は、「人を責めるんじゃなくて、仕組みで守るべき」だと考えています。タヅナは、挑戦する人たちの“安心の土台”になる存在です。
データの正しさを保証し、活用のスピードと安全性を両立させる。それが、僕たちが信じている“データ活用の理想のかたち”です。信じられるデータがあるだけで、人はもっと自由になれる。
だから私は、今もタヅナを企業でがんばる人たちを支える「最高の仕組み」になることを目指してメンバーとともに開発し続けています。
正直、ユーザーの立場で言えば、どこの国で作られたソフトウェアかどうかよりも、「自分にとって使いやすいか」「価格やサポートの安心感があるか」といった観点の方がずっと大事だと思っています。
だからこそ、“国産だから選ぶべき”とは思っていませんし、“選ばなきゃいけない”とも思いません。
ただ、自分自身がエンジニアとして、日々海外の優れたライブラリやツールに助けられながらデータ分析や開発をしている中で、ふと思ったんです。「このまま海外のツールにゲタを履かせてもらって、僕たちは本当に“作る側”に回れているのか?」って。
カッコいいのか?それでいいのか?と。かつて日本は、バブル期に世界の時価総額ランキングの上位を多くの企業が占めていた時代がありました。でも今、その姿はほとんど見られません。
それって、「作る側を担い続けられたかどうか」の結果なんだと思うんです。便利なものに“あやかる”のではなく、たとえ誰かがすでに作っていたとしても、
自分が大切だと思うことなら、自らの手で作る。
自分で考えたものの方が、最高に決まってる。
そういう姿勢でいないと、この国は、そして僕たちの世代は、もう一度世界で戦えるようにはならないと思っています。
実際、日本が今も世界に発信できている領域って、アニメとか食文化とかですよね。
サッカー漫画だけで何十作品もあるし、ラーメンだって「○○系」がいくつもある。
それぞれが“自分の最高”を社会に提案し続けたからこそ、業界が洗練され、世界に誇れる文化になったんだと思います。逆に、それを怠ったのがスマートフォンや家電の領域。
誰かの真似で満足していたら、気づけば世界と勝負できなくなっていた。データ活用という分野でも、同じような道を辿ってほしくない。
僕も、ありがたいことに、先人たちが作ってくれたこの市場のおかげで、独立し、仕事として成り立たせてもらっています。だからこそ思うんです。この業界に恩返しをするなら、“使う側”に甘んじるのではなく、“自分が思う最高”を形にして、社会に提案していくことだと。それが、目の前の企業やユーザーにとっての価値になるだけでなく、
この業界そのものを、もっと誇れるものにしていく道だと信じています。
多くの日本企業が、海外製のソフトウェアを「便利だから」と無意識に使い続けています。
でも、実際には日本への対応は後回しで、新機能も届くのが遅い。アップデートには高額な費用がかかり、結果的に古いバージョンを使い続ける企業も少なくありません。
「便利さ」の裏側で、自分たちの成長が他国の事情に縛られているという現実に、もっと危機感を持つべきだと思うんです。僕は、自分たちのためのものを、自分たちで作るという選択肢を持つことが、これからの日本企業にとって大事だと考えています。
便利なサービスが生まれなければ働き方は変わらず、価値を生み出せなければ経済も回らない。
その結果、人々の選択肢はどんどん限られてしまいます。私にとっての“豊かさ”とは、選択肢があり、それを自分の意志と主導権をもって選べることです。
だからこそ、選択肢を“自分たちの手で”増やしていくことが、自由で豊かな社会につながると信じています。たとえば、トヨタが車をつくり始めたとき、日本にはすでに海外製の車が存在していました。
それでも、「自分たちの手で最高のものをつくる」と挑戦した人たちがいたからこそ、日本の自動車産業が世界に通用する産業へと育っていった。選択肢を生み出す意志と行動が、社会全体の力になったのだと思います。
データの領域も、まったく同じです。日本には多くの海外製ツールがあり、優れたものも少なくありません。
けれど、「すでにあるからそれでいい」という姿勢のままでは、私たちはいつまでたっても“使う側”にとどまってしまう。だから私は、“私たちが信じる最高のプロダクト”を、自分たちの手でつくることを選びました。現場の声に耳を傾け、日々の業務や意思決定に本当に役立つものを、自分たちの責任で設計し、届けていく。
その積み重ねが、企業や社会にとって新たな選択肢となり、価値になると信じています。そして願わくば、私たちのプロダクトや姿勢に触れたことで、「自分たちでもつくってみよう」と考える人が増えていってほしい。
リスクをとって、信じた道をかたちにする人が、少しずつでも増えていくこと。“作る側”に立つ人たちが増え、それぞれが思い描く価値を社会に届けていく――そんな未来を、私たちは目指しています。
深野さん、インタビューありがとうございました!