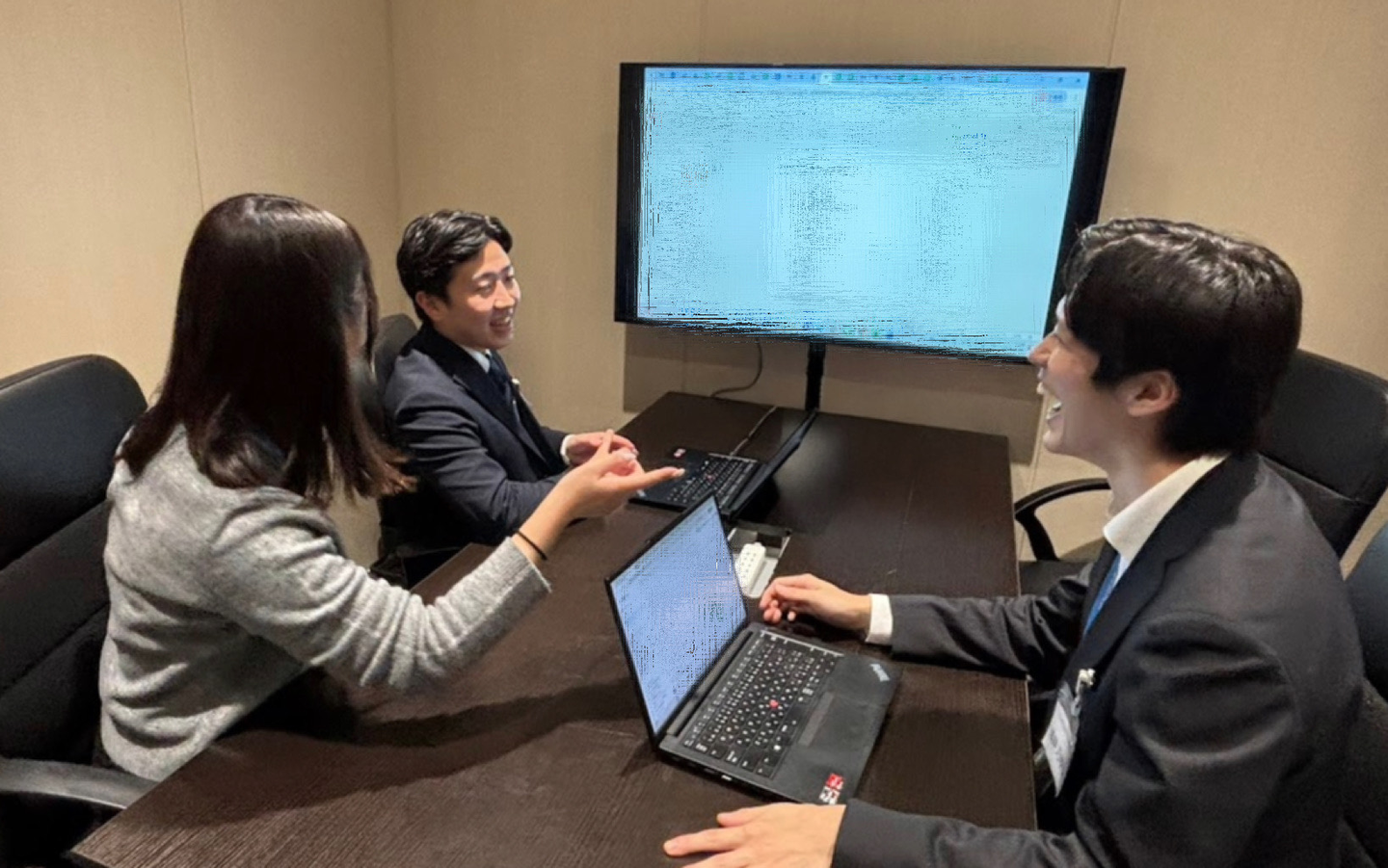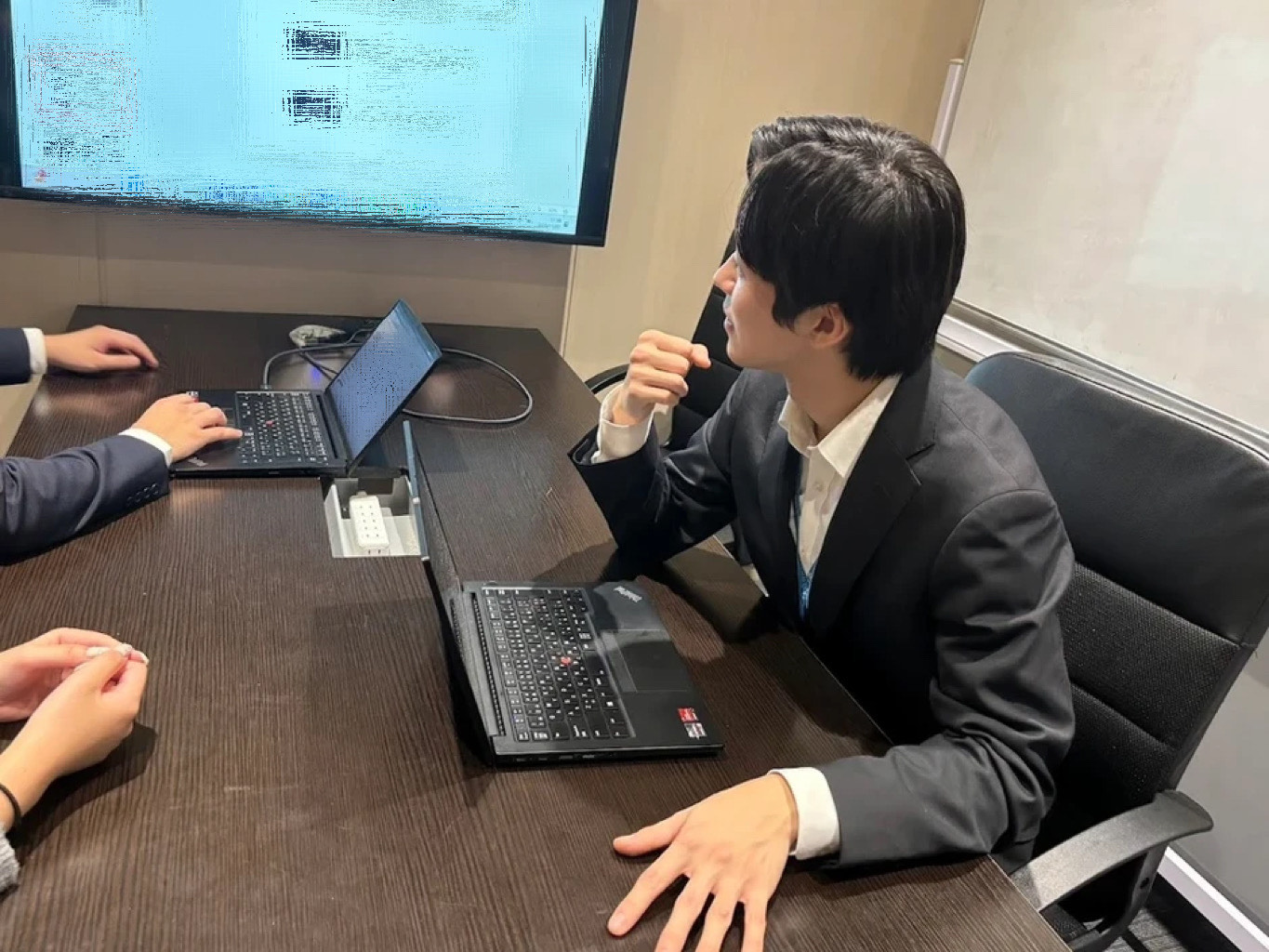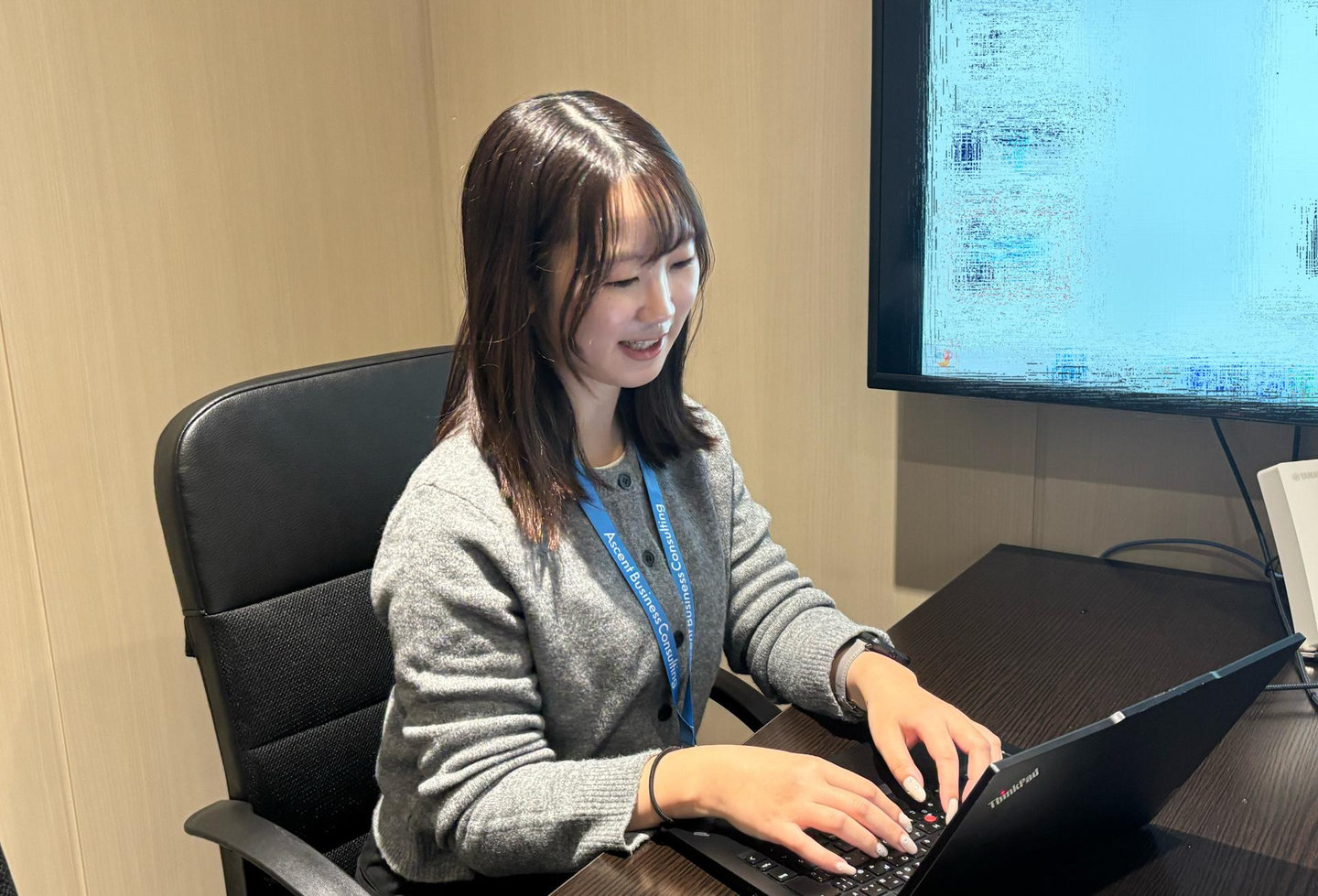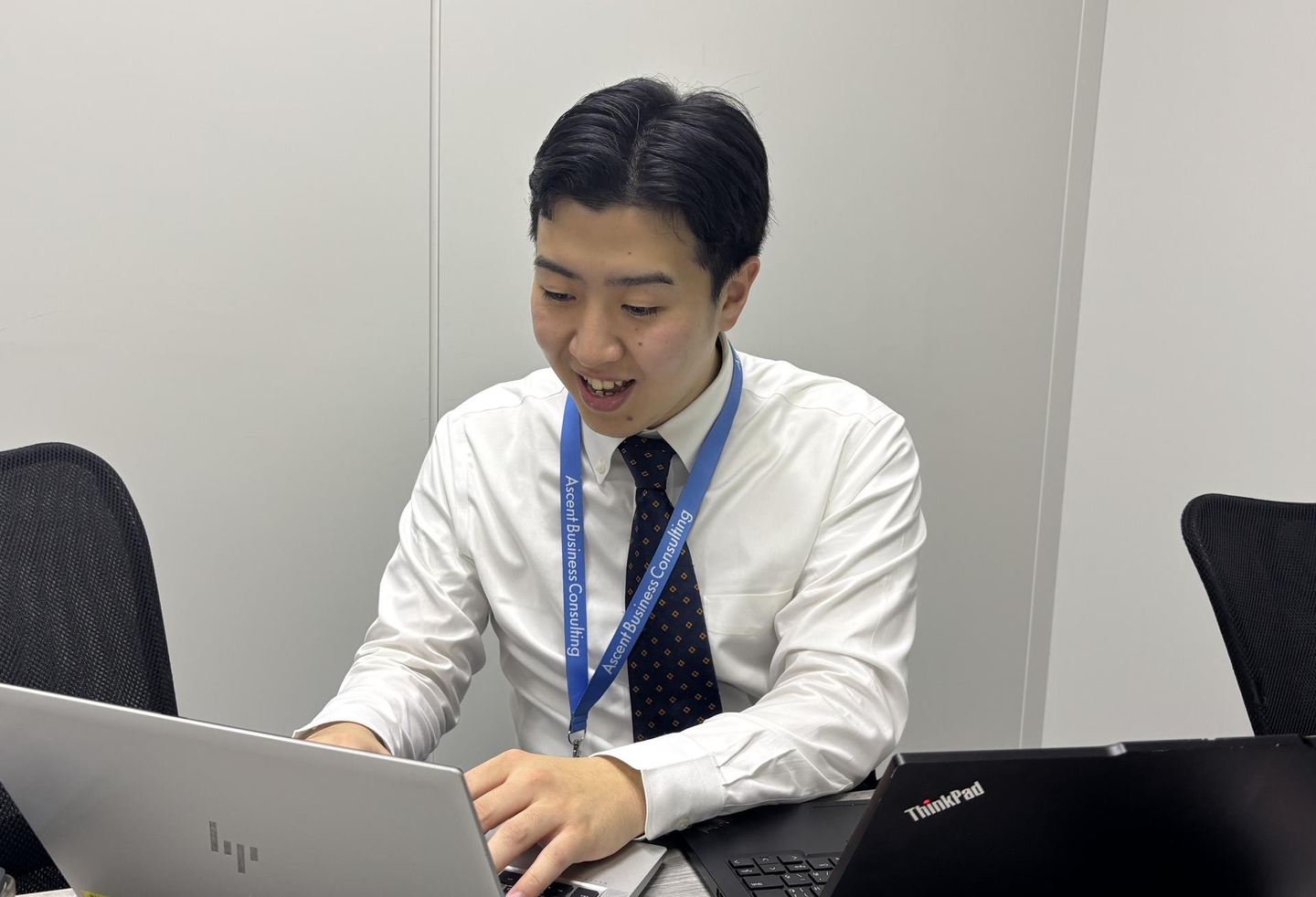コンサルタントに興味がある方
寿司パーティー!先輩コンサルタント/エンジニアとカジュアルに話しませんか?
Ascent Business Consulting株式会社
こんにちは。Ascent Business Consultingの採用担当です🌟
今回は、入社から8ヶ月が経った25卒の若手社員3名に集まってもらい、
日頃どのように部門を越えて関わっているのか、リアルなエピソードを聞いてみました!
「初めて任された案件での印象的だった連携」
「他職種だからこそ生まれるギャップや学び」
「ABCの“横のつながり”を象徴する日常のコミュニケーション」
社内の温度感や人間関係の良さが自然と伝わってくる内容になっているかと思います。
この記事が、ABCで働く姿を想像するきっかけになれば幸いです😊
浅井(コンサル):コンサルタント事業部の浅井乃映瑠です。
PMOとして、お客様のプロジェクトが円滑に進むよう、プロジェクトマネジメント周りのサポートを行っています。
吉野(エンジニア):DXソリューション事業部でエンジニアをしている吉野萌と申します。
現在の現場では、PM業務の一部を担当しながら、案件の保守作業にも携わっています。上流のプロジェクト管理と、下流の実機を触るような現場作業の両方に関わることで、幅広い工程を経験しています。
黒越(営業):営業部の黒越亮史です。
主にエンジニアが参画する案件の獲得に加え、案件の技術要件やメンバーのスキルセットを踏まえ、最適な人材配置を設計・調整するような業務を担当しています。
※以下、(コンサル)=(コ)、(エンジニア)=(エ)、(営業)=(営)
浅井(コ):他部門との連携は頻繁で、ほぼ毎日発生しています。
主に営業部門とのやり取りが中心で、顧客から人材の要望があった際には、営業と直接連携しながら最適な提案ができるように調整しています。
そのため、業務の中で自然と他部門との関わりが生まれているといった形です。
一方で、エンジニアとの関わりは少ないですが、毎月の全社定例の運営では案件内容や日々の業務について直接伺う機会があります。社内のつながりを深める大切なコミュニケーションの場になっています。
吉野(エ):私は案件先に常駐しているので、浅井ほどコンサルや営業とがっつり関わる機会は多くありません。
それでも、契約周りの調整で営業とチャットでやり取りすることはあります。
また、同期とは、月に1回の全社定例での担当業務などがあり、コンサルとはそのタイミングで交流することが多いです。
黒越(営):エンジニアの方に関しては、業務上頻繁に関わりがあります。相談事があれば1on1の時間を設けて、悩みや相談にも対応するようにしています。
出社しているコンサルの方とはランチに行くこともありますし、同期とは全社定例の企画・運営を一緒に行っています。
ありがとうございます。
それでは、ここからはまず浅井くんにコンサル目線でのお話をいろいろ伺えればと思います。
浅井(コ):部門が違うと、前提となる知識や認識が大きく異なることがあります。
そのため、会話の中で内容が伝わりづらくなる場面も出てくると思います。
そうならないように、まず「この話をしている背景は何か」「目的は何か」といった前提をしっかり共有することを意識しています。
浅井(コ):あります。
営業メンバーの視点で助かるのは、お客様が本当に求めている人材像やスキルを知れることです。営業は日々顧客と会話しているので、具体的な要件や人物像を把握しており、その情報を共有してもらえることで、より実態に合った提案ができます。
エンジニアについては、企画やタスクが「技術的に実現可能か」を確認できる点が大きいです。全社定例の企画・運営につながってくるのですが、現場の作業内容や難易度、必要なスキル感を踏まえたフィードバックをもらえることで、実行可能な企画が作れるようになり、コンサルとしても非常に勉強になっています。
浅井(コ):1つ目は物理的な近さです。ワンプール制で営業・コンサル・エンジニアが近くにいるため、情報もスムーズに共有でき、気になったこともすぐ確認できます。
2つ目は人としての話しやすさです。ABCは適度にウェットな関係性で雑談もしやすく、そこから業務の相談にも自然につなげられます。遠慮なく意見交換できることが、連携のしやすさにつながっています。
各部門の強みを活かしながら、部門を越えた連携がスムーズにできているのが印象的ですね!
続いて、ここからは吉野さんにエンジニアの目線でいろいろお聞きできればと思います。
吉野(エ):エンジニアは本社に出社する必要のない日が多く、仕事のスタイルもだいぶ違います。そのため、チャットでのやり取りが多いので、言葉の選び方やニュアンスを間違えないように意識はしています。
また、さっき浅井が言っていたように定例の打ち合わせ等で「あれ、私ここ分かってないんだけど」っていう部分がどうしてもお互い出てきてしまうことがあったので、そういう時には一旦止めて「ごめん、それって何?」みたいな感じで前提を合わせていくこともとても大事かなと思ってますし、実際にしています。
吉野(エ):私自身が新卒・未経験からエンジニアになったので、「分からない側の感覚」を一番覚えているんです。
そのため、専門用語をそのまま使うのではなく、身近なものに例えて噛み砕いて説明するようにしています。
社内でエンジニア同士会話をしていると、他部門の方が置いてけぼりになることもあるので、「例えば〇〇みたいな」といった形で具体例に置き換えて説明すると相手も理解しやすく、コミュニケーションがスムーズになることが多いです。
吉野(エ):全社定例の企画・運営につながる話なんですけど、入社してすぐの2週間研修を職種ごちゃ混ぜで受けたじゃないですか。あの期間でめちゃくちゃコミュニケーション取ったので、「この人ってこういうタイプなんだな」って結構つかめたんです。
そのおかげで関わりやすいというか、「この人はここが得意だから任せよう」「ここはこの人に聞けば分かりやすく教えてくれそう」みたいに、お互い助け合いやすい関係ができてるなって思います。
全社定例とかで一緒に動いてるときに特にそれをよく感じますね。
吉野(エ):それこそ、さっき話した2週間のコンサル研修で学んだことが、今の業務にかなり生きてるなって思ってます。
今、私はPMっぽい立ち位置で仕事していて、クライアントと要望をすり合わせたり、社内の関係者と連携して進捗管理したりっていう“コンサル的な業務”と、基本設計書を作ったり技術的な判断をしたりする“エンジニア的な業務”の、両方をやる必要があるんです。
その中で、前提をまずちゃんとすり合わせるだとか、結論ファーストで考えるみたいなコンサル的な思考は、技術の場面でもコンサルの場面でも本当に役立っていて。
職種とか関係なく使える“考え方の土台”みたいなものを、研修で身につけられたのは大きかったなと、今の業務を通してすごく実感しています。
吉野(エ):私は出社が月1回の全社定例の日だけの月もあるんですが、出社すると部門関係なくみんなが自然に挨拶してくれたり、「最近どう?」って声をかけてくれたり、そういうフレンドリーさはすごくABCらしいなと思います。
エンジニア内では「今の案件でこういう構築が必要なんですが、詳しい人いますか?」という会話が自然に生まれ、経験のある人を紹介してくれたり、分からないところを教えてくれたりと、技術的な助け合いがとても強いです。
私自身も、今の案件では新卒も女性も自分だけですが、サーバー周りで悩んだときに先輩につないでもらえて、技術相談や資格勉強の相談までできています。
こうした仕事の悩みから技術面まで気軽に相談できる“太いパイプ”があるのは、ABCのエンジニア組織ならではのチームワークだと感じています。
吉野(エ):今も部門内ではよくあったりしますが、案件先で分からない分野が出てきたり、「こういうスキルの人が欲しい」といった場面があったときに、部門を越えてすぐに相談・連携できる関係性を大事にしたいと思っています。お互いに頼り合って解決していける環境を強めていきたいですね。
ABCの“人の良さ”と“横のつながりの強さ”がとても伝わってきました!
それでは、続いて黒越くんに営業の目線でいろいろお聞きしていきます。
黒越(営):初めて任してもらえた案件において、要件定義・スキルセット・稼働条件を精緻に整理したうえで候補者をサーチし、技術・志向性ともに高いマッチ度でアサインすることができたことです。
└全社定例の感謝貢献プロジェクトで発表されてましたね!
黒越(営):まさにその件が僕が初めて一任してもらえた案件でした。
黒越(営):専門技術に関してはエンジニアの皆さんの知識が圧倒的に深いため、わからないことはよく出てきます。
そういう時は、その都度素直に聞くようにしています。曖昧なまま進めず、早い段階で認識を揃えることで、勘違いやアサイン時のミスマッチなどが生まれないように気を付けています。
黒越(営):相手の立場に立って話すことを意識しています。
自分の視点だけでなく、相手がどう受け取るかを想像しながら伝えることで、多角的な視点で会話ができ、認識のズレもなくなるのでお互いに理解しやすいコミュニケーションが取れると感じています。
黒越(営):仲の良さですかね。
横のつながりも縦のつながりもすごく深く、仕事の相談はもちろん、プライベートな話も気軽にできる雰囲気があって、誰に対しても声をかけやすい環境だと思います。
黒越(営):現状、部門によっては社内で顔を合わせてコミュニケーションをとるだけで完結してしまう関係性もあります。
今後は、そうした会話ベースのつながりにとどまらず、一緒に取り組める業務の幅も広げていけたらと考えています。部門間で協働する機会が増えれば、より理解も深まり、組織としての力も高まると思っています。
営業とエンジニアの連携がうまくいっている要因を再認識できました!
それでは最後に皆さんに改めてお聞きします。
浅井(コ):この会社の魅力は、頼り頼られてお互いを高め合う文化の強さですかね。
仕事でもプライベートでも、些細なことから大きなことまでお互いにサポートし合える環境があり、その中で貢献や成長を実感できる点が大きな魅力であると思います。
吉野(エ):言われてしまいましたが…当たり前に助け合えるところがこの会社の魅力だと思います。
関係ができていない人同士で「助け合おう」と言われても、実際どう動けばいいか分からないですよね。でも、社内プロジェクトや全社定例などで他部門の人とも自然に関わる機会が多く、助け合うハードルが低くなっています。
そのおかげで、業務の相談もしやすいですし、プライベートでも仲良くなれる環境が、仕事にも良い影響を与えていると思います。
黒越(営):協働のしやすさでも触れましたが、やはり仲の良さが大きな魅力ですね。
部門を超えても上司と冗談を言い合えるような関係性があり、とても居心地の良い環境です。
浅井(コ):大きく分けて2つですかね。
1つ目は、いろんな情報を自分で理解して咀嚼しようとする人。
2つ目は、自分一人で突っ走るのではなく、メンバーと歩調を合わせて動ける人です。
吉野(エ):やっぱりコミュニケーション能力が大事だなって思ってます。
ただお喋りが上手ってだけでなく、相手が今何を求めてるかとか、この人の指示の背景は何かっていうのをちゃんと考えて理解し、自分の意見を返せるような人だと一緒に仕事もしやすいですし、ABCにも合ってるんじゃないかなと思います。
黒越(営):俯瞰して状況を見ながら行動できる人ですかね。
そういう人と一緒に働きたいですし、そういう人は実際に活躍している印象も強いです。
浅井(コ):この就活のタイミングで、ぜひ自己分析はとことん進めてほしいです。
人生の中で、自分のことを振り返ったり分析する機会ってそう多くないと思うので、今が本当にいいチャンスだと思います!
この際に、自分のやりたいことや合っていること、入社後のイメージまで、納得いくまで固めてみてください。
そのうえで、ABCがマッチしていれば、ぜひ挑戦していただけると嬉しいです。
吉野(エ):就活中に私が大事にしていたのは、とりあえずやってみることでした。
自己分析も大切ですが、ハードルが高く感じることもあるので、気になる会社は直感で調べてみるのもおすすめです。行動してみて違えば次に進めばいいですし、そうすることで会社の雰囲気と自分の感覚が合うかどうかも分かります。
ABCでは寿司パーティーなどのイベントも定期的に開催しているので、ぜひ活用してみてください。
黒越(営):面接は怖くない!
面接において、委縮してしまうと自分の強みを十分に伝えられません。面接官も人間なので、あくまで会話の場として臨めば大丈夫です。緊張は程よく持つくらいがベスト。
怖がらずに、自分の良さを存分にアピールできるよう頑張ってください!
******
いかがでしたか?
ABCの強みは、職種の違いにとらわれず“同じ方向を向けるチームであること”。
誰かが困っていたら声をかけ、必要なときは手を貸し、時には学び合う。そんな文化が、メンバーの成長を後押ししています✨
「いろんな人と関わりながら成長したい」「一緒に頑張れる仲間が欲しい」──そんな方には、きっとフィットする環境だと思います。
少しでも興味を持っていただけたら、ぜひABCを覗きにきてください!