- PMM
- Web Engineer
- エンタープライズ
- Other occupations (43)
- Development
- Business
- Other
インサイドセールス(以下IS)経験者として2024年にアンドパッドに入社し、ビルティングエンタープライズ領域のISを手掛ける宇田川。当社のISは、一般的な業務とは一線を画すと語ります。今回は、アンドパッドのエンタープライズ領域におけるIS業務の特徴と、入社後得られたスキルなどについて、宇田川と部長である小林との対談インタビューを実施しました。
エンタープライズ領域 部長 小林 英祐(写真右)
2019年インサイドセールスとしてアンドパッドに入社。当初は数名の人数であったが、組織の成長とともにハウジング領域、専門工事領域など様々な部署の立ち上げやマネジメントを経験。さまざまな企業規模を対象に新規開拓を行い、2023年7月にエンタープライズISの立ち上げメンバーとして従事。2021年よりマネージャー、2025年より同事業部の部長就任。
小林の当時のインタビュー記事はこちら
エンタープライズ領域 インサイドセールス 宇田川 敦史(写真左)
2018年に大学を卒業後、求人広告事業を展開する企業に入社し、都内エリアの法人営業を担当。採用課題のヒアリングから企画提案まで幅広く経験し、2021年からは、採用支援プラットフォームを提供する企業にてインサイドセールスに従事。新規開拓から商談・受注まで一気通貫で担当。2024年2月、アンドパッドにインサイドセールスのメンバーとして入社。現在は大手メーカーや商社系企業を中心に新規顧客へのアプローチや商談機会の創出を担当。
市場価値を上げる環境を求めて転職
――宇田川さんのこれまでの経歴について教えてください。
宇田川 新卒で入社したのは、求人情報サイトの運営会社です。営業としてアポイント獲得から受注、原稿作成、効果検証までをトータルに手掛けていました。仕事で心掛けていたのは、本質的な課題解決を目指すこと。経営視点を意識し、お客様の事業成功に結び付く提案を大切にしていました。例えば個人経営の飲食店で正社員3名を募集する場合、背景や理由を確認し、離職や定着に課題がないかを探ります。給与や昇給などの条件面だけでなく、職場の魅力を整理し、改善点を明確にすることで、より良い人材採用につなげる提案をしていました。一度の商談で得られる情報には限りがあるため、足しげく店舗に通い、飲食店なのでランチの時間に顔を出すなどして関係を深めることも意識していました。そうした継続的な関わりを通じて、本音を引き出せるような信頼関係を築くことを心掛けていました。
――なぜそこまでしていたのですか?
宇田川 私の営業スタンスとして、「物売りをしたくない」という思いがあったためです。無形商材を扱う営業として、お客様と密接に関わりながら企業経営を支援したいと考えていました。経営視点に近い仕事をしたいという思いが年々強くなり、3年後にダイレクトリクルーティングサービスの運営会社に転職しました。ここでは全国の中小企業様向けのISというキャリアを選んだのですが、魅力に感じたのは、遠方のお客様に対して一度もお会いすることなく契約に結びつく点です。お客様とは一切関係値のないところから、信頼関係を築き、一度もお会いする事無くオンライン商談のみで自社の商品に魅力を感じてもらう。自分の商談力が試される環境に目新しさを感じました。実際、商談先は社長や部長、経営層がメインなので、それこそ表面的ではなく、より経営に踏み込んだ提案ができるようにもなったと思います。頑張ったら頑張った分だけ評価される仕組みも自分に合っていましたし、いい会社だなと感じていました。
小林 転職を意識したきっかけは何でしたか?
宇田川 自発的に動ける環境がなかった点が大きかったため、転職を視野に入れるようになりました。前職は、上層部が設計した施策通りに動き、施策通りの商談をして、施策通りの成果を出す人を評価する体制でした。それは効率化や商談確度の観点から非常に練られた素晴らしいものでしたが、ワークフローも提案のプロセスも全て決められていたため少し窮屈に感じるようになっていました。またその体制だと極端な話、独自の動き方でトップセールスを達成したとしても評価されにくい環境でもありましたし、自分で考えて挑戦する余地がなければ、成長の頭打ちになると焦りを感じるようになっていました。
小林 この会社で通用しても、他社では通用しないと思うようになっていたんですね。
宇田川 はい。自分の中で型も出来上がっていたので、業界ごとの課題感や提案内容もパターン化していました。だからこそ、考えなくても行動できるようになっており、そこに危機感を感じました。市場価値を上げていくためにも、この環境に居続けるのは限界があると思ったためです。
自発的な行動が望まれる環境に惹かれた
――実力を磨ける会社に転職する、というのが大きなテーマになっていたと。
宇田川 転職活動を始めるにあたって、自分に必要な力は何か?を考えました。まず磨くべきだと思ったのは、商談力です。商談力を磨くためには、大手企業への営業が適切ではないかと感じました。というのも、大手企業への提案はより深い視点、高い視座で提案が必要だからです。今まで何よりも重要だったのは、電話をする行動量でした。しかしながら一社一社に真摯に向き合える環境で、どのような課題に向けて、どのような方法で、どのような提案をすべきかを自発的に考えられるようになりたいと考え、転職活動に臨みました。
小林 より難易度の高い仕事にチャレンジしたいと思ったわけですね。大手企業への提案活動において多岐にわたる部署があるだけでなく、キーとなる部署がどこかも分からないことが多いので、戦略的に考えなければいけませんし、それこそ表面的な提案では絶対に受注はできません。宇田川さんは、どういった企業を転職活動の軸にしていましたか?
宇田川 漠然とSaaS業界など、無形商材を扱う成長企業を中心に受けていました。そんな中でエージェントから紹介いただいたのが、アンドパッドのエンタープライズ領域のISでした。入社していきなりエンタープライズ企業を担当させていただける仕事はなかったので、とても魅力に感じましたね。
小林 SaaS業界のエンタープライズ領域においてISという職種に特化した採用は、あまり多くはありません。アンドパッドの第一印象はどうでしたか?
宇田川 プロダクトは知っていましたが、具体的なことは何も知りませんでした。企業研究を通じて事業内容や展望を知り、今後の成長が想像できましたし、自発的に動ける環境がありそうだと感じました。入社の決め手は、先輩社員との面接です。アンドパッドが求めている人物像と、自分がなりたい像が合致していましたし、自発的に動ける人を求めていることも分かり、挑戦できる環境がここにある、と心に刺さりました。もともと企業研究をしていく中で、ISの業務内容や求める人物、アンドパッドの未来、組織風土などを想像できていたので、面接で答え合わせができて安心できた、という認識が強かったです。
小林 なるほど。ISという職種は、電話をたくさん掛けてアポイントを取るというイメージがあるかと思いますが、当社エンタープライズ領域のISは架電以外の業務も多く、アライアンスや取材、セールスマーケットのコンテンツ企画など、プラスアルファの業務を通じて、自発性を発揮でき、キャリアを広げていくことができます。色々な挑戦ができる環境に魅力を感じてもらえたんですね。
宇田川 まさにそうです。また戦略的アプローチを考えて実行できる環境も魅力でした。基本的には「なぜこのタイミングで」「この方にアプローチをするのか」「かつ何を伝えたいのか」「どのようなメリットを感じていただくのか」という4段階でトークを組み立てていき、アポイントを取ることでお客様のビジネスをどう支援していきたいのかまで見据えていると伺い、今の自分にはない視点だったので、深く感銘を受けました。
――面接を受けて志望度は上がりましたか?
宇田川 はい。第一志望にグッと上がりました。自分の成長が、会社の成長につながる仕事を任せてもらえると確信を持てたのは大きかったです。例えば、自分で組み立てたトークを全体に周知して、効果検証しながら一つの型を作っていく。お客様に興味を持っていただくための施策を企画し、自分が旗振り役を任せてもらう。上から降りてきた仕事をこなすのではなく、自分で考えて行動できる。むしろそれが求められているというところが、一番の決め手になりました。
――小林さんにお聞きしたいのですが、自ら考えて動ける自由度の高い環境にも、ある程度限度はあるかと思います。そのバランスはどのように考えていますか?
小林 もちろん完全に個人の裁量に任せているわけではありませんが、目標達成や事業成長の上でプラスになることであれば、色々なことに挑戦してほしいと考えています。風土としても、費用対効果を踏まえつつ、メンバー同士でコミュニケーションを取りながら、良いアイデアであればどんどん取り入れていくカルチャーが根付いています。
組織理解を踏まえ、戦略的アプローチを組み立てる
――宇田川さんは現在、どのような業務を担当していますか?
宇田川 私は現在、大手メーカーや商社などのお客様を担当しています。一部の部署ではANDPADをご利用いただいているのですが、まだご利用いただいていない別部署にアプローチする役割を担っています。重要なのは、ABM (Account Based Marketing*)の観点で個社ごとにどのように開拓していくのかを戦略を立てること。ときにはアカウントマネージャーやカスタマーサクセスの力を借りながら、多角的観点でアプローチ先を分析し、どのように商談につなげていくかを考え行動しています。
*具体的に企業・団体(アカウント)をターゲットとして設定し、ターゲットアカウントからの売上を最大化するために戦略的にアプローチするマーケティングの考え方または手法
――例えばどのように仮説を立てていくのでしょうか?
宇田川 すでにご利用いただいている部署を担当している営業メンバーに、過去の商談内容や社内の雰囲気をヒアリングしたり、実際に自ら立てた戦略を相談したり。今回の商談を経て、決裁者や導入責任者の方をご紹介いただくところまで見据えてアプローチ方法を組み立てています。
小林 電話をする段階で、その部署がどのような役割、どのような業務を担っているのか、会社の中での立ち位置はどうか、という全貌が分からないケースも多いので、部署の役割や担当レイヤーの方の日々の業務内容、業務を行う上での課題感、決裁ルート、システム推進の流れなどを全部ヒアリングするようにしています。
――まずは組織内を知るところから始まるケースが多いと。
小林 例えばDX部とシステム部がどのような構図になっているのか、キーレイヤーの方はどの方か、どの部署が工事でどの部署がアフターフォローを担当しているのかなど、電話や商談を通じてヒアリングし、整理していくことがまずは大前提として重要です。
宇田川 同じ部署名であっても、企業によって担っている業務が異なるケースもあります。DX部門と一言で言っても、既存業務を維持・管理することに主眼を置いた現状運用型もあれば、現場外の視点から積極的に改善を推進する変革志向型の業務を行う企業もある。部署の名称だけで判断できないことも多いので、その点は難しいなと感じます。
――入社されての当初のイメージとのギャップは何かありましたか?
宇田川 これまでの職場では架電件数がKPIとして設定されていましたが、当社ではあまり重視されていないのは、結構衝撃的でした。
小林 架電数に重きをおいたKPIにしていないのは、数だけではなく特に質にこだわっているからですね。ホリゾンタルSaaSと比べると、バーティカルSaaSは営業先リストにも限りがあるもの。架電数が多いか少ないかが重要ではなく、お客様の興味を持っていただけるように、戦略的にアプローチすることに重きを置いています。宇田川さんは、前職の型にはまった営業を脱したいという思いや、ISのキャリアの幅を広げていきたいという思考が強く、我々もそこに期待をしていました。
――なるほど。宇田川さんは入社前に、戦略的アプローチができる環境を望まれていましたが、アンドパッドで実現できていますか?
宇田川 はい。チャレンジできています。現在は、電話以外の新しいアプローチ方法の実験的取り組みや、商談の質を高める型づくりに挑戦しています。
――新しいアプローチの可能性も常に探っているのですね。後者の商談の質を高める型づくりとは何ですか?
宇田川 次回の提案につながる商談かどうかを事前予測するために、押さえておくべきヒアリング項目を可視化する取り組みをしています。本質的な課題解決が実現でき、お客様から興味を持っていただくためのトークスクリプトを試行錯誤しながら作っている最中です。
小林 宇田川さんは、一つの型を体系化して、成功事例を作り、それを社内外に普及していくほどの熱量がある方だと思います。実際に入社後も、チャレンジ精神や吸収力、自分で何かを切り拓いていきたいというマインドも高く、組織に良い影響を与える存在になってくれていますよね。
――宇田川さんの存在が、組織を活性化しているのですね。宇田川さんはどんなところにやりがいを感じますか?
宇田川 建築・建設業界と聞くと建物を建設する企業のみと限定されているように思われますが、実は建設や施工に携わる会社は商社やメーカー、一部小売業なども含まれます。そのような企業は商流やカルチャーも大きく違いますし、ANDPADの使い方も異なります。現在では業界外のアプローチも増えており、色々な企業様と接点を持てることが刺激になっています。
小林 今後のプロダクト展開では、さらに対象となる企業様も拡大していく予定ですので、まだまだ新たな発見がありそうですよね。ちなみに、宇田川さんはどのようなモチベーションで仕事と向き合っていますか?
宇田川 成果を出すための施策を考え、実現することが一つのモチベーションになっています。かつそれが型化でき、中核メンバーとして浸透させていくときに、自分の成長ややりがいを感じます。それはこれまで経験してきた会社では絶対に得られなかったものだと思います。それがすごく興味深いですね。
――数字として成果が出ないときは、モチベーションが下がりませんか?
宇田川 成果が出ないと気持ちは下がりますが、しっかり先輩との対話の中で原因を突き止め、「次回はこうしてみよう」とトライアンドエラーができるので、それほど落ち込むことはありません。私の場合は原因が分からないで悩み続けているほうがモチベーションは下がるので、ありがたい環境だなと思います。
小林 チーム内のコミュニケーションは取りやすい環境ですよね。
宇田川 毎日出社されている方も、在宅で働かれている方も、「いつでも相談してください」という雰囲気なので、気軽に相談できます。定期ミーティングでのナレッジ展開も盛んですし、自分が挑戦したいこと、今考えていることも含めて協議する時間もあります。
小林 私たちのチームでは、部長である私からミーティングを実施することは多くありません。上からトップダウンで落とすのではなく、各メンバーが考えて自発性をもって周りを巻き込むことが、自分の成長につながると思っているので、そういう環境を大切にしています。
宇田川 テキストのコミュニケーションだけでなく、対面や電話、ミーティングも多く、疑問を持ったままで終わることは絶対にないので、安心して仕事に取り組めています。
――そういった環境の中で、自己成長を実感されていると。さまざまな企業様と接点を持つ中で、ご自身のキャリアも広がりを見せていきそうですね。宇田川さんの今後の目標について聞かせてください。
宇田川 一つは、成果を出すことです。優先順位を決めながら安定的に成果を出していきたいと思っています。課題に感じているのは、事前準備の部分です。誰に何を伝えたいのか、どんなことに魅力を感じていただきたいのか、タッチポイントを通じて次回どのようなアクションにつなげたいのかなど、ヒアリングやトークの部分でより突き詰めて考える必要があるのに、目先のアポイント獲得が気になって、行動量で取り返そうとしてしまう癖があるなと。
小林 なるほど。私たちは組織攻略を重視していますよね。企業の事業内容、個人の売上、役員メンバー、組織図、決裁ルート、決裁者の方の登壇記事、その方のミッションなど、細かくまとめて事前準備をしています。そういうところはアンドパッドのエンタープライズ領域のISの大きな特徴かもしれません。
――その戦略的アプローチは、エンタープライズ領域だからこそ必要とされているわけですよね。
小林 そうです。エンタープライズ領域で絞り、そこからさらにご提案すべく優先度を選定すると、一人当たりのリストも決して多くはありません。より一社一社の提案内容がとても重要です。宇田川さんは将来的にどのようなISを目指していますか?
宇田川 現時点の明確なキャリアは想像しきれていないのですが、当社に入社して、複数の選択肢が増えました。というのも、今までは社歴が長くなるとリーダーやマネージャーといったポジションを目指さなくてはいけないものだと思っていたのですが、当社はプレイヤーとして一流の方もいれば、マネージャーという肩書ではなくても周りに影響力のある方もいるので、ポジションの有無は関係なく自分の存在感を発揮できる環境があると実感しています。
小林 確かにそうかもしれません。リーダーやマネージャーといった縦のキャリアだけでなく、ISのスペシャリストも目指せますし、IS業務やりながらも横断的に、マーケティングやセールスマーケティング、アライアンス、企画など、さまざまな領域にキャリアを広げていくこともできます。年功序列でポジションアップするような組織とは全く異なり、自分の成長という観点でいろいろな選択肢が用意されている環境だと思います。
この2年間でさまざまな成功事例や失敗事例など、戦略的アプローチについてのナレッジをたくさん蓄積してきました。またチームの人数も増えて、育成環境や組織の内部環境も良くなりました。ただ一方で、まだまだISの型も組織も完成していないので、新しい方をお迎えすることで100%に近づけるような組織を一緒に目指していきたいと思っています。
/assets/images/17292714/original/430e2990-0e6e-480f-a391-9284c3b996b3?1710319697)



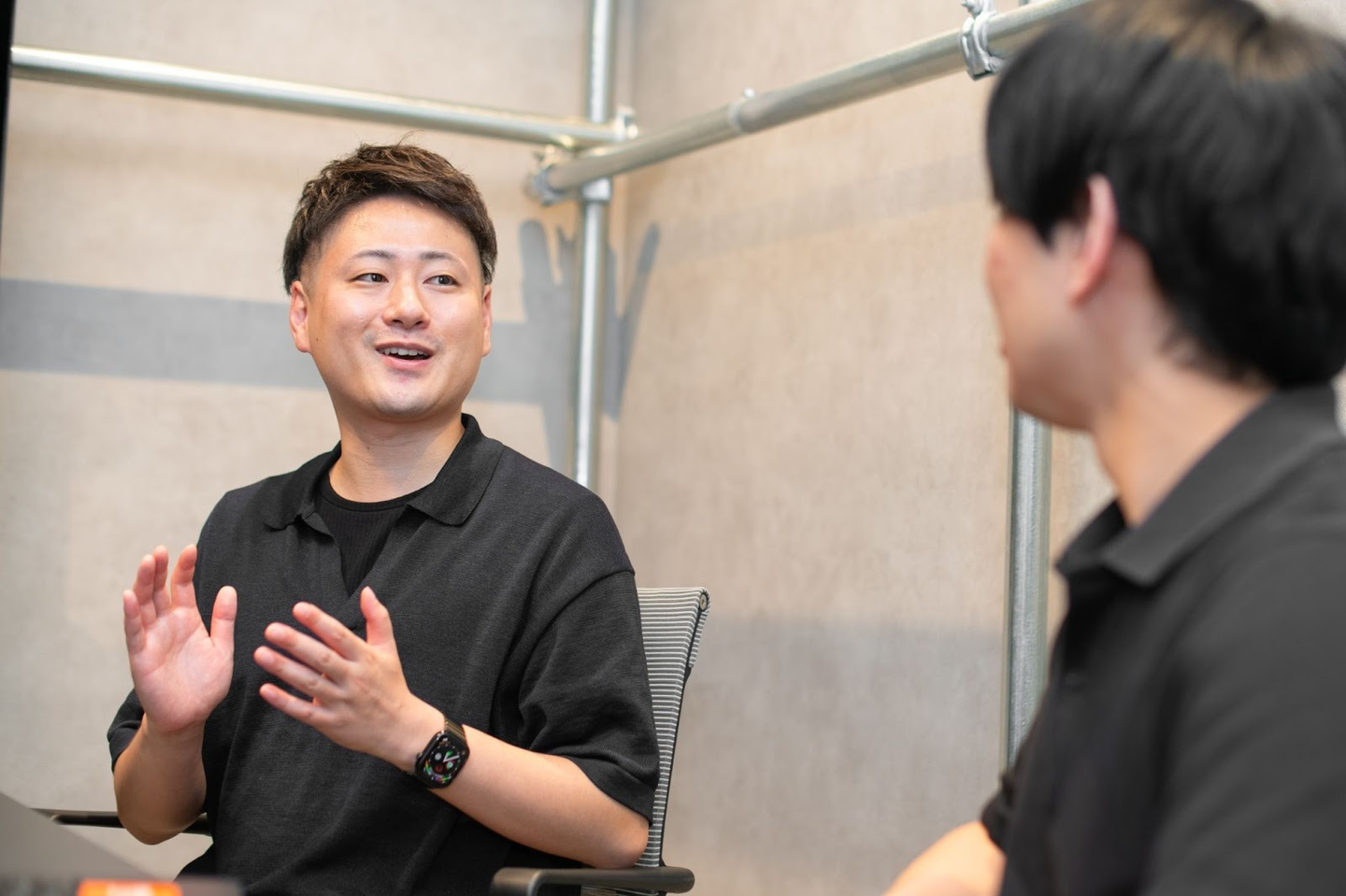


/assets/images/5005916/original/cfb868de-638f-44e1-8f8e-b8e63f273e48?1589330015)


/assets/images/5005916/original/cfb868de-638f-44e1-8f8e-b8e63f273e48?1589330015)

