「そりゃこのゲームは売れるわって。純粋に『負けたな』と思ったんです」
そう語るのは、オンラインゲーム運営担当の竹澤。新卒でAimingに入社後、他社で新規開発やパブリッシング業務を経験。再びAimingに戻ってきた「出戻り社員」だ。
今回は、他社の視点も持ち合わせた次世代のリーダー候補に向けて、Aimingの運営という仕事のリアル、他社を経験したからこそわかる組織文化、そして「これからどんな仲間と働きたいか」を、率直に語ってもらいました。

――まずは自己紹介をお願いします。
竹澤: 竹澤です。よろしくお願いします。新卒でAimingに入社し、2021年に一度離れました。その後、他社を経験し、2025年1月にAimingに再入社しました。
現在は『ウィンヒロ』(WIND BREAKER 不良たちの英雄譚)の運営チームで、主にキャラクター関連の業務を担当しています。ゲームとしてのバランスを鑑みた調整や、お客様にどう見せれば「魅力的か」を考え、商材としての価値を担保する、事業の根幹に関わる仕事です。
――ありがとうございます。一度Aimingを離れ、再び戻ってこられたわけですが、まずは新卒で入社した当時のお話から聞かせてもらえますか?
竹澤: 当時は「ゲーマー採用」という枠で、未経験のプランナーとして運営中のプロジェクトに配属されました。今思えば、とても安定したプロジェクトで、先輩方に余裕をもって手厚く指導していただいたと感じています。データ作成からゲームバランス調整、生放送の対応まで幅広く経験させてもらいました。
――そこから、なぜ一度Aimingを離れる決断を?
竹澤: 決して不満があったわけではありません。ただ、当時のAimingの状況では、自分が望んでいた「新規開発」や、より早いスピードでの「リーダー業務」の経験を積むことが難しいと感じていました。自分のキャリアを考え、今以上の裁量と挑戦を求めて転職を決断した、というのが正直なところです。
外の世界で手に入れた「俯瞰の視点」
――他社では、希望していた経験ができたのでしょうか。
竹澤: はい。大手ゲーム会社で、希望通り新規開発に携わることができました。そこで衝撃を受けたのが、そこがパブリッシングに軸足のある部署だったことです。モノづくりはほとんど開発会社任せで、その分「人月単位でのお金の動き」や、「開発中のゲームが本当に市場で戦えるクオリティか」を多角的に見る必要がありました。
Aiming時代が「現場」だとすれば、他社では「俯瞰」の視点を手に入れた感覚です。この経験は、今Aimingの現場に戻ってきて「どこに注力すればいいか」を判断する上で、非常に大きな武器になっています。
「これは負けた」――出戻りを決めた、元同期の傑作
――俯瞰の視点を得た竹澤さんが、なぜ再びAimingに?
竹澤: 一番の決め手は、Aimingが作った『陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン(カゲマス)』の存在です。
当時、僕も転職先で同じようなゲームシステムのタイトルを担当していたんです。キャラクターをいかに可愛く見せるか、どう売るかを必死に考えていました。そんな時、同時期にリリースされたカゲマスを見て、衝撃を受けました。
ホーム画面のクオリティ、キャラクターモデルの出来、ターゲットに刺さる見せ方……どれをとっても、「これは負けたな」と。純粋に「そりゃこのゲームは売れるわ」と納得させられるクオリティでした。

――競合として「負けた」と。
竹澤: はい。そして「このゲームを誰が作ってるんだ?」と調べたら、僕の新卒時代の同期や年齢の近いメンバーが中心になって作っていたんです。
「彼らが、こんないいゲームを作ってるのか」と。大きな驚きと同時に、「もう一度ここで挑戦したい」という強いモチベーションが湧き上がりました。それが、戻ってきた一番の理由です。
「チームで頑張ろう」戻ってきたからわかる、Aimingの文化
――実際に戻られて、ギャップはありませんでしたか?
竹澤: なかったです。当時カゲマスを作っていた同期が、今では自分より上の職位で活躍している。それは新卒当時から彼が持っていた視点や経験値を考えれば当然のことで、素直に受け入れられましたし、自分も頑張ろうという気持ちになりました。
――他社を経験したからこそ、改めて感じるAimingの文化はありますか?
竹澤: 戻ってきて改めて感じたのは、「チームで仕事をしている」という意識の強さですね。
もちろん会社ごとに素晴らしい文化がありますが、Aimingは特に、チーム全体でプロジェクトを成功させよう、という雰囲気を感じます。
バックグラウンドや役職に関わらず、フラットに意見を言い合える。そういった「チームで頑張ろう」という文化が、僕にとっては非常に魅力的でした。
チームの課題:「円滑さ」の先にある「ストイックな分析」へ
――チームの雰囲気は非常に良い反面、課題に感じていることはありますか?
竹澤: まさにそこと繋がっています。チームが仲良く円滑に進んでいるのは素晴らしいことですが、個人的には「もう少し数値に関してはストイックでもいいんじゃないか」と感じる部分はあります。
僕自身、もっと「ダメだったことの分析」を頑張りたいと思っています。施策の「効果測定」を恐れずにやり、PDCAを回して次に活かす。言うのは簡単ですが、運営業務においてこれをやり切る難易度は非常に高いです。
だからこそ、新しく入ってこられるリーダー候補の方には、この「ちゃんと反省して次に活かす」という部分を一緒に強化していきたいと思っています。
運営も企画も、本質は「プランニング」し続けること
――リーダー候補の方に向けて、Aimingの運営の「やりがい」を教えてください。
竹澤: 僕はAimingで企画と運営のどちらも経験しましたが、ゲーム作りというのは「運営」や「企画」といった枠組みに関わらず、「プランニング」をし続けることだと感じています。
一見、ゲーム作りは企画職の仕事だと思われがちです。ですが、お客様の意見を直接汲み取り、それをどうゲーム内に反映するかを考える運営チームこそ、ゲーム作りの「0→1」を生み出すのに最も近いチームだと言えます。
だから、例えば「これまで売上やお金の動きには一切関わってこなかった」というプランナー出身の方でも、その「プランニング」の経験はAimingの運営で絶対に活かせますし、とてもおすすめです。
――「プランニング」というと、「どう稼ぐか」だけでなく、「どう面白くするか」も含まれますね。
竹澤: 「運営」と聞くと、もしかしたら「お金稼ぎの仕組みを作る」というイメージが強いかもしれません。もちろんそれも大事ですが、それだけではないんです。
最近の売れているゲームの多くは、「まずお客様を喜ばせること」を最優先にしています。高いクオリティの体験を提供して、心から楽しんでもらう。その結果として、お客様が価値を感じて課金してくださる。この順番が主流だと感じています。
ですから、「どうやって稼ぐか」という視点だけでなく、「どうしたらお客様が喜んでくれるか」というゲーム作りの視点を強く持っている人も、運営には絶対に必要な存在です。その両方を高いレベルで実現できるのが、Aimingの運営チームの面白さだと思います。
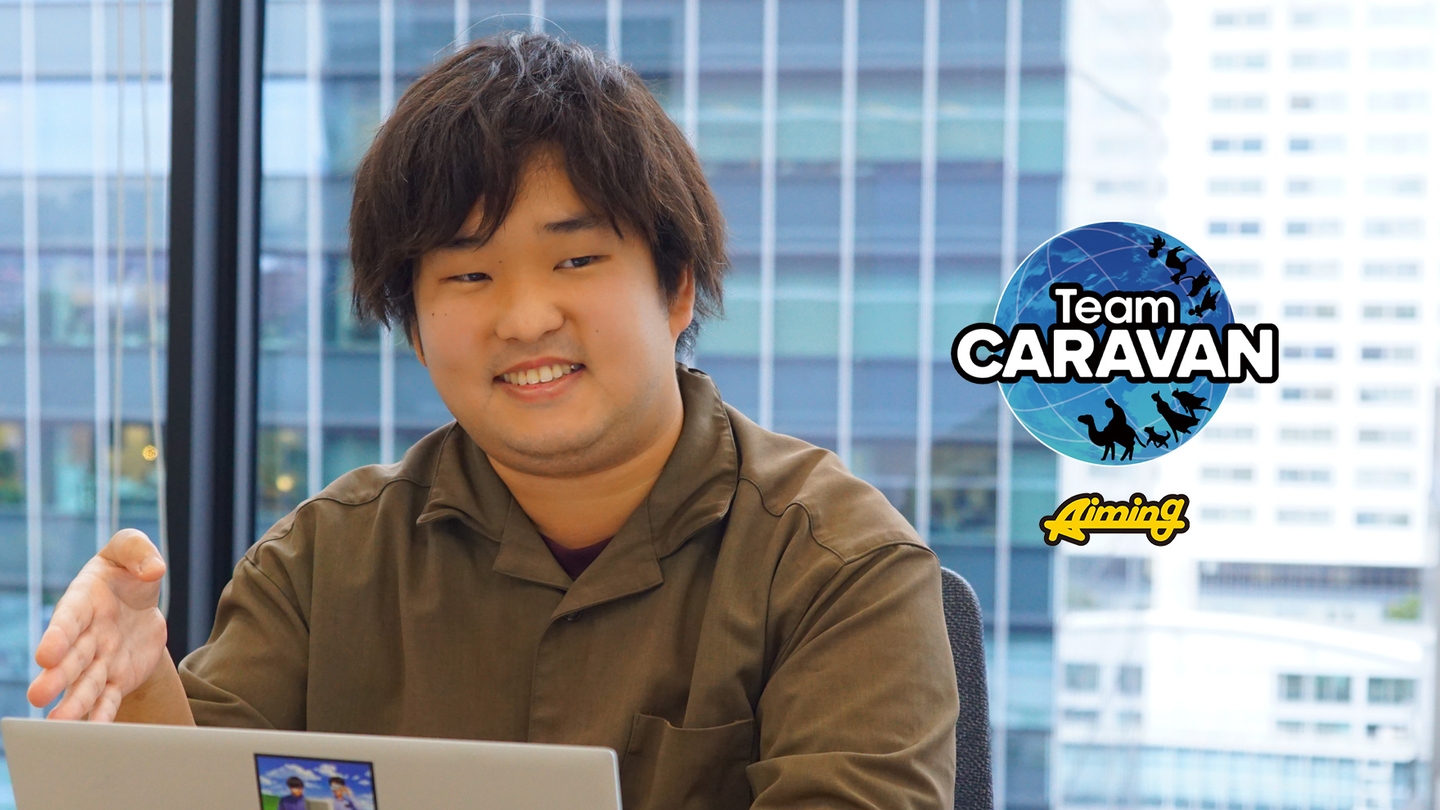
「1位の景色」と「なんでも屋」の経験が、次のリーダーを作る
――ずばり、どんな方と一緒に働きたいですか?
竹澤: マインド面で言うと、「1回めちゃくちゃゲームをやり込んで、1位を目指した経験がある人」ですね。
トッププレイヤーの目線という単純な話ではなく、「1位になった時の景色」を見たことがある人は、その過程で目標達成のために何をすべきか学んでいるはず。それは絶対に業務に活きます。特に、チームを引っ張って目標に向かうようなゲーム経験は最高ですね。
――中途の経験としては、いかがでしょう。
竹澤: 「一人で何でもやったことあります」という経験がある方です。
例えば、「少人数のプロジェクトで、リーダーではなかったけど、実質“なんでも屋”でした」みたいな人。 そういう人は、企画も分析も進行管理も、すべてを高いレベルでやらざるを得なかったはず。その経験がある人は、あと一歩でリーダーになれると僕は思っています。
――ありがとうございます。最後に、この記事を読んでいる未来の仲間にメッセージをお願いします!
竹澤: Aimingは、運営チームだけでなく、どの部署も本当に和気あいあいとゲーム作りを楽しんでいます。「お客様を喜ばせたい」という情熱も、「ゲーム作りで稼ぐ仕組み」への興味も、ここでは両方叶えられます。
ご一緒できる日を楽しみにしています!
/assets/images/22322146/original/249be6bd-b5b1-42f6-862c-411810e305c2?1761120363)
/assets/images/13998491/original/2c0bacdc-acdf-43fa-b0fd-64e707846940?1690437015)
/assets/images/13998491/original/2c0bacdc-acdf-43fa-b0fd-64e707846940?1690437015)
