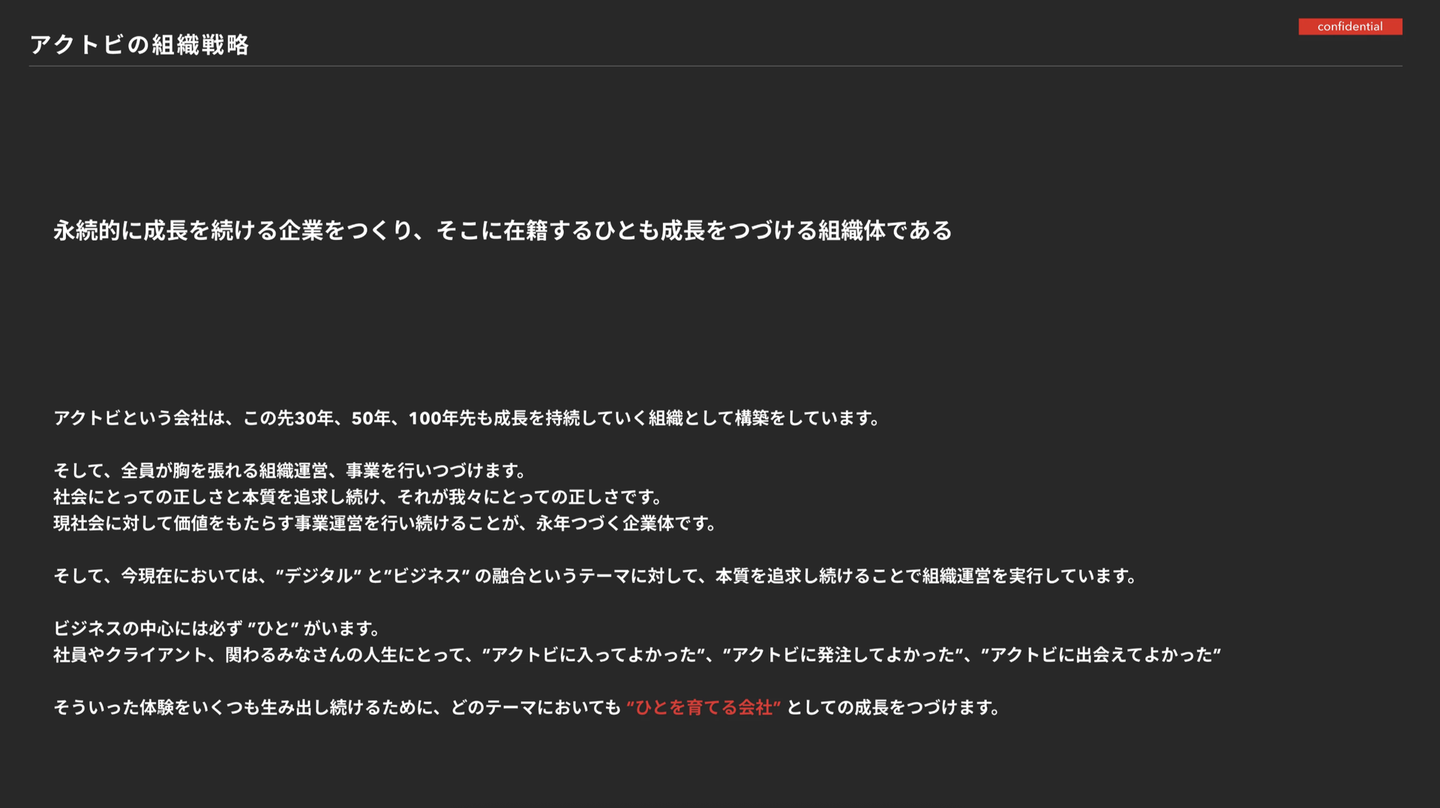こんにちは。アクトビ代表の藤原です。
アクトビは2025年で9期目を迎えました。
おかげさまで、事業は黒字成長を続け、仲間も増え、パートナーからのご相談も増えています。会社としての健康状態は、一見すると悪くありません。
でも最近ふと、「本当にこのままでいいのか?」と立ち止まる出来事がありました。
目次
あらためて見ると、企業の“生存率”は衝撃的だった
「利益が出てる=安心」という思い込み
成長しているように見えても、“成長設計”がなければ限界がくる
「人の成長が止まった瞬間に、会社の成長も止まる」
アクトビが目指す「100年先も成長し続ける組織」
創業期から変わった、“会社観”というスタンス
「これって、何のため?」が自然に飛び交う組織
変えるべきことは柔軟に、変えてはいけないことは頑なに
「アクトビに出会えてよかった」と思ってもらえる会社でありたい
「生存率を上げたい」からやっているわけではない
最後に──100年後も、「ちゃんと残ってる会社」であるために
あらためて見ると、企業の“生存率”は衝撃的だった
創業当初によく目にしていたデータがありました。
「企業の生存率」です。
- 創業5年後に残っている企業:およそ40%
- 創業10年後に残っている企業:およそ6.3%
つまり10年で約9割の会社が消えていく。
これは “赤字になったら潰れる” という単純な話ではありません。
黒字でも、社員がいても、事業が続いていても、企業は静かに終わっていく。
このフェーズに入ってから、もう一度その数字を見てみたとき、背筋がゾッとしました。
目の前の業績だけを見ていると、 “今” はうまくいっているように見えます。でも、じゃあ “10年後も” 同じように存在できているのか?
「利益が出てる=安心」という思い込み
アクトビはここ数年、安定して黒字を出し続けています。
採用もできているし、チームの雰囲気も悪くない。
でも、それって本当に「安心できる状態」なんだろうか?と。
というのも、僕自身これまでに、黒字でも潰れた会社や一見順調でも急速に衰退していった企業を何社も見てきました。
それらに共通していたのは、「変化に適応する準備がない」こと。
• 現場では新しい挑戦が生まれていない
• 組織がマンネリ化し、思考停止していく
• 成果は出ていても、目的を見失っている
そうした「静かな衰退」は、気づいたときにはもう手遅れなことが多い。
いくら売上が上がっていても、「なぜそれをやるのか」が明確でなければ、会社はあっという間に “ただ回ってるだけの組織” になります。
そして、気づかないうちに、成長の天井にぶつかっていく。
成長しているように見えても、“成長設計”がなければ限界がくる
「成長すること」と「成長しているように見えること」は、まったく違います。
短期的な売上アップや、新規事業の立ち上げ、採用の成功などは、目に見えやすい “成長の成果” です。でも、それが “持続するかどうか” は、まったく別の話。
成長には、「再現性」と「継続性」が必要です。
- 成果が誰か一人に依存していないか?
- そのやり方は、3年後、5年後も通用するか?
- 新しい挑戦が生まれ、仕組み化されているか?
そこで大事にしているのは、“その場しのぎの成果”ではなく、構造としての成長があるかどうか。
つまり、成長の“設計図”があるかどうか。
これが、「会社が続くかどうか」の分かれ道だと考えています。
「人の成長が止まった瞬間に、会社の成長も止まる」
アクトビの思想はとてもシンプルです。
「人が成長し続けられる限り、会社も成長できる」
僕らが扱っているのは、技術でも、プロダクトでもなく、人の知見と行動 そのものです。
エンジニアやデザイナーの技術力は大切ですが、もっと大事なのは「その人が、どれだけ早く学び、変化に対応し、意味を問えるか」という人間力の部分。
特に今のような変化が激しい時代、昨日の正解が今日には通用しなくなる。
そんなとき、「変化を前提に、自分自身を更新し続けられる人」が会社の未来をつくる。
だからこそアクトビは、“個人の成長”を企業戦略の中核に据えているのです。
アクトビが目指す「100年先も成長し続ける組織」
![]()
アクトビが掲げる組織戦略は明確です。
「この先30年、50年、100年先も、正しく成長を続ける企業体であること」
だから、僕たちは「会社をつくる」のではなく、「成長を設計する」ことに時間を使っています。
その設計の中核にあるのが「ACTBE Operating System(OS)」です。
アクトビで働く人が、どこにいっても活躍できる“本質的なビジネスパーソン”になるための成長設計。
具体的には、
- 専門性だけでなく、思考力・言語化力・本質的な視点を鍛える評価制度
- エンジニア・デザイナーが“作れる”ではなく、“意味を問える”人材になる文化
- 目的から逆算して動けるチーム設計
こうした仕組みを、地道に・徹底的に、作ってきました。
創業期から変わった、“会社観”というスタンス
創業1〜2年目のころは、僕自身「自分の会社」という感覚が強かったと思います。
正直、自分の延長のように会社を見ていたし、社名に自分の意志がそのまま反映されていた。
でも3期目くらいから、大きく意識が変わりました。
「これは みんなの会社 なんだ」
組織の未来は、社員やパートナー、その家族にも関わってくる。自分の判断が、他人の人生を左右する。
その事実に向き合ったとき、僕の中で 会社のあり方 が一変しました。
事業をつくるだけじゃ足りない。
「ここにいる人が、正しく育っていく場所」にしなければならない。
その想いが、今のアクトビの経営方針のコアになっています。自分の判断が、社員の人生に影響を与える。
その重さを感じた瞬間、会社のビジョンが変わりました。
事業を成長させるだけじゃ足りない。
“ここにいることで、人が成長し続けられる場所”でなければ意味がない。
それが今のアクトビの原点になっています。
「これって、何のため?」が自然に飛び交う組織
アクトビでは、「目的思考」が社内の共通語になっています。
どんな場面でも「なぜそれをやるのか?」が問われます。
- プロダクト設計でも
- 営業資料の1枚でも
- 社内会議のアジェンダでも
常に、「これって何のため?」という問いが飛び交う。
手段のための手段にならないこと。
作ることが目的にならないこと。
この思想が浸透しているからこそ、変化に対して強く柔軟な組織でいられると感じています。
これが、僕らが掲げる Purpose Driven(目的駆動) という思想です。
変えるべきことは柔軟に、変えてはいけないことは頑なに
僕たちはこれまで、いろんなやり方を変えてきました。
- 提供サービスの形も変わった
- 価格設定の考え方も変えた
- 契約形態もアップデートした
- 技術スタックも、働き方も柔軟に変えてきた
でも、理念だけは一度も変えていません。
「人を育てる会社であること」
「社会にとって本質的に意味があることをすること」
この2つの軸さえ守られていれば、やり方はいくらでも変えていい。
むしろ、変えるべき。
これが、アクトビの“変化を前提とした一貫性”です。
下記のYoutubeでこれまでについて振り返っています。
「アクトビに出会えてよかった」と思ってもらえる会社でありたい
僕が最も大事にしている言葉があります。
「アクトビに出会えてよかった」
これは、社員からでも、クライアントからでも、パートナーからでもいい。
誰かの人生の中で、「この会社があってよかった」と思ってもらえる存在でありたい。
そのためには、目先の売上ではなく、その人の未来にとって意味のある関わり方 をしなければならない。
だから僕たちは、単なる受託会社ではなく、「伴走支援のパートナー」として機能し続けることにこだわっています。
「生存率を上げたい」からやっているわけではない
ここまで語っておいてなんですが、
僕たちは 企業生存率を上げたいから、この方針を選んだわけではありません。
「社会にとって意味のあることを、本気でやり続けたい」
ただ、それだけです。
意味のあることをやり続けるには、会社が続いている必要がある。だから僕たちは続く構造をつくっている。
順番は、逆なんです。
最後に──100年後も、「ちゃんと残ってる会社」であるために
10年後も、50年後も、100年後も。
「アクトビ、ちゃんと残ってるよね」
そう言われる会社でありたい。
ただ“残ってる”だけじゃなく、意味があるから残ってる 会社でいたい。
そのために、これからも自分たちの在り方を問い続け、アップデートを続けていきます。
この記事が、どこかの誰かにとって「続く会社とは何か」を考えるきっかけになれば嬉しいです。
YoutubeやPodcastでアクトビの経営や考え方についてはなしていますので、そちらもぜひご視聴ください!