- Product Manager
- コーポレートエンジニア
- Customer Support
- Other occupations (22)
- Development
- Business
- Other
こんにちは、ユニファ採用&広報チームです。今回は、ユニファVPoEの柿本にインタビュー。エンジニアとしてキャリアをスタートした原点、ユニファに入社するまでの経緯や開発から感じた保育における社会課題などについて語っています。ぜひ、最後までご覧ください!
※本インタビューは2025年9月時点の情報です。
プロフィール
柿本 玄(かきもと・しずか)
VPoE 兼 プロダクトデベロップメント本部 副本部長
ワークスアプリケーションズに新卒入社。JavaエンジニアとしてSCMを始めとするERPパッケージとECシステムの開発に従事。その後、ITコンサルに転身し、PMOの業務を行う傍ら、自身でクラウドファンディングやQRコード決済サービスを構築。2018年9月にユニファに参画し、新規事業の開発担当として、ルクミーICTを立ち上げ。現在は6歳と3歳のこどもを育てる二児の父。
機械工学からソフトウェアへ。一貫して追求した「ユーザー視点」
― アメリカでの機械工学専攻からプログラミングの世界へ
私のエンジニアとしてのキャリアは、アメリカで機械工学を学んだことから始まりました。私自身、兄と姉がいるのですが、二人ともアメリカの大学に通っていたという家庭環境もあり、自然と私もアメリカの大学への留学を選択していました。
正直、英語という言語自体に不安はあったものの、数学が得意だったこともあり、「最悪数字だったら言葉が通じなくてもできるのでは(笑)」という思いで、大学では最初の3年間は物理学を、その後機械工学を学び、合計5年間をアメリカで過ごしました。
大学では航空力学を専攻し、飛行機の羽の形状が揚力にどう影響するかなどをシミュレーターで研究する日々を送っていました。このシミュレーターをプログラミングで構築する経験が、ソフトウェア開発に興味を持つきっかけになりました。
― インターンと新卒で学んだ「ユーザーの困りごとをシステムで解決する」というやりがい
ソフトウェアエンジニアになることを決定づけたのは、大学在学中のインターンでの経験です。ある時、当時の主任に「ログをまとめてレポートにするツールをVBAで作ってくれない?」と言われました。ツールとしてのプログラムを作るのは初めての経験でしたが、VBAの本を読み漁って、最終的にボタンひとつでレポートを作成するツールになりました。それを主任に見せたところ「すごい!これまで毎週2時間かけていた仕事が1秒で終わるよ!」とものすごく喜んでいただきました。
その時、ソフトウェアの持つ力の大きさに衝撃を受け、大学卒業後はソフトウェアエンジニアとして新卒でワークスアプリケーションズに入社しました。Javaエンジニアとして、SCM(サプライチェーンマネジメント)を始めとするERPパッケージやECシステムなどの開発に4年間従事しました。特に販売管理システムにおいては、受注データの入力、在庫確認、他システムとの連携、発注処理など、幅広い業務の開発を担当させてもらいました。

この頃から、「ユーザーがどう使うか」というユーザー視点を常に意識するようになっていました。仕事をする上で大切にしているひとつでもある「ユーザー視点で物事を考える」という姿勢はもちろん今もあり、今後のキャリアに繋がる重要な基礎を築けた場所でしたね。
‟作りたいもの”を形にする挑戦と、“こどものため”に働くという転機
― ITコンサルとして上流工程へ。自社サービス開発で「形にする」喜び
様々な経験を積む中で「より上流工程に携わりたい」という思いが強くなり、さらなる挑戦としてITコンサルに転職しました。
最初の3年ほどは客先常駐をして、クライアントの業務改善とそれに合うステムを構築する、いわゆるPMO業務をしていました。既存業務をなるべく変更したくないクライアント社員とパッケージ製品をなるべくそのまま導入したいベンダーとの板挟みなど、ITコンサルの業務は想像以上に泥臭く、何度も逃げ出したくなりました(笑)。それでも最後にはクライアントに「このシステムいいね!」と言ってもらえるとすごく嬉しくて、ソフトウェアが大勢の人の役に立つことを実感した経験でした。
その後、「自社サービスを作りたい」という当時の社長の思いと「自分の手でゼロからプロダクトを作りたい」という私の思いが重なり、自社サービスを作ることになりました。週3日はITコンサルタントとして顧客案件に対応しながら、残りの週2日と週末は自身でクラウドファンディングやQRコード決済サービスを開発するなど、高い熱量で働いていました。自分で営業して問い合わせ対応もしていたので、毎日が本当にチャレンジの連続で、もちろん大変な場面もありましたが、それ以上に、「自分たちでサービスを作り、ユーザーに使ってもらう」という、‟作りたいもの”を形にする挑戦ができた時は、本当に喜びでいっぱいになりました。
― 「こどものため」という気持ちの変化と、ユニファで切り拓く新たなキャリア
日々業務に取り組む中で、私の妻が上の子を妊娠したことが、仕事の価値観における大きな転機になりました。これまでは、「自分が作りたいものを作る」ことに主眼を置いていましたが、第一子を迎えるにあたり、「こどものためになる仕事や、もっと直接的に子育てや社会のためになるサービスに関わりたい」という思いに価値観が変化していったんです。

もちろん、これまでもやりがいを持って働いていたのですが、こどもの教育や保育に関する分野でキャリアを築きたい、と思ったタイミングでユニファに出会いました。
私がユニファに入社した2018年当時は、保育業界はICT化が進んでいない未開拓の分野だと認識していました。いくつかの企業で転職を検討する中、ユニファの「テクノロジーの力で、家族をもっと豊かに」という当時のビジョンに共感したことと、私が得意としていたRubyという技術スタックがユニファの事業内容と合致したことが決め手となり、入社しました。
― ルクミーの基盤に携わることでみえた、保育における業務課題や社会課題
入社後は、ちょうどパッケージ製品として保育ICTを構築するプロジェクトが動き出しており、その開発担当となりました。一方、当時のルクミーは「フォト」「午睡チェック」「体温計」のみで、顧客データなどマスターデータが保育ICTの構築に耐えられる状態ではなかったため、まずはその整備に着手しました。
その後、パッケージ製品をゼロから作るのではなく、当時他社が運用していたキッズリー※を買収することになり、その移管プロジェクトの開発リーダーを担当しました。キッズリーの安定運用後は、キッズリーとルクミーのアカウント統合プロジェクトを経て、2020年からは、今のルクミーのICT部分である連絡帳や帳票管理などの機能開発を本格的に開始し、保育者の業務課題解決に深く関わってきました。
※リクルートマーケティングパートナーズ社より買収したICTサービス。2026年3月31日をもってサービスをクローズし、順次ルクミーのICTにお乗り換えをご案内しています

2025年1月、ユニファのVPoEに就任し、以降はセキュリティ・技術負債の対策など技術戦略の策定と採用・評価制度の構築・技術広報など、開発組織全体の成長強化を推進しています。
こどもが生まれることをきっかけに保育や子育てに興味を持つようになりましたが、実際に開発を進める中で、保育現場には多くの課題が残されていることを感じました。入社時に共感した”テクノロジーの力”で、さまざまな課題と向き合い、より多くの子育て世帯やこどもたちが輝けるよう、今後も信頼できるメンバーたちと挑戦を続けていきたいです。
AIで社会課題を解決し、挑戦を続ける「Play Fair」な組織へ
― 現在注力するAI活用と今後の挑戦
ユニファは組織全体としてもAI分野に注力しており、開発組織もこの動きを加速させています。AIは世の中にとっても、我々エンジニアにとっても新しい技術であり、プロダクトに実装してすぐに価値提供できるものではありません。だからこそ、恐れずに挑戦していく組織でありたいと考えています。
AIをはじめとする新しい技術に積極的に取り組むマインドを持ったエンジニアの方には、ぜひユニファで挑戦をして欲しいです。ユニファには、AIやLLMに強みを持つR&Dチームがあり、勉強会なども開催しているので、スキルを学ぶ環境も提供しながら、メンバーの技術的成長を後押ししていきたいと考えています。
今後でいうと、ユニファ/ルクミーは、保育・子育て業界における社会課題解決という魅力的な事業内容ではあるものの、まだサービスを知らない方がいるのも実態です。サービスの魅力を伝えるために、実際に私自身もさまざまなイベントに登壇しています。
今年2025年3月には、ユニファがGOOGLE CLOUD主催の「第3回 生成 AI Innovation Awards」にて多数の企業の中からファイナリストに選ばれ、ピッチコンテストに参加しました。また、その後8月に開催された「Google Cloud Next Tokyo」では事例紹介もさせていただき、聴衆の方から「私のこどもが通う保育施設にも導入してほしい」「素晴らしいサービスですね」などといった声もいただいたんです。

2025年8月5日に東京ビッグサイトで開催された「Google Cloud Next Tokyo」登壇の様子。保育AI開発の最前線として、ルクミーの「たよれるくん」を生成AI活用事例として紹介
ユニファのサービスが多くの方に求められていることを実感し、単純に嬉しかったですし、このサービスを今まで一緒につくり上げてきたメンバーにも本当に感謝しています。
「Kaigi on Rails 2025」では託児スポンサーとして協賛をし、子育てをしながらエンジニアとして働く方々のサポートも積極的に進めていこうと思います。
― 現在のメンバーと、一緒に働きたいメンバー像
現在在籍しているメンバーは、自分の論理や正論を振りかざすのではなく、お互いをリスペクトし「Play Fair」に対等で建設的なコミュニケーションが取れる人たちが多いと思っていますし、実際にそうした方が活躍できると思います。
さらに、現状維持に満足せず、一歩踏み込んだ「One More Step」な行動を起こせる方も歓迎しています。AIのような新技術への挑戦意欲が高いエンジニアは、ユニファでも大きく成長できると思っています。ユニファは子育て中のメンバーが多いですが、もちろんこどものいない方も大勢活躍しており、家族の有無に関わらずお互いの立場を尊重し合い、多様性を許容する文化が根付いてるのではないでしょうか。今後も、相互で助け合いながら、「個人」「組織」共に成長していけると嬉しいですね。
AIのような新しい技術に果敢に挑戦し、自らが開発したサービスが子育てや社会に貢献していく喜びを感じたい方や、ユニファの開発組織の未来に共感し、自らが貢献できるポイントを見出された方は、ぜひお気軽にご連絡いただけると嬉しいです。
/assets/images/4845745/original/6afe4845-0065-4ed6-8d6a-511d59b4697c?1585798047)

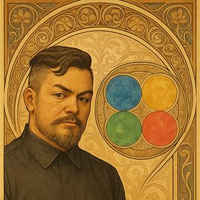








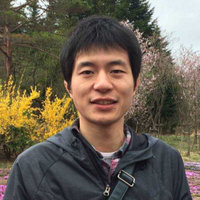

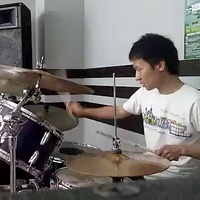




/assets/images/4845745/original/6afe4845-0065-4ed6-8d6a-511d59b4697c?1585798047)


/assets/images/4845745/original/6afe4845-0065-4ed6-8d6a-511d59b4697c?1585798047)
/assets/images/4845745/original/6afe4845-0065-4ed6-8d6a-511d59b4697c?1585798047)

