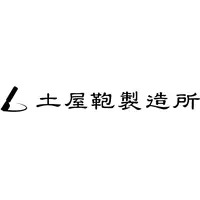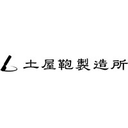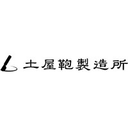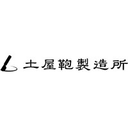長野県軽井沢町・発地にある「 ほっちのロッヂ 」は、5年間愛されてきたまちの診療所です。診療所が面する道を車で5分ほど進むと、土屋鞄製造所の 軽井澤工房店 があります。
業種は異なりますが、両者には 地域との関わりを大切にしている という共通点があります。鞄をお届けするだけでもなければ、診療を行うだけでもない。ランドセル職人が地域でワークショップを行ったり、地域の人たちが気軽に診療所でお茶をしたりしています。
前編では、ほっちのロッヂ共同代表・藤岡聡子さんを迎え、軽井澤工房店 店長・韓宏宣が対談。地域といかに関係性を深めてきたか、その取り組みについて話してきました。 ▼前編の記事はこちら
地域での取り組みを広げていくうちに、働く仲間のモチベーションやブランド価値の高まりにも貢献しているのを実感しているといいます。 さらには、シームレスな働き方が、個人の暮らしの実感にも結びついているのだそう。 後編では、このことについて詳しく話しました。
目次 子どもたちからの手紙が職人へ
場所のリズムにのって、ライフサイクルを描く
働くも暮らすも、どちらも楽しい
子どもたちからの手紙が職人へ 韓 宏宣: 毎年5月にヤッホーブルーイングさんが主催されている「 超宴 」に今年も出店しました。
職人たちとレザー缶ホルダーをつくるワークショップをしたんですが、午前の予約は満席の盛況ぶりで、お客さまが喜ばれる姿をみた職人たちも、すごくうれしそうな表情を浮かべていました。 地域と関係性を持つようになってから気づいたことですが、それが実は、 組織の肯定感を生み出し、ブランドにとっても強さになることだと思っています 。
軽井澤工房店には、遠方からランドセル工房を見に来てくださるお客さまもよくいらっしゃいます。 どんな工程をしているのか紹介すると、お子さまだけではなく、親御さんも前のめりに、すごくキラキラとした目で興味津々に見てくださるんです。
韓: 地元の小学校の皆さんも、例年社会科見学に来てくださるんですが、そのときにも小学生が職人たちがミシンを使って仕上げる様子に歓声をあげて喜んでくれて。
手紙もたくさんいただいて、工房へと繋がる廊下には、そんなお手紙でいっぱいです。 そういう光景に出会うたびに、僕は職人でないのにもかかわらず、いつも誇らしくなるんですが、地域に出店することで、職人さんが実際にそのようなお客さまの生の声を知ることができるようになりました。
いまの時代においては、「つくる」と「売る」という製造から販売まで時間軸としては一番遠いものが会社で一貫してあり、かつ場所も近くにあるという環境は、とても貴重で恵まれていると思います。
今年は10周年の記念に、普段は立ち入ることができない軽井澤工房でのランドセルづくりの様子を、間近に見学できる「 親子で工房見学 」が7月25日に開催予定です。
藤岡 聡子: 面白いことに、組織としてほっちのロッヂはすごく構造が似ていると思います。 プロフェッショナルと、お客さまや利用者をつなぐ仕事をしているという意味で、私たちは似ているのかもしれません。
医師や看護師もランドセル職人さんと同様に専門職で、基本的には固定化された場面でしか会わないんですが、ほっちのロッヂは、多面的な関わりをします。 好きなこととか、気が合ったとか、関心ごとなど、普通の社会と同じ出会い方ができる場所であり続けるということをここでは大事にしているので、音楽とか編み物を一緒に楽しみます。
だから、少し変に聞こえるかもしれませんが、ほっちのロッヂは、患者さんのリピート率がすごく高いんですよ。 医師と患者として顔を合わせるときとはまったく異なる、柔らかい表情に出会えることで、ハイストレスな現場にとっても、いい影響が生まれるようになりました。 「医師や看護師のみなさんが、機嫌よく働いているのは一体なぜですか?」と聞かれることもあります。
場所のリズムにのって、ライフサイクルを描く 藤岡: ほっちのロッヂという場所を地域にひらくようになってわかってきたことですが、 場所には場所のリズムもありますし、エリアにおけるリズムもある。
例えば、軽井沢は春から夏にかけてお客さまが増え、冬は減るというリズムがありますよね。
藤岡: それらに合わせていくと、 ひとつの働き方に留まらない自分を表現する舞台があるっていいなと思います。 役割がひとつではないから、まちに複雑に主体的に関われるようになる。 それってすごく大事なことだと思っていて。自分を消費しないというか、 新しくライフサイクルを自分なりにつくっていくことが、幸せにつながると思っているからですかね。
提供:ほっちのロッヂ
藤岡: そういう意味ではこの軽井沢という土地は、 どんな景色でどんな暮らしがしたいのか、どういうことに関心があるのか、ということに人々が目を向けてくれるので、自分の生活を組み立てやすいなと思います。
季節によって戻ってくる仲間がいたり、二拠点で生活する仲間がいたり。
働くも暮らすも、どちらも楽しい 韓: このまちは、人が少ないからこそ、目を見て話してくれる。時間をかけて向き合ってくれる人が多いんですが、最初は正直それが嫌で(笑)。
「何に興味があるの」「これから何をしたいの?」となんでこんなに問いかけてくるのと、来たころは戸惑ったりしていました。 でも、 知ってもらうってとても大切なことだとも思います。 僕は在日4世で尼崎の朝鮮学校に通っていたときは、朝学校に行くと何かが投げ込まれてることもありました。
公立高校へ進学して委員長などに立候補して、 自分という個を知ってもらえるよう積極的に動いていったとき「知ってもらえたら、ちゃんと友だちになれる」って気づいたんですよね。
韓:軽井沢に初めて来たときも、新しい環境で自分を知ってもらうことの続きだ、と思いました。 巻き込み、巻き込まれながら、ブランドや地域を変えていくということを、このまちでもしようと色々もがきました。 必死にやっているうちに、段々と「このまちの皆さんは、みんな一生懸命に生きているな」とすごく刺激を受けるようになっている自分がいて。
長期的なビジョンを持っていて、かつ目の前のことを楽しんでいる。 素敵な人たちに出会うなかで、自分を使っていろんな仕事を輝かせられたらいいし、自分も輝かせたいなと思うようになっています。 藤岡: 韓くんはいつも応援したくなる存在です。 ローカルって働くにしても暮らすにしても、自分の方法を探すことができる、本当に面白い場所 だと改めて教えてもらった気がして、うれしいです。
▼プロフィール
藤岡 聡子(ふじおか・さとこ) / 福祉環境設計士、ほっちのロッヂ共同代表 徳島県生まれ三重県育ち。長野県軽井沢町在住。夜間定時制高校出身。人材教育会社を経て2010年、24歳で介護ベンチャー創業メンバーとして有料老人ホームを創業。2015年デンマークに留学。その後、東京都豊島区のゲストハウスで「診療所と大きな台所があるところ ほっちのロッヂ」を立ち上げ、医師と共に共同代表に。第10 回アジア太平洋地域・高齢者ケアイノベーションアワード2022 Social Engagement program部門で日本初のグランプリ受賞、同年グッドデザイン賞2022受賞/審査員の一品にも特別選出。2023年日米リーダーシッププログラム日本代表団として選出。3児の母。 韓 宏宣(ハン・クァンソン) / 土屋鞄製造所 軽井澤工房店 店長 兵庫県生まれ、長野県軽井沢町在住。尼崎朝鮮初中級学校出身、在日コリアン4世。2017年に立命館大学国際関係学部に入学。カナダへの留学などを経て2021年4月土屋鞄製造所に新卒入社。丸の内店にて1年半務めた後、2023年1月に軽井澤店に異動。店長となる。BAR三笠 THE BASE マネージャー。
▼関連記事はこちら
病気の人はただ弱い存在ではない。軽井沢の森の中に「人と人とが補い合う場所」ができるまで
その人らしく命を終える瞬間のために、最大の力を尽くす。白衣を着ない軽井沢の診療所
▼対談をした場所
土屋鞄製造所 軽井澤工房店 住所:長野県北佐久郡軽井沢町発地200 営業時間:10:00-18:00(時期によって変動あり) 軽井澤工房店の開店10周年を記念して、2025年7月11日からさまさまなイベントを開催します。
文:安重 百華
コーポレートブランド推進室所属。2023年、土屋鞄製造所 入社。土屋鞄の社内報『革ノオト』編集部。
主な写真:小林明子
コーポレートブランド推進室室長。ハリズリーに入社した2022年に創刊したOTEMOTOは、丁寧なものづくりと人に寄り添うウェブメディア。
(掲載情報は取材当時のものです)