個人の能力に頼り、属人化しがちな営業の成果を「見える化」し、「最大化」するセールスイネーブルメント。スタディプラスの大学広告事業部に2025年から新設されました。効果最大化の方法は、会社それぞれで異なるため、スタディプラスでは今まさにその道筋づくりをしています。グループを率いる杉村高志さんは、「今」と「未来」両方を大事にできるセールスイネーブルメントでありたいと話します。その真意を紐解き、思いに迫ります。
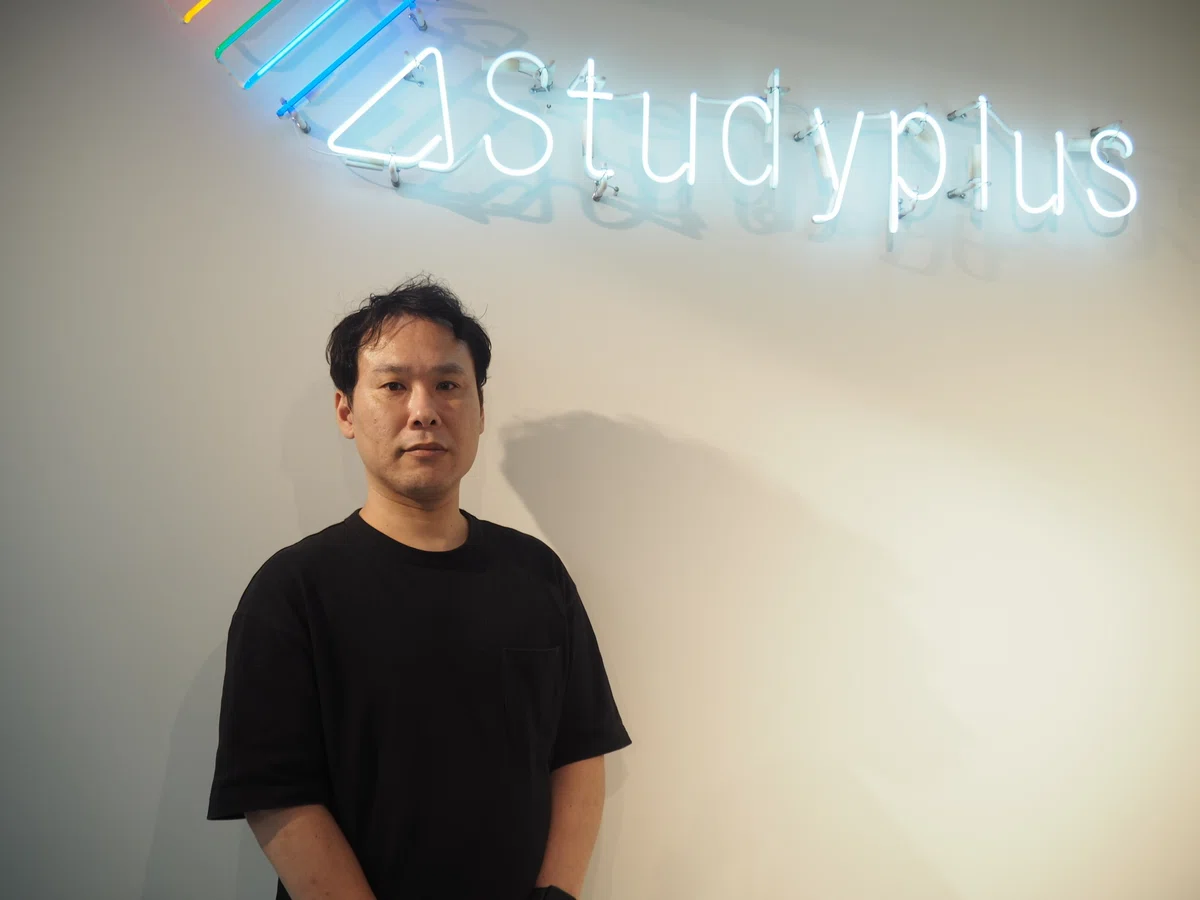
杉村 高志(すぎむら たかし)Studyplus Ads事業本部
セールスイネーブルメントグループマネージャー
2025年入社、2025年4月よりAds事業本部セールスイネーブルメントグループマネージャーに就任。当社参画前は、メディア事業会社にて営業マネージャーとして従事し、セールスイネーブルメント部門の立ち上げを担当。その後、法務系SaaS企業にて同部門の立ち上げおよび責任者を務めたのち、コンサルタントとして企業のセールスイネーブルメント支援を行う。
セールスイネーブルメントとは
ーセールスイネーブルメントって具体的にはどんなことをするのでしょうか?
杉村:「ハード面」と「ソフト面」2つあると思っていて、「ハード面」は、営業に必要な事象をフェーズ化して達成すべきことを見える化したり、足りない能力を補うために育成したりするいわゆるイネーブルメントの仕事です。一方「ソフト面」は、普段から困ったときに助けてくれる存在になるイメージで、具体的には「こんなことに困っている」という営業の皆さんの話を聞いたりアドバイスをしたり、伴走していく取り組みです。私としてはこの「ソフト面」が非常に大切だと考えているんですよね。
ーなぜそのように考えているのですか?
杉村:例えばイネーブルメントとしてフェーズ作りをして、営業パーソンの育成・トレーニングを実施したとしても、明日から急激に営業成績が伸びることって、ないですよね。でも未来のためにやらなくてはいけない。一方で、営業の皆さんは、今を見ています。「今月達成しなくてもいいから3年後、達成してね」みたいな会話はしないですよね。
そうなると、イネーブルメントは「未来」を見てるよね。営業は「今」を見てるのに。という視点のズレや対立が生じてくる。やっぱりまずは、人と人との関係から始まりますので、「今」の視点を大事にしながら一緒に「未来」を見ていけると、良い組織作りができるのではないかと、考えているんです。

「自分のコピー」を作ろうとした営業時代
ー少しずつセールスイネーブルメントの仕事が見えてきたような気がします。杉村さん自身のことも伺っていきたいのですが、当初は営業職をされていたと伺っています。そこからセールスイネーブルメントになったのには何かきっかけがあったんですか?
杉村:それはね、自分自身の失敗なんですよ(笑)営業の仕事をしていた時にマネージャーも経験したんですが、今でも本当に「ああ、失敗したな」と思ってるのが、自分のコピーを作ろうとしてたんですよ。
ーどういうことですか?
杉村:営業ってほとんどの場合、結果を出した人がマネージャーになるんですよね。なので、自分自身で売れた自負みたいなのがあるじゃないですか。ある種の武勇伝みたいな。それを100%押し付けてたんですよ。
ーやってしまいがちですけどね・・・
杉村:うまくいくわけないですよね。部員の個性やキャラクターとか、多様性みたいなことを完全に無視したやり方で、本当に結果が出なかったんです。それで色々調べていたら「セールスイネーブルメント」という考え方に出会いまして、ミイラ取りがミイラになるみたいな、面白い考え方だなと思ったんです。
杉村:調べながら、2年目からはイネーブルメントの考えを取り入れて行ったんですが、そしたら昨年度の2倍の実績になりまして、さらにいうと、そのとき私のチームは人数が半分になっていたので、400%の成果を出したことになりまして、お前は何やったんだ!ということになったんです。

パーパスの実現が持続的な組織作りにつながる
ーそこからセールスイネーブルメントとしての道を切り開いて行ったんですね。その後、法務系SaaS企業の同部門立ち上げの責任者を経験し、コンサルタントとして各企業を担当したのちスタディプラスへのジョインということになりますが、スタディプラスで目指していきたいことはありますか?
杉村:スタディプラスが掲げているパーパスを実現することによって持続的な組織作りにも繋げていきたいと思っています。
ーどうすればいいのでしょうか?何かポイントはありますか?
杉村:取り組みの順序って大事ですよね。具体的には、What(ありたい姿)→Why(なぜ必要か)→How(どう実現するか)の順序で進めるべきだと思っています。
ー詳しく教えてください
杉村:会社の中には、見えている課題も見えてない課題も、いろいろありますが、ほとんどの場合、その課題に対して直接アプローチしたくなると思うんです。今問題が起きてるから何とかしたいねとか、どうしたら良くなるのかなとか。でも実はこれHowの議論で、理想はどこか、なぜやらないといけないのかという議論や言語化はされていないことがほとんどなんですよね。
杉村:まずはWhatでありたい姿を描くこと、ここが非常に重要ですが、忘れられがちです。しっかりWhatが見えてから、現状を引き算して、問題をあぶり出し、その中で優先順位をつけていく。この順序を大事にしていくと、いろんなものがクリアになって、皆さんの中に納得感が生まれてきます。その答えが「確からしい」って思ってないと人って本気で取り組めないですよね。Whatを定めて、みんなが受容した状態を作れば、Howは方向転換や修正ができますので、最終的に持続性にも繋がっていきます。

杉村: スタディプラスのValueに「理想を描く」「学び変化する」がありますけど、イネーブルメントの仕事と近いなと思っていて、先ほどお話しした通り「理想を描く」はWhat(ありたい姿)ですし、その後にHowを考えながら改善していこうというのは「学び変化する」ことだと思います。学び変化するためにはその変化を感じ取れることが必要なので、私は営業の結果の記録を残して、小さな変化に気づかせてあげたい。さらには営業だけではなくて、他の部署でもこの公式に沿って考えてくれる人が増えてくれるといいなと思っています。
ー最後に、スタディプラスで働くことを検討している方に一言お願いします!
杉村:私が今取り組んでいるのは一人で抱え込まない組織づくりです。リモートワークですし、自由な働き方ができますが、能力を伸ばす機会や、学ぶ機会は個人に委ねるのではなく組織全体で生み出していけるようにしたいと思っていますので、不安に思わないで欲しいなと思っています。
一緒に働く仲間を探しています
スタディプラスでは働くメンバーの募集を行っておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひ以下をご覧ください。
スタディプラス株式会社's job postings

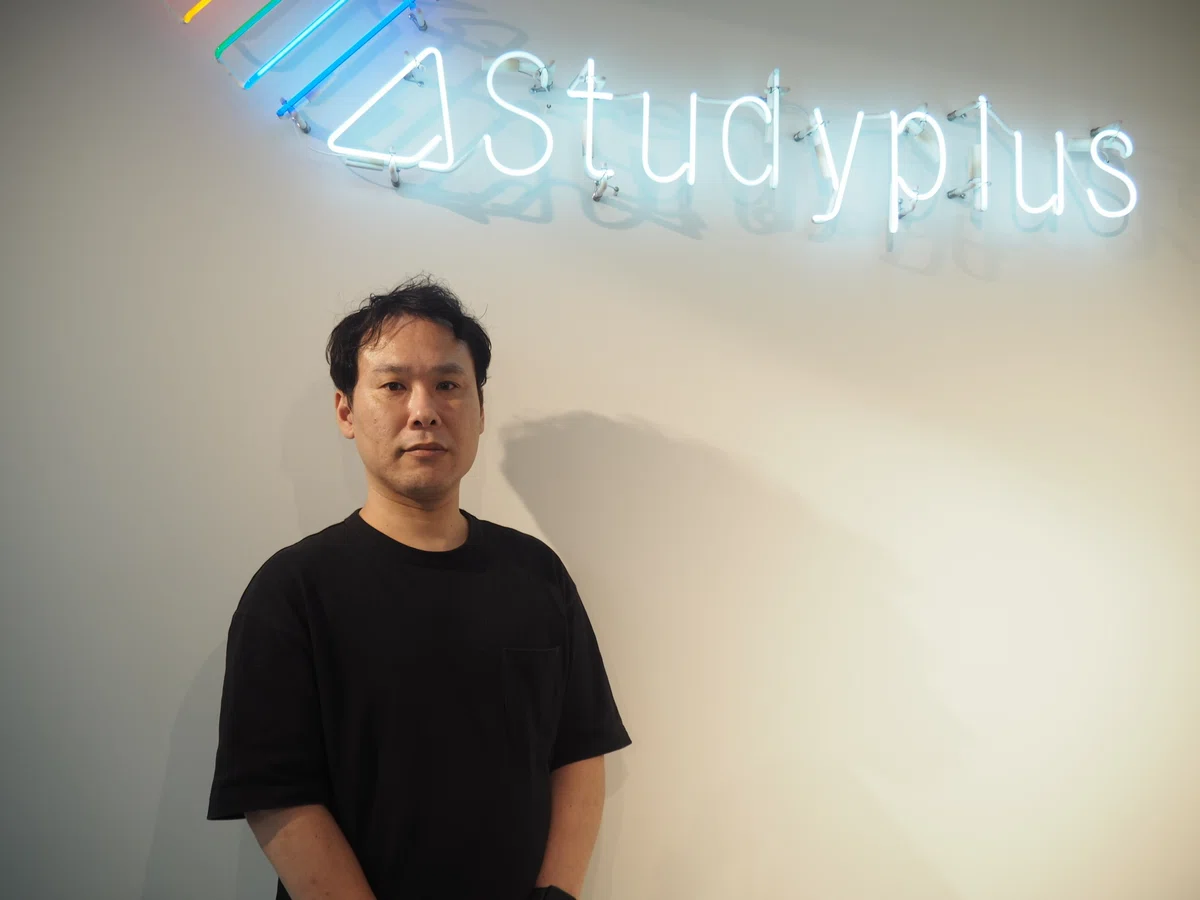



/assets/images/3034/original/a11dd7b2-bdaf-4920-b5c8-790dba7ffb49.png?1392712845)


/assets/images/3034/original/a11dd7b2-bdaf-4920-b5c8-790dba7ffb49.png?1392712845)
/assets/images/3034/original/a11dd7b2-bdaf-4920-b5c8-790dba7ffb49.png?1392712845)

