組織で働く私たちは、どんな過程を経て、より高い視座を持つリーダーへと成長していけるのか。サクラグには、「B/ ボードライン(Boardline)」という全社的な視点を持って事業と組織を動かすことが求められる、次世代の経営幹部を目指すキャリアラインがあります。その中でB4とは「ジュニアマネージャー」にあたる役職で、「ボードライン」の入口にあたるポジションです。
今回は、B4として活躍するUchida、Kondo、Yoshidaの3名にインタビューを行いました。この記事では、3名がその重要な役割を経験して感じたリアルなやりがい、個人から組織へと視座が変わる中で得られた成長、そしてチームを率いる上での工夫について、三者三様の視点から語られた内容をお届けします。以下のような方々の参考になれば嬉しいです。
・若手でも経営に近いポジションで成長したい方
・組織やチームを俯瞰しながらリーダーシップを発揮したい方
・新しいことに取り組み、成長スピードを実感したい方
・プロフィール
Kondo
コンサルティングディビジョン所属。2022年に長崎大学を卒業し、現ビジネス職として新卒入社。在学中はイタリア・中国・韓国・フィリピンなどに留学し、サクラグの選考で、仕事を精一杯楽しむメンバーの姿に憧れて入社を決めた。現在の業務は多岐にわたり、営業のチームリーダーから全社で実施する「みらい会議」の運営なども務めている。2022年の新人賞を受賞。
Uchida
福島大学在学中に内定者インターンを8か月経験し、2022年4月に新卒入社。2年目で福岡支社立ち上げメンバーに抜擢され、リーダーに就任。
現在はSangoport事業の営業とキャリアアドバイザーを兼任し、新規事業の立ち上げを準備している。
Yoshida
早稲田大学創造理工学部在学中に、インターンとしてサクラグにジョインし、Sangoportの開発を通じてエンジニアとしてのキャリアをスタート。2023年10月に正式入社。
現在はプロダクトディビジョンに所属し、Webディレクターとして多数のクライアントサイトの立ち上げ・運用を担当。制作事業のリーダーとして、営業からサイト運用まで幅広く推進している。また、社内開発プロジェクトの管理やメンバーの技術支援など、ディビジョン運営にも携わる。
目次
キャリアの歩みとチームの雰囲気
経営と現場の架け橋に。B4が語るそれぞれの役割と、深まる仲間との連携
メンバーの想いと会社のビジョンを繋ぐために
『難しさ』と、その先にある『やりがい』と『成長』
組織を牽引する存在になるための、次なる挑戦とキャリアプラン
最後に
キャリアの歩みとチームの雰囲気
━━まず、皆さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
Kondo:私は、新卒でQDXコンサルティング事業のセールス職として入社し、営業活動をメインに行ってきました。入社2年目以降はマネジメントに携わるようになり、同時に新卒採用や会社説明会などにも関わってきました。そして、2024年からB4に就任しています。
Yoshida:私は、2021年5月からインターンを経て、2023年10月に正式に入社しました。入社当初は社内開発を担当していましたが、その後クライアントワークも経験し、制作事業のリーダーとして体制づくりやプロジェクト推進を任されるようになりました。そうした経験を経て、2024年4月からB4を務めています。
Uchida:私も、入社前にインターンを経験し、2022年に新卒入社しました。内定者インターンでは事業立ち上げに携わり、入社後はQDXコンサルティング事業のセールスとして丸2年間営業活動を行いました。そして、入社3年目の4月からは現在のSangoport事業に異動し、営業活動を行っています。さらに、福岡支社の立ち上げや社内運動会、朝礼チームなど、部署を横断したプロジェクトも色々と担当してきました。
━━それぞれ忙しい中でコミュニケーションを取られていると思うのですが、実際のやり取りや雰囲気ってどんな感じなんでしょうか?
Uchida:基本はチャットでやり取りしています。全社視点で動かすプロジェクトや事業部を超えた進捗を共有しています。役員陣も入っているグループチャットなので、自然と会社全体の動きが見えるようになっています。
━━ミーティングもされているんですか?
Yoshida:はい。週1回ほどB4ミーティングを行っていて、その場で全体の進捗を共有しながら議論や意思決定を進めています。
経営と現場の架け橋に。B4が語るそれぞれの役割と、深まる仲間との連携
━━会社全体を見たときに、B4としての自分の役割をどのように捉えていますか?意識していることも含めて教えてください。
Kondo:私の最も大きな役割は、マネージャーや代表が描くビジョンを、高い解像度で深く理解し、それをメンバーに的確に伝える「橋渡し役」だと考えています。これからは、その役割に加えて、私自身が事業の未来を描き、経営陣に積極的に提案していく挑戦も増やしていきたいです。
Yoshida:B4メンバーの中で、エンジニア視点・技術者目線で事業や会社の方針について意見できるのが、自分の役割かなと感じています。そのために意識しているのは、自分がまだ知らない経営の知識について、臆さずに質問し、純粋な視点で吸収していくことです。私の素朴な疑問が、結果として役員の方々にとっても「この方針は本当にこれで良かったのか?」と議論を再確認するきっかけになることもあり、そこに自分の価値を発揮できていると感じています。
Uchida:Yoshidaくんの話に少し補足すると、私の視点からも、彼はプロダクトDiv.の良いモデルケースとして後輩たちを導く、重要な役割を担っていると感じています。
私自身に求められているのは、Kondoさんと同じく「橋渡し役」です。プレイングマネージャーとして現場に立つからこそ、役員が描くビジョンや戦略を、その熱量や意図を損なうことなく、同じ粒度のまま、自分の言葉でメンバーに伝えることを強く意識しています。あとは、部署やチームを横断したプロジェクトの推進など、組織全体を動かしていくことが求められていると理解しています。
━━B4というポジションになって、お互いの関係性は変わりましたか?
Kondo:変わりました。2人に「これってどう思う?」というような壁打ちを細かくするようになり、すごく距離が近くなったと感じます。
Uchida:私も同感です。コミュニケーションの頻度が増えたことで、目指す方向性など多くを語らずとも分かる関係になりました。前提のすり合わせなしに、抽象度の高い話ができるようになったのは大きな変化です。また、お互いをよく見るようになった結果、「この人の強みはここだ」というのが分かるようになったのは、B4になってからの大きな変化です。
Yoshida:確かに、それはB4として全社的な知識を共有しているからこそだと思います。業務で直接関わることが少なくても、全社的な話をする機会が増え、コミュニケーションも自然に増えたと思います。
メンバーの想いと会社のビジョンを繋ぐために
━━チームやDiv.を動かす上で工夫していることがあれば教えてください。
Uchida:メンバーのやりたいことと、経営が求めることの間を取ることを大事にしています。どちらの意図も汲み取れる状態を目指してチームを動かしています。
Kondo:B4というポジションは、代表が言うように「あくまで役割であって、偉いわけではない」と認識しています。そのため、後輩メンバーともフェアでフラットに議論できる環境作りを意識しています。
Yoshida:私は、コミュニケーションを大事にすることを意識しています。B4になってからより意識的にメンバーとコミュニケーションを取るようになりました。また、B4ミーティングで出た改善点や意見を、経営の意図も含めてメンバーに伝えるようにしています。その結果、メンバーが経営の視点を自分ごととして捉えられるようになり、チーム全体に良い影響が生まれていると感じています。
『難しさ』と、その先にある『やりがい』と『成長』
━━今のポジションで難しいと感じる瞬間と、それをどう乗り越えてきたかを教えてください。
Kondo:そうですね。いちプレイヤーとしての意見ではなく、来期の予算達成のために事業部としてどう成果を上げるか、という視点を持つ必要がある点に難しさを感じます。ただ、経営やマネージャーに近いところで直接インプットをもらえるようになり、より視座が上がったと実感しています。乗り越え方としてはまだ試行錯誤の途中ですが、自分の感情と実際の判断を意識的に切り分けて考えることを大切にしています。
Yoshida:私もKondoさんと似ている部分があります。難しいと感じるというか、意識的な変化があったのは、いちエンジニアや個人の目線から、組織目線で考える必要が出てきたことです。会社全体としてどう良くしていくかを考えるために、自分の行動や判断も組織目線で捉えるようになりました。
Uchida:2人の話もすごく分かります。私の場合は少し視点が違って、短期的な成果と、中長期的な投資視点でのリソースや予算の使い方のバランスを取ることが難しく、日々学んでいる最中です。目先の半年や1年だけでなく、3年から5年先を見据えた上で判断することが求められるので、その多角的な視点が必要な点に、このポジションならではの難しさを感じています。
━━では、やりがいを感じた出来事についてお聞かせください。
Uchida:やりがいを感じるのは、B4という立場だからこそ、経営目線とメンバー目線の両方を理解できる、という点に尽きますね。経営陣がどういう傾向で意思決定をするのかが見えてくるので、それを踏まえて「メンバーが求める成果を出すためには、どう説明すれば承認を得やすいか」を一緒にメンバーと考えることができます。
以前、あるシステムの導入を進めた際も、メンバーとしての提案だけでなく、経営の視点を持った上で提案できたからこそ、スムーズに話が進んだ実感がありました。このように、双方の視点を繋いで物事を前に進められた時に、特にやりがいを感じます。
Yoshida:私の場合は、これまで以上に制作事業に注力できていること、そしてそれがチームの拡大という形で目に見える成果になっていることです。チームの増員が実現し、それが制作事業への還元にもつながっていることに、大きな達成感があります。
Kondo:私は、大きく2点あります。1点目は、2人の話にも通じますが、経営とメンバーの「橋渡し役」としての存在価値を感じる瞬間です。私たちがメンバーだった頃はマネージャー層の考えが分からず意思疎通が難しいと感じることもありました。今はB4として、経営の意図を噛み砕いて伝えたり、メンバーの誤解を解いたりできる時に、自分の存在価値を感じます。
2点目は、自身の長期的なビジョンに繋がる成長実感です。「女性経営者になりたい」という長期的なビジョンがあり、そのために全社を巻き込むような難易度の高い仕事に挑戦できる環境で、4年目の今でも成長実感が得られることにやりがいを感じます。
━━次に、B4になって自分自身がどう成長したかを教えてください。
Uchida:一番大きな変化は、物事を考える時間軸ですね。これまでは短期的な半年や1年の成果を追う視点が主でしたが、5年先を見据えた投資や経営判断を考えるようになりました。また、個人の数字だけでなく、「チームやディビジョンとしてどう成果を上げていくか」という視点が格段に強くなったことが、自分の中での成長だと感じています。
Yoshida:Uchida君と似ているのですが、目線が個人から組織に変わったことが1番の成長です。自分の所属するプロダクトDiv.だけでなく、採用やバックオフィスなど普段直接の関りが少ないDiv.のことも含めて、「会社としてどうすれば良くなるか」を考えるようになりました。
Kondo:私は大きく2つあって、1つ目はマネジメントに関する考え方です。以前はリーダーとして「プレッシャーをかければ何とかなる」と単純に考えていた部分があったのですが、B4になって経営陣から多くのインプットをもらい、それではうまくいかないと学びました。今では、チームの心理的安全性を考慮し、ミーティングの進め方などを深く考えるようになりました。
2つ目は「会社としての視点」の解像度が上がったことです。前期のスローガン「*ZEBRUG2025」のように、利益と社会性の両立を本質的にどう考えるかといった、より抽象度が高く難しい問いについて役員とディスカッションする機会を通じて、視座が大きく引き上げられたと感じています。
*注釈:ZEBRA(ゼブラ企業)とSAKURUG(サクラグ)を組み合わせた造語で、利益と社会貢献の両立を目指す企業として成長することを示すものです。
組織を牽引する存在になるための、次なる挑戦とキャリアプラン
━━今後挑戦したいことやキャリアの目標について教えてください。
Uchida:役職としては、Div.長や役員を目指していきたいです。それに加えて、役職とは別の軸で挑戦したいこともあります。それは、組織の中で「間に落ちているボール」を拾い、それをプロジェクト化してメンバーを巻き込みながら推進していく、という役割です。今も横断的なプロジェクトを動かす機会がありますが、この動きをさらに加速させていきたいですね。
Yoshida:私も役職で言うと、Div.長のような組織のリーダーとしてのポジションにチャレンジしたいです。これまでプロジェクトリーダーは経験してきましたが、プロジェクトを率いることと、組織を率いることは役割が違うと感じています。目的がより抽象的で難しい挑戦になるとは思いますが、チーム全体をより良くするために、組織を引っ張っていく役割を担ってみたいです。
Kondo:私は、長期目標としては「女性経営者」、中長期的には子会社の社長になることを目指しています。そのために、マネジメントや営業・採用などの担当領域で、プロフェッショナルとしての強さを磨くことを意識しています。
最後に
━━最後に、サクラグで働く上での魅力を教えてください。
Uchida:経営陣との距離の近さがもたらす、圧倒的な成長スピードが最大の魅力です。私自身、入社3年目の後半でB4に任命されるなど、若手でも活躍できる環境があります。代表がすぐ近くで仕事をしていたり、気軽にチャットで意見を送れたりする物理的・心理的な距離の近さがあります。自ら視座を高く持ち、経営視点を吸収しようとすれば、若手であってもいくらでも成長機会を掴める環境です。
Yoshida:「やりたい」と声を挙げれば、積極的に任せてもらえる挑戦的な環境です。さらにサクラグでは、明確な目標がある人はもちろん、「まだ自分のやりたいことが定まっていない」という人でも、様々なチャンスの中から自分の可能性を試し、キャリアを切り拓いていける風土があります。
Kondo:年齢や社歴に関わらず活躍できる環境で、周りには、「本気で会社や事業を大きくしたい」という高い熱量を持つメンバーが集まっており、日々刺激を受けながら切磋琢磨できています。

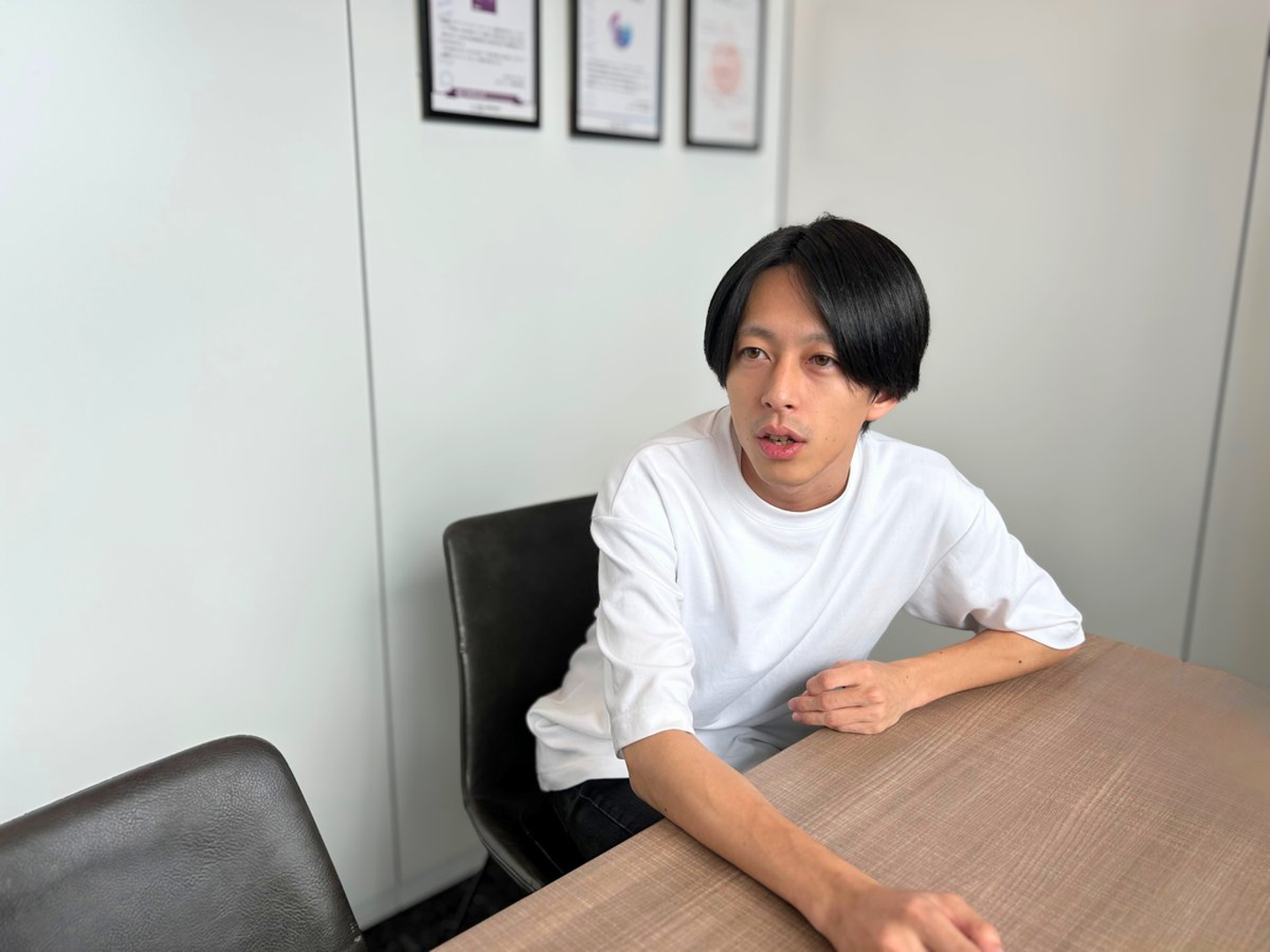




/assets/images/5670114/original/55bc4c9d-888e-40d3-8a9a-53ee2642632b?1603169356)
/assets/images/5670114/original/55bc4c9d-888e-40d3-8a9a-53ee2642632b?1603169356)

