人材不足と地方衰退が深刻化する日本。その課題解決の鍵は「営業のデジタル化」にあると語るのが、株式会社openpage代表取締役の藤島誓也氏だ。カスタマーサクセスを軸とした事業で多くの企業の営業DXを支援し、デジタルセールスルーム(DSR)「openpage」を展開。キヤノンマーケティングジャパンをはじめとする大手企業から地方の中小企業、さらには自治体まで、幅広い組織での取り組みが拡大する中、その社会的意義について聞いた。
デジタルセールスルームで変わる営業の常識
―まず、openpageとはどのようなサービスなのでしょうか?
藤島氏:openpageはデジタルセールスルームという、お客様への提案をデジタルでできるツールです。顧客への提案や打ち合わせの議事録を書くだけのシンプルな仕組みで、操作はWordよりボタンが少ないので簡単。PowerPointより提案は簡単なので、どんな企業でも使えます。
―具体的にはどのような成果が出ているのでしょうか?
藤島氏:受注率の改善や取引単価の向上が図れており、受注率は150%増、取引単価が500%増という驚異的な効果も出せています。
背景には、openpageを活用していい提案ができるようになり、顧客を動かすことができるようになっていることがあります。営業と顧客が双方納得して進められるソリューションがopenpageなんです。
取引の成功確率が上がるだけでなく、そこから取引の単価を上げられている。これは、openpageがカスタマーサクセス領域のプロフェッショナルであることも大きいですね。

「最初は理解されなかった」―営業をデジタルで変革する発想の原点
―開発当初はいかがでしたか?
藤島氏:営業活動をデジタルでやる、口頭の提案をデジタルに落とすという考えは、初めは理解されませんでした。資料をただ読み上げたりする営業が多かったんです。
でも営業は本来、対話が必要で対話が仕事です。それをデジタルでマネジメントしました。成功体験を積み重ね、営業手法やコミュニケーション技術について数千ページに及ぶノウハウ資料を作り、どんな会社でも実現できるノウハウやステップに落とし込んでいきました。
新規営業から既存営業まで―日本独自のポジションを確立
―openpageの特徴的な強みは何でしょうか?
藤島氏:新規営業だけでなく既存営業でも使われているツールというのは、日本でも独自のポジションだと思います。大手企業から中小企業まで、日本企業特有のルートセールスやパートナーセールスの商慣習も根強く、そこを強力に支援できます。
日本の強みは顧客との関係構築、複雑な交渉を細かなサービスや気遣いでやり遂げる総合力です。和製のセールステックとしてはそれを尊重しています。

SalesforceやHubSpotとは何が違うのか―「社内管理」から「顧客体験」へ
―既存の営業ツールとの違いを教えてください。
藤島氏:従来の営業手法や営業テクノロジーを分析すると、営業担当を育成することに着眼点が置かれすぎているんです。でも、そもそも育成する人材もいない。人手不足の中で営業活動を再現性を持って行うという観点のものがなかったので、openpageを展開しました。
SalesforceやHubSpotは営業機能が社内管理に閉じており、法人取引における顧客体験作りまではできません。
全国の大手企業から中小企業まで活用するとなると費用対効果もシビアに見られます。単に「育成します」だけでなく、「提案力が上がり売上利益が上がりました」というところまで持っていかないと導入されない。openpageはそこを徹底してきたのが独自の強みです。
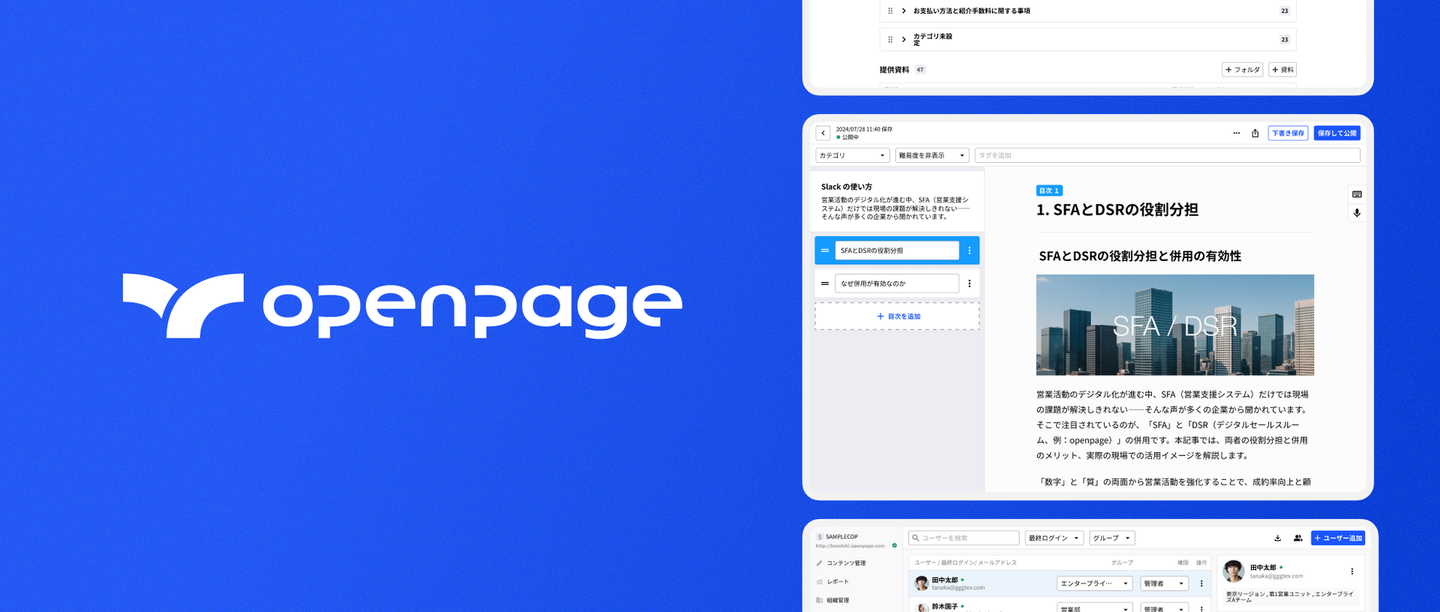
地方こそ必要なデジタル営業―"日本全体"の課題解決への直接アプローチ
―地方企業での取り組みが増えているとのことですが、どのような成果が生まれていますか?
藤島氏:openpageのDXによって実現したいのは、「中小企業の生産性向上」「地方企業の雇用創出」「働き方改革の推進」です。地方の企業ほど都心部にアクセスしにくい分、営業のデジタル化が生産性向上に不可欠なんです。
山形や仙台、福岡など各地の年配の方でも簡単な操作性でopenpageを活用して営業生産性を上げています。初めて導入するITツールがopenpageという会社も多いです。
―具体的にはどのような変化が?
藤島氏:地方企業の売上向上は、そのまま地方の雇用創出につながります。面白いのは、地方でopenpageを活用した企業が取引先に良い営業体験を提供し、その企業もopenpageを契約するという好循環が生まれていることです。
リテラシーやリソースが限られていても、営業提案や顧客交渉という企業の基本動作をDXするものなので、現場業務に直結して運用しやすい。現場で作業着を着ながらopenpageを操作して顧客提案している会社もあります。
提案力が上がるので目に見える成果が得やすく、形骸化しないDXが実現できています。
社会インフラのDX推進―福祉・建設・行政まで広がる活用領域
―社会性の高い分野での取り組みについて聞かせてください。
藤島氏:福祉・介護施設や建設現場へのDX提案など、社会自体のDXを加速させる提案でもopenpageは活用されています。openpageによって新しい取り組みの意思決定スピードが上がり、社会進化のスピードを上げられると考えています。
行政や財団法人との取引もスタートしており、最新のテクノロジーだけでなく公的な提案もopenpageがサポートしています。単なる業務効率化ではなく、新しい取り組みや意思決定を進められるようにすることで、社会の構造転換を早める会社になることを目指しています。
キヤノンマーケティングジャパン様が見据える「8掛け社会」への対応
―キヤノンマーケティングジャパン様との連携について教えてください。
藤島氏:キヤノンマーケティングジャパン様は人材不足社会を見越してopenpageに投資いただきました。今後の8掛け社会で人口が減る中で、デジタルをハイブリッドした新しい営業のあり方を啓蒙し、人材不足に対応できるプロダクトとして位置づけています。
これまで不透明感が強かった営業の大幅な見える化に成功し、透明になりトレースできることで教育格差を大幅に縮小できています。

「知識の民主化」を目指す情報発信
―情報発信にも力を入れられていますね。
藤島氏:openpageには出版・メディア業界経験者も在籍しており、社名の通り、オープンな知識発信を増やしたいと考えています。これまでも営業の専門家と連携を取りながら、数十万字以上の情報発信をしてきました。
最先端のデジタルの知見をわかりやすく日本全国の企業に展開したいんです。
目指しているのは「知識の民主化」と「現場知見の社会的共有」です。
openpageはSNSを主体に多くの媒体で無償で営業ノウハウを発信し、研修事業者やコンサルティング会社などパートナーにも無償提供、教育機関や行政機関にも惜しみなくノウハウ還元しています。書籍出版やテレビ出演もしましたが、今後も代表自らがメディアを通じてノウハウ発信を継続していきます。
多様な働き方の実現―誰もが活躍できる社会へ
―ダイバーシティ&インクルージョンについてはいかがでしょうか?
藤島氏:デジタルを主体とする営業活動により、家庭で忙しい女性や、足の悪い高齢者などもopenpageを使って仕事ができる世界観を実現したいと考えています。持続可能な働き方、企業経営を支援することが私たちの使命です。
自治体との連携で地方創生を加速
―地方創生への具体的な取り組みを教えてください。
藤島氏:自治体と連携した地方創生の取り組みでは、事業開発部長の北森を中心とした専門チームが、地域の魅力を活かした戦略的な提案活動を展開しています。openpageのデジタルセールスルームを活用することで、地方の持つ本来の価値を効果的に伝え、新たな可能性を切り開いています。
私たちは、地域と企業をつなぐコミュニケーションの架け橋として、持続可能な地方創生の実現に貢献していきたいと考えています。

海産物の港町から十勝の大地へ―地方と都市を知る起業家の原点
―藤島代表の個人的な背景についてお聞かせください。
藤島氏:私自身は海産物が有名な港町で、ふるさと納税全国でもトップクラスの紋別市で生まれ、十勝地方の自然豊かな広尾町で育ちました。東京の都市も好きですが、地方の魅力もよく分かります。実は父だけでなく祖父や叔父も地方公務員として北海道や札幌市の仕事をしていたため、地方行政の仕事に務めることも検討して、政治・行政の大学に進学していたんです。
その後、デジタル、マーケティング、メディア、営業と自分のキャリアで広く関わってきました。これまで培ってきた経験を総動員して、社会課題解決に取り組みたいと考えています。
―地方への思い入れは強いのでしょうか?
藤島氏:openpageは会社の合宿で必ず地方に行くんです。ご飯も美味しいし観光も最高です。自分自身がビジネススキルやデジタルスキルを身につけてきた経験を活かし、同じような環境にいる人たちの可能性を広げたいと考えています。
日本の未来への提言―イノベーションが決まる社会を目指して
―日本の未来についてどのようにお考えですか?
藤島氏:新しい働き方に最適化されていく中で、openpageもその一助になりたいと考えています。
イノベーティブな取り組みがopenpageを介してどんどん決まっていく社会を実現したいんです。
私たちが目指しているのは、"社会変革のエンジン"としてのopenpageです。
単なる営業ツールを超えて:
- 地方と都市部のデジタル格差解消
- 多様な人材の活躍支援
- 社会インフラのDX推進
- 教育機関・NPO・自治体との連携強化
これらを通じて、企業の枠を超えた社会貢献企業として、日本全体の課題解決に貢献していきたいと考えています。

/assets/images/21165365/original/3ff4f912-5858-4406-b3ee-8f29caf7faf7?1747810835)


/assets/images/21165365/original/3ff4f912-5858-4406-b3ee-8f29caf7faf7?1747810835)



/assets/images/21165365/original/3ff4f912-5858-4406-b3ee-8f29caf7faf7?1747810835)

