理念が共鳴したリーディングマークへ。“人に真摯であること”を軸に、テクノロジーで価値を生み出す――AI推進室 室長が目指すもの
こんにちは!株式会社リーディングマークの広報担当の黒澤です。
本日は、AI推進室 室長の石澤さんにインタビューをしてまいりました。
- リーディングマークに参画した背景
- リーディングマークで変化しているもの、変わらないもの
- リーディングマークの魅力
についてお話しして参りますので、人とテクノロジーの共創に興味がある方や社会的価値の高い仕事に挑戦したい方はぜひ最後までご覧ください。
AI推進室 室長 石澤さんプロフィール
新卒でメガベンチャーの開発職としてキャリアを開始したのち、HRテック企業に転職し、プロダクト導入コンサルを担当。その後、学生時代に立ち上げたサービス「NEXVEL(ネクスベル)」を法人化し、副代表として経営に参画。そして2019年、ネクスベル事業をリーディングマークへ売却し、同社に参画。
リーディングマーク参画後は、新卒就活支援事業「ミキワメ就活」にて学生対応・企業コンサルを推進。続いてサービス開発部で新卒就活支援事業の開発を担当し、事業部へ復帰後、コロナ時代の事業転換を実施しながら、採用支援事業部長へ就任。
現在はプロダクト企画本部に所属し、新規プロダクト「ミキワメ マネジメント」の立ち上げをPdMとして主導。並行してAI推進室を設立し、プロダクトおよび社内業務へのAI活用を横断的に推進。デザイナー組織のマネジメントや、自社新卒採用プログラムの設計も担う。

多様な経験から生まれた、“社会に還元する”という軸
ーリーディングマークに入ってから、幅広いポジションを経験されていますね。
たぶん、社内でいちばん異動していると思います(笑)。
エンジニア組織と事業部と採用チームを行き来しながら、新規事業の立ち上げや開発に携わってきました。一貫してHRという領域に関わりながらも、ビジネスと開発と人材育成の三面から会社を支える立場でキャリアを積んでいます。
いわゆるBizDev的な役割を、企画・開発・推進といったフェーズで横断的に担ってきたイメージですね。
ー0→1の立ち上げを任されることが多いですか?
どちらかというと、ピンチヒッター的な役割が多いですね。事業が少し下を向いてしまっているタイミングや、前任者が抜けて「誰がやる?」となったときにアサインされることが多かったです。
結果的に0→1のフェーズに関わることもありますし、立て直しや再構築の局面を担うこともあります。そうした場面で、状況を整理して仕組みを整え、次の成長につなげていく。
そんな役回りが多いかもしれません。
そういった中でも成果を出せてこれたのは、その時々で仲間に恵まれたことが大きく、今まで携わってくれた仲間への感謝の気持ちが大きいです。
ー幅広く任される中で、ご自身の価値観が変わったターニングポイントはありますか?
副代表として運営していた「NEXVEL」というキャリアコミュニティが、大きな転機でした。
高学歴層の学生が多く所属しているコミュニティで、「将来、日本を動かしていく責任を担う人たちが集まっている集団」ともいえるかと思います。だからこそ、就職活動を“自分の幸せのためだけ”に考えるのではなく、社会のためになるキャリアを選んでほしいという想いで活動していました。
彼らにはよく「人材の不良債権にならないで」と伝えていました。もちろん、高学歴といえる大学に合格した努力は本人のものですが、環境や学ぶ機会といった“投資”を受けてきたはず。誰かの支えがあって今があるという前提のもとで、その恩をどう社会に還元するかを意識してほしかったんです。
そうした考えを学生に発信する以上、自分自身も“社会のために働く”姿勢を貫かなければ説得力がないと思うようになりました。失敗を恐れるよりも、「この課題を乗り越えることで、会社が次のステージに進めるならやってみよう」。そんなマインドが、今の自分のキャリア観のベースになっています。

リーディングマークで得た、わが子の成長を見守るような喜び
ーNEXVELの事業売却先としてリーディングマークを選んだのは、どんな理由だったのでしょうか?
売却条件だけで見れば、ほかの会社さんのほうが良かったと聞いています。それでもリーディングマークを選んだのは、目指す方向性や理念が一番近かったからでした。
リーディングマークが掲げていたミッションと、NEXVELが目指していた「人と社会の可能性を広げる」という想いが重なっていたんです。
単に事業を手放すというよりも、「志を共に叶えてくれるパートナーを見つけたい」という気持ちのほうが大きかったですね。結果的にNEXVELが今でも続いて大きくなっていることを踏まえると、正解だったと思っています。
ー石澤さんの「社会貢献」への強い動機は、どこから生まれたのでしょうか?
社会に出るたびに、「自分よりすごい人がたくさんいる」と痛感してきました。たとえば就職活動のときに出会った友人の1人1人がとても印象的でした。人格者で、勉強もできて、意思決定力にも優れていて「人としてのあり方って、こんなにも立派なんだ」と感じました。
NEXVELを運営していた頃も、人間的に優れた学生が多く集まってくれました。年齢は下でも、社会を良くしたいという想いを持って努力している姿に刺激を受けましたね。そういう人たちと関わるうちに、自分本位よりも、他者軸で物事を考えられる人のほうが魅力的だと感じるようになったんです。
あと、大好きな北方謙三さんの作品の影響もあるかもしれません。大義に生き、想いに殉じて散っていく登場人物たちを通して、「自分の人生を通して、後世に何か還元できたら」という死生観を持つようになりましたね。
今の会社でもミッションを通じて、社会をより良い形にしたいという多くのタレントが集まってくれており、日々一緒に頑張る動機の源泉になっていると思います。
ー仕事の中でやりがいを感じる瞬間はどんなときですか?
プロダクトの成長が、お客様の成功とほぼ同義である――そこに一番のやりがいを感じています。自分が直接感謝されることもうれしいですが、それ以上に“自分の手を離れたものが誰かの役に立ち続けている”瞬間に喜びを感じます。
近いのは、子どもの成長を喜ぶ感覚。「この子、こんなことができるようになったんだ」と感じられる瞬間が、プロダクトに対してもあるんですよね。
たとえば、今年2月にリリースした「ミキワメ マネジメント」。PdMとして立ち上げに関わりましたが、今は私の手を離れています。それでも、「1on1が前より意味のある時間になった」「メンバーと話しやすくなった」といったお客様の声を聞くと、あの仕組みが自走して価値を生み出しているんだ…とやりがいを感じますね。
立場上、経営に近くなり、色々な物事に携わり後任者に託してきた背景があるので、すべてを自分で動かすことはなくなりました。それでも、自分が関わった事業やプロダクトが信頼できる仲間によって成長し、それを使うお客様がハッピーになっている姿を見ると、本当に“やっていてよかったな”と感じます。
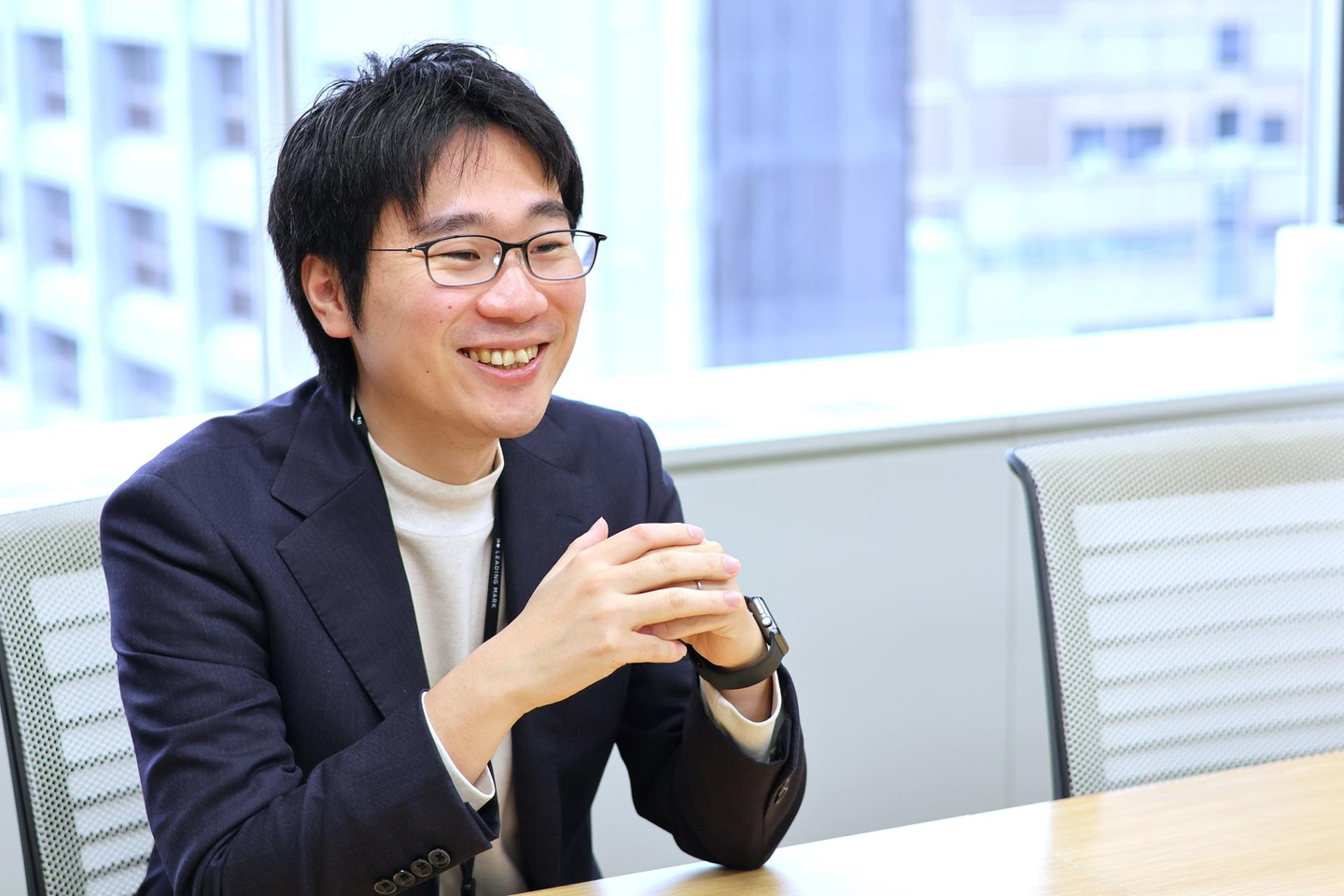
提唱し続けた世界観が、いま“社会の常識”になりつつある
ーリーディングマークでの約7年を振り返って、どのような変化を感じていますか?
一番変わったなと思うのは、“明日を心配しなくてよくなった”ことでしょうか(笑)。当時はリソースも限られていて、何に時間を使うか、どこに賭けるか――まさに一発一発が博打のような日々。絶対に判断ミスできない緊張感の中で働いていたと思います。
今では、仲間の数も増え、専門性の高いメンバーが多く加わり、会社としての土壌がぐっと豊かになりました。挑戦は変わらず続けていますが、明日の心配ではなく「どう成長していくか」を考えられるようになったのは大きな変化です。
ありがたいことに、プロダクトのファンも増えました。以前は一部の大企業の人事担当者に知られるサービスという印象でしたが、今では社会の中での認知や存在感を実感できるようになっています。
ー社会の中で、リーディングマークの存在感はどう変わってきたと感じますか?
「社会の公器」という手応えを、少しずつ感じられるようになってきました。
リーディングマークは、適性検査を通して“その人に合う仕事や環境を見つける”ことを支援し、その結果として、働く人のエンゲージメントや働きがいが高まる世界を目指して発信を続けてきました。
今では、その考え方が社会全体にも広がり、「人と仕事の相性を大切にするのは当たり前」という価値観が根づきつつあると感じます。
私たちが提唱してきた世界観が、少しずつ社会の常識になってきている。その変化を肌で感じられることが、何よりも嬉しいですね。
ーリーディングマークが変わらず大切にしていることは何でしょうか?
変わっていないのは、“事業家主義”のカルチャーだと思います。課題を「誰かが解決してくれるもの」ではなく、自分が解決するものとして捉える。その主体性こそが、リーディングマークを動かす原動力です。
会社と社員が対立するのではなく、「会社=自分たちでつくるもの」という感覚が根づいている。“会社がこうすべき”ではなく、“自分たちがこうしたい”と動くメンバーが多いのは、変わらない魅力です。
あとは単純に、ミッションが好きな人が多い。誰かの成功を素直に喜べる人ばかりで、ビジネスが難しい局面でも、人に責任を押しつけるのではなく、「課題にどう向き合うか」を考える文化が根づいています。そこは昔から変わらない、リーディングマークらしさですね。

“人に真摯であること”を軸に、テクノロジーで価値を生み出す
ー現在の課題、そして今後の目標を教えてください。
今はAI推進室の室長として、AIの力をどう活かせば会社を、そして業界を成長させられるかというテーマに取り組んでいます。
AIの必要性はこの1〜2年で急速に高まりましたが、まだ「こうすればうまくいく」という定石がない分野。だからこそ、HRテック領域でNo.1を目指す私たちにとって、AIを正しく活用しながら新しい価値を生み出していくことが重要だと感じています。
そのためには、AIそのものの知識を深めるだけでなく、「HR×AIの活用方法」そのものを業界のスタンダードにしていく必要があります。
「ミキワメAI」は、業界でも早期にAIを導入したプロダクトの一つですが、まだムーブメントを牽引できているとは言えません。今後は、私たちが培ってきた人の内面を可視化する性格検査の技術とAIを掛け合わせ、人がより前向きに価値を生み出せる世界を実現していきたいと思っています。
ー石澤さん個人として、今後叶えたい夢はありますか?
社内での自己分析や内省をしていたときにふと思ったんです。
「ドラえもんを作りたいな」って(笑)。
ゲームや漫画でよくあるような、常にそばにいて、味方でいてくれて、必要なときにサポートしてくれる相棒。でも、指示や管理をするわけではなく、あくまでその人自身が自分の力で進んでいけるよう背中を押してくれる存在です。
そんな“伴走するテクノロジー”をつくりたい。それが、結果的に一人ひとりの可能性を引き出し、「やりたいこと」や「やるべきこと」を実現できる世界につながると思っています。人の可能性をそっと支える仕組みを形にすることが、私の夢ですね。
ー最後に、石澤さんが感じるリーディングマークの魅力を教えてください。
「人に真摯であること」が、リーディングマークの一番の魅力です。
社内のメンバーに対しても、お客様に対しても、そして“人間という種そのもの”に対しても、誠実でいようとする姿勢がある。私たちは、単に業務を効率化するSaaSをつくる会社ではなく、人の内面を理解し、その人がより良く生きられるよう支援する会社でありたいと考えています。
人に向き合い、真摯であり続けながら、テクノロジーの力で価値を創り出していく。その考え方を軸に、ビジネスも組織もデザインしている――それが、リーディングマークの魅力ですね。
ー石澤さん、ありがとうございました!


/assets/images/1660941/original/693755ac-ea3b-4448-85d5-d7e610e55b3b.png?1496669821)


/assets/images/1660941/original/693755ac-ea3b-4448-85d5-d7e610e55b3b.png?1496669821)


/assets/images/1660941/original/693755ac-ea3b-4448-85d5-d7e610e55b3b.png?1496669821)

