こんにちは!PR担当の冨田です。
ケップルは『Create New Industries 世界に新たな産業を』というミッションを掲げ、スタートアップエコシステムの発展に貢献するため、投資家・起業家を支援する多くのプロダクトやサービスを展開しています。そして、エコシステムにおけるさまざまな課題を解決すべく、ケップルの事業も多角化を続けています。
ケップルでは2025年から新卒採用をスタートしました。新卒採用開始の背景については下記インタビューで代表の神先(カンザキ)よりお伝えしていますので、ぜひご覧ください!
今回は、「KEPPLE CREATORS LAB」のマネージャーを務める石野に話を聞きました!ぜひご覧ください!
石野 純 jun Ishino Corporate Creative Group / KEPPLE CREATORS LAB / Development Section / Section Manager 2015年に新卒で大手Slerに入社。2019年にケップルに入社し、エンジニアとして自社のプロダクト開発に従事。2023年より「KEPPLE CREATORS LAB」のマネージャーとして、エンジニアリング組織のパフォーマンスを最大化する施策を推進している。家庭では1歳の子どもの父。年内に社内部活動でフルマラソン挑戦予定。 AI変革に挑む実践形式の「KEPPLE AX」が始動 2024年秋から2025年春にかけて、実践形式の社内プロジェクト「KEPPLE AX」を実施しました。テーマは「自分の仕事を生成AIに任せてみよう!」です。まずは全社で有志を募り、生成AIの基礎知識や最新トレンドをインプット。その後、チームに分かれて「自分の業務のどこをAIに任せられるか?」を議論し、実際に試していきました。毎週の定例会では、実際に試した結果や直面した課題を共有し、現場視点のノウハウを蓄積。最終回には全体報告会を開催し、「どこまでAIに任せられたか」「今後どう活用していくか」といったテーマで、それぞれのリアルな経験と学びを共有し、知見を深め合う機会となりました。
このプロジェクトが始動した背景には、ある種の危機感がありました。2024年頃から生成AIの進化は目覚ましく、「これは単なるツールではなく、ゲームチェンジャーになる」と強く感じていました。一方で社内を見渡すと、半数以上の社員が生成AIをまだ業務に活用できていないという現実があり、すでに活用を進めていあるメンバーとの間には、徐々にスキルのギャップが生まれつつありました。この状況を少しでも改善するために立ち上げたのが、「KEPPLE AX」プロジェクトです。
エンジニアチームに留めず、全社を巻き込んだ立ち上げ 生成AIは、決してエンジニアだけのものではありません。営業資料の作成、経理の仕訳、法務の契約レビューなど、あらゆる業務領域に活用の可能性を秘めています。だからこそ、これは会社全体で取り組むべきテーマだと考えました。
また、「一部の人が推進する」のではなく、「さまざまな部署のメンバーが集まり、多様な視点で試してみる」ことが、より実用的で広がりのある活用アイディアにつながるはずです。こうした考えから、当初検討していた一部の専門チームによる推進は見送り、エンジニアチーム内に閉じることなく、全社から有志メンバーを募る方針をとりました。今はまだ"誰かが引っ張る"フェーズではなく、「AI活用の小さな成功体験」を全社で積み重ねていく段階だと判断したからです。この方針のもと、部署や役職の垣根を越えてオープンに呼びかけた結果、予想を超える20名以上のメンバーが手を挙げてくれました。参加者の多くは、生成AIとこれから向き合おうとしている段階でした。だからこそ立ち上げ期では、AIに不慣れな人でも安心して参加できるよう、用語や仕組み、具体的な使い方などを丁寧に説明することを心がけました。専門的な内容に偏りすぎず、まずは「少し試してみたい」「活用できるようになりたい」と感じてもらうこと。それこそが、このプロジェクトの立ち上げ期における重要なポイントだと考えたからです。
今回のチャレンジでの気づき・得られたもの プロジェクトが生んだ気づきと危機感 このプロジェクトを通じて、全社でAI活用の重要性を共有できたと実感しています。同時に、今後使いこなせないことへの危機感も生まれ、これが良い意味でのプレッシャーとなり、さらなる活用への意欲につながりました。こうした意識変化に加えて、実際の業務面でも目に見える成果が現れています。業務内容によって差はあるものの、実際に業務を大幅に効率化したメンバーや、従来よりも精度の高いアウトプットを継続的に出せるようになったメンバーも複数現れています。例えば、作成に数時間かかっていたインタビュー記事を数十分に短縮したケースや、リサーチに活用してユーザー向けのレポートを新たに提供し始めたケースなど、各部署で手応えのある改善が見られました。何より価値があったのは、参加者がブレストや実践を重ね、実際に手を動かしながら成功も失敗も包み隠さず共有していたことです。このプロセスを通じて、多くのメンバーが「AIに自分の業務の一部を任せられる」という実感を得ることができました。完璧でなくても、まずは試してみる。うまくいかなければ改善する。こうした試行錯誤を恐れない取り組み方が参加者の間で自然に行われたことは、初めての取り組みとしては成功だったと考えています。
行動を起こすことで得たもの 私自身がプロジェクトを通じて実感したのは、「何事も行動あるのみ」ということです。AIという新しい技術に対して、まずは理論や完璧な計画を求めるのではなく、実際に手を動かして試してみることの重要性を改めて感じました。ケップルには挑戦を後押ししてくれる土壌がありますし、部署を越えて全社を巻き込みやすい風通しの良い雰囲気です。こうした組織の特性があったからこそ、変化をもたらすことができたのだと思います。実際に、このプロジェクトを機に社内の生成AI活用が着実に進んでいます。プロジェクト参加者だけでなく、その周囲のメンバーからも「自分も試してみたい」という声が聞こえるようになり、AI活用への関心が自然と広がっています。当初目指していた「全社でAI活用の小さな成功体験を積み重ねる」という変化をもたらすことができたのではないかと感じています。今後は、今回の経験と反省を活かした取り組みを続けていくつもりです。具体的には、今回のような幅広いテーマではなく、「AIを活用したワークフロー構築」や「資料を自動生成するツール作成」など、より具体的で業務につながる実践的なテーマに絞って短期集中で実施することを考えています。
「誰よりも早く変化する」ことへのこだわり 今回、私一人の力だけでは大きな影響を与えられなかったと思います。しかし、以前から全社の課題意識を持ち、ただひたすら当たり前のことに取り組み続け、自身ができることを個人→チーム→組織へと広げ続ける意識を持ち続けてきました。ケップルは「Create New Industries ~世界に新たな産業を~」というミッションのもと、次々と新しい事業が立ち上がり発展を続けてきた、変化の激しい環境です。今後私たちを取り巻く環境がどう変化していくか未知な部分も多い中、私自身「誰よりも早く変化する」ことを目指し、そのために行動しています。今回の「KEPPLE AX」は、そうした意識を具体的な形で実現できたプロジェクトだったと思うので、引き続き行動に移していきたいと思います。常に変化し進化し続けるケップルで力を発揮していくためにも、気力・体力が一番重要なので、心身を鍛えていくことも頑張っていきたいと思います(笑)







/assets/images/3733281/original/e05e3c9e-5aab-4619-a90d-c4f238f060e3?1655536150)


/assets/images/3733281/original/e05e3c9e-5aab-4619-a90d-c4f238f060e3?1655536150)
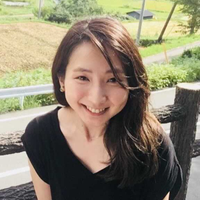
/assets/images/3733281/original/e05e3c9e-5aab-4619-a90d-c4f238f060e3?1655536150)

