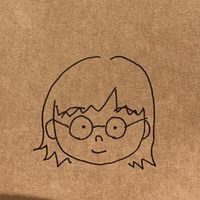- 災害時子ども支援スタッフ
- 渉外担当・コーディネーター
- 高校生への伴走担当/学校連携
- Other occupations (18)
- Business
- Other
ーまず、1月1日、能登半島地震発生直後の動き方について教えてください。
地震発生時は、自宅でベランダの掃除をしていました。アラートが鳴って、緊急地震速報が流れて間もなく大津波警報が発令されて……「逃げてください」という言葉が繰り返し流れていました。
徐々に火事や津波といった被害状況がわかってきた段階で、「sonaeru」のチームメンバーとコミュニケーションをとり始めました。
ーどういったコミュニケーションをとったのでしょうか。
まずは担当を分けてみんなで情報を収集して、翌日午前にミーティングすることに。「sonaeru」では災害の規模に応じて、現地調査へ行くかどうかの判断をしているのですが、ミーティング実施時点で基準は満たしていたので、出発に向けて準備を進めました。
北陸新幹線は3日から再開が決定したため、できる限りの情報だけ集めて、あとは現地で調査することになりました。
ー現地での動きについても教えてください。
新幹線で金沢市まで行き、現地の方とコミュニケーションをとることから始めました。
金沢市にあるユースセンターの代表の方や、以前災害支援に関する講演会で関わった七尾市の方など、とにかく石川県内でつながりのある方へ連絡をとって会いに行きました。
「sonaeru」としての最優先事項は、被災地における子どもの居場所づくり。居場所を開設できる場所を探しているときに、地域とのつながりが深い方から七尾市にある避難所を紹介してもらえて。避難所を運営している方からも、「ぜひここで子どもの居場所を展開してください」と言っていただけたので、1月4日に七尾市で居場所を開設することができました。
ーすごいスピード感ですね。石井さんは1月に「sonaeru」の責任者になったばかりでした。一つひとつ判断していくことに難しさを感じるようなことはありませんでしたか。
1月10日ぐらいまでは前任もまだいてくれましたし、代表の今村も現地に来ていて、3人で相談しながら判断できていたので、頭を抱えるほど悩むようなことはありませんでした。
何より被災地では動けば動いただけ力になれるので「とにかくやっていこう」と今村とも話をしていて。とにかく一人でも多くの方と会ってお話を聞き、必要な支援は何か自分たちの頭で考えるように努めました。迷っている暇はないから「やれることをやりましょう」と。
ー1月4日以降の動きについても教えてください。
七尾の居場所づくりは「sonaeru」の他メンバーに任せて、僕は今村と一緒に、より被害が大きかった珠洲市へ行くことにしました。
金沢市から珠洲市までは、普段なら3時間ほどで行けるのですが、6時間経っても予定の半分ぐらいしか進めませんでした。
翌日の朝、やっと珠洲市に到着し、今村の友人ですでに物資支援に入っていた方から紹介してもらった避難所の飯田高校に入りました。
避難所責任者となっていた校長先生とお話しし、大人だけでなく避難所にいる地元の高校生たちにも声をかけて「子どもの居場所」を運営していく仲間になってもらい、翌日1月6日に子どもの居場所をオープンしました。
居場所を開設してから2〜3日間ほどは僕も現場でサポートするのですが、応援が来たり、稼働が安定してきたら次への場所へ行って……という動き方で珠洲市でさらに1ヵ所、輪島市で1ヶ所をオープン。同時に金沢市、能登町、志賀町でも地域の人や地元NPOの力を借りながら子どもの居場所の立ち上げと運営をしていました。
「今できることをやろう」という気持ちで動いてきて、振り返ると様々な人たちと連携協力しながらできる支援をとことん形にしてきたなと思っています。
ーかなり慌ただしい日々を過ごされていたように思います。
カタリバが今までやってきたことを信じて、本当にがむしゃらに毎日を過ごしていました。
子どもの居場所ができる前は避難所の隅で一日中スマホをいじって静かに過ごすしかなかった子どもが、オープン後は居場所に来て楽しそうに過ごし、明らかに表情も変わっていて。「こういう場所って必要なんだ」と強く実感できました。
保護者のなかにも、「夫は行政職員だからずっと出ずっぱりで、子どもは自分ひとりで守らなきゃいけないと思っていて、誰にも相談できずにいっぱいいっぱいになっていた」という方がいて。「でも、居場所ができて子どもを預けられたので、やっとこれからのことを考えられる」と涙ながらに話してくれました。その言葉を聞いて、子どもだけではなく親にとっての居場所の必要性も同時に感じました。
ー難しさを感じたことはありますか?
復旧フェーズから、復興フェーズに入ってきているなかで、カタリバとしての関わり方をどう形にしていくか方向性を定めることに難しさを感じています。
ひとつ決めていたのは、地域の人たちが復興の主役であるということ。カタリバは違う地域で災害が起きたらそこへ足を運んで支援していくことになるので、ずっと能登支援に全力を注ぎ続けるのはどうしても難しいです。
そのため、もっと中からも外からも能登支援に関わる人を増やすことで、子どもを取り巻く環境を充実させていきたいですね。
ー被災地支援で学んだことはありますか?
僕らのような外の人間が関わることの意味です。特に災害発生直後の緊急フェーズは、被災地域のみなさんは肉体的にも精神的にも疲弊していて、先がわからない状況に不安でいっぱいです。
そんなときに、外部から来た人間だからこそ支えられるときもある。地元の人たちがどうしても配慮してしまうこと、たとえば地域の人間関係などは気にせずどんな人にでも「今どんな支援が必要ですか?」「なにかできることはありますか?」と声をかけてきました。
ー今回の取り組みを通じて、ご自身の人生観や仕事観などに変化はありましたか?
「どんな環境に生まれ育っても、『やりたい』と思えるものを見つけて、実現できるような社会にしていきたい」という気持ちは変わらずあります。
それは被災地に限らず、一緒に働く「sonaeru」のメンバーに対しても同じ気持ちで。僕よりも若いメンバーばかりですが、みんな素直で、タフで、本当にメンバーに恵まれているなあと日々感じています。
だから、彼らがカタリバに限らずどんな環境へ行ってもチャレンジしていけるように成長できる環境を整えて、背中を押していきたい。そう思っても形にするのはなかなか難しいですが、僕自身が本当にいろいろな経験を積ませてもらってきたので、今度は次の世代につないでいきたいですね。