前編ではお二人のキャリアや、HRという仕事に対する考え方、当社の組織としての魅力についてお話を伺いました。後編では、業務の中で特に意識していることや、採用活動のポイントについて伺っていきます。
【参加者】
野家 慶子さん 人事・採用・広報グループマネージャー
村松美奈子さん 人事・採用・広報グループ
目次
社内のメンバーとの接し方
HRに対するイメージと現実
採用活動で大切にしていること
次の職場として当社を考えている方へのメッセージ
社内のメンバーとの接し方
司会:HRの業務では、社内のメンバーとの関わりが業務の中心になるというお話がありましたが、お二人がメンバーとの接し方で心がけていることがあれば教えていただけますか?
村松:そうですね。これは前職から個人的に意識していることなんですが、管理部やHRはどうしてもお役所的な固いイメージを持たれやすいので、メンバーとは、「HRの村松として」というよりも、同じ会社の一員として接してもらえるような関係性を築きたいと思っています。当社の管理部のメンバーは、皆さんすごく親切で丁寧なので管理部に対してそこまで固さや圧迫感を感じている方はいないと思うんですけど、HRも、会社としての方針に沿って動いていかなければならない一面もありつつ、私個人には一従業員としての側面もあるので、何か相談を受けたときには、単に「こういうルールだから従ってください」ではなく、きちんと話を聞いた上で、解決策を一緒に考えるようなコミュニケーションを心がけています。
司会:確かに、村松さんに対して固さや圧迫感を感じている人はほとんどいないと思います。
村松:そもそも、管理部の人らしくもないですしね(笑)
司会:野家さんはいかがですか?
野家:私もまさに村松さんと同じ気持ちなんですが、私の方がより全社向けに発信する機会が多いという点で村松さんとはまた違う見られ方をしているんじゃないかとは思っています。そういう意味で意識しているのは、これはHRに限った話ではないし、当たり前のことなのですが、あえて言語化すると、全ての方に対しての敬意を持ち続けることでしょうか。例えば、HRは職業柄、機密性の高い情報を扱うこともあるので、皆さん個人から「こんな人に自分の大切な話はできない」と思われる状態ではそもそも成り立ちません。また、採用のプロセスでお会いして、その時には当社とご縁が無かった方も、今後、当社のお客様やパートナーになることはあり得ます。HRが関わるシチュエーションは多様ですが、どのような内容の対話であっても、常に敬意を持って対応することが重要だなと。
これは過去に自分と関わって下さった尊敬する方々の背中を見て吸収したいと思ったスタンスです。まだまだ自分は未熟なため、後から反省することも多いのですが、そんな自分だからこそより強く意識しないといけないと考えています。
司会:ありがとうございます。

HRに対するイメージと現実
司会:さて、ここで少しゆるめの質問も挟ませていただきたいと思います。HRは縁の下の力持ち的なポジションなので、日々の業務も他の部署からはあまり見えないのですが、第三者がイメージするHRと実際のHRとの違いってあるのでしょうか?
野家:「HRって面倒くさそう」っていうのは言われたことありますね(笑)
村松:そういう見られ方をすることはありますね。
野家:確かにそれはそうかもしれませんが(笑)一方で、HRには謎に何かしらの権力がある、と思っている人もいらっしゃいますよね。「社員の情報を握る部署だから、HRで働きたい」と言う話も聞いたことがあったり。その人はHRはやめた方が良いなと強く思いましたが。
村松:HRは経営陣と距離が近いので、いい顔してるんじゃないか、みたいな見られ方もあるようですね。
野家:そんなこと無いんですけどね。それどころか、これはHRに限らずスタートアップで働いている人全員に言えることかもしれませんが、とめどなく課題が降ってくるので、その対応をし続けないと前に進めず倒れるのが実情です。当たり前すぎて「あるある」ですら無いかもしれませんが。
村松:一日のスケジュールを立ててもあまり意味がないところはありますね。
司会:臨時対応が多いイメージはありますね。
村松:一般的に、「とりあえず人事に相談してみて」という感じで話を振られるケースは多いです。
野家:だからこそ、過去に当社でHRを担当されていた私の当時の上司は、部の内外で「役割とすべきこと」の分類と整理を強く進めていました。私もそこは大切な考え方だと思っています。「とりあえず人事に相談」といった流れがあった時でも、「この課題の管掌はHRではなく〇〇部ですが、この部分についてはサポートできます」といった感じで連携できるようにしています。HRはよろず相談所になりやすく、それ自体はむしろ歓迎されることですが、本来の役割以上のことまで受けてしまうと適切な対応ができない・必要な場面で本来の役割が発揮できないことにもなりかねません。特にスタートアップの場合、相談ルートや権限が定まっていないことも多いので、そこの整理や分類は重要です。そのためにも、日ごろから今のフェーズでのHRの担当領域が何かということを考え続けていく必要があると思っています。
村松:それぞれの部署の役割が明確になっていればある程度窓口も整理されると思いますが、バックオフィスはひとまとまりに見られやすいところもありますよね。HRはバックオフィスの窓口と思われているのかなとも思います。野家さんもお話しされていた通り、それは組織やHRにとっても良いことなのでぜひお声かけいただきたいですね。
野家:それはそうですね。我々が話を聞いて、「その担当はあちらです」「こちらです」と案内できるのでウェルカムです。むしろ、リモートの割合が高い当社ですので、分からないことは私たちにどんどん聞いてほしいですよね。HRがよろず相談所になるというのは組織として健全だと思いますし、私としても相談してもらえることは喜ばしいことです。
司会:臨時対応が多くてスケジュール通り進めるのが難しいこともあるということですが、業務の中には当然スケジュールがきっちり決まっているものもあると思います。その両立はどうされているんですか?
村松:評価については野家さんがメインで担当されていますが、評価ってスケジュールがかなり緻密に決まっていて、期日までに終わらせる必要があるので、評価期間はただでさえお忙しいわけですが、評価が佳境に入ると、「今はその件は対応できません(ので、いつ以降に)」とコミュニケーションされていますよね。
野家:はい、手元にある業務を詳細に全体に開示することは不可能ですが、「今の私の優先順位はこうなっています」ということはいつでも周囲には説明できるようにしておかないといけないとは思っています。
司会:メリハリを付けつつ、社内の一時相談所の役割も担われているわけですね。

採用活動で大切にしていること
司会:ではここからは少し採用にフォーカスしてお話を聞いていきたいと思います。村松さんは採用を主に担当されていますが、会社として、また、村松さん個人として、採用活動で大切にしていることを教えていただけますか?
村松:私が候補者の方と最初にお会いするのはカジュアル面談です。候補者との最初の場であるカジュアル面談で私が意識しているのは、その候補者の転職軸がどこにあるのかということです。そもそもなぜ転職したいと思っているのか、その希望が当社で叶えられそうかということを重点的にヒアリングするようにしています。
面接や面談の場というのは緊張もしますし、誰でも「良いこと」を言おうとするものです。でも、本来は、本音で話すことにこそ面談の意味があるはずですし、候補者にとってもその時間自体がキャリア支援につながると思うので、面談の雰囲気づくりや質問を工夫することで、本音で話しやすい空間になるよう心掛けています。例えば、というのをお伝えしたいのですが、これを読んだ未来の候補者の方に意識させてしまったら申し訳ないので割愛させてください(笑)
司会:私も入社前に村松さんとカジュアル面談でお話しさせていただいたのですが、それなりに緊張していたので、村松さんの柔らかい雰囲気に救われたのを覚えています。
村松:ありがとうございます。世の中には「カジュアル面談って、カジュアルって言っているけど結局面接でしょ」という声もあると聞いているので、私の場合、特に「カジュアル」の部分に力が入っているのかもしれません(笑)
司会:候補者からすると、村松さんは最初に出会う当社の人ですから、会社の印象にもつながる重要な役割ですよね。
村松:そうですね、カジュアル面談はスキルの見極めの場では無く、いかに当社に魅力を感じていただき次のステップに進んでもらえるかという場だと思うので、自分も候補者の方から評価をされているということは意識しています。
司会:企業の規模を問わず、採用に関しては採用後のミスマッチという永遠の課題があると思います。カジュアル面談もまさにミスマッチを防ぐ一つの場だと思いますが、採用担当として、ミスマッチを防ぐために気を付けていることはありますか?
村松:「この人を採用したい!」と思うと、どうしても良い情報を多く提供したい気持ちになるものですが、良いところだけでなく、リアルな課題の部分もお伝えする必要があると考えています。どんなに成功している会社であっても課題が無い組織はありませんので、「今あるこういう課題を一緒に解決してもらいたい」といった切り口で現状の課題をお伝えすることも意識しています。
もう一つ、候補者の方にご自身の気持ちをできるだけ言語化していただくことも重要と考えています。例えば、転職理由や、将来どういう自分になりたいのかをカジュアル面談の場で言語化していただくことで、ご自身も原点に立ち返ることができると思いますし、当社としても適切な判断ができると考えているからです。大きな概念を段階的に紐解きながら候補者の本質的な価値観を伺い、当社とマッチしそうかという見極めに生かしています。
野家:村松さんが今おっしゃっていた通りで、「(当社が)一社目の面談です」「久々の面談です」という方の中には、自分自身を深掘りできてない人も少なくありません。今、私は採用からは少し離れていますが、これまでの経験を振り返ると、「今回の転職で何を実現したいのか」や「本当に欲しいものは何か」という質問に対する答えが形式的だと感じたときには、「主語があなただとした場合、本当に欲しいものは何ですか?」という形で候補者の方と一緒にその方の意識を深堀りしていたことを思い出しました。
司会:そういうものなんですね。ちなみに、村松さんは今どのくらいの頻度でカジュアル面談を実施されているんでしょうか。
村松:時期によって変わりますが、多い時で1日3~4件、週単位では7件くらいです。面談時間は1回1時間程度で、前半30分は会社説明、後半30分は候補者の方からの質問を受ける流れにしています。
司会:それだけ場数を踏んでいるからこそ、あの柔らかい雰囲気が出せるわけですね。本当に素晴らしいと思います。
次の職場として当社を考えている方へのメッセージ
司会:それでは最後に、お二人に、次の職場として当社を考えている方へのメッセージをお願いしたいと思います。
村松:私自身も2回転職を経験しているのですが、職場を変えたからといって今までできなかったことが急にできるようになることは全く無いんですよね。職場環境を理由に転職を考える方は一定いらっしゃいますが、私は、自分以外の何かに期待して転職しても状況はあまり変わらないのではないかと思っています。
会社を選ぶときに、福利厚生や年収、将来性はもちろん重要な要素ではありますが、それ以上に、『この環境で自分のスキルがどう活きるか』『誰とどんな挑戦ができるか』という視点を持っていただくことの方が、その方にとっても有益だと感じています。ぜひ当社のこともそういった視点で見ていただけたらと思います。
野家:村松さんから、今伝えたいメッセージを伝えていただいたので、私からは、現在募集中のHR職についてお話させていただきますね。
当社はリモートワークの割合が高いため、HRもオンラインで社内メンバーと関わることが多いです。ただ、やはりオンラインだけではキャッチできる情報や伝えられることには限りがあるのが正直なところです。そのため私たちは日々、少し制約のある環境で、会社の目指す方向性やボードメンバーの想いをどう伝えるか、一体感をどう生み出すか―そんな「会社全体を後押しするような仕掛け」にHRとして微力ながらもチャレンジしています。もし「そういう環境でこそ、HRとして働いてみたい」と思ってくださる方がいらっしゃれば、ぜひ一度お話ししましょう。そして何より、「なんかこのチーム面白そう」「一緒に働いてみたいかも」と感じてくださった方も大歓迎です。カジュアル面談でぜひお話しましょう。よろしくお願いします!
司会:最後はしっかりお知らせでまとめていただきありがとうございます(笑)
インタビュー中も終始和気あいあいとした雰囲気でしたが、言葉のひとつひとつに、業務に対する真摯な想いが詰まっていると感じました。「こういうチームで働いてみたい」と思われた方、ぜひ直接お話してみてください!



/assets/images/19636006/original/e755afc6-ab61-4e4f-970d-7b313f2b6db8?1730888349)
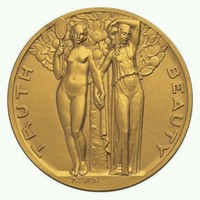




/assets/images/19636006/original/e755afc6-ab61-4e4f-970d-7b313f2b6db8?1730888349)

