株主との“対話”を生み出す、デジタルプラスの新規事業の最前線
PBR1倍割れ、上場基準を見直し、新NISAの開始──揺らぐ「株主との関係性」
いま、日本の上場企業は、かつてないほど「株主との関係構築」が問われる時代に突入しています。
東京証券取引所は、2023年よりPBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る企業に対して、改善方針や取り組み内容の開示を求めるなど、上場維持基準の強化しています。
また、2024年にスタートした新NISA制度の影響も大きく、長期保有を前提とする個人株主が急増しました。個人株主数は過去最多の1,599万人(注1)に達し、かつてのように一部の機関投資家が中心だった時代から、個人が企業を選ぶ時代へと大きく変化しています。
こうした中、再び注目を集めているのが「株主優待」です。
株主還元へ手段のひとつとして、上場企業の約3社に1社が株主優待制度を導入しています。配当と並び、投資判断に影響を与える重要な要素としてその存在感が高まっています。
(注1)日本証券協会「個人株主の動向について」より引用
「株主優待の常識を変えよう」経験と社会的変化から生まれた新規事業
このような変化にいち早く着目し、上場企業における株主優待の再設計を支援しているのが、私たちデジタルプラスの「株主優待ギフト事業」です。
デジタルプラスが株主優待ギフト事業に本格的に参入したきっかけは、大きく2つあります。
1つ目は、すでに自社で株主優待ギフトを運営してきた実績と知見がありました。これまで培ってきたノウハウを、より多くの企業に提供できると考えました。
2つ目は、新NISAの開始により個人株主が増え、配当だけでなく株主優待も注目されるようになりました。加えて、政策保有株の解消や新上場維持基準の影響もあり、企業は株主との関係を見直すタイミングを迎えています。
こうした背景から生まれたのが、既存の枠組みにとらわれない株主優待ギフトという仕組みです。
今では、上場企業のIR・総務部門からも引き合いが増え、企業価値を高めるIR施策の一環として導入が進んでいます。
今回は、この事業の立ち上げから事業責任者として関わってきた【 石渡 】に、その背景や想いを聞きました。
インタビュー|事業責任者・石渡が語る「株主優待に、まだできることがある」

ーーなぜ、株主優待ギフトの事業を始めようと思ったのですか?
株主優待ギフト事業を始めた理由は、大きく言うと社会の変化と、企業からのリアルなニーズの高まりが重なったからです。
もともと私たちデジタルプラスでは、2022年から自社の株主優待としてデジタルギフトを提供してきました。当初は事業化を強く意識していたわけではなかったのですが、ここ1〜2年で「自社でも導入したい」という企業からのお問い合わせが一気に増えたんです。
背景には、2024年からスタートした新NISA制度の影響で、個人投資家が大きく増加したことがあります。株を選ぶ基準も、「成長性」や「財務」だけではなく、「総合利回り(=配当+優待)」のような、実感しやすいリターンに注目する個人投資家が増えてきました。それに対して、企業側も株価対策の一環として、個人株主を意識した優待を新設・見直す動きが活発になってきています。
そこで私たちは、「いまの優待の仕組みに、デジタルギフトという選択肢を提案できるのでは」と考えました。従来の紙の金券に比べて、受け取り手が自由に選べる利便性、企業側のコスト最適化、そしてIR戦略に活用できるデータ取得機能など、新しい価値を提供できると確信したんです。
社会の動きと企業のニーズ、そして自社の強みが噛み合った──そんなタイミングで、この事業を立ち上げました。
一番苦労した点はどのようなことでしょうか?
大きく分けて、2つあります。
1つ目は、株主優待ギフトという新しい形のプロダクトをゼロから立ち上げていく難しさです。
もちろん、もともと「デジタルギフト」という基盤はありましたが、株主優待向けとなると用途やターゲットが大きく異なります。どんな設計が企業にとっても株主にとっても喜ばれるのかを模索しながら、ニーズや課題を丁寧にヒアリングしていきました。その声をもとに開発チームや運用チーム、バックオフィスとも連携しながら、仕組み自体を一つひとつ作っていきます。まさにプロダクトを「創る」ことに近く、現在も改善を続けているところです。
2つ目は、IRや株主還元といった分野に関する知識のキャッチアップです。
自分自身は株式投資の専門家でも、株価コンサルタントでもありません。だからこそ、IR担当者や経営層の方々と対等に対話するためには、株価対策や優待制度の位置づけなど、業界特有の前提知識をゼロから学び直す必要がありました。そのうえで、企業ごとの課題に合った提案ができるようになるまでには、相応の時間と努力が必要でした。
ですが、そうした苦労があったからこそ、今のサービスの土台が築けたと思っています。
ーー「株主優待ギフト」には、どんな社会的な意味がありますか?
株主優待ギフトには、企業と株主の双方に新たな価値を提供する社会的な意義があると考えています。
まず株主にとっては、「本当に使いたいものを自由に選べる」ことが最大のメリットです。従来の金券型優待では、使える場所が限られ、結果的に使われずに終わることも多くありました。一方で、デジタルギフトならば、PayPayマネーライトやAmazonギフトカード、dポイント、ビットコインを筆頭にした暗号資産など、株主自身のライフスタイルに合った形で受け取れるため、優待に対する満足度やエンゲージメントが大きく向上します。
企業側にとっては、未使用分の返金などによるコスト効率の改善が期待できるだけでなく、優待設計の柔軟性も広がります。また、ギフト配布の導線にアンケートや動画視聴、メールアドレス取得などを組み込むことで、株主との新たな接点を生み出し、IR活動の一環としての情報発信や株主理解の深化にもつながります。
これまで「一方通行の贈り物」に過ぎなかった株主優待が、企業と株主をつなぐ対話のきっかけへと進化しています。株主優待ギフトは、そうした新しいコミュニケーションの形を社会に提示する仕組みだと思っています。

※2025年度中間期社員総会でのMVP受賞スピーチ時の写真
ーーこの事業にどんなやりがいを感じていますか?
一番のやりがいは、企業・株主・自社、すべてにとってプラスになるサービスを提供できているという実感があることです。
営業という仕事では、どうしても「先方にとって得かどうか」を軸に考えることが多いですが、この株主優待ギフト事業は、それだけではありません。
企業はコストを抑えながら株主との関係性を強化できます。
株主は、自分が本当に使いたいものを自由に選べて、満足度も高くなります。
そして私たち自身も、そこに新たなマーケットと価値を創出できています。
関係者全員がハッピーになれる事業って、実はそう多くはないと思うんです。
さらに、まだまだ新しい市場だからこそ、正解が決まっていない部分も多く、自分のアイデアや工夫がそのまま事業の成長にダイレクトに反映されています。
「自分たちの手で新しい常識を作っている」という実感を持てることが、この事業ならではの面白さだと感じています。
ーーどんな人にこの仕事をおすすめしたいですか?
この仕事は、「誰かの役に立つこと」や「社会にとって意味のあること」を自分の手で広げていきたい人におすすめです。
特に、営業だけにとどまらず、事業づくりや仕組みの改善にも興味がある方には、すごくフィットすると思います。
今、株主優待の在り方そのものが見直されるタイミングにあり、その中で私たちの提案は「新しい当たり前」をつくる挑戦でもあります。だからこそ、まだ世の中にない価値をつくっていきたい人、仕組みそのものに介在したい人には、大きなやりがいを感じてもらえるはずです。
また、クライアントとの対話を通じてニーズを引き出し、仕組みに落とし込むまで一貫して関わりたい人にもおすすめです。単なる営業ではなく、顧客と一緒に優待の形を考えるコンサルティング的な要素が強いので、柔軟な発想力や課題解決力を発揮できる環境です。
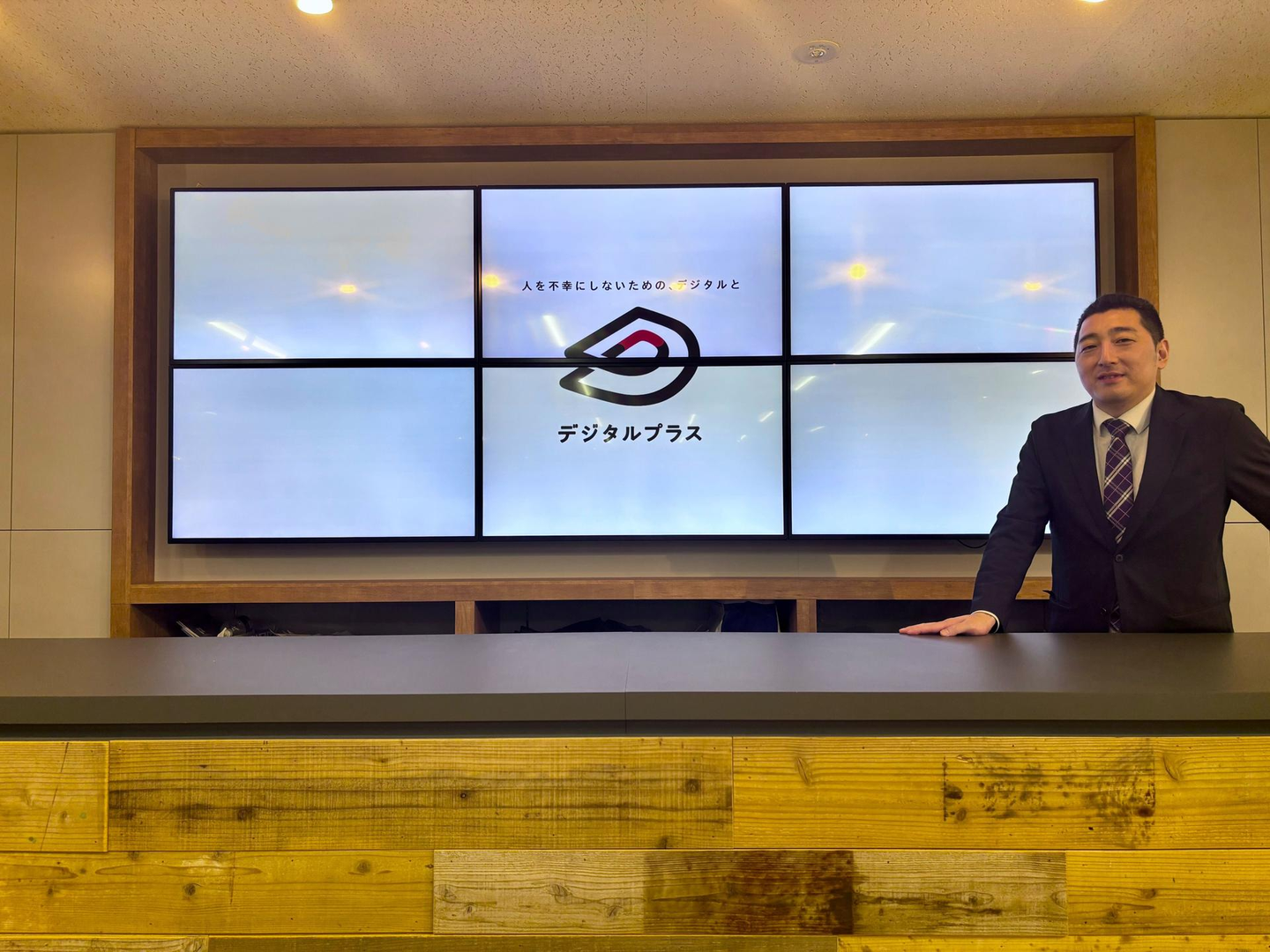
ーー最後に、この記事を読んでくれた方へメッセージをお願いします。
まだ誰も取り組めていない市場で、圧倒的ナンバーワンを一緒に目指しませんか?
株主優待という制度は、現在日本の上場企業の約40%、1,600社近くが導入しており、今後も拡大が見込まれる成長市場です。一方で、私たちデジタルプラスがすでにお取引している企業数はまだ60社程度。まだ誰も本気で取り組めていない市場が、まさに目の前に広がっています。
このタイミングで参画するということは、単なる営業や運営ではなく、「市場そのものをつくっていく」仕事だと言っても過言ではありません。株主優待×ギフトという新しい領域で、圧倒的ナンバーワンのポジションを本気で狙いにいく。そんな挑戦に一緒に取り組んでいただける方と出会えたら嬉しいです。
未来の「あたりまえ」を、一緒に作りましょう。

/assets/images/9025781/original/32d64cc5-9aab-4e90-84b7-df0b35d71a8d?1646888527)


/assets/images/9025781/original/32d64cc5-9aab-4e90-84b7-df0b35d71a8d?1646888527)
/assets/images/9025781/original/32d64cc5-9aab-4e90-84b7-df0b35d71a8d?1646888527)

