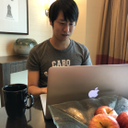「このドキュメント、全部読むの…?」絶望を希望に変えたAI "NotebookLM" という第二の脳
はじめまして。フルリモートで、AIエンジニアとして楽しく働いてる者です。
新しいプロジェクトへの参加。それはエンジニアにとって心躍る瞬間ですが、同時にちょっと憂鬱なイベントが待ち構えています。そう、「大量のドキュメントの読み込み」です。
共有されるGoogle Driveのフォルダ。中には、過去1年分の議事録、数十ページに及ぶ要件定義書、アーキテクチャ設計書、関連技術の公式ドキュメントへのリンク、etc...。
「これを全部読まないと、会話に参加できない…」
わかってはいるんです。でも、正直キツい。どこに何が書いてあるのかもわからないドキュメントの海を、ひたすら Ctrl+F でキーワード検索しながら泳ぎ続ける日々。重要な情報を見落として、後から「それ、この資料の5ページに書いてありますよ」なんて言われた日には、もう…。
そんな「ドキュメントの沼」に絶望しかけていた私を救ってくれたのが、Googleが開発した NotebookLM でした。
今日は、この「第二の脳」とも呼べるツールと、私の仕事がどう変わったのか、そのリアルな話を少しだけさせてください。
出会いは「またGoogleか」。でも、藁にもすがる思いで…
NotebookLMを知った当初の私の感想は、「またGoogleが新しいAIツール出したのか」という、少し冷めたものでした。生成AI戦国時代、次から次へと新しいツールが出ては消えていく。キャッチアップするのも一苦労です。
しかし、ある大規模なバックエンド刷新プロジェクトにアサインされた時、私の考えは一変します。
渡された資料は、まさに「ドキュM(ドキュメントの沼)」。仕様変更の歴史が刻まれた複数のPDF、担当者ごとに思想が異なる複数の設計書、そして大量の過去の議事録。機能Aと機能Bの連携について知りたいだけなのに、関連情報が複数のドキュメントに点在していて、全体像を掴むだけで一日が終わってしまいました。
「もう無理だ…誰か助けてくれ…」
脳内が完全にオーバーフローしたその時、ふと頭の片隅にあったNotebookLMの存在を思い出しました。
「ソースとなるドキュメントをアップロードして、それについて対話できるツール…」
藁にもすがる思いで、私はそのプロジェクトに関するドキュメントを片っ端からNotebookLMに放り込んでみたのです。
私だけの「プロジェクト専属AIアシスタント」が爆誕した瞬間
NotebookLMの使い方は驚くほどシンプルでした。
ノートブックを作成: プロジェクトごとに新しいノートブックを作ります。
ソースを追加: 手元にあるPDF、テキストファイル、Googleドキュメント、さらにはWebサイトのURLなどを「ソース」としてアップロードします。
質問する: あとはチャット画面で質問するだけ。
....と、こんな感じで第一弾はサラッと終了させていただきます!(笑)
NotebookLM並にシンプルな文章構成になってしまいましたが、また他のAIツールを活用して効率化や絶望から助けてもらったりしているので、気が向いた時に綴らせていただきます...!
あ、株式会社テックネクストでは絶賛エンジニアを募集中なので、ぜひ一度会社ページを覗きに来てくださいね!
AI/ML、フロントエンドエンジニア、サーバーサイドエンジニア、WEBディレクター/コーダーからSaaSシステムのカスタマイズ開発エンジニアに転身した方など、さまざまな職種、ポジションでエンジニア社員が活躍しております!
それではまたいつか〜!m(_ _)m
/assets/images/21571055/original/955c260c-56db-49a0-9e06-c40405e3b632?1752250610)

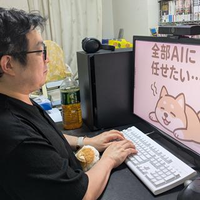
/assets/images/20969161/original/76273079-861c-4aa6-b9c5-0a86207cc479?1753231964)

/assets/images/21571055/original/955c260c-56db-49a0-9e06-c40405e3b632?1752250610)

/assets/images/21571055/original/955c260c-56db-49a0-9e06-c40405e3b632?1752250610)