「技術だけで終わらない」エンジニアの次の武器、プロジェクトマネジメントを学ぶ
Photo by Stephen Dawson on Unsplash
こんにちは!ReIT合同会社の人事総務の諸藤です。
本日は弊社が特に力を入れているプロジェクトマネジメントについて触れようかと思います。
なぜ今「プロジェクトマネジメント」なのか?

急速に変化するビジネスとテクノロジーの世界。開発現場もまた、日々その変化の最前線に立たされています。
一方で、開発プロセスの複雑化、AIの台頭などにより「良いプロダクトをつくる」だけでは通用しない時代になりました。
求められるのは、チームやステークホルダーと連携し、価値ある成果を導ける力です。
プロジェクトマネジメント能力は今後さらに重要なスキルとなってきます。
そうした背景の中、私たちはエンジニアの市場価値向上と成長支援を目的に、PM講習を開催しました。
講習のベース:PMBOK第7版とは?
PMBOK(Project Management Body of Knowledge)は、PMI(Project Management Institute)が発行する、世界的なプロジェクトマネジメントの知識体系です。
その最新版である第7版は、従来のプロセス中心のアプローチから、価値と柔軟性を重視するマネジメントへと大きく変わりました。
今回の講習では、PMBOK第7版の中心概念である以下の2つにフォーカスしました:
- 12の原則(Principles):PMにおける普遍的な行動指針
- 8つのパフォーマンス・ドメイン(Domains):プロジェクト成功のための重点領域
12の原則:どの役割にも必要な“人間力”のガイドライン

※講習資料プロジェクトマネジメント講習から抜粋
この12の原則は、プロジェクトマネージャーだけでなく、全てのプロジェクト関係者が持つべき姿勢を示すものです。
- スチュワードシップ:信頼される行動、誠実さ
- チーム:安心して意見を出せる環境づくり
- 価値志向:成果の先にいるユーザーへの意識
- 適応力と回復力:不確実性の中で前に進む力
これらは、日々の開発業務に自然に活かせる要素ばかりで、若手エンジニアからは「自分の立ち回りに指針ができた」「プロジェクト全体を意識するようになった」といった声が挙がりました。
8つのパフォーマンス・ドメイン:実務を成功させる実践知識

※講習資料プロジェクトマネジメント講習から抜粋
続いて取り上げたのが、実務で成果を上げるための8つのドメインです。
- ステークホルダー:信頼と情報共有のバランス
- 不確実性:リスクとチャンスの見極め
- 測定:KPIやOKRを活用した進捗管理
- 開発アプローチ:ウォーターフォールとアジャイルの最適な使い分け
これらは、プロジェクトの全体設計や進行、成果物の評価など、実際にどのような領域でどのような作業をしているかを掘り下げており、マネジメント経験のないエンジニアからは「PMってこんな仕事をしているんだ」「マネジメントのやることを体系的に理解しやすい」といった声が挙がりました。
エンジニアの“これから”にマネジメントの視点を

講習を通して改めて感じたのは、「プロジェクトマネジメントはPMだけのものではない」ということ。
今や、エンジニア自身が“どう動くか”が、プロジェクトの成否に大きく影響します。
特に、AIがコードを書く時代になった今、「なぜこの設計なのか?」「どう進行を最適化するか?」という判断力やチーム力が、エンジニアとしての新しい市場価値になります。
受講者の声(抜粋):
「開発者視点しか持っていなかった自分が、チーム視点を持てるようになった」
「“プロジェクトが成功するとはどういうことか”を初めて考えた」
【受講者募集中】プロジェクトマネジメント講習、継続開催中!

このプロジェクトマネジメント講習は、社内外で定期開催しています。
次回の案内はWantedly上のMeetUpにアナウンスされますので、ぜひご参加ください。
- 「PMに興味がある」
- 「プロジェクトをより良く進めたい」
- 「視座をひとつ上げたい」
そんな方にこそ、この講習はきっと大きな気づきを与えてくれるはずです。
あなたの参加を、お待ちしています。


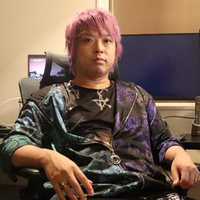
/assets/images/20381060/original/807f8928-cb1b-4e6d-bb23-8f9ee8a2a84b?1739149777)


/assets/images/20381060/original/807f8928-cb1b-4e6d-bb23-8f9ee8a2a84b?1739149777)
/assets/images/20381060/original/807f8928-cb1b-4e6d-bb23-8f9ee8a2a84b?1739149777)

