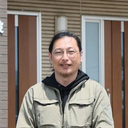みなさんはじめまして!
北海道の浦河で「神馬建設」という工務店の社長をしている神馬充匡(じんば みつまさ)です!
【プロフィール】
代表取締役6年目になる、今年47歳。 学生時代から17年間土木を学んだ後、 実家の工務店にもどり、建築14年目を迎える三代目です。 やらない後悔より、やって後悔。 一度きりの人生。楽しくやりきろうって思っています。
氷河期世代とは?
ここではまず、氷河期世代に関する基本事項をまとめます。
定義と背景

「氷河期世代」とは、主に1993年から2005年の間に就職活動を行った世代を指します。特に1975年から1984年に生まれた人々は「就職氷河期コア世代」と呼ばれることもあります。この世代が直面した最大の壁は、バブル崩壊後に訪れた長期的な不況でした。
日本の経済は、1980年代後半までのバブル景気によって活況を呈していましたが、1991年にバブルが崩壊すると、企業は次々に採用を抑制しました。新卒一括採用が主流であった日本において、企業が新卒採用を減らすことで、多くの若者が就職の門を閉ざされる結果となりました。特に1998年から2002年にかけては「超就職氷河期」とも呼ばれ、この時期に就職活動を行った人々は特に厳しい状況に置かれていました。
就職活動の厳しさは数字にも現れています。例えば、2000年の新卒求人倍率は0.99倍と、一人の学生に対して1つの求人すらないという状態でした。これにより、多くの若者が望んでいた職に就けず、正社員として働く機会を失いました。
日本社会は長年にわたり、新卒一括採用を基盤として人材を育成してきました。そのため、新卒での就職に失敗すると、その後もキャリアを取り戻すことが非常に困難になるという仕組みが出来上がっていたのです。
就職氷河期の影響

就職氷河期の影響は、一時的なものではなく、現在に至るまで多くの人々に深刻な影響を与え続けています。就職氷河期を経験した世代の多くが非正規雇用に追いやられ、安定したキャリア形成を行うことができなかったのです。
特に問題となっているのは以下の点です:
- 非正規雇用の増加
- 就職氷河期に正社員として採用されることが難しかったため、やむを得ず非正規雇用として働き始めた人が多く存在します。
- 非正規雇用では賃金が低く、正社員と比較して待遇や福利厚生が不十分であることが一般的です。
- 非正規から正社員への転職が難しく、キャリアアップの機会が非常に限られています。
- 収入の低さと将来への不安
- 非正規雇用で働き続けることで、収入が安定しない、もしくは賃金が低い状況が続きます。
- 結婚や子育て、住宅購入などのライフイベントに対する不安が大きく、将来に対する見通しを持つことが難しい人が多いです。
- 社会的孤立と精神的な負担
- 正社員としてのキャリアを築けなかったことによる自信喪失や社会的孤立が問題となっています。
- 精神的な負担が大きく、うつ病や不安障害といった精神的な健康問題を抱える人も少なくありません。
就職氷河期世代は、単なる一時的な経済的状況の変化に翻弄された世代ではなく、日本の雇用制度や社会の構造的な問題の影響を色濃く受けた世代です。特に、日本独自の「新卒一括採用」制度がこの世代にとっては大きな障壁となり、その後のキャリアを大きく制約する結果となりました。
第1章:氷河期世代が直面する現状
ここでは、氷河期世代が直面する現状についてまとめてみました。
雇用状況と経済的課題

氷河期世代が抱える大きな問題の一つが「雇用の不安定さ」と「経済的な課題」です。就職氷河期に新卒採用の門戸を閉ざされた世代は、正社員としてのキャリアを築けないまま、非正規雇用として働き続けるケースが多く見られます。特に40代後半から50代前半の世代では、その傾向が顕著です。
厚生労働省の調査によれば、氷河期世代の約4割が非正規雇用であるというデータがあります。非正規雇用の場合、以下のような問題が生じやすいです。
- 低賃金の固定化: 正社員と比べて賃金が低く、生活を安定させることが難しい。
- 待遇の格差: 社会保険や福利厚生が整っていないケースが多く、将来への不安が強い。
- キャリアアップの難しさ: 長年非正規雇用として働いてきた人が、年齢を理由に正社員としての採用機会を得ることが困難。
特に日本の雇用システムにおいては、「新卒一括採用」が主流であり、一度そのタイミングを逃すとキャリアのやり直しが難しいという問題があります。企業側は「即戦力」を求める傾向が強く、氷河期世代の人たちが新たなキャリアを築こうとする際に、ハードルが高くなっているのです。
また、最近の若手人材確保の動きによって賃上げが進んでいるものの、その恩恵は主に20代〜30代の若手層に向けられており、氷河期世代への賃金改善はほとんど進んでいません。これは「今さら中高年に投資する価値はない」といった企業側の考え方も影響していると考えられます。
結果として、氷河期世代の多くは「働き続けても将来が見えない」という状況に追い込まれています。経済的な安定を得られないまま、日々の生活費を稼ぐことで精一杯というケースも少なくありません。
社会的孤立と精神的影響

雇用の不安定さや経済的な課題は、単に生活の問題にとどまらず、精神的な健康や社会的なつながりにも深刻な影響を及ぼしています。
社会的孤立の拡大
氷河期世代の中には、社会とのつながりを失い「孤立状態」に陥る人も多く存在します。特に以下のような状況が原因となることが多いです。
- 非正規雇用の不安定さ: 短期契約や派遣での仕事が多く、同僚とのつながりが薄くなりがち。
- キャリアの断絶: 職場での昇進機会が限られており、自己肯定感の低下や社会的評価の欠如を感じやすい。
- 家庭環境の問題: 独身者が多く、家庭内での支えがないことで精神的な孤立感が強まるケースも見られます。
引きこもりや無業状態にある人も少なくありません。内閣府の調査によると、40歳〜64歳の「中高年引きこもり」の推定人数は約61万人。その多くが、就職氷河期を経験した世代に当たります。
精神的影響と健康問題
社会とのつながりを失うことで、精神的な健康にも悪影響が及びます。特に以下の問題が指摘されています。
- うつ病や不安障害の増加: 経済的な不安定さや社会的な孤立が長期化することで、心の健康を損なうケースが増えています。
- 自己評価の低下: 特に日本社会では「正社員として働くこと」が価値とされる傾向が強く、それを達成できなかった人が「自分には価値がない」と感じることが多い。
- 生活習慣の乱れ: 不規則な勤務形態や不安定な収入によって、健康的な生活を維持することが難しくなるケースもあります。
精神的な健康問題は、個人だけの問題ではなく、社会全体に影響を与える深刻な課題です。特に氷河期世代は長期にわたって厳しい状況に置かれてきたため、精神的な負担も蓄積されているのが現状です。
第2章:社会への影響
ここでは、氷河期世代と社会への影響についてまとめています。
少子高齢化との関連

氷河期世代が直面している問題は、個人の課題にとどまらず、日本社会全体に大きな影響を与えています。その中でも特に注目すべきなのが「少子高齢化との関連」です。
日本は世界でも有数の高齢化社会です。2025年には高齢者人口が約3,600万人に達すると予測されており、総人口に占める高齢者の割合も増加し続けています。一方で、少子化が進行し、現役世代の人口が減少する中で、氷河期世代が社会で果たす役割は非常に大きいものです。
子育て世代の減少と未婚率の上昇
氷河期世代の多くが、安定した収入を得られない状況にあるため、結婚や出産といったライフイベントを先延ばしにするケースが増えています。その結果、未婚率が上昇し、少子化の一因ともなっています。
特に氷河期世代にあたる40代〜50代の未婚率は過去最高を記録しており、これは日本全体の出生率の低下にもつながっています。安定した職に就くことができず、経済的に自立できない状況が、家庭を築くことへのハードルを高くしているのです。
また、結婚していても収入が低いために子供を育てることが難しいと感じる世帯も多く存在します。これによって、出生率の低下に拍車がかかり、日本の少子化問題をさらに深刻化させています。
労働力不足への影響
少子化によって現役世代の人口が減少する中、氷河期世代は労働力の一翼を担う重要な層です。しかし、非正規雇用や低賃金の問題によって、そのポテンシャルが十分に活かされていないのが現状です。
特に、企業が若手人材の確保に注力する中で、氷河期世代が正規雇用の機会を得にくいという現象が起きています。この世代が労働市場において適切に活用されないことで、日本全体の労働力不足がさらに深刻化しています。
政府は「就職氷河期世代活躍支援プログラム」を打ち出し、就業機会の拡大を図っていますが、実際に成果が見られるのは一部に限られています。この世代を活用できるかどうかが、日本の労働市場全体の安定に大きく影響することは明らかです。
社会保障制度への負担

氷河期世代の雇用問題は、社会保障制度にも大きな影響を与えています。特に年金制度や医療保険制度に対する負担が増加している現状があります。
年金制度への影響
日本の年金制度は現役世代が高齢者を支える「世代間扶養」を基本としています。しかし、氷河期世代が安定した職に就けず、低賃金で働き続けることで、納められる年金保険料が少ないという問題があります。
さらに、非正規雇用者や短期労働者の場合、厚生年金ではなく国民年金のみに加入するケースが多くなります。国民年金の保険料は比較的安価であるため、将来的に受け取れる年金額も低くなります。結果として、老後の生活資金が不足し、生活保護に頼らざるを得ないケースが増えることが懸念されています。
現時点で年金制度への影響が顕在化しているわけではありませんが、今後、氷河期世代が高齢者となった時に、年金受給者の数が増加する一方で、納付者が減少することで大きな財政負担となる可能性が高いです。
医療保険制度への影響
雇用の不安定さや経済的な問題は、健康面にも影響を及ぼします。氷河期世代は不安定な生活環境によって、健康管理に十分な時間や資金を割けないケースが多く、結果として生活習慣病やメンタルヘルスの問題を抱える人も少なくありません。
特に、精神的な問題として「うつ病」や「不安障害」といった症状を抱える人が増えており、これが医療保険制度に対する負担をさらに増加させています。さらに、低所得者層においては医療費の負担が重く、病院にかかることを避ける傾向も見られます。
また、引きこもりや生活困窮によって健康保険料を支払えない人が増えると、医療保険制度そのものの維持が困難になる恐れもあります。
氷河期世代が抱える課題は、単に個人の問題ではなく、日本社会全体に大きな影響を及ぼしています。少子高齢化や社会保障制度への負担といった問題は、今後さらに深刻化することが予想されるため、早急な対策が求められています。
第3章:解決策と支援策
ここでは、氷河期世代の問題に対する解決策と支援策についてまとめます。
政府や企業の取り組み

氷河期世代の雇用問題が社会全体の課題として認識されるようになり、政府や企業が様々な取り組みを進めています。特に「就職氷河期世代活躍支援プログラム」が注目されています。
就職氷河期世代活躍支援プログラム
厚生労働省は、就職氷河期世代が社会に再参入できるよう、2020年度から「就職氷河期世代活躍支援プログラム」を本格的に展開しました。このプログラムは、以下の3つの柱で構成されています。
- 正社員雇用の促進
- ハローワークを通じた職業紹介を強化し、正社員雇用を目指す取り組みを支援。
- 特に中小企業が氷河期世代を採用する場合、助成金が支給される「特定求職者雇用開発助成金」を設けています。
- スキルアップ支援
- 職業訓練や資格取得支援を通じて、氷河期世代が新たなスキルを身につけられるよう支援。
- ITスキルや介護職など、需要の高い分野への転職を促すための教育プログラムを提供。
- 就労支援の充実
- キャリアカウンセリングや職場定着支援を行い、再就職後も長く働き続けられるようフォロー。
- メンタルサポートを通じて、就労に対する不安やストレスを軽減する取り組みも実施しています。
企業による採用支援
企業側も、氷河期世代の活用を進めています。特に以下の取り組みが目立ちます。
- 中途採用強化
- 「即戦力」としての期待だけでなく、「育成」を前提にした採用を進め、未経験者を積極的に受け入れる企業が増加中。
- スキルアップ研修の提供
- 入社後の研修を充実させ、ITやマーケティングなど新しい業務スキルを習得できる環境を整備。
- 働きやすさの向上
- フレックスタイム制やテレワークの導入など、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を実現する企業が増えています。
個人が取るべき対策

政府や企業が支援策を整備する一方で、氷河期世代自身が「自ら動くこと」も重要です。個人としてできることを以下にまとめました。
1. 自分の強みを再確認する
氷河期世代の多くが感じている「自己肯定感の低さ」は、転職活動を困難にさせる要因の一つです。まずは、自分の経験やスキルを客観的に見つめ直し、強みを再確認しましょう。
- 職務経歴を洗い出す
- これまでのキャリアを振り返り、自分が培ってきたスキルや経験をリストアップする。
- アピールポイントを明確に
- 非正規雇用であっても培ってきた能力(接客力、コミュニケーション力、忍耐力など)を、具体的に示せるように整理する。
2. スキルを磨き直す
キャリアの再構築には、スキルアップが欠かせません。以下のような方法を取り入れてみましょう。
- 職業訓練校の活用
- 地域の職業訓練校では、ITスキルや介護スキルなど、需要が高い分野の講座が開催されています。
- オンライン学習プラットフォームを活用
- UdemyやYouTubeを使って、無料・有料問わず新しいスキルを学び直す。
3. 柔軟な働き方を視野に入れる
都会での雇用機会が限られている場合、地方でのエッセンシャルワーカーとしての働き方も検討してみましょう。
- 地方移住を検討
- 物価が安く、自然豊かな環境で働きながら生活コストを抑えられる。
- 地域おこし協力隊などの制度を活用
- 地方自治体が提供している移住支援や職業紹介を活用し、新しいキャリアを築く。
4. メンタルヘルスを意識する
氷河期世代が抱える心の負担を軽減するために、メンタルケアも忘れてはなりません。
- 相談窓口を活用
- 地方自治体やハローワークで、カウンセリングやキャリア相談が受けられます。
- 自分を追い込みすぎない
- 転職がうまくいかないときには、一度立ち止まり、心身をリフレッシュすることも大切です。
新しい道を切り開くために
氷河期世代が直面している課題は非常に深刻ですが、支援策が拡充しつつある今だからこそ、チャンスを掴むことができます。政府や企業がサポートを強化している中で、個人も積極的に情報を収集し、行動することが求められています。
僕自身も、氷河期世代としてこれからも多くのチャレンジが待っています。しかし、やらない後悔より、やって後悔する方が絶対にいい。自分自身を信じ、少しずつでも前に進んでいきましょう。
最終章:氷河期世代こそ田舎でエッセンシャルワーカーになるべき理由
「氷河期世代」と呼ばれる私たちの世代。気づけば40代〜50代となり、社会人としての経験を重ねながらも、未だに思うような働き方ができずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
- 子育てが終わり、夫婦2人の生活を考え始めた人
- 昇進ができず、仕事のやりがいを見失っている人
- 低賃金で働き続けることに疲れてしまった人
こうした現状にある方々にこそ、「田舎でエッセンシャルワーカーとして働く」という選択肢を考えてほしい。今回は、その理由をじっくりお伝えします。
3-1. 田舎は物理的な豊かさより「暮らしの豊かさ」のある場所

都会には、便利なショッピングセンターや娯楽施設があり、何でもすぐに手に入る環境が整っています。
一方で、田舎にはそれほどの利便性はないかもしれません。
ですが、田舎には「物質的な豊かさ」ではなく、「暮らしの豊かさ」があるのです。
- 広大な自然の中で心が癒される
- 新鮮で美味しい食材が手に入る
- 地域の人々とのつながりが生まれる
特に、「子育てを終えた方」にとっては、都会での利便性にこだわる必然性はありません。むしろ、夫婦2人の暮らしを大切にし、心地よく過ごせる環境を選ぶことができる世代です。その点、浦河のような地方都市は、ゆったりとした時間の流れの中で、心豊かに生きることができる場所だと言えます。
3-2. 田舎ではエッセンシャルワーカーが「本当に必要とされる」仕事になる

都会と田舎の違いは、単に「便利かどうか」だけではありません。特にエッセンシャルワーカーに関しては、田舎の方がはるかにその価値が高いのです。
都会では「誰かがやる」仕事でも、田舎では「いなければ成り立たない」仕事
たとえば、介護・福祉、建設、物流、医療などのエッセンシャルワークは、都会では代替が効くかもしれませんが、田舎ではそうはいきません。
エッセンシャルワーカーがいなければ、地域の暮らしが成り立たないのです。これは、ただ「仕事がある」という話ではなく、地域にとって本当に必要とされる存在になれるということ。
都会では「なんとなく働いている」仕事でも、田舎では「自分の仕事が、誰かの暮らしを支えている」という実感を持てるのです。
3-3. 田舎こそ「やりがい」と「安定」が手に入るチャンスがある

また、エッセンシャルワーカーを雇用する田舎の企業は、深刻な人手不足に直面しています。その理由は、若い世代が都市部へ流出し、上の世代が次々と引退しているから。
つまり、田舎では「上のポスト」が空いている状態なのです。都会では年功序列やポストの詰まりによって昇進のチャンスが限られますが、田舎では即戦力として重要な役割を担える可能性が高いのです。
- キャリアアップのチャンスが多い
- 待遇改善が進んでいる
- 安定した生活を送ることができる
さらに、田舎ではエッセンシャルワーカー不足が深刻だからこそ、賃金改善の動きが加速しています。都会よりも、むしろ田舎の方がエッセンシャルワーカーの待遇が良くなっていく可能性があるのです。
4.浦河で「自分らしい生き方」を見つける。神馬建設のサポート体制とは?
「働くこと」と「生きること」。どちらか一方を優先するのではなく、どちらも大切にしながら自分らしい暮らしを実現する。そんな理想を、浦河で叶えるために、神馬建設は“あなたに合った働き方”を用意しています。
「田舎でエッセンシャルワーカーとして働く」という選択肢を考えるなら、仕事だけでなく、その人自身の生き方に寄り添うことも大切です。そこで今回は、神馬建設がどのように社員一人ひとりの生き方をサポートしているのかについてお伝えします。
4-1. 3つの働き方から、自分に合うスタイルを選べる

私たちは、一人ひとりが理想のライフスタイルを実現できるように、3つの働き方を用意しています。
- もっともっと成長コース
仕事を通して自らの成長を最優先に考えたい人を対象にしています。仕事における目標設定のウエイトを少し高くしています。 - 着実コース
仕事を着実にこなしながらも、プライベートも充実させたいと考える方を対象にしています。ワークライフバランスのとれた生活スタイルを望む方にふさわしいコースです。 - ゆっくりコース
自らの人生を豊かにするために、仕事に必要な能力を着実に高め、他者や会社の役に立ちたいと望む方に最適なコースです。
私たちは、ただ働く場所を提供するだけではなく、一人ひとりのライフスタイルに寄り添った働き方をサポートします。就労時間の柔軟性もその一つ。ライフステージに応じた働き方の変更も可能です。
4-2. 就労時間が比較的短くライフ重視の生活が可能

また、勤務時間も非常に特徴的で、比較的就労時間が短く残業もないので、プライベートや休息の時間もゆっくり取ってもらえるようになっています。
▼(4/1〜9/30)
勤務時間:7:45〜17:00(実働:6.75時間)
休憩時間(2時間)
am 10:00~10:30
pm 12:00~13:00
pm 15:00~15:30
▼(10/1〜3/31)
勤務時間:7:45〜16:30(実働:6.75時間)
休憩時間(1.5時間)
am 10:00~10:30
pm 12:00~13:00
4-3. あなたの人生に寄り添う、柔軟な福利厚生制度

働く上で欠かせないのが、「ライフイベントに寄り添う制度」です。たとえば、一般的な育児休暇に加え、次のような柔軟な休暇制度を取り入れることを考えています。
①介護休暇
親の介護が必要になったとき、仕事との両立は容易ではありません。だからこそ、介護と仕事を両立できる仕組みを整備し、サポートしていきます。
②パートナーケア休暇
もし大切な人が病気になったら——
例えば、パートナーが癌を患い、支えが必要になったとき。
そんなときに、「一緒にいる時間を確保できる制度」があればどうでしょうか?単なる「仕事の休み」ではなく、大切な人のために使える時間をつくる。私たちは、そんなサポートを企業として提供していきたいと考えています。
その他福利厚生の面に関しては、下記の記事でもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
5.浦河の魅力──小さな幸せと、消えゆく日本の四季を感じる暮らし
都会には、物質的な豊かさが揃っています。高層ビルが立ち並び、どこへ行ってもコンビニやスーパーがあり、少し歩けばスターバックスやおしゃれなカフェが見つかる。
一方で、浦河のような田舎には、そういった便利な環境はありません。最寄りのスターバックスまで車で2時間。札幌までは、移動に4時間かかる。
でも、そんな浦河だからこそ、都会では決して味わえない魅力が詰まっています。今回は、浦河での暮らしを豊かにする2つの大きなポイントをご紹介します。
5-1. 小さな幸せをたくさん感じられる場所

浦河には、最新の商業施設や派手な娯楽施設はありません。
しかし、その代わりに、何気ない日常の中に溢れる小さな幸せがあります。
たとえば、
- 車で1時間走れば、まだ人間の手が入っていない大自然が広がる。
- 「こんな花がこの時期に咲くんだ」と、季節の移ろいを肌で感じる。
- 「こんな鳥がいるんだな」と、今まで見たことのない野生動物に出会う。
都会にいると、どうしても日々の忙しさに追われて、こういったささやかな発見に気づくことが難しいものです。浦河では、自然の中に身を置くことで、五感が研ぎ澄まされ、心が豊かになる瞬間を何度も味わえます。
5-2. 日本から消えゆく四季を、間近で感じられる
地球温暖化の影響で、日本の四季は徐々に変わりつつあります。
都市部では、春と秋が短くなり、冬の寒さも昔ほど厳しくありません。
しかし、浦河には、まだはっきりとした「四季」が残っています。
春──生命が芽吹く季節

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
浦河の春は、桜が咲き乱れ、子馬たちが立ち上がる美しい季節。
まだ冷たい空気の中で、新しい命が次々と生まれ、
「春が来た」と実感することができます。
夏──爽やかな風が吹く季節

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
都会の夏は蒸し暑く、エアコンが欠かせませんが、
浦河の夏は、海辺に昆布が干され、涼しい風が吹く過ごしやすい季節。
汗をかくほどの暑さが少なく、自然の風が心地よく感じられます。
秋──色彩が変わる季節

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
木々が燃えるように紅く色づき、
鮭が川を上る姿を見ることができる浦河の秋。
ただの景色ではなく、生き物たちの営みの中で季節が巡ることを実感できます。
冬──静かで穏やかな季節

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
本州のような豪雪地帯とは違い、浦河の冬は雪が少なく、穏やか。
しかし、海辺ではオオワシやオジロワシが羽を広げる姿が見られ、
冬の厳しさの中にも、生命の力強さを感じられる特別な季節です。
5-3. 都会にはない、浦河ならではの豊かさ

引用元:©2020 jinba kensetsu all rights reserved.(https://www.urakawa-tabi.com/about/)
「物がたくさんあること=豊かさ」ではない。浦河の暮らしは、そう気づかせてくれます。
日々の何気ない発見、季節の変化をじっくり味わう時間、都会では気づかなかった小さな幸せが、ここにはたくさんあります。
「浦河での暮らし、ちょっと気になるかも…」
そう思ったら、一度訪れてみてください。きっと、都会では味わえない「本当の豊かさ」に出会えるはずです。
結論:今後の展望と提言
ここまで「氷河期世代が直面する現状」と「解決策と支援策」についてお話してきました。日本社会全体で、氷河期世代の課題に向き合おうとする動きは確実に進んでいますが、それでもまだ多くの問題が残されています。
今後の展望
- 政府と企業の支援強化の必要性
政府や企業が提供する支援策は年々増えつつありますが、それだけでは十分とは言えません。特に地方においては、労働力不足が深刻化しており、氷河期世代が活躍できる環境をさらに整備していくことが重要です。 - 働き方の多様化を受け入れる社会へ
氷河期世代の多くは、正社員としてのキャリア形成に困難を抱えています。リモートワークやフリーランス、エッセンシャルワーカーとして地方で働くなど、多様な働き方を社会全体で認め、支援することが必要です。 - 精神的・社会的サポートの拡充
氷河期世代においては、社会的孤立やメンタルヘルスの問題も深刻です。就労支援と並行して、心理的サポートやコミュニティづくりを支援する取り組みが求められています。
提言:氷河期世代が未来を切り開くために
- 自分自身のキャリアを見直し、再構築すること
氷河期世代だからといって、自分を過小評価する必要はありません。これまでに培ってきた経験やスキルを見つめ直し、それを活かせる仕事を探すことが大切です。 - 新しいスキルの習得を積極的に行うこと
現在、ITや介護、農業などの分野での人材不足が問題となっています。自分の興味や適性に合った分野でスキルを磨き、新しいキャリアを切り開くことを目指しましょう。 - 地方での働き方を視野に入れること
地方でエッセンシャルワーカーとして働くことは、都会では得られないやりがいと安定を提供してくれる可能性があります。特に、僕がいる浦河のような場所では、自然豊かな環境での暮らしが心の豊かさをもたらしてくれます。 - メンタルヘルスを大切にすること
就職活動やキャリアチェンジは、精神的に大きな負担となることがあります。無理をせず、自分のペースで取り組むことを心掛けてください。また、必要であれば専門家のサポートを受けることも重要です。
最後に
僕自身も氷河期世代の一人として、多くの挑戦と葛藤を経験してきました。でも、だからこそ伝えたいのです。「やらない後悔より、やって後悔」を信条に行動し続けることで、必ず道は開けるということを。
地方での働き方、特にエッセンシャルワーカーとしての働き方は、氷河期世代にとって大きなチャンスだと思います。安定した職場環境と豊かな暮らしを両立できる場所が、ここ浦河にはあります。
もしこの記事を読んで少しでも興味を持ってくれたなら、ぜひ一度僕たちの工務店「神馬建設」にも足を運んでみてください。きっと新しい道が見つかるはずです。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました!


/assets/images/4861760/original/28144748-d770-45d9-bc7a-c44efc7f127e?1586147985)
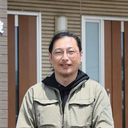
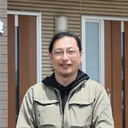
/assets/images/4861760/original/28144748-d770-45d9-bc7a-c44efc7f127e?1586147985)
/assets/images/5132539/original/28144748-d770-45d9-bc7a-c44efc7f127e?1591765232)