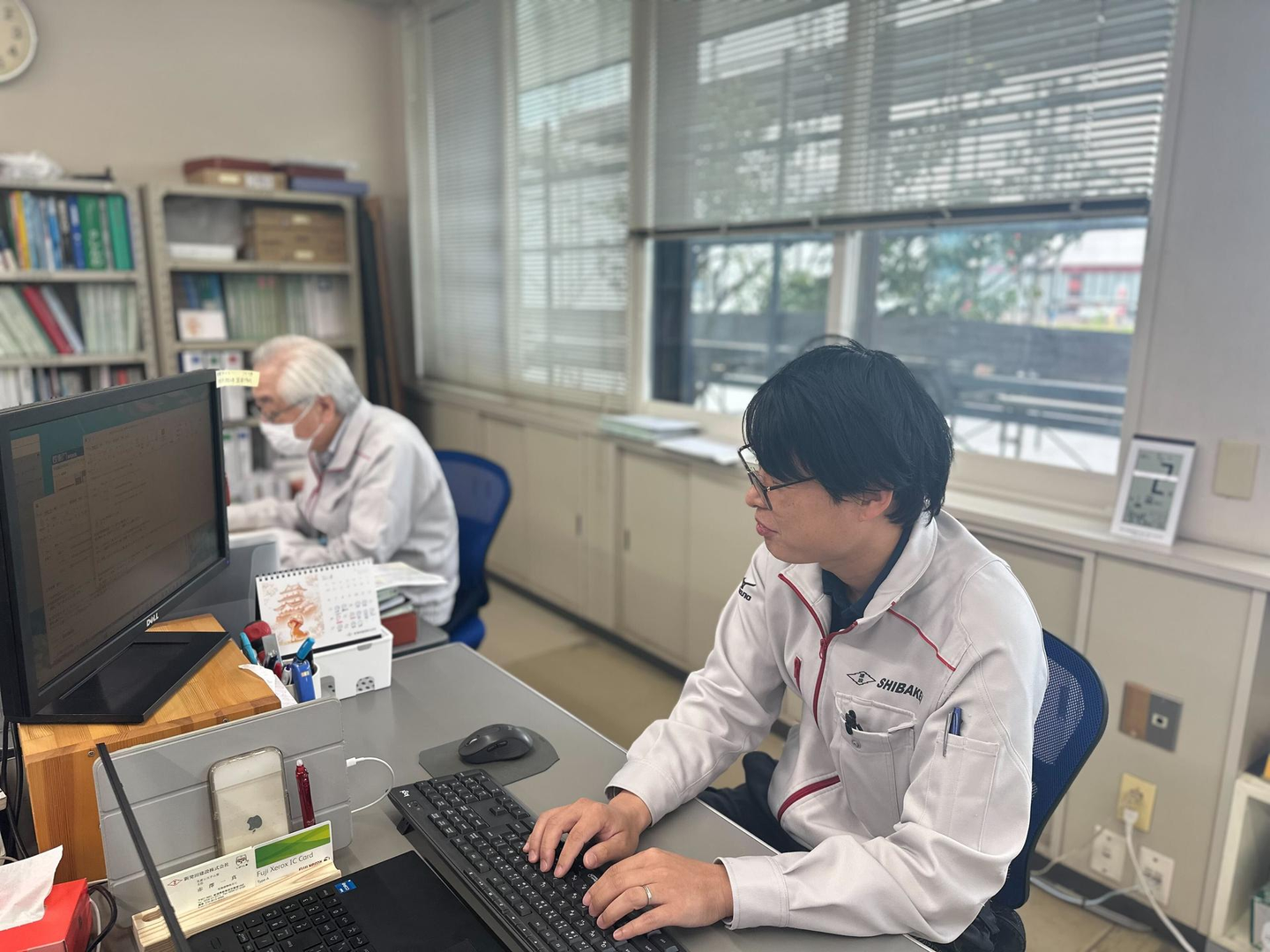「現場を支える、もうひとつの最前線──"時間をつくる仕事"の正体」ものづくりの会社 新発田建設社員インタビュー | 新発田建設株式会社
生産システム室 主任 赤澤 一真生産システム室 主任 坂場 勇希建設現場の最前線で汗を流す現場監督たち。そのすぐ隣で、見えない場所から現場を支え続ける存在がいる。新発田建設 生産システム室、坂場...
https://www.wantedly.com/companies/company_7610932/post_articles/972087
生産システム室 主任 赤澤 一真
生産システム室 主任 坂場 勇希
目立つことなく、しかし確かに現場を支え続ける二人の姿勢は、やがて会社全体の未来をも左右する存在になっていく。坂場さんと赤澤さんが見据える「次の時代に選ばれる会社」とは、どのようなものなのか。後編では、彼らの未来へのビジョンと、新発田建設への熱い想いに迫る。
※この記事は前編の続きです。まだ前編を読んでいない方は、そちらからご覧ください。
坂場さんは、今の新発田建設についてこう語る。「現場は頑張ってる。でも、会社全体がもっと成長するには、上からの改革を待つだけじゃだめだと思っています。」経営陣や管理職だけに任せるのではなく、現場の一人ひとりが意識を変え、行動していく必要があるという。
赤澤さんも同じ想いを持つ。「会社の未来を考えるのは、経営層だけの仕事じゃない。僕たち若手こそが、自分たちの働く場所を、自分たちでより良くしていくべきなんです。」
この“自分事意識”こそが、二人が今最も大切にしている価値観だ。
現場支援のあり方も、いま変革が求められている。「昔は、やり方を一つに統一することが効率的だと思っていました。でも、よく見るとそれぞれのやり方にいいところがある。」
赤澤さんも頷く。「一人ひとり、得意不得意も違うし、仕事の進め方にも個性がある。それを無視して『効率のいいやり方』って押し付けても、現場は良くならない。」
現場支援においては、画一的な方法論よりも、現場ごとの状況に合わせた“個別最適”な対応が必要とされる。だが一方で、生産システム室は「教育支援」というミッションも担っており、その領域では“一定のナレッジの平準化”も欠かせない。「実務は現場に合わせた柔軟性が求められる。でも、教育は違う。バラバラなやり方をそのまま伝えても、再現性がないから、どこを共通化できるかを見極めるのが難しいんです」と坂場さんは語る。個別対応と平準化。相反するように見えるこの2つのテーマに向き合いながら、彼らは「型を押しつける」のではなく、「現場から学び、再構築する」支援のあり方を模索している。
日々の業務を通じて、坂場さんと赤澤さんが意識しているのは、「支援のバランス」だ。「現場監督の負担を減らすことが目的ですが、事務作業も監督自身が一定はできないといけない。やっぱり、自分で乗り切る力って必要です」(坂場さん)
全てを代行するのではなく、どこまで支援し、どこを任せるか。現場ごとに判断し、バランスを取りながら支えていく。これこそが、現場支援の理想形なのかもしれない。
坂場さんが「これからの新発田建設」に必要だと感じているのが、「制度の整備」だ。
「今の社内は、ルールや仕組みが曖昧だったり、属人的に運用されていたり、これまで口頭伝承で受け継がれてきた部分があると思います。そのこと自体は否定するものではありませんが、少子高齢化が進む中、安定的に技術者を確保し続けるためにも、仕組みとして残していくことが大事だと感じています。」
今年、新発田建設は技術系の新卒採用において、理系だけでなく文系学生も対象にする方針へと舵を切った。知識や経験のバックグラウンドに差がある若手でも、しっかりと学べる環境づくりが求められている。
そして、もう一つの大きなテーマが、「技術の継承方法」だ。「上の世代の方たちは、うちの宝だと思っています。長年の経験に裏打ちされた技術があるからこそ、今の新発田建設があります。でも、その方々の引退は避けられない現実です」
新しい技術や仕組みに対応していくのは、世代を問わず大変なこと。誰にとっても“慣れ親しんだやり方”からの変化には、時間とエネルギーが必要だ。だからこそ坂場さんは、“伝え方”の進化に着目している。
「これまでのように、一対一で口頭で伝えるやり方ももちろん大切です。でも、それだけじゃなくて、ITによる技術を活用すれば、一人ひとりが持つ知見や、経験、技術といったものを一度に多くの人に共有できる。そうした“継承の効率化”にも挑戦していきたいんです」昨年はチャットツールの導入や、写真データ・資料のクラウド管理体制の整備など、デジタル基盤の構築も進めてきた。これらを活かしながら、技術やノウハウが自然と組織全体に行き渡るような「仕組み」のハブとなること。それもまた、生産システム室の大切な役割だ。
支援のかたちも、組織のあり方も、技術継承も変わらなければいけない時代に、変わる勇気を持って挑んでいる二人。「現場を支える」という役割に、熱意と責任を込めて向き合うその姿が、新発田建設の未来を、そして業界の次の時代をつくっていく。