土木工事課 工事主任 佐藤 康幸
建設業界には「現場は生き物だ」という言葉がある。天候、地盤、資材の遅れ、人員配置――あらゆる要素が常に変化し、計画通りに進むことなどほとんどない。そんな中で、佐藤さんは10年のキャリアを積み重ね、成長し続けてきた。彼にとって現場とは何なのか。その思いに迫る。
建築志望から土木へ
「もともとは建築がやりたかったんです。家を建てる仕事に憧れていました。でも、高校では土木科に進むことになって。最初は『ま、いっか』くらいの感覚でしたね。」
新発田南高校で土木を学び、短大では建築を専攻。しかし、就職活動で新発田建設の募集にエントリーしたことが、彼のキャリアを変えた。建築枠で内定を得たものの、入社直前に土木部への異動の打診を受ける。
「『お前、土木出身なんだから、こっちでやってみないか?』って言われて。しかも会社の車を支給すると(笑)。深く考えずに受けましたけど、今となってはそれが正解だったと思います」こうして彼は土木の世界へと飛び込んだ。

田んぼの現場と、土地柄に根付いた仕事
現在担当しているのは、新潟ならではとも言える水田の造成工事だ。小さな区画に分かれていた水田を広げ、農作業の効率を上げるための地盤整備を行う。水路を埋設し、農業インフラを整備するこの仕事は、単なる土木工事にとどまらない。
「田んぼの造成って、あまり馴染みのない仕事かもしれませんが、この地域では非常に重要です。新発田周辺では、こうした農業関連のインフラ整備も僕たち土木技術者の大切な仕事なんです。」
舗装された道路とは違い、泥の中での作業が中心となるため、重機の扱いも特殊だ。天候に左右されやすく、工期管理の難易度も高い。それでも、地域に密着した仕事を手掛けることに誇りを感じている。
「自分たちの仕事が、農家の方々の作業効率を上げることに直結している。そう思うと、やりがいがありますね。」
初めて任された現場と責任の重さ
入社3年目。佐藤にとって、ターニングポイントとなる現場が訪れた。
「この現場が、僕にとって初めて担当責任者として任された重要な作業でした。もちろん、周りの先輩たちがサポートしてくれましたけど、発注者と直接やり取りをして、施工の采配を振るうの、プレッシャーがすごかったですね。」その現場で、ある重要な構造物の施工中、計測データの見落としから深さの設定を誤ってしまう。
「検査のときに違和感に気づいて、頭が真っ白になりました。あのときの冷や汗は今でも忘れられません。」すぐに上司に報告し、発注者・設計と連携して補修方法を協議。追加工事と調整で大事には至らず、現場は無事に前に進んだ。
「現場って、ほんのわずかなズレが、構造や安全に大きく影響するんです。ましてや地中や基礎の仕事は、あとから簡単に直せるものじゃない。だから僕はそれ以来、“確認することを後回しにしない”ということを徹底するようになりました。」
この経験を境に、「ただ作業をこなす」から「現場を預かる」という意識へと大きく変わったという。

現場を預かる”監督業”としての矜持
現場の責任者として、佐藤さんは今、多くのプロジェクトを任される立場にある。「まだまだ半人前」と謙遜するが、その目は確実に未来を見据えている。
「監督っていう立場は、単に仕事を回すだけじゃなく、職人さんたちの動きや、協力会社との調整、発注者との折衝……すべてに目を配らなきゃいけないんです。僕1人でやれることなんて限られてる。でも、だからこそ、チームをどう動かすかが大事なんです。」
彼は、現場の空気を読むことに長けている。誰がどう動けばスムーズに進むのか、職人たちの疲労度やモチベーションまで見抜きながら、全体をコントロールする。その姿勢は、後進にも大きな影響を与えている。
「正直、つらいこともある。でも、そればっかりじゃない。やりがいもあるし、達成感もある。何より、自分が関わったものが地図に残る。それがこの仕事の醍醐味ですよね。」
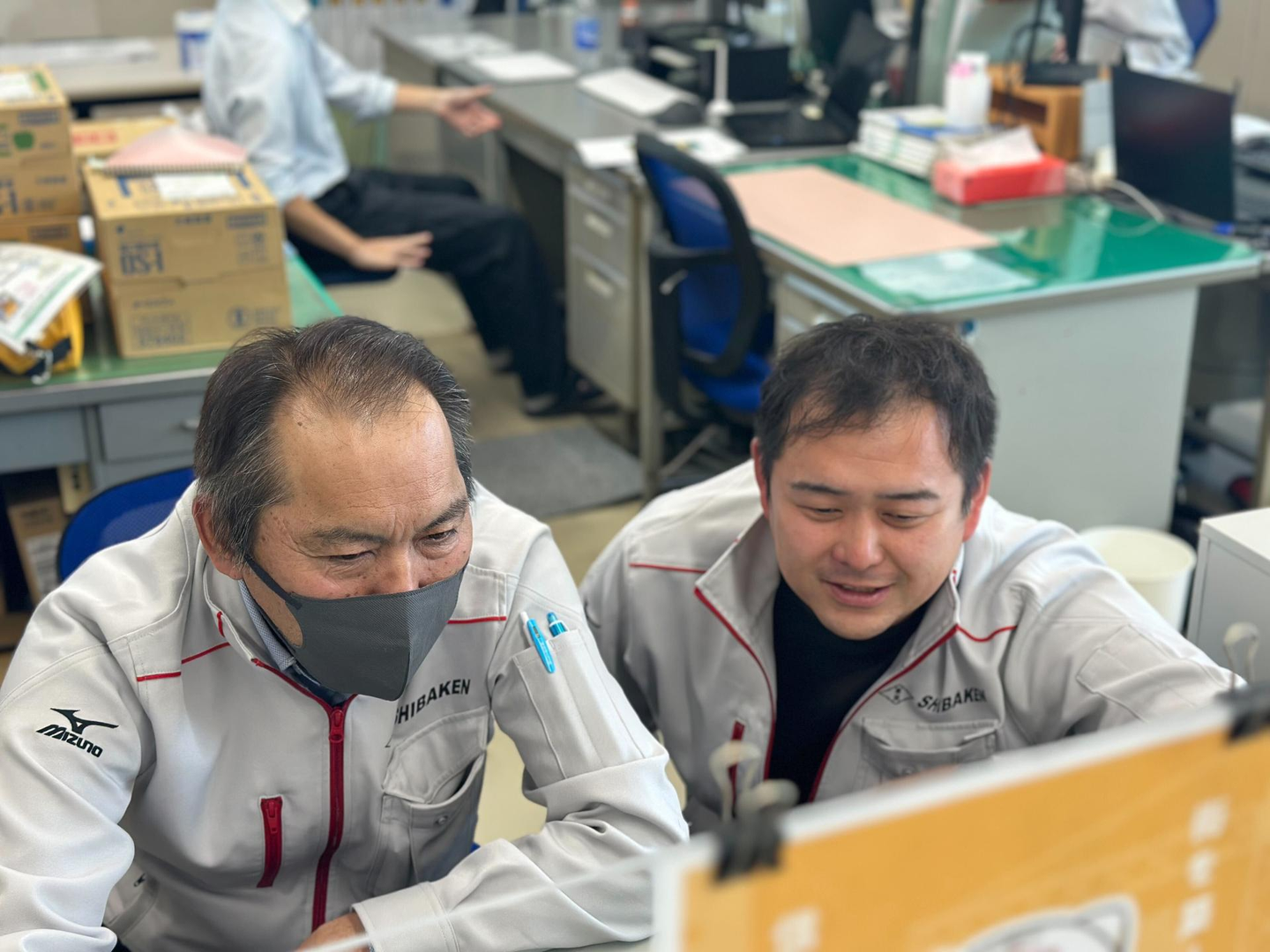
これからの目標
佐藤さんには、明確な目標がある。それは、「後輩を育てること」だ。
「僕も最初は何もわからなかった。でも、先輩たちが教えてくれたから今がある。だから、次は僕が若い人たちにバトンを渡す番。厳しいことも言うけど、それは本気で成長してほしいからこそ。うちの会社は若手が多いし、成長できる環境がある。それを存分に活かしてほしいですね。」
これから入社する人たちへのメッセージを尋ねると、少し笑って答えた。
「学生時代は思いっきり遊んでほしい。色んな人と出会って、色んな経験をしてほしい。現場は、人との関わりがすべてだから。その経験が、きっと仕事にも生きてくるはずです。」





