PROFILE
平野 真啓(inquiry system team)
2009年にアクセンチュアに新卒入社。システム開発や大規模SI、BPO案件のPMOを担当。2018年にTXP MedicalのCOOに転職し、創業フェーズから救急医療DXを推進。全国の大病院を訪問しプロダクト展開に尽力。2021年からはフリーランスとしてAI活用を含む業務改善コンサルを多分野で手掛けている。
「誰のために働くか」を問い直して。価値観とともに歩むキャリア
──現在に至るまでのキャリアについて教えてください。
2009年にアクセンチュアに新卒で入社しました。実は最初、公務員を目指していたのですが、大学の説明会で話をしてくれたOBの方がとても印象的で。フランクで親しみやすい人柄なのに、仕事の話になると一気に真剣な表情で語ってくれて、「こういう幅のある人ってすごくかっこいいな」と思ったんです。そんな人がいる場所で働けば、自分も成長できるんじゃないかと感じて、アクセンチュアへの志望を決めました。
入社後は、システム開発やアウトソーシング、BPOといった大規模プロジェクトで、PMOとしてさまざまな業務に携わりました。正直なところ、システム開発に強い興味があったわけではありません。ただ、経済学部出身の文系の自分でも「唯一“ものづくり”に関われるのがシステムだ」と言われて、自分でも何かを形にできるという点に、強く魅力を感じました。
その後、約9年間勤めたのち、2018年に医療系スタートアップのTXP Medical株式会社に転職しました。きっかけは、第一子の誕生に伴い育休を取得していたタイミングで、「自分は誰のために、何のために働いているのか?」という問いと、改めて真正面から向き合ったことでした。家族との時間、自分自身の価値観。それらを大切にしながら、意義ある仕事をしたいという思いが強くなっていた中で、偶然元上司から「一緒にやらないか?」と声をかけてもらい、COOとしてジョインすることになりました。TXPでは、救急医療の現場を支援する様々なプロダクトをつくっており、全国の病院を回って、医師の方々へプレゼンして、導入とその後のサポートまで一貫してやってました。現場の先生たちと一緒に課題と向き合い、仕事ができるのは本当にやりがいがありましたね。
その後、シリーズBを終えて、自分としては一区切りがついたので、今はフリーランスとして、いろんな企業の業務改善や企画支援をしています。生成AIを使った効率化や新規事業開発などを、マーケティングから人事・経理まで、業界問わずやっています。領域を限定せず、新しいことにどんどん挑戦できるのは、すごく自分に合ってるなと思っています。
誠実さとプロ意識が場をつくる──強い“本物志向”に惹かれて
──クロステック・マネジメント(以下XTM)には、どういった経緯でジョインされたんですか?
入社のきっかけは友人のご紹介でした。正直なところ、当初から「教育に携わりたい」という強いモチベーションがあったわけではありません。ただ、XTM代表の小笠原や京都芸術大学職員でXTM責任者の木原と話したときに、「この方々となら、何か面白い取り組みができるのでは」と直感的に感じたことが大きな決め手でした。事業内容よりも、まず“人”に惹かれたというのが率直なところです。
また、XTMには、それぞれが専門性を持ちながらも、成熟した視点で物事に向き合う“大人”が集まっています。私はよく「マチュア(mature)」という言葉を使いますが、形式や肩書に頼ることなく、経験に裏打ちされた誠実さやプロ意識によって場をつくっている。その熱量と姿勢に強く惹かれました。「こうした環境で働けたら、自分自身にも大きな刺激があるだろう」と感じたことが、参画の大きな動機の一つです。
加えて、XTMには当時は私のようなコンサルティング出身者がいなかったこともあり、そうした環境で自分がどのように価値を提供できるのか、試してみたいという想いもありました。自分の強みである「仕組み化」のスキルを活かし、外部的な視点を取り入れることで、これまでになかった新しい価値を生み出せるのではないか。そんな挑戦の機会としても、大きな魅力を感じています。
業務負荷のアンバランスを解消する戦略的アプローチ
──現在はどのようなお仕事をされていますか?また、どのような課題に取り組んでいるのでしょうか?
現在は、職員の皆さんの業務負荷が特に高い「問い合わせ業務の効率化」に取り組んでいます。もともと学園内業務の棚卸と見える化を行う中で、最も工数が集中していたのがこの領域でした。
電話・チャット・メールなど複数チャネルからの問い合わせが発生している一方で、それを一元管理する仕組みがなく、また既存のチャットボットやFAQも一部の情報が現状と合わなくなっており、部署をまたいだ管理体制も整っていない状態でした。結果として、簡単な「図書館の開館時間」のような質問も、深刻な「履修・単位に関する内容」も同じ窓口に集中し、一部の職員に業務が偏っていました。こうした課題に対し、まずはチャネルの統合とログの分析を通じて現状を見える化し、「改善計画の設計」「運用設計」へと段階的に進めています。
──この取り組みを通じて、どのような成果や展望を描いていますか?
目指しているのは、「問い合わせ自体を減らす仕組み」と「対応効率を高める仕組み」の両輪での最適化です。たとえば、情報源である学習ガイドやチャットボットの回答を常に最新に保ち、学生一人ひとりの状況やタイミングに応じて最適な回答を自動提示できるようにすることで、問い合わせ数の削減が期待できます。さらに、電話・メール・チャットなどの全チャネルを横断的に分析・統合し、ナレッジとして体系化していくことで、対応の迅速化は勿論、品質向上にもつながります。
将来的には、このモデルを京都芸術大学だけでなく、瓜生山学園の高校や日本語学校にも横展開し、瓜生山学園全体の業務効率化に寄与していくことを目指しています。
「やりたいことを実現できる」土壌があるからこそ実現できる教育DX
──この仕事の魅力や、やりがいについてはどう感じていますか?
1つ目は、関わるメンバーの多様性とプロフェッショナリズムです。
関わるメンバーは多様かつ高い専門性を有しており、それぞれの分野で第一線の経験を積んできた方々とフラットに意見交換できる環境は、大きな魅力のひとつです。IT、教育、ビジネスといった異なるバックグラウンドを持つメンバーと協働しながら、新たな価値創造に取り組めることに、日々大きなやりがいを感じています。このような優秀なチームと共に働けることが、仕事の最大の魅力です。
2つ目は、DXを推進しやすい土壌があることですね。かつて私は医療ベンチャーに在籍し、現場の医師や看護師の方々と密に連携しながら医療業務の改善に挑んでいました。しかし、制度の硬直性や組織の複雑さが大きな壁となり、現場の声が変革に反映されにくいジレンマを何度も経験しました。
一方で、今関わっている教育の現場では、多層的なステークホルダーが存在しつつも、学園の理事、現場で働く教職員、経営層、そしてXTMのメンバーが確実に同じ方向を向き、手を携えて進める環境が整っています。この一体感と推進力は、他に類を見ない稀有な土壌と言えます。「やりたいことを確実に実現できる」—この強固な基盤こそが、DXの成功を加速させる最大の魅力です。
このような環境だからこそ、現場で働く人々が本来の力を存分に発揮できる仕組みをつくっていけると感じています。今後は、教育の現場で“働く人”が本来の価値発揮に集中できるよう、基盤となる仕組みから支えていきたいと考えています。たとえば、教職員が煩雑な問い合わせ対応や事務作業に追われることなく、学生一人ひとりと丁寧に向き合い、「学生のために何ができるか」にしっかり向き合える環境を整えること。それが、その第一歩になると捉えています。


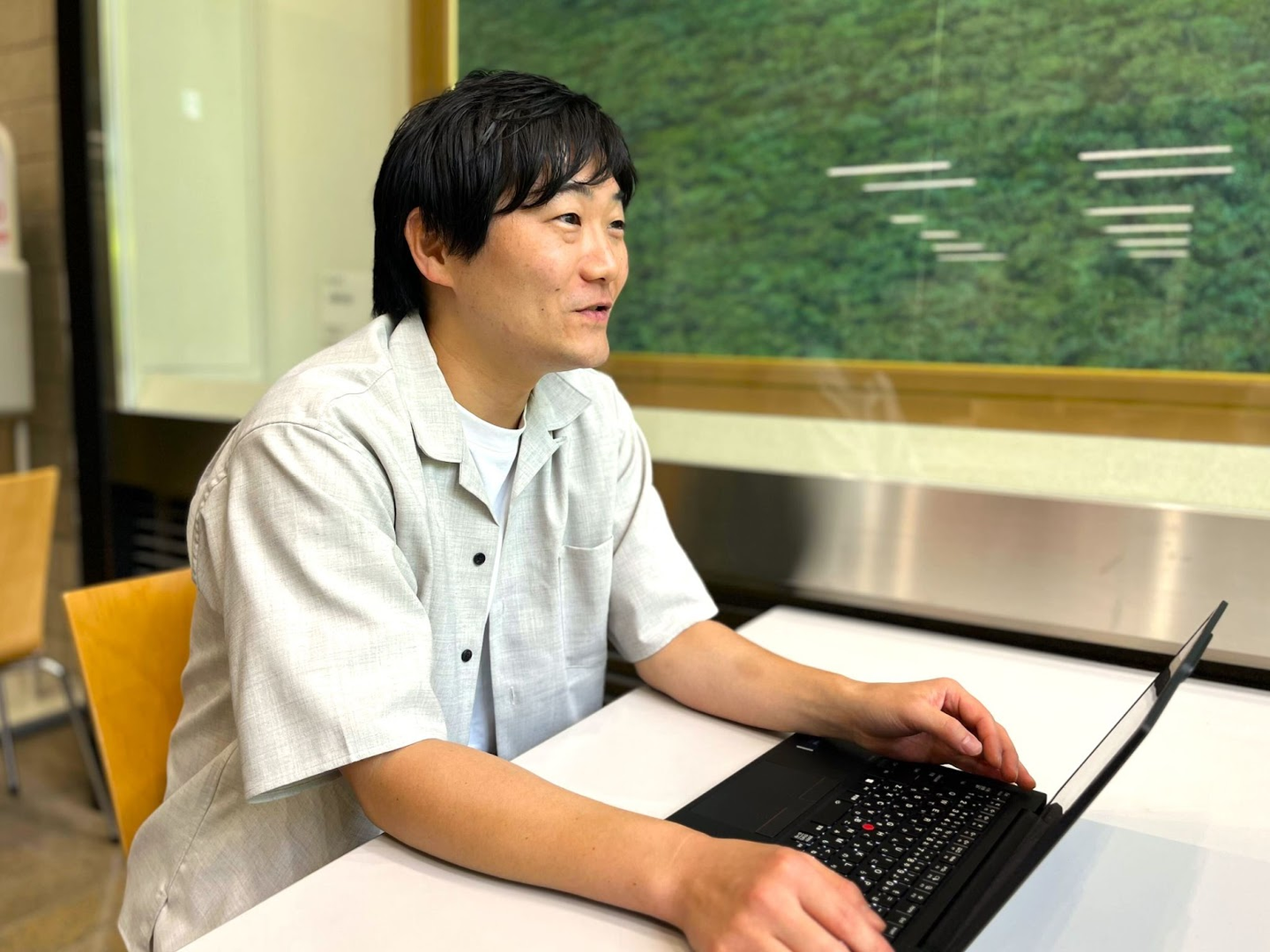
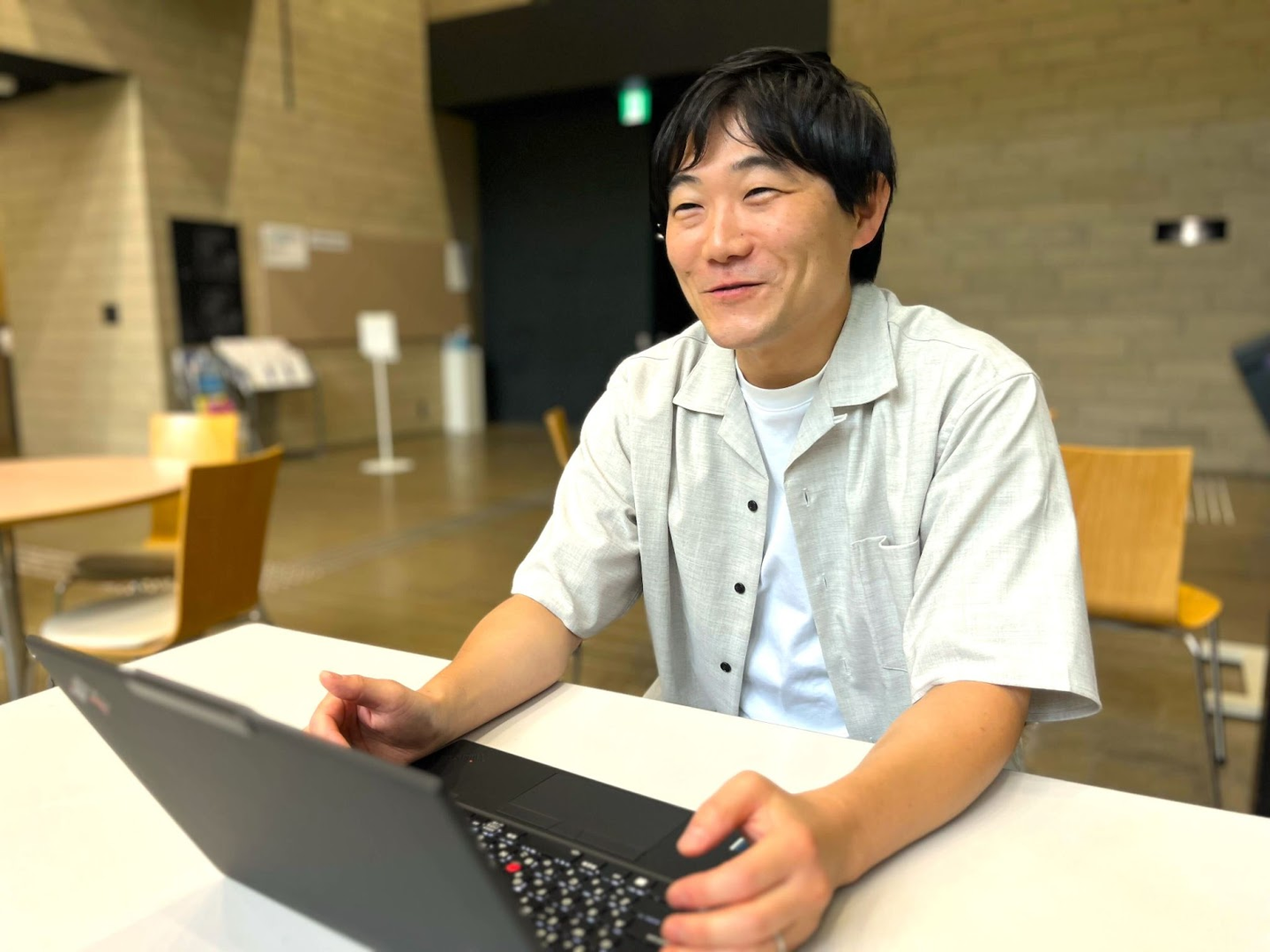
/assets/images/17505905/original/3d188f27-efbd-4a3d-814a-71a1218c42e2?1712163922)


/assets/images/17505905/original/3d188f27-efbd-4a3d-814a-71a1218c42e2?1712163922)



/assets/images/17505905/original/3d188f27-efbd-4a3d-814a-71a1218c42e2?1712163922)

