AI時代の学びは、いま静かに変わり始めています。学生がAIとともに学ぶ姿を観察していると、そこには明確な2つの傾向が見えてきました。
「思考を深めるためにAIを使う人」と、「効率的に答えを得るために使う人」。
この違いは単なる使い方の差ではありません。
脳の特性、情報処理のスタイル、そして「考える」という行為そのものの変化を示唆しています。本プロジェクトでは、AIとの対話を通じて「人がどのように考え、どう学ぶか」を改めて問い直してきました。その過程で浮かび上がってきたのは——“AIは思考を奪う存在ではなく、育てる存在になりうる”という可能性でした。
技術とともに進化する人類
人類は常に技術とともに身体も思考も変化させてきました。火の発見により柔らかい肉を食べられるようになり、消化に使うエネルギーが減った分、脳を大きく発達させることができました。文字の発明や印刷技術は記憶力中心の学習から思考力重視の学習へと知の中心を移し、社会の構造や学びのスタイルを変えました。
現代ではデジタル技術が私たちの脳や注意の使い方を再び変えつつあります。クロステック・マネジメントでの活動や若年層との接点からは、短時間で複数のタスクを効率的に処理する能力や要点を素早く把握する力が高いことが見えてきました。これは「劣化」ではなく、新しい時代に適応した思考スタイルだと私たちは考えています。こうした認知の変化を理解することが、教育や学習支援におけるAI活用の鍵となります。
教育現場で広がる新しい学びの形
教育現場でもAIによる学習の変化は顕著です。授業中、学生がAIに解答を求める光景は珍しくありませんが、同じ問題の応用問題になると手が止まる場面も多く見られます。AIを禁止しても解決にはならず、むしろAIを前提にした新しい学び方の模索が必要です。
重要なのは「AIをどう使い、どう向き合うか」です。便利なだけでなく、思考の余白を残し、問いを立てる力を育む設計が求められます。デジタル環境で最適化された脳特性を活かしつつ、自ら考える機会を失わない学習環境をつくること。それが教育の質を左右する時代になっています。AIとの関係性をどう築くかが、学びの深さや成長に直結するのです。
Neighbuddy(ネイバディ)──学びの隣にいるAI
私たちが開発している「Neighbuddy(ネイバディ)」は、単なる学習支援AIではなく、学びのパートナーとして設計されたAIです。京都芸術大学のデジタルキャンパス局が中心となり、学生のノートや過去の対話をもとに思考を深める仕組みを開発しました。
名前は「Neighbor(隣人)」と「Buddy(仲間)」を組み合わせたもので、学びの隣にいて一緒に考える存在でありたいという想いが込められています。
その名の通り、学生が学習を深めていく過程における専任のパートナーとして、学生の問いや迷いにAIとして回答を示すだけでなく、弊学にある過去データや個人の学習ログを活用しながら、必要な情報を提供したり、思考を深めるサポートをしたり、学びの手順を提案したりするAIエージェントです。
試験運用では、学生の85.9%が継続利用を希望し、「使えなくなると困る」と回答。AIが単に答えを提供する存在ではなく、思考を引き出す仲間として受け入れられつつあることが分かりました。
利用データからは、対話を通じて理解を深める「探究型」と、効率重視で答えを求める「効率型」の二つの学習スタイルが見えてきました。AIとの向き合い方によって学びの深さや思考力に差が出ることも分かり、Neighbuddyは考える余白を残す設計として注目されています。
学びの未来を一緒に創る
デジタル時代の学びでは、単に情報を得るだけでなく、関係性が学びを深める鍵になります。短時間集中型の特性を持つ学生でも、信頼できる関係性があれば思考を継続できるのです。Neighbuddyは「何を知りたいの?」「どんなふうに考えてみた?」と問いを返すことで、隣で伴走する友人のように学びを支えます。
将来的には、個人の脳や認知特性を理解し、最適な学び方を提案する「ニューロタイプモデル」の実装を目指しています。一人ひとりの脳の特性を「情報処理の多様性」として尊重することで、これまで評価されにくかった才能も発見され、花開く可能性があります。学びの未来は、人とAIの関係性によって形づくられるのです。私たちはAIを「答えを与える存在」ではなく、「共に考える仲間」として設計することで、学習の質をより高めたいと考えています。
一緒に、「学びの未来」をつくりませんか?
※Neighbuddyの開発に関わった屋田さん
本プロジェクトは2024年頭に始動して今まで進んできました。目指してきたのは、単なる「学習支援AI」の開発ではありません。AIがなんでも教えてくれる時代に「どうAIに話しかければいいのか」「どんな問いを立てれば新しい発見につながるのか」ー 人とAIのあいだに生まれる「問いのセンス」を探り続けてきました。
私たちは応答が変化する仕組みを理解し、考えてもらえる機会をつくることにも挑戦しました。一方で実際に会話を試してみると、機能そのものよりも「AIのふるまい」に注目するなど、予想もしなかった発見が何度もありました。
AIモデルの進化とともに、よりパーソナライズされた「バディ」を実現することができるようになってきます。もし何か共感する部分があれば、ぜひ気軽に声をかけてください。
一緒に「学び」の未来をつくる仲間をお待ちしています。




/assets/images/17505905/original/3d188f27-efbd-4a3d-814a-71a1218c42e2?1712163922)
/assets/images/17505905/original/3d188f27-efbd-4a3d-814a-71a1218c42e2?1712163922)

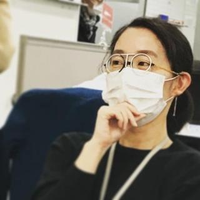


/assets/images/17505905/original/3d188f27-efbd-4a3d-814a-71a1218c42e2?1712163922)
