(“W”ewillポーズで失礼します……!笑)
バックオフィス業務のDX化を支援するスタートアップ「Wewill」には、多様なバックグラウンドを持つメンバーが集い、それぞれの専門性を高め合いながら活躍しています。
前職の経験を生かし、新たな領域に挑戦する人。子育てと両立しながら、バックオフィスを極める人。SaaSのプロフェッショナルとして、キャリアアップを目指す人――全員がWewillのカルチャーと成長環境をフル活用し、自身の市場価値を高めています。
この記事では、カスタマーサクセス本部(以下、CS本部)で活躍する6人のリアルな声を通じて、CS本部のやりがいや魅力をお届けします。
キャリアの可能性を広げる“Wewill”という選択。それぞれのキャリアチェンジストーリー
――今日は、皆さんにCS本部のやりがいや、どんな想いで働いているのかを教えてもらえたらと思います。まず、皆さんの今の仕事内容をお聞きできますか?
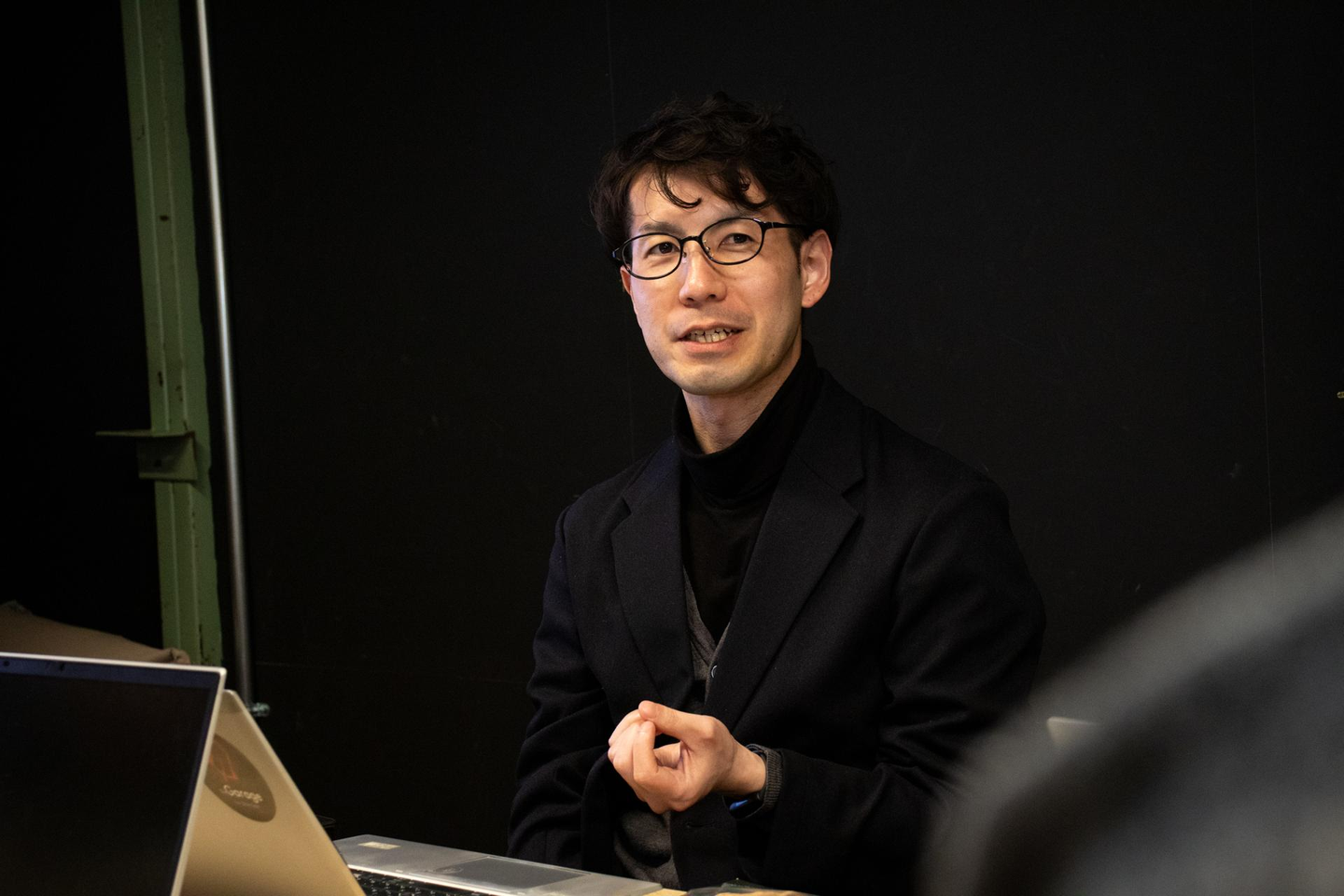
濵中 省吾|大手の総合化学メーカーの研究職からキャリアチェンジし、WewillではCSサポート室の責任者として組織拡大に貢献。
濵中:私は現在、昨年9月に新しくできたCSサポート室という部署で、室長としてメンバーのアサイン管理や業務改善を担当しています。一方、Wewillに入社当初から継続してCS本部のコンサルタントとしてお客様を担当しており、今はCSサポート室長とCS本部のコンサルタントを兼務している状況です。
Wewillでのやりがいは、自分の仕事が会社の急成長を支えることに直結していて、かつ自分のスキルアップや市場価値の向上にもつながっている点ですね。私は大手企業からキャリアチェンジしましたが、Wewillに入社して約2年半で大幅な昇格・昇給を経験できました。

金原 佳寿美|子ども英会話教室の運営会社からWewillへ転職し、未経験から経理業務のプロへ成長。アソシエイトリーダーとして、メンバーの育成にも力を注ぐ。
金原:私は、アソシエイトリーダーとして、アソシエイトが行う会計業務全体をチェックする役割を担っています。私自身、経理業務は未経験でWewillに入社したこともあり、新しく入社したメンバー皆さんの成長を支えられる今の役割にやりがいを感じています。

苅田 絢子|証券会社の営業、給与計算業務、銀行事務などの経験を経て、Wewillでは未経験から経理業務に携わり、パートから正社員へキャリアアップ。子育てと両立しながら、新しいことにも積極的に挑戦。
苅田:私は、お客様先の会計処理と社内のバックオフィス業務の両方に携わっています。社内業務では総務や法務などの幅広い業務に携わっていて、そのようななかでパートから正社員にもステップアップできました。

若松 千裕|税理士事務所に10年以上勤務し、Wewillではお客様の実務に踏み込んだ支援を実現。深い知識と経験を活かし、お客様へ最適な提案を行う。
若松:私はCS本部のコンサルタントとして、おもに浜松地域のお客様の業務効率化を支援しています。地域特有の課題や、お客様ごとの個別課題にあわせたバックオフィス支援をするなかで、お客様先のバックオフィス業務が徐々に効率化されていき、お客様に感謝の言葉をいただいたときはうれしくなりますね。

河原﨑 誠|自動車部品メーカーやスタートアップ、中国発スマホの日本法人などで経理を歴任。Wewillでは事業会社経理としての経歴を生かした支援を行っている。
河原﨑:Wewillで私が携わっている業務は、おもに2つです。まず、CS本部で記帳代行支援している顧客に対して、業務効率化の提案や財務数値を経営戦略へ活用している支援などを行うプロジェクトマネージャーを務めています。もう1つの役割としては、当社の記帳支援サービスにおいて、各メンバーが経理分野における記帳代行業務を円滑に進められるように、「WeFASS(ウィーファス)」という社内研修プロジェクトを主導しています。

伊藤 佑美|金融機関、社労士事務所を経てWewillへジョイン。労務エキスパートとして労務に関する幅広い知識と経験を顧客へ提供している。
伊藤:私は、シニアアソシエイトとして、労務案件を中心に20社程度のお客様を担当しています。お客様先の給与計算や労務関連の手続きを担い、人事労務ソフトの導入を支援することもあります。前職は社労士事務所で9年ほど務めていました。これまでの知識を生かし、お客様の労務課題を解決できたときにやりがいを感じます。
――それぞれの業務内容やポジションでご活躍ですね。バックグラウンドもさまざまな皆さんですが、Wewillにキャリアチェンジしたきっかけを教えてください。
濵中:私は入社前にメンバーと話した際に、書籍から得た学びを当たり前にカジュアルに語り合えたことで、「こういう仲間と一緒に働きたい!」と感じたことが決め手の一つでした。前職のような大きな組織では、こういった言動は「意識高い系」に見られて浮いてしまいがちだったと思います。
\総合化学メーカーの研究職からコンサルタントへ!濵中さんのストーリーはこちら/
https://www.wantedly.com/companies/company_5559701/post_articles/975754
金原:前職では、子ども向けの英会話教室を運営する愛知県の企業に勤めていました。後進の育成や業務改善にも取り組み、やりがいを感じていたのですが、結婚・育休を機に愛知から浜松に引っ越すことに。子育てとの両立を考えると通勤は難しく、浜松で仕事を探すことになったのですが、不慣れな環境で不安も感じていました。
そんなとき、IT人材育成と企業マッチングがセットになった研修プログラムを見つけて参加。その選考プロセスでWewillと面接したのですが、未経験からでも大丈夫と言ってもらえたことが決め手になりました。Wewillにはチームで助け合う社風が感じられたことや、子育て中のメンバーも多く時短勤務もできることが後押しとなりました。
\転職をキッカケにはじめて向き合った「私のキャリア」金原さんのストーリーはこちら/
https://www.wantedly.com/companies/company_5559701/post_articles/409359
苅田:私も金原さん似ていて、Wewillに入社した決め手は、「とにかくやってみては?」という杉浦さんの言葉でした。前職では証券会社の営業や給与計算のアウトソーシングなどを経験していたのですが、経理業務は未経験ですし、出産で働くことから離れていた期間もあったので……。
ですが、杉浦さんが「やってみてから考えてもいいんじゃないか?」と言ってくれたんですね。一度ブランクができたらキャリアも止まると思いこんでいた私は、今からでもチャレンジしていいんだ!と可能性を感じ、入社を決めました。
若松:私は、税理士事務所で10年以上の勤務経験があるなかで、お客様の実務に踏み込んだ支援がしたいという気持ちが強くなり、Wewillに転職しました。Wewillは、お客様先のバックオフィス支援や課題解決それ自体を本業にしており、「自分が税理士事務所でやりたいと思っていたけど手が回らずできていなかったことを、ここでなら本業としてできるのではないか」という期待感がありました。
河原﨑:私は、フルフレックス・リモートワーク可の働き方で、自分のこれまでのキャリアを生かしながら家族のケアも両立できるのではないかと、Wewillの求人を見て興味をもったことがきっかけです。
前職では、東京と静岡を往復するような働き方をしていました。楽しくやりがいのある仕事でしたが、妻が腰痛を患ってしまい、同じような働き方を継続することが困難になりました。妻をサポートするために、在宅や地元企業への就職を検討していたときに、Wewillの求人を見つけて応募することを決めました。
Wewillでは、シニアアソシエイトとして入社し、その期間は、おもに経理業務の記帳代行などを担当しました。入社するメンバーが自分の働き方に合わせて、職務上の役割を設定できる点について面接時に説明を受けたことも、Wewillで働く決め手の一つになりました。また実際にそのように今働けています。
伊藤:私は、金融機関で4年間、窓口業務を務めたあと、結婚を機に浜松に引っ越し就職先を探しました。当時は手に職をつけたいと考え、社労士事務所にキャリアチェンジ。9年間勤務する中で、給与計算から年末調整まで一通りの業務を経験しました。
労務の仕事そのものは楽しかったのですが、育休明けから短い時間で勤務したいという事情により正社員からパート転換することとなり、特定のお客様を持たずにピンチヒッターとして動くような役割に変更となりました。それはそれで重要な役割とは理解していましたが、一担当者としてお客様に向き合う仕事にチャレンジしたい気持ちから、転職を検討するようになりました。時短でも正社員として勤務して、社労士事務所での経験を生かしながら、さまざまな経験を積めることに魅力を感じ、Wewillへの入社を決めました。
また、応募要件の一つに簿記知識の理解があったのですが、ちょうど育休中に簿記を取得していたことも後押しに。簿記の勉強を通じて会計にも興味を持っていたので、Wewillでの業務経験を通じて、労務と会計を両立できるかもしれないという期待もありました。
ぶつかる壁はそれぞれ、でも「やりきること」が成長の第一歩、1人ひとりのブレイクスルー
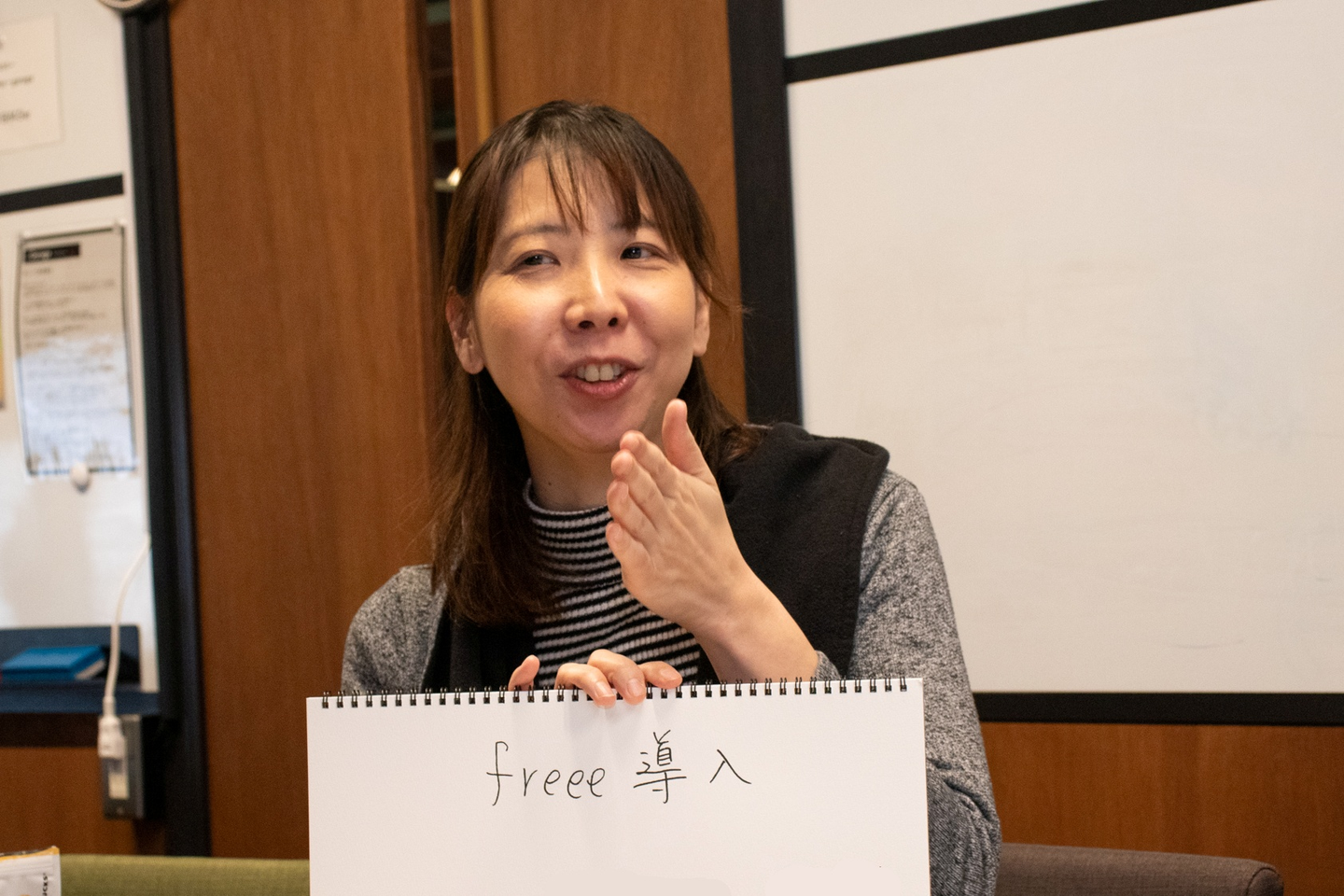
――Wewillに入社した当初の期待と、今の仕事やポジションにギャップはありますか?
濵中:私の場合は、いい意味でのギャップを感じています。Wewillでは自身のスキルアップが給与に明確に反映されるので、前職の昇給カーブを上回ったことに驚きました。
Wewillはジョブディスクリプションが社内で公開されていて、職責に対する年俸の提示が明確です。勤続年数や年齢ではなく、自己研鑽した分がちゃんと昇給・昇格につながるインパクトは予想以上でした。
金原:たしかに、杉浦さんが「成長機会への平等なアクセス」と言っているように、自分が勉強しただけキャリアアップのチャンスを得られる環境ですよね。私も、勤務体系とキャリアアップの両方で希望が叶っています。パート勤務から正社員に、そしてリーダー職になれました。今では新規のお客様の会計処理にも自信をもって対応できます。
苅田:そもそもキャリアアップが期待できるとは思ってもいなかったことと、子育てとの両立があったので、私も最初はパート入社でした。正直、入社の時点では、「こういうキャリアを築きたい」という期待や高い志はなかったかもしれません。
ですが、入社してからいろんな業務に携わり、さまざまな経験を積む中で「こういうことにも挑戦していいんだ」と自覚が持てるようになりました。日々の業務に応えるなかで、正社員にスキルアップしてきた感じです。
河原﨑:月初は一日14時間ほど働くことが続くこともありますが、月後半は業務調整するなどフルリモート・フルフレックスで働けることにギャップはなかったです。妻のサポートをしながら働くという希望を一定程度叶えることもできています。クライアントワークは初めてでしたが、事業会社経理でやってきた経験は生かせていると思っています。
伊藤:労務の知識やスキルを積めている点では期待が叶っていますが、予想外のギャップもありました。これまで経験のなかった業種のお客様のバックオフィスに携わる中で労務の奥深さを知り、会計と両立するのではなく、労務一本に絞りました。今後も労務の専門性を高めたいと考えています。
若松:おおむね希望どおりですが、想像していたよりハードなことも多いです。実際の支援の現場では、お客様はかなり具体的な実務対応を求めているんだと勉強になります。あるお客様の請求書発行業務DX化プロジェクトを担当したのですが、「請求書発行システムを導入し、請求書を電子化したら以上、終了。」ではなく、その請求書を受け取るお客様の取引先様への説明コストまで見据えた総合的なバックオフィス支援を求められました。
また、これは地方都市に共通していることかもしれませんが、浜松は紙でやり取りする文化がいまだに根強いと感じます。そのため、デジタル化を推進する際には、支援先への細やかなレクチャーが欠かせません。

(司会の富田です…!)
――皆さんに共通するのは、Wewillの業務や環境を通じて、バックオフィスのプロとして成長していることかなと思います。それだけ業務のレベルも高いのかもしれませんが、どんなハードルを乗り越えて、自身の成長につなげてきましたか?
濵中:私にとって成長につながった業務は、会計ソフトの導入支援ですね。私はポテンシャル採用で入社し、入社当時は経理未経験、会計ソフトも触ったことがありませんでした。そんな中で導入支援担当者としてアサインされ、必死で食らいついて一つ一つの案件に向き合ってきました。お客様とのミーティングの前には、時間をかけてでも納得いくまで徹底的に準備をしましたし、勉強してきました。
ただ、1年半ほど経ったあるとき、会計ソフトの提供企業から高い評価をいただきました。「濵中さんの担当企業はスケジュール通りに導入プロジェクトが完了しているし、お客様満足度も高い」「濵中さんがお客様に導入支援をしている様子の動画を、他の導入支援担当者へのお手本事例として公式のチュートリアルとして使いたい」と言っていただいたんです。
「未経験から始めた自分でも、ここまでやれるんだ」と自信を深めた出来事でした。一つ一つの案件を「やりきる」ことの積み重ねが、成長への近道かなと思いますね。
河原﨑:業務量が非常に多いので、引継ぎを受けた現状のやり方をすべて是としないことが重要かなと思っています。もちろん経理上、企業会計原則や会計基準などに照らし合わせて、変更を加えてよいか判断する必要はありますが、あるお客様の業務で、すべてを目視でチェックしていたら終わらないくらいの作業があったので、出力したCSVから関数を組んで照合箇所を自動化するような仕組みを制作することでなんとか乗り越えました。
苅田:振り返れば私も、あるスタートアップ企業のバックオフィス支援が成長ポイントになっています。経理・労務・総務・営業事務といったバックオフィス業務を一手に引き受けるという支援内容で、幅広い業務に戸惑うこともありましたが、先輩のサポートを受けながら一つずつ問題を解決し、そのお客様とは今でもよい関係が続いています。
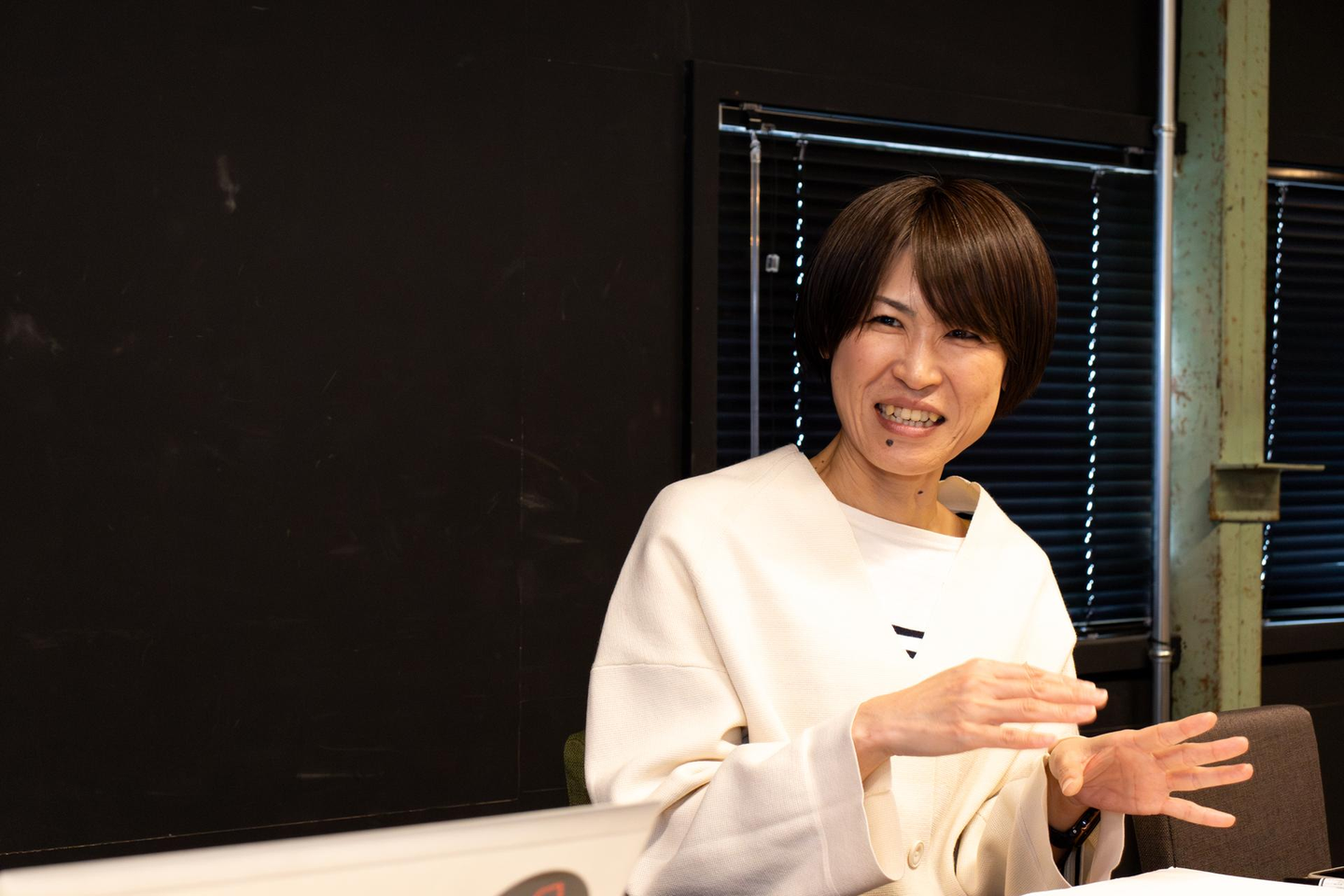
金原:お客様も「困ったときの苅田さん」と思って、いろんな相談をくださっていません?お客様が信頼して任せてくださるからこそ、この仕事にやりがいを感じる部分は大きいです。
若松:前職では会計ソフトの縛りがあって、特定のソフトしか使っていませんでした。Wewillでは会計ソフトだけでなく、ワークフローシステムや経費精算ソフト、請求書発行ソフトなどさまざまなSaaSを扱いますので、その経験がスキルアップにつながっています。また、SaaSとお客様先の基幹システムを連携することもあり、運用を見据えた仕組みを作っていく経験そのものがノウハウになっていると思いますね。
伊藤:私にとっての成長ポイントは、とあるお客様先で3ヶ月フレックス制度の導入を担当したことです。3ヶ月フレックスは非常にマイナーな制度で、存在こそ知ってはいたものの全く扱った経験がありませんでした。この制度について厚生労働省が出している資料を熟読するところから始まり、人事労務システムもカスタマイズし、何とか導入が間に合って、集大成的な出来事になりました。実は、表計算ソフトもそれまでほとんど使えなかったんですけれど、関数の知識をそのとき身に着けたことは秘密です(笑)。
苅田:表計算ソフトを使いこなしている伊藤さんにも、そんな時期があったとは!今ではCS本部のみんなが、労務で分からないことがあったら伊藤さんに聞いていますよね。
伊藤:私自身、CHRO・社労士の竹内さんにご教示いただくことがまだまだ多いですよ。労務は勉強すれば勉強するほど奥が深くて、もっと勉強しなきゃって思います。
金原:私は「性善説に立った会計の現場」で学んだことが印象に残っています。ある企業では、「前任者の仕事は正しいもの」という前提の下に連綿と記帳がされてきていたのですが、Wewillが記帳業務を受託した時点で帳簿上の残高が全く合わず、顧問税理士でも原因が分からない状況に陥っていたんです。
最終的に何とか残高を合わせることができたのですが、その企業の会計支援を通じて、性善説の危うさを学んだと思います。経営者やバックオフィスのスタッフ、士業の皆さんと会話を重ねていくうちに、どんな企業の会計処理でも対応できる自信が得られました。
それぞれの専門領域とスピード感で、プロフェッショナルとしての成長を目指す

――それでは最後に、皆さんの今後の目標を教えてください。
濵中:Wewillは、ここから3年くらいで規模が10倍になる見込みです。CS本部のメンバーも今より10倍になると考えると、Wewillのサービスを安定的に提供できる仕組みづくりが必要です。カルチャーも組織に浸透させないといけません。その役割を担っていくのがCSサポート室であり、私はその責任者として、組織に貢献するのが目標ですね。いつかWewillの上場に立ち会い、会社の成長を支えた1人として、誇りを持てるような仕事をしていきたいです。
金原:今後もさまざまなメンバーが入社する中で、アソシエイトリーダーとしてメンバーの成長をサポートしていきたいと思います。業務の中でぶつかる壁は人それぞれなので、個別の状況に寄り添って、一緒に成長を感じられるチームを作るのが目標です。経理パーソンとしても、より踏み込んだ会計処理まで担当できるように、新しい業務にチャレンジしたいと思っています。
苅田:私は明確な将来像があるというよりも、今後も自分のペースで一歩ずつ着実に知識を深めていきたいかなと思います。河原﨑さんが提供してくれるWeFASSの集合学習や、先輩方のレクチャーを受けるだけでも、スキルアップにつながるのがプロが集うWewillという組織のすごいところ。会計や経理のスキルはどこでも通用するものですし、今後も会計・経理を極めていきたいですね。
伊藤:私も苅田さんと同じく、日々の業務を通じて成長していきたいですね。そして、「労務のことなら伊藤に聞けば何でもわかる」と言われる存在になることが大きな目標です。私たちの判断一つがお客様企業に与える影響は小さくありません。先日も、あるお客様から労務相談をいただき判断に迷う場面があったのですが、それは自分の聞き取りが甘かったことが要因でした。労務のプロとして自立できるように、今後はさらに労務知識を深めることはもちろん、コンサルティング能力も磨いていきたいです。
若松:どんなにシステムが発展しても、お客様の状況に合わせた細やかなチューニングは人間が行う必要があると考えます。今後、さらに多くのSaaSを勉強していきつつ、お客様にとっての最適な提案をできるようになりたいですね。複数の案件から得られた学びも社内外に還元していきたいと思います。
河原﨑:これまでのサービス提供の中で記帳業務効率化や経営管理支援に関わるさまざまなSaaSを利用していますが、実務で求められることと、SaaSが提供できることの間にある、いわゆるラストワンマイルの課題はまだまだあるなと感じています。
そのようなラストワンマイルにあるさまざまな「不」の解消を、Wewill「SYNUPSBackOffice」としての、お客様に本質的に役立つようなサービス提供により改革していきたいと思っています。

/assets/images/9915904/original/6df0ac7a-52c3-4022-bf2c-588e42c65cc7?1657856242)


/assets/images/9915904/original/6df0ac7a-52c3-4022-bf2c-588e42c65cc7?1657856242)





/assets/images/9915904/original/6df0ac7a-52c3-4022-bf2c-588e42c65cc7?1657856242)

