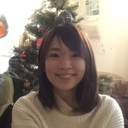こんにちは、ワミィの採用コンサルティング/RPO担当の石川です。
本日のテーマは「新卒エンジニア採用を成功させる3つの手法!」です。新卒エンジニア採用は中途採用とは異なるアプローチが必要となってきます。今回は、現在のトレンドとなるアプローチ方法も含めてお伝えします。
1. 企業の成長と新卒エンジニアの必要性
現代において企業成長のためには、ITエンジニアの確保が各社急務の課題となっています。今後のIT人材需要が不足するという問題や、現在のエンジニア中途採用における困難さを鑑みると、新卒エンジニアを採用し育成を図ることは組織拡大のための重要な施策してとらえ、いち早く動き出す必要があるといえるでしょう。
これは、育成のコストを含めても新卒エンジニア採用の方が中途に比べて低くなることや、今の学生がIT環境に恵まれた中で学んでおり、トレンドの把握や一定の技術力を有している可能性が高いという背景もあります。
2. スキルレベルと採用・育成について
新卒エンジニアの採用活動を行う際にやっておきたいことの一つとして、学生のレベルの把握や、採用したいターゲットを設定しておくことが挙げられます。レベルについては以下のように3段階に分けることができます。

・即戦力レベル:入社後すぐに戦力として期待できるレベルの学生です。学生時代から積極的に開発に取り組み、インターンシップやアルバイトで実務経験を積んできたため、現場で即活躍できる技術や問題解決能力を持っています。
・成長潜力レベル:企業での実務経験はありませんが、学生時代に独自に企画や開発を行い、実践的な経験を積んできた学生です。自ら学ぶ姿勢があり、必要なスキルを早期に習得し、成長するポテンシャルを持っています。
・基礎力レベル:自主的な開発経験は少ないものの、授業や課題を通じて基礎的な知識や開発経験を有している学生です。実務においてはまだ習熟が必要ですが、基本的な知識やツールの使用経験があり、これからの学習意欲や成長を期待できます。
レベルによっては採用難易度が高いため、以降に述べる採用戦略を複数組み合わせる必要があります。
また、レベルに合わせた採用後の「育成」についても予め考えておく必要があります。採用はゴールではありませんので、新卒学生が着実に力を付け、現場の戦力としてはもちろん、将来的に企業をリードできる人材になるよう長期的に計画する必要があります。そのためには現場部門の社員に新卒エンジニアを育てていくのは自分たちである、という当事者意識を持ってもらうためにも、インターンシップを実施したり、OJTの体制を整えておくなど早い段階から会社全体での意識付けを行うことが有効です。
3. 効果的な新卒エンジニア採用戦略
限られた母集団の中から優秀な学生を採用すべく、重要になってくるのがどの採用手法でアプローチするかということです。中途採用と同様に、獲得したい人材レベルや自社に合った採用手法を見出し、アプローチを行う必要があります。
現在、エンジニアの新卒採用において主流となっているのが次の3種類の方法です。

どの手法をとっていくかは、採用したい人物像や企業側の人員体制、採用状況によって異なりますが、多くの企業では複数の手法を組み合わせて行っています。
1 1on1イベント
1on1イベントとは、学生が1日で複数の企業のエンジニアやCTO、人事担当者と個別に話ができるスカウトイベントです。メガベンチャーや大手人気企業などが集まり、学生は企業に対し研究内容やスキルをアピールするのに対し、企業が気になる学生にオファーを送り、個別面談を行うという内容です。学生が企業を募集する形態から「逆求人」と呼ばれています。
即戦力となる上位層と呼ばれる、これまでに技術力を磨いてきた学生や、プログラミング・開発経験を持つ学生は、この1on1イベントを活用する傾向が高く、これら上位層の学生2~3名を採用目標にしている企業の場合は注力する価値のある手法といえるでしょう。
2 スカウトサービス
スカウトは企業が直接学生に就職のオファーを行う採用方法のことです。企業は欲しい人材にアプローチできる他、自社のことを知らない層に対してもアピールができます。
要件となる技術力や、ピンポイントでターゲットとしている大学を検索設定し、条件に当てはまる学生にインターンシップや説明会、座談会などの企画をオファー。
学生側がオファーを受け取れば、その後の選考に向けてコミュニケーションが取れるというものです。
オファーを送ったり学生との連絡を継続していく等、採用担当者の工数が一定かかりますが、求める人物像に近い母集団形成の実現や自社アピールの機会向上というメリットが挙げられます。
3 人材紹介サービス
採用担当者が限られており、採用活動に十分な時間が取れない場合におすすめなのが人材紹介サービスの利用です。
企業は人材紹介会社に求人の詳細や求める人物像、自社の魅力について共有しておく必要がありますが、共有がうまくいくと、学生に対する自社の魅力づけや応募促進を紹介会社がフォローしてくれるようになります。
また、選考を辞退されても学生側の意見として紹介会社からのフィードバックがあるため、選考フローの改善に取り入れることができます。
この他、夏~秋・冬にかけて行うインターンシップや、X、インスタグラム、TicktokなどのSNSを活用した採用活動も盛んであり、これまで企業認知や母集団形成を目的とした企画やサービスの利用が最近では選考に直結するように活動を行う企業が多い傾向にあります。
4.まとめ
新卒のエンジニア採用のトレンドは数年で移り変わっていくため、採用担当者は引き続き今のトレンドを注視する必要があります。
就職活動を行う学生が何を重視しているのかを理解し、そのニーズに合わせて自社の魅力を効果的に伝える戦略を立てることが、新卒採用成功の鍵を握ると言えるでしょう。
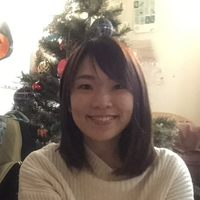
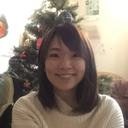
/assets/images/6500526/original/6411caec-80f7-4e17-ad47-ceacea058240?1617351092)




/assets/images/6500526/original/6411caec-80f7-4e17-ad47-ceacea058240?1617351092)