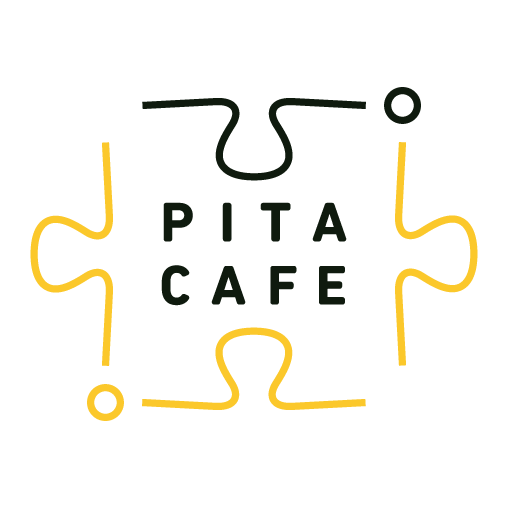はじめまして。ぴたカフェ代表の平田です。
本記事では、私が銀行員から幼児教室の起業家へと転身した理由、その背景や想い、そして幼児教室レクルンの教育理念やカリキュラムの特徴についてご紹介します。
ベンチャーキャピタル時代とエドテックとの出会い
2006年、みずほ銀行に入行し、神田支店や福岡支店で法人営業を経験。その後、2011年にみずほキャピタルへ出向し、約3年間ベンチャー支援に従事しました。
当時は「エデュケーション×テクノロジー=エドテク」と呼ばれる分野が盛り上がりを見せており、教育とITを掛け合わせたベンチャー企業が次々と誕生していました。私もエドテク企業を中心に多くのベンチャー支援を行い、同時期にはメルカリのような新興企業も創業していました。
IT企業だけでなく、多店舗展開を行う企業も一定数上場を果たしています。私は東京ビッグサイトで開催されていたフランチャイズショーで、幼児教室の企業ブースを訪れたことが、幼児教育に興味を持つきっかけとなりました。そのブースで「幼児教育を受ければ将来の可能性が広がる」と説明を受け、そんな世界があるのかと驚いたのを今でも覚えています。
自分の原体験と幼児教育への関心
振り返ってみると、私が幼児教育に惹かれたのは、みずほ銀行の新人時代と、幼少期から高校まで続けていた野球や運動の経験が大きく影響していると感じます。
みずほ銀行の新人時代、私は年に10回もの泊まり込み研修を受け、毎回最終日にテストがありました。毎日復習しても平均点程度しか取れず、一方で東大出身の同期は毎日飲みに行っても高得点を取っていました。神田支店に配属された際も、同期は東大・一橋・京大・早稲田といった名門大学出身者ばかり。私は明治大学出身で、しかも浪人経験もあり、稟議書の「て・に・お・は」レベルのミスを赤ペンで指摘される日々。他の同期は稟議のスピードも正確性も圧倒的で、学力の差が仕事にも如実に現れることを痛感し、劣等感を抱いていました。
一方で、私は幼少期から運動が得意で、高校まで野球に打ち込んできました。運動に関しては何でも前向きに取り組め、難しいこともできるまでのプロセスを楽しめるタイプでした。友人よりも運動の飲み込みも早く、成功体験を積み重ねてきた自負があります。
この「運動での得意さ」や「新しいことへの好奇心」が、実は知的な分野にも通じるのではないか――。自分自身の経験から、幼い頃に何かに夢中になったり、できるまで挑戦したりする体験が、大人になってからの知的好奇心や学びの意欲にもつながるのだとリアルに感じました。だからこそ、幼児期にこそ"学びの楽しさ"や"挑戦する喜び"を体験できる環境が必要だと強く思うようになりました。
起業から幼児教室立ち上げまでの経緯と教育理念
2013年11月、みずほフィナンシャルグループを退職し、福岡に本社を置き、幼児教室を多店舗展開している企業へ転職しました。しかし、入社してみると教育事業よりもフランチャイズ展開が主軸で、教育そのものより店舗開発に重きを置く企業でした。私は本当にやりたかった幼児教育に携わるため、2ヶ月で退職し、自分で幼児教室を立ち上げることを決意しました。
資金もノウハウもない中、事業計画を多くの方に説明し、約半年かけて資金援助者やプログラム開発・講師の協力者を見つけ、2014年8月に創業。2015年4月の教室オープンを目指し、約半年間準備を続けました。
当初は1歳児から6歳児までのプログラムを検討していましたが、特に3歳児以下の教育が将来に与える影響が非常に大きいという研究結果が数多く報告されていることから、この年代に特化する意義を強く感じました。加えて、4~6歳児は競合が多い一方で、3歳児以下は競合が少ないという市場環境もあり、最終的に1~3歳児に特化した幼児プログラムを開発することにしました。
プログラム開発では、まず6歳児時点のゴールを描き、そこから逆算して5歳児、4歳児…と1年ごとにゴールを設定。さらに1~3歳児の3学年を12ヶ月に分けて各月ごとに目標を設け、1ヶ月3回のレッスンをどのように楽しく反復し、できることを増やしていくかを設計しました。
また、幼児期に獲得しやすい能力や将来伸びやすい力、将来役立つ能力についても検討し、1回のレッスンで約15個、1個あたり3分程度のプログラムを設定。子どもが飽きないよう、できるだけ同じ教材は使わず、3学年で1,000個以上の教材を準備しました。初年度は約600個、2年目に400個の教材を作成し、2年間かけて教材・プログラム開発を行いました。
教室は東京電機大学の山田先生と学生に協力していただき、全て自分たちの手で作り込んでいきました。
レクルンの教育理念とカリキュラムの特徴
レクルンでは「学びを遊びに」「成長する喜び」を大切にし、子どもたちの自発性や行動力、オリジナリティを育むことを目指しました。20世紀型の「パズル型能力」から、21世紀型の「レゴ型能力」へ――正解を覚えるのではなく、自分で考え、創造し、行動する力を重視しました。
毎月のテーマ(例:動物、鳥、親子、乗り物、生活、町・お店、魚、虫、形、果物・野菜、色、天気・自然)や歌を設定し、日常とは少し違った特別な世界の中で学びを体験できるカリキュラムを組みました。
1日の流れは「あいさつ」から始まり、「うた&運動」「絵本」「思考&概念」「手先活動」と続きます。手先を動かす体験型のハンドメイド教材を中心に、フェルトなど多様な素材を使い、子どもが主体的に学べる工夫をしました。
教室空間も「光・風・草木」をモチーフに、明るく爽やかで優しい雰囲気づくりを目指し、プレイスペースやラウンジスペース、ユーティリティスペースなど、子どもも大人も安心して過ごせる環境を整えました。
他教室との違いは、手先を動かす体験型教材(ハンドメイド)や多素材の活用、子どもの自発性・オリジナリティ重視の教育方針にあります。
おわりに
ここまで、私がなぜ銀行員から幼児教室の起業家へ転身し、レクルンを立ち上げたのか、その背景や想い、そしてレクルンの教育理念についてお伝えしてきました。
しかし、理想を掲げてスタートしたものの、実際の起業や教室運営は決して順風満帆ではありませんでした。次回は、創業当初に直面したさまざまな苦労や、現場で感じた課題について、リアルな体験をお伝えしたいと思います。
ご興味のある方は、ぜひ次回もご覧ください。