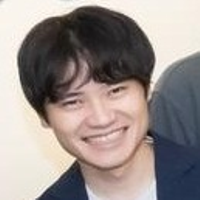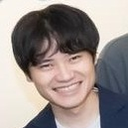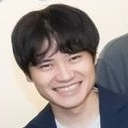「エンタメの感動」を最速で届けるため、ぴあは今年、内製開発チームであるIT共創開発部を立ち上げました。新しい挑戦の船出において、私たちが課題としたのは「スピード」と「効率」です。少数精鋭で最高のパフォーマンスを出すため、私たちはGitHub CopilotやDevinといったAI技術を現場に導入することを決断し、「AI駆動開発」に取り組んでいます。
本記事では、この新しい取り組みの現場に参画した開発エンジニアの一員である私が、AIを開発の相棒にしたリアルな取り組みと、実際に体験して感じた正直な感想を公開します。AI駆動開発がもたらした開発速度の向上や、仕事の「面白さ・やりがい」の変化とは?
転職を考えるPM・開発者の方へ。未来の働き方を探求するぴあの新しい開発現場を、ぜひ覗いてみませんか?私たちと一緒に、エンタメの感動を「共創」する仲間をお待ちしています!
目次
💡 導入(詳細): 内製開発チーム発足のリアル
🧩 課題と解決策: AI駆動開発の具体的な取り組み
🎢 過程と学び: 開発者のリアルな感想と変化
✅ 成果と展望
まとめ・結び
💡 導入(詳細): 内製開発チーム発足のリアル
「エンタメの感動を最速で届ける」という命題のもと、ぴあが今年立ち上げたのがIT共創開発部です。
私たちが内製化を決めた最大の動機は、デジタル技術の進歩と市場ニーズのスピードに俊敏に対応するため、「意思決定の高速化」と「ノウハウの蓄積」が必要不可欠だと判断したからです。
現在、私たちのチームが取り組んでいるのは、エンタメの現場の業務改善を目的としたツールの開発です。例えば、チケット当選者に対して座席を割り当てる際に、最適な割り当て方法をシミュレーションするツールや、これまで手入力で行っていた公演情報の入力を自動化するためのツールなど、現場の生産性を高めるために業務にあたる従業員と共に「共創開発」を行っています。
新しい内製組織の船出において、私たちは「少ない人数で最大の能率を上げる」という課題に直面。迅速なニーズの反映とリードタイム短縮を実現するため、最先端の「AI駆動開発」を組織の柱に据えることを決断しました。
🧩 課題と解決策: AI駆動開発の具体的な取り組み
AI導入以前の課題は明確でした。それは「ニーズを迅速に反映し対応するには、時間と人員コストがかかる」という点です。お客様や現場の「今すぐ欲しい」という要望に対し、リードタイムを劇的に短く機能実装したいという強いニーズがありました。
この課題を解決するため、私たちはGitHub CopilotとDevinを「開発の相棒」として迎え入れました。
具体的なフローは、人間(開発者)が実装したい機能をIssueとして明確化し、そのIssueを元に機能実装からテストコードの記載までをAI(Devin)が行うというサイクルです。
AIが実装した内容は、最終的に人間がレビューしてフィードバック(FB)を行い、さらに実装を繰り返します。驚くべきことに、時にはDevinが実装したものをGitHub Copilotがレビューするという、AI同士の「共創」も取り入れ、人間のレビューコストの最適化を図っています。
また、AIによる開発の精度を高めるため、Readmeや開発標準などのコンテキストをMarkdown形式であらかじめ詳細に記述し、それを参照させるという工夫を徹底。DevinのPlaybook機能なども活用し、意図しない実装を防ぐための環境構築にも注力しています。
🎢 過程と学び: 開発者のリアルな感想と変化
AI駆動開発に初めて携わった私自身の正直な感想は「驚嘆」でした。これまで一人で2〜3週間以上かかると見込んでいた機能が、場合によっては半日かからずに開発できてしまうのです。
特に驚いたのは、コードの実装だけでなく、コードを元に設計書をリバースで記載するといった業務も可能で、フォーマットの正確性などは人間が個別に行うよりも精度よくできる場合があることです。これにより、ユーザーと「動くものベース」で会話できるまでのリードタイムはかなり短縮されました。
一方で、課題も見えてきました。コードの実装が瞬時に行われるため、人間のレビューが追い付かずボトルネックになる点です。また、最終的な判断は人間が行う必要があり、その判断のための技術知識は必須。これまで以上に技術習得のスピード感が求められると感じています。
そして、AIへの指示の出し方(プロンプトの書き方)は、人間への指示の出し方に通じるものがあります。具体性がないと意図せぬコードが出来上がり、かえって時間がかかることもあるため、この点ではエンジニアでありながら、より上位のマネジメント的な視点も必要になってくることを痛感しました。
この実践を通して得られた最大の学びは、「AIがやってくれるから、人間は学習しなくてもよい」という発想は真逆だったということです。AIが生成したものを「根拠を持って正しい」と説明するには、人間側も同水準に学習していなければ対応できません。これまで個人で実装していた時に発生した「実装方法を考え、学習する時間」がオミットされるため、これまで以上に意図的に学習しないといけないという高い意識が芽生えました。
✅ 成果と展望
AI駆動開発は、内製開発チームのスタートダッシュに明確な成果をもたらしています。定量的な側面では、体感として、開発に費やす時間が20%〜30%削減されたと実感しています。
しかし、得られる価値は速度だけではありません。DevinやCopilotというAIを単なるツールではなく、「ジュニアエンジニア」として捉えることで、開発者一人ひとりの隣にもう一人、優秀なサポートメンバーがついたような感覚を得ています。実装やテストコード作成といった定型的な作業をAIが担うことで、私たちは「考える時間」や「より付加価値の高い業務」に集中できるようになりました。これは少数精鋭のチームにとって、圧倒的な効率向上であり、私たちが目指す「超速」共創開発の実現に近づいています。
今後は、現在の機能実装などの開発業務中心のAI利用から一歩踏み出し、要件定義などのより上層の工程でもAIを活用し、発展させていくことを試みる段階です。AIとの「共創」をさらに深め、開発プロセス全体を革新していきます。
まとめ・結び
本記事では、ぴあIT共創開発部が推進するAI駆動開発のリアルをお届けしました。
少数精鋭のチームでエンタメの最前線を支えるため、私たちは常に最新技術に挑戦する圧倒的なスピード感と、AI時代だからこそより求められる高い学習意欲を核に開発を進めています。
AIを恐れるのではなく「相棒」として迎え入れ、エンジニア自身が成長し続ける。そんな新しい開発の未来に興味を持たれた方、ぜひ私たちと一緒に、感動を生み出すエンタメの舞台裏を支えませんか?
未来の仲間への熱いメッセージ
私自身、半年前までは前職の現場でAIが全くかかわらない開発を進めていましたが、ぴあに入って先進的なAI駆動開発に触れ、驚嘆とともに大きな刺激を受けています。
ぴあのIT共創開発部には、自発的に「開発でやってみたいこと」「学習してみたいこと」などを後押ししてくれる風土があります(勉強会の開催など)。
新しいことがしてみたい、そして何よりエンタメ業界に貢献したいと考えているエンジニアにとっては、とても恵まれた環境です。 ぜひ私たちと一緒に、未来のエンタメ体験を創り出しましょう。ご応募をお待ちしています!