地域の未来を支える若者たちのキャリア教育と、地域の観光産業の人材不足──。一見異なる課題のようで、実は深くつながっています。観光業は地域の魅力を伝え、持続可能な経済を生み出す重要な産業。しかし、若者が将来の働き方にリアルなイメージを持てず、業界への関心が薄れている現状があります。
そんな中、Nazunaは、地域の中学生を受け入れて職業体験を実施。地域の教育機関と企業が連携し、若者の未来と地域の活力をつなぐ新しい試みを始めています。
中学校と観光宿泊業が手を組む理由
「子どもたちには“リアル”を体験してほしいんです」
そう語るのは、京都市立神川中学校でキャリア教育を担当する菊谷敏之先生。
いま、教育と観光業という一見交わらないように見える世界が、手を取り合おうとしています。
今回、キャリア教育の一環として行われた職場体験をきっかけに、中学生と観光宿泊業の現場が出会いました。この記事では、その背景や取り組みに込めた想いを、教育現場と企業それぞれの視点から深掘りしていきます。
コロナ世代が抱える“経験の空白”に向き合う
──まず、企業と学校が手を組む背景として、教育現場が今、どのような課題を抱えているのかを教えてください。
菊谷先生:
もともと僕自身がキャリア教育に関心があり、“本物に触れさせたい”という気持ちが強くあります。
特に今の中学生たちは「コロナ世代」です。小学2〜4年の間にコロナ禍での自粛生活を経験し、人間関係を築く大切な時期に、外の世界と接することができなかった。
だからこそ、彼らにとって人と人とのコミュニケーションの「質」が、我々の世代よりも圧倒的に乏しいという実感があるんです。
その不足を埋める手段として、”外に出て、リアルな人や仕事に触れる”ことは、今の教育現場にとって非常に重要な意味を持っています。
「義務教育だからこそ失敗できる」――キャリア教育の価値
──在学中に社会と接点を持つことには、どんな意義があるとお考えですか?
菊谷先生:
いきなり社会に出ると「仕事が合わない」「こんなはずじゃなかった」という“ミスマッチ”が起こりがちです。
でも、それって仕事が悪いんじゃなくて、“合ってなかった”だけ。だからこそ、「自分にとってのいい仕事・いい会社」を知るための経験が必要なんです。
その第一歩を義務教育の中で経験できるのは、すごく価値がある。失敗が経験としてカウントされる安全な環境ですから。
本気で働く大人に触れることで、「仕事=しんどい」だけではない、熱意ややりがいを感じてもらいたい。
今回のNazunaさんとの出会いは、まさにその意味でも大きなチャンスでした。
共鳴した「業界構造への違和感」
──観光業の立場から、今回の取り組みに参加された背景を教えてください。
Nazuna 渡邊:
実は僕、昔教育実習に行ったことがあって、中高の教員免許を持ってるんです。だから教育現場に対する関心はずっとありました。
一方で、観光宿泊業界も教育と同じように「上の世代の構造に課題を感じている業界」だと僕は思っていて。
業界の平均年齢は40歳超え。サービス残業が当たり前、離職率も高い――。この構造をなんとか変えたい、という思いがありました。業界に対するアンチテーゼ”になると感じたんです。
僕たちは「おせっかい」を企業理念に掲げていて、できることがあれば全力で手を差し伸べたいと思っています。
たとえその中に生産性がなかったとしても、“あのお兄さん、お姉さんに出会えてよかった”と思ってもらえる体験を提供したい。
それが、今回受け入れを決めた一番の理由です。
教室では教えられない“社会での役割”
──学校では教えきれない部分、職場体験だからこそ学べることとはどんな点でしょうか?
菊谷先生:
文科省の方針では「生きる力」を育む教育が求められています。
でも、現場レベルではどうしても高校進学というゴールに引っ張られ、“座学偏重”にならざるを得ないんです。
ただ、社会で求められる力はそれだけじゃない。
例えば体育祭や合唱コンクールのような“みんなで何かを作り上げる経験”の方が、むしろ社会に近い感覚に思えたりする。
社会に出ると、「自分の役割を果たし、価値を生み出す」ことが求められる。
その感覚を、教室では見えにくい個性と結びつけることができるのが、職場体験の醍醐味です。
“本気で働く大人”に出会うことの価値
菊谷先生:
やっぱり職場体験において一番大きいのは「人との出会い」ですね。
この世の中、簡単にお金は稼げません。簡単に倒産してしまうこの世の中で、本気で働いてる人には”必死さ”、そしてその”必死さ”の中には”面白味”や”充実感”がにじみ出てる。
それに触れることこそが、生徒たちにとって最もリアルな学びになると思っています。

中学生が外国のお客様を接客している様子
言葉の壁を越えて、お客様との温かなやりとりが生まれる瞬間に、現場が優しい空気に包まれました。
「子どもが来ることで、大人が初心を思い出す」
──逆に企業側として、受け入れたことでの学びや気づきはありましたか?
Nazuna 渡邊:
観光業って、外からは華やかに見えても、意外と閉じた業界なんですよ。同じスタッフとばかり顔を合わせて、社外の人と接する機会が少ない。
だからこそ、中学生という“全く知らない存在”が職場に入ると、すごくいい刺激になるんです。
「この子たちに、何をどう伝えればいいか」と自問する中で、自分自身が一社会人としての原点を思い出すきっかけにもなる。
大人になっていくと、どうしても「これぐらいは分かるだろう」という前提でコミュニケーションしてしまいがちです。言わなくても伝わるはず、察してくれるはず。そんなふうに、肝心な基本の部分をすっ飛ばして話を進めてしまう場面が増えてきます。
でも、中学生相手には、それが通じない。
むしろ「一から千くらい」丁寧に伝えなければ、全然伝わらないんです。
けれど実は、教育や指導の本質って、まさにそこにあるんじゃないかと思っています。
“自分が理解していること”を、“まったくわかっていない誰かに伝える”というプロセスにこそ、育成の原点がある。
大人も、初心を思い出す大切な瞬間です。
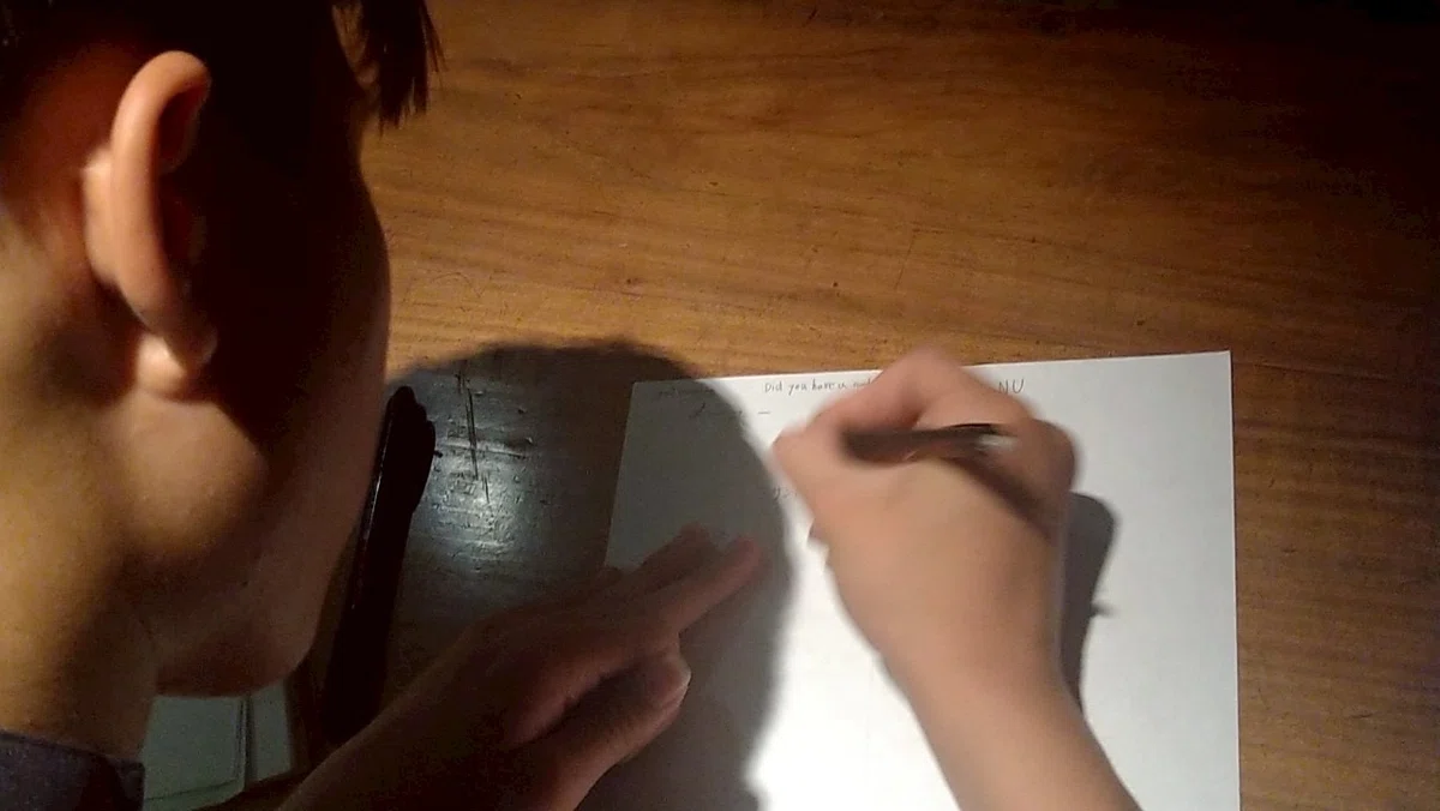
外国人のお客様宛てに英語で手紙を書いている様子
Nazunaの「おせっかい」精神に触れ、“誰かのためを思って行動する”ことの大切さを、自分の言葉で表現しようとする姿が印象的でした。
地域で未来を育てる、という選択肢
──最後に、この取り組みを今後どう生かしていきたいか、展望をお聞かせください。
菊谷先生:
今回の体験が、子どもたちにとって「社会の縮図」としての学校運営に活かされればと思っています。
部活動や生徒会といった学校内の活動も、「自分がどう価値を発揮できるか」という視点で取り組めるようになるといい。
また、自分の進路を選ぶときにも「どんな高校に行けるか」ではなく、「どんな大人になりたいか」から逆算して進路を選ぶ。そんな未来の見方ができるようになってくれたら嬉しいですね。
Nazuna 渡邊:
宿泊業は、学歴よりも“人間力”が活きる仕事。高卒で活躍する人もたくさんいます。
そういう意味でも、「学歴がすべてではない」と伝えることができたら、僕らが果たす意味は大きい。
そして、この体験を通じて「英語が楽しい」「留学してみたい」みたいな小さな変化が芽生えてくれたら、それだけでも十分嬉しい。
“自分の未来にワクワクできる”きっかけを、この職場体験が与えられたら本望です。


/assets/images/19923091/original/3fedfb48-a8fd-4aa1-a78f-c8d7180105f3?1733840430)
/assets/images/19923091/original/3fedfb48-a8fd-4aa1-a78f-c8d7180105f3?1733840430)

