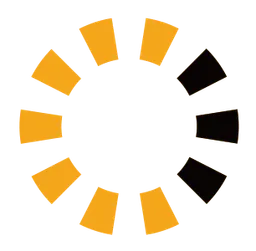「医療と介護の現場で、さまざまな困難を乗り越えながら22年間のキャリアを積み上げてきました」そう語るのは、長年にわたり医療・介護の現場で活躍した後、2025年8月に「ケアチーム」でスーパーバイザー(SV)として就任し、新たなキャリアを築いている吉沢氏。
今回は、吉沢氏が見てきた介護業界の課題に加え、SVとしてそれらの課題解決に貢献するための組織改革について深掘りしていきます。
目次
22年のキャリアが語る、看護師としての歩み:キャリア変遷
-これまでのご経歴・キャリアについてお聞かせください。
現場で感じた限界 ― 介護業界が抱える人手不足と業務過多
-長年現場に立たれる中で、リアルに感じた介護業界の課題は何でしたか。
「仕事を優先して家庭を犠牲にしていいのか」
-働き方を見つめ直したきっかけと、休職の経緯についてお聞かせください。
請求業務の「属人化」が引き起こすリスク
-訪問看護の管理者としてレセプトを実際に担当されて、「ケアチーム」のメリットはなんだと思いますか。
「現場感のある支援」と働きやすいチームづくり
-SVの視点から見た、「ケアチーム」が乗り越えるべき属人化のリスクとは?
「ケアチーム」が介護業界の希望の光に!
-最後に読者へのメッセージをお願いします。
22年のキャリアが語る、看護師としての歩み:キャリア変遷
-これまでのご経歴・キャリアについてお聞かせください。
私が看護業界へ足を踏み入れたのは、高校時代にさかのぼります。母子家庭だったため進学は難しいと感じていながらも進学を熱望し、最終的に選んだのは看護師の専門学校でした。きっかけは、友達に誘われて参加した病院でのボランティア活動で、男性看護師の存在を知ったことです。調べてみると看護師学校は学費が比較的安く、通学しながら働けるということが分かり、「これならアリだ!」と思い、看護師になる道を選びました。
看護師歴は22年になります。手術室・病棟勤務を経て、集中ケア認定看護師としてICUや循環器の急性期医療に15年間従事しました。その後は訪問看護に7年間携わり、その内4年間は管理者としてステーション運営を担いました。またデイサービス等、複数の介護事業を行う会社の取締役や社長も経験し、医療・介護の両面を幅広く見てきました。
私がこれまでに培ってきた医療・介護でのキャリアは、急性期から在宅での終末期まで多岐にわたります。認定看護師の資格を取得してからは、看護師としての仕事の合間にスタッフ研修のために、多い時は年間で20回もの勉強会も行っていました。中でも、「集中ケア認定看護師」として得た専門知識と経験は、その後の訪問看護での管理者業務にも大きく活かされました。
現場で感じた限界 ― 介護業界が抱える人手不足と業務過多
-長年現場に立たれる中で、リアルに感じた介護業界の課題は何でしたか。
ステーションで働き始めてからは夜勤はなくなったものの、看護師の業務に加えて管理者としても責任も重なり、ハードな日々が続いていました。それでも、患者さんやご利用者の苦痛が少しでも和らぎ、安心につながるケアが提供できればと、この仕事にやりがいを感じていました。しかし、長年現場に立つ中で、私は介護業界が抱える深刻な課題に目の当たりにしました。
在宅では、利用者対応から記録、事務処理まで1人のスタッフに重くのしかかる構造があります。現場のスタッフが「やるべきことが分かっているのに、こうしたらもっといいケアができるのに……」という思いを抱えながらも、改善のための時間や人が足りず、限界を感じる場面が少なくありません。
特に訪問看護では人材不足が顕著です。「医療経験がないと難しいのでは?」「1対1で利用者と向き合うのはプレッシャーが大きい」といったイメージが、人材確保を難しくしている要因の1つだと感じています。私のステーションには専任の事務員がいなかったため、書類処理が業務全体の2〜3割を占め、現場でのケアに集中できない状況が生まれていました。
人手不足に加え、複雑な運用ルールに基づく煩雑な業務が重なり、現場のスタッフが疲弊していく様子を何度も目にしてきました。
「仕事を優先して家庭を犠牲にしていいのか」
-働き方を見つめ直したきっかけと、休職の経緯についてお聞かせください。
多忙を極めていた頃、私自身が大きな転機を迎えました。2024年9月に肺炎を患い、2か月間の休職を余儀なくされたのです。
入院は避けられたものの、管理者として、そして現場で働く看護師としても走り続ける中で体調がなかなか回復せず、自分自身がとても疲弊していることに気づきました。さらに妻も助産師として夜勤をこなしており、3人の娘の送迎や日々の生活を支える時間が私たち夫婦には明らかに足りていませんでした。
そんな中で私が下した決断が、「休職」でした。
「仕事を優先して家庭を犠牲にしていいのか…」そう立ち止まって考えたことが、休職を決める大きなきっかけでした。妻からも「働き方は1つではない」「家族も自分も大切にできる選択肢はある」と説得されたことで価値観が変わりました。その時、妻が私の専門性や経験を認め、支えてくれたことは、今振り返っても大きな励みとなっています。
この期間を通じて、自身の働き方や価値観を深く見つめ直すことができました。
そして、家族との時間を大切にできる職場を模索する中で、ケアチームでのスーパーバイザー(SV)という新たな働き方に出会いました。
請求業務の「属人化」が引き起こすリスク
-訪問看護の管理者としてレセプトを実際に担当されて、「ケアチーム」のメリットはなんだと思いますか。
訪問看護の管理者として請求業務を担当しましたが、もともと現場で看護師として働いていたので、当初は制度への関心も知識もありませんでした。訪問看護における診療報酬制度は複雑で、高度な知識が求められます。小さなミスが経営に大きな影響を及ぼすこともあるため、毎月非常にプレッシャーを感じていました。
多くのステーションで請求業務が特定の事務員に集中しがちで、その人が休職・退職した場合に業務が滞るリスクがあります。私自身も、「誰にも頼めない」「自分がやらなければ」と1人で請求業務を抱え込み、心身ともに負担を感じていた時期がありました。
だからこそ、「ケアチーム」の請求代行サービスのような仕組みは、現場の管理者や現場スタッフの負担軽減につながり、本来注力すべき業務に安心して取り組める環境づくりに貢献できると考えています。
「現場感のある支援」と働きやすいチームづくり
-SVの視点から見た、「ケアチーム」が乗り越えるべき属人化のリスクとは?
SVとして働く今、かつての自分が直面した課題を、客観的な立場から支援できるようになりました。私にできるのは、医療保険制度や介護保険といった制度面にとどまらず、急性期から終末期まで幅広く経験してきたからこそ提供できる『現場感のある支援』です。
レセプト業務においては、今もなお「請求業務が特定の人に集中してしまう」属人化の傾向が多くのステーションで見られます。訪問看護では、制度や算定ルールの複雑さから、情報共有や引き継ぎが難しく、属人化がより顕著になりがちです。これは、ステーションに限らず、私たち「ケアチーム」においても起こり得るリスクです。
専門性の高い業務においては、担当者の休職・退職が即、業務停滞につながる可能性があります。だからこそ、安定的な人員体制と円滑なチームワークが不可欠です。
SVである私に求められているのは、「特定の人に業務が集中しない」「チームで支えあう」体制を整えることです。どうしたらスタッフの皆さんが働きやすくなるかを考え、「ここで長く働きたい」と思える組織を目指しています。
チームとして足並みを揃え、サービス品質の均一化と向上を目指すことは、そのまま顧客であるステーションの属人化解消にもつながります。「ケアチーム」のサービスが、ステーションの持続可能な組織づくりに貢献できることを、心から願っています。
「ケアチーム」が介護業界の希望の光に!
-最後に読者へのメッセージをお願いします。
介護・医療の仕事は確かに大変ですが、それ以上に大きなやりがいがあります。
ただし、これまでのやり方を見直さなければ、現場の方々が過剰な負担を背負い続け、事業としての継続や成長も難しくなってしまいます。「ケアチーム」が提供するレセプト支援は、介護現場で日々奮闘している方々に大きな希望を届けるものだと信じています。
私自身が働き方を見直したことで、家族との時間を守りつつ、仕事でも力を発揮できる環境に出会えました。介護業界の外にいる方でも、これまでの経験を活かして働き方を変え、「介護業界に新たな風を吹き込みたい」「日本の未来を、笑顔あふれる明るいものにしたい」といった私たちの想いに共感いただける方がいらっしゃいましたら、ぜひカジュアル面談でお話ししましょう!

/assets/images/20265731/original/43a710f0-a656-4c2f-b093-5d6d973f11d3?1737742032)