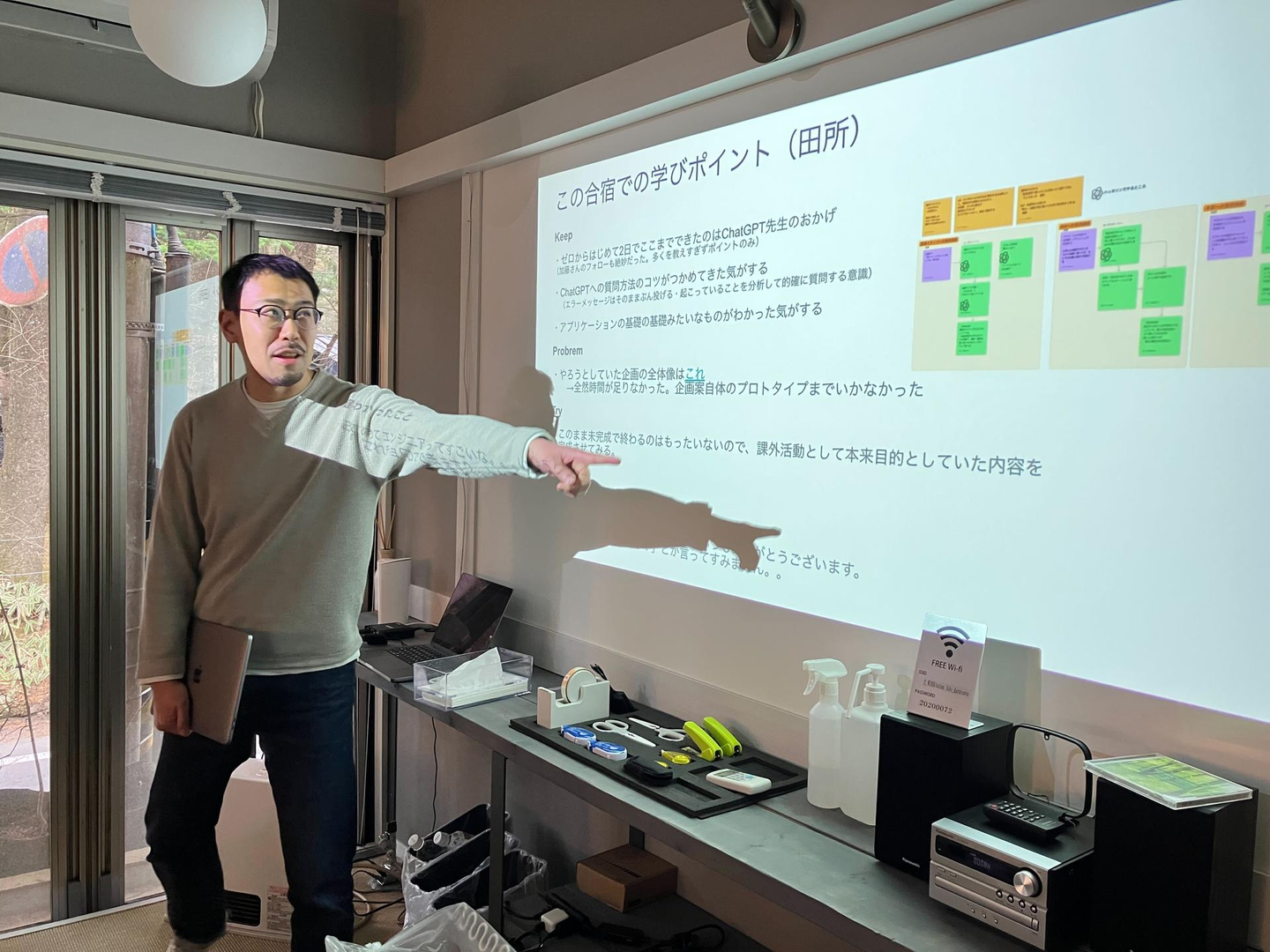ABILI Clip(ClipLine)の機能 |
ABILI Clip(ClipLine)にはクリップ(短尺動画)とToDoという二つの主要機能・特長があります。クリップでは動画の特長を活かし、言葉やOJTだけでは伝えきれなかったノウハウや技術をわかりやすく・正確に伝えることができます。ToDoの内容・利用設定は目的、業務や施策に合わせて柔軟にコントロールできます。
https://service.clipline.com/clip/feature
ClipLineのサービスは、現場における人の動きや情報の流れをテクノロジーで支えるものです。しかし、実際のリアルな声や感覚を正確に捉え、「現場で活きる」プロダクトにするのは簡単なことではありません。
今回は、開発とCS、営業など社内のハブとなって動き、時には現場へも足を運び、プロダクトと現場をつなぐ役割を担うプロダクトマネージャーの田所さんのインタビューです。地に足のついた開発業務について語っていただきました。
田所 祥勇 Akio Tadokoro
アプリケーション開発部 プロダクトマネージャー
中堅SIerでコンシューマ向けPCソフト企画を手掛け、社内コミュニケーションSaaSのスタートアップでプロダクトマネジメントを経験。
ClipLineではABILI Clipのプロダクトマネージャーを務める。
――まず業務内容について教えていただけますか?
私は現在、「ABILI Clip」のプロダクトマネージャーとして、プロダクトマネジメント全般を担当しています。主には、本部と店舗間の情報共有を行う「業務連絡機能」の改善や運用支援、既存クライアントからのVOC(お客様の声)を基にした改善対応などです。
また、複数ある開発チームのリリース計画を立てたり周知する「リリースマネージャー」のような役割も担っています。
――リリース情報の社内共有については、どういった形で行っているのですか?
各部署の定例ミーティングに私が参加して周知しています。私が参加している主な会議体としては、週次でチーム間の連携や少し先の開発計画について話し合う「プロダクトマネージャーミーティング」、プロダクトの方針やクライアントの声を部署横断で共有する「プロダクト成長会議」などがあります。それぞれの部署で話していることがサイロ化しないように、集約して全体共有に努めています。
様々な会議や情報共有の場に出席。こちらは開発部合宿でのプレゼンテーション
――リリース情報を共有するだけでなく、部署横断の情報のハブになっているのですね。以前からそういった立ち位置なのですか。
はい。もう3年前になりますが、入社当初感じたことがあります。それは、部署ごとにそれぞれの業務に集中していて、他部署の取り組みが少し見えづらいということでした。特に開発部門から社内への情報発信がまだ十分とはいえない部分もあるのかなと感じました。
だから開発と他部署の距離を縮めたいと考え、まずはCS(カスタマーサクセス)のメンバーと個別にコミュニケーションをするようにして、会議に参加する機会を作ったりして、交流機会を増やしていきました。そうやって部署間の距離が3年かけて少しずつ変わってきた実感があります。
――そうした情報共有の積み重ねが、プロダクト改善にもつながっているのでしょうか。
そう思っています。ABILI Clipは元々教育用途からスタートした経緯があり、情報共有や業務支援の面では後追いで機能が追加されてきました。その中で、使いやすさや役立ち度を高めるには、現場視点が欠かせません。なので、お客様の声を改善につなげることが私の重要な役割だと思っています。たとえば「業務連絡機能」も、お客様やCSの声を反映して改善してきた部分です。
<業務連絡機能とは>
店舗・拠点単位での業務指示や連絡を本部から発信することができる機能。ただ発信するだけでなく、エリアや拠点単位での情報の出し分けやタスクの設定も可能で、着実なマネジメントと実行徹底をご支援します。
詳しくは下記の機能ページをご参照ください。
業務連絡に限らず、何か機能開発をする時には、実際の業務プロセスを把握して判断することを徹底しています。お客様に「あの機能が欲しい」って言われた時に裏側にある課題は何だろうと。前後にどういう業務があって、その機能で何が解決されるのかを把握しにいくっていうことは、しっかりやっていると思います。 CSの皆さんにご協力いただいて、直接お客様にお話を聞きに行くこともあります。
あと、個人の動きとしては、現場の人達の話を聞く機会を増やすことを心がけています。商談に同席したり、店舗訪問したりシフトインさせてもらったりというのを含めて、現場感を把握したいと思っています。はっきりとした要望は上がってこないけど、現場には確かにこんな課題があるんだという空気感もつかんでいきたいと思っているし、そういうことができるのはこの会社のいいところですね。
――実際に現場に行かれることもあるんですね。
はい。クライアントの店舗でシフトインさせてもらったことがあるんですが、そのときに「オペレーションの合間にPCやタブレットを見る時間なんてない」ということをはっきり感じました。当たり前のことのようですが、現場に行かないとわからないことです。
社内では「困ったらABILIで調べて」と言いがちですが、現場ではそう簡単にいかないということが改めてわかりました。あと、見逃しがちなのが、ABILI Clipを使う端末には他の業務アプリも入ってることが多いということ。一台の端末が色々な用途で使われているので、いつでもABILI Clipを使えるとは限らないんです。
こうして現場に行かないと分からない部分は凄くあるなと思っていて、その辺を知らないで開発をすると、使ってもらえない機能を作ることになってしまいますね。
――今後の展望について教えてください。
現場向けのものを作ってる以上、これからも現場に近い場所に出て行きたいと思っています。時には展示会で来場者とお話するようなことも含め、現場の課題を掴み、社内で共有することにもっと注力していきたいと思っています。 ただ、全員がそういう場に行けるわけでもないので、共有の仕方を仕組化すべきだと思ってます。
あとは、教育用途以外にマネジメント観点でもさらに強化していきたいと思ってます。サービスラインナップの中でも後発のABILI Board、Voice、Careerは割とマネジメント起点で作られているところがあります。
でも一番初めに立ち上がったClipは先ほども言った通り、教育起点なんですよ。だから今の機能を整理して、足りないものは足すし、ABILI全体で多拠点マネジメントを支援するサービスとして確立させていくことが大事かなと思っています。
――特に注力点があるとしたらどんなところでしょうか。
ミドル層への対応でしょうか。ABILI Clipは本部と現場をダイレクトに繋ぐというコンセプトになっていますが、間に位置するミドルマネジャーの人たちも使い勝手がよくないといけないと思っています。人手不足の影響などもあり、組織を大きく変えるお客様が増えてきており、ミドルマネジャーの働き方を変えたり、管轄店舗の数を増やせないかという話は頻繁にありますので、それに対応できるプロダクトでなければいけないと思います。
当社には幸い、店長出身者などのドメインエキスパートが多数いますので、相談にのってもらいながら進めてるところですね。
――田所さん自身はどんな事業共感があってClipLineに入社されたんでしょうか。
大学時代にリユースショップで4年間アルバイトをしていたんです。接客の他に仕入れや値付けなど、ある程度自由度がありました。その時に、スタッフが判断できる材料をもらって自主的に動く働き方って楽しいよなって思っていました。前職ITツールベンダーにいた時も小売や飲食系のお客様が多かったので、本部から現場に対して、情報や理念などをちゃんと伝えることの重要性を認識していました。なので、そういったことがClipLineに入社する動機になったと思います。
――最後に、今後入社される方に期待することを教えてください。
そうですね、少人数のチームで動いている会社なので、特定の分野に特化するというよりは、ジェネラリストタイプで、いろいろなことに興味を持ち、他部署と積極的に関わっていける方が向いていると思います。
プロダクトマネージャーについて言えば、技術的なバックグラウンドをお持ちの方がいればもちろん心強いですし、開発と細かいやりとりを進める上でも助かる場面は多いと思います。
でも一番大事なのは、プロダクトやお客様の課題にしっかり向き合いたいという気持ちです。そこがあれば、専門分野やキャリアにとらわれず、どんな方でも一緒に挑戦していけると思っています。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。
懇親会にて、CSチームのメンバーと
最後までお読みいただきありがとうございました!ClipLineでは一緒に働くメンバーを募集しています。採用情報はこちらからご覧いただけます。
■開発チームにはこんなメンバーもいます。
■サービス業の支援を通して社会貢献したい方、お待ちしています。