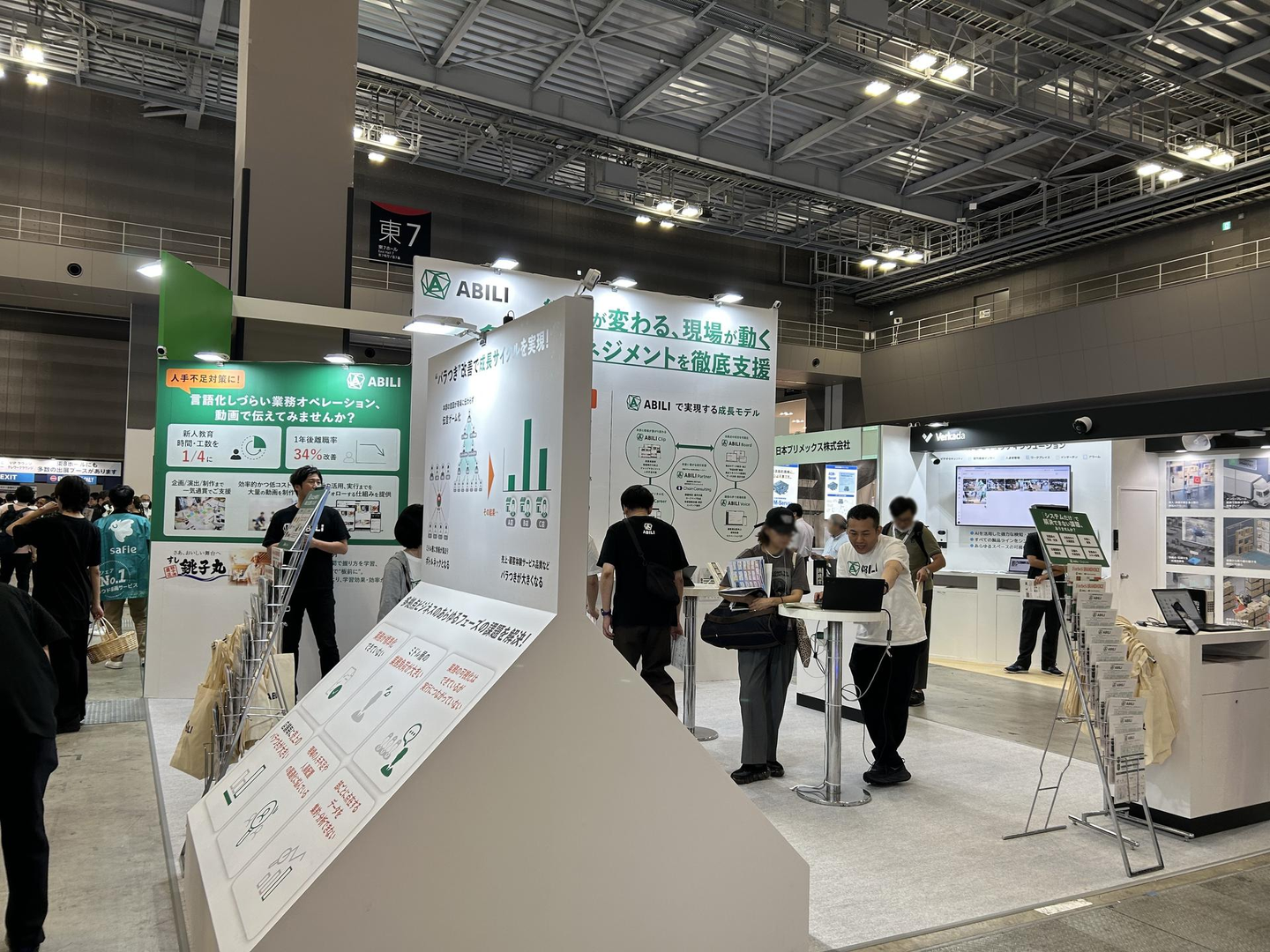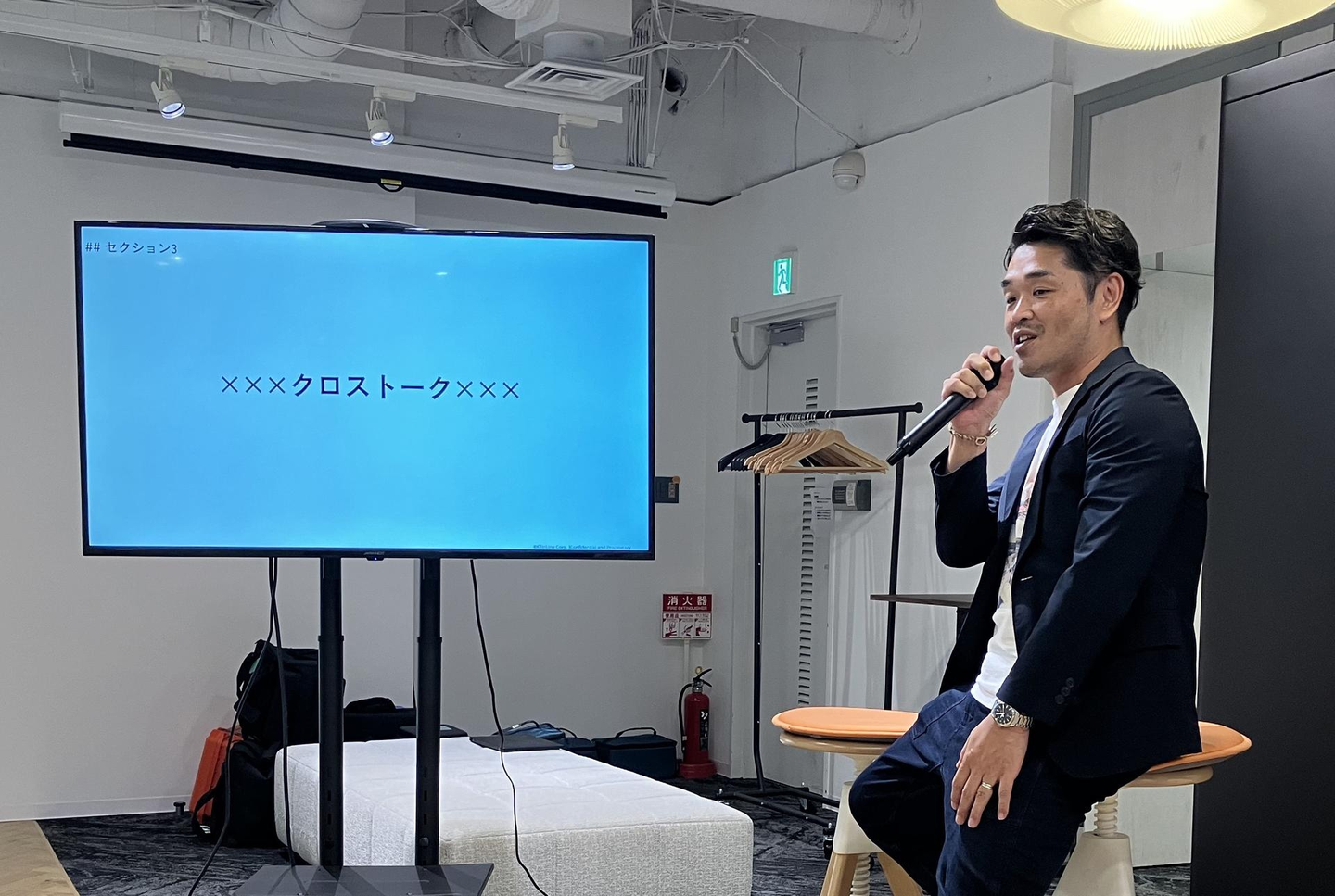「多店舗×IT」の課題解決にフォーカスしたセミナーを開催しました! | ClipLine's blog
当社は多拠点展開ビジネスを対象にサービス提供を行っています。このたび、同じように多拠点・多店舗展開企業の課題に向き合い支援を行っているIT企業と合同で「多店舗×ITの最適解を考える」オンラインセ...
https://www.wantedly.com/companies/clipline/post_articles/869689
これまでは主に部門単独で進めてきたClipLine社のマーケティング。しかし最近、その枠を超え、部門横断で力を合わせる新しい挑戦が始まりました。その現場を知るために、今回はマーケティング部の清水さん、斎藤さんの2人に話を聞きました。
清水 俊亮 Toshiaki Shimizu (写真左)
マーケティング部長代理
インサイドセールス部長/アライアンス担当責任者
外資系および国内企業でフィールドセールス・インサイドセールスに約20年携わる。2022年ClipLine入社。インサイドセールスの再構築を経て、アライアンス事業も手掛ける。2025年からマーケティング部門の責任者も兼務。
斉藤 健善 Kenzen Saito (写真右)
マーケティング部 ディレクター
コールセンターシステムのSI事業部で法人営業とプリセールスを経験した後、ホリゾンタルSaaS企業でマーケティングに従事。2025年3月ClipLine入社。
ーーまずはおふたりの役割を教えてください。
清水:私は部長代理として、戦略企画やコスト管理など全体の舵取りを担当しています。戦略や施策を実行するのは、主に斉藤さんです。 斉藤:私は日々の実務を中心に担当しています。マーケティング部には私のほかにパートナーの方が3名、さらに業務委託のアドバイザーが加わる体制になっています。カバーしている領域は幅広いですが、主にイベントマーケティング、メール施策、Web施策改善といった分野です。 企画や立案は清水さんと一緒に進めながら、実際の運用部分は基本的に私が回しています。具体的な施策としては、自社主催イベント、経営者向けラウンドテーブル、展示会出展などが直近の中心施策です。 清水:企画から運用まで二人で連携しながら進める二人三脚の体制ですね。幅広いチャネルを活用しながら、限られたリソースをどう最大限活かすか、そこが私たちの特徴だと思います。
ーー現在のマーケティング活動における課題はどんなことでしょうか?
斉藤:これまではできるだけ多くの方にサービスを知っていただいて接点を作ることを重視してきましたが、最近では私たちの価値をより深く届けられる方との出会いに重点を置くようになっています。
そのため、幅広い施策を並行して進めるよりも、一つひとつの取り組みを丁寧に設計し、より良い体験を提供することを意識しています。ただ今の体制では、全てを高い品質で網羅的にやるのは難しい。だからこそ、一つ一つの施策の成果を最大化するだけでなく、既存のアセットを連動させて効果を高める必要があります。その解決策として、部門横断のマーケティングチームを発足し、効率よくアプローチすることを目指しています。
清水:今期の戦略的な方向性は「組織的マーケティング」です。従来はマーケティング部が単独で仕組み作りや手法に取り組んできましたが、新たな出会いを広げるだけでなく、既存顧客とも、より深く長くお付き合いいただける関係づくりが重要です。そのため、部門を巻き込みながらマーケ活動を行える体制を進めています。
特に斉藤さんの役割は大きいですよ。実務を担うマーケターとして、ほぼ一人で幅広い業務を回しつつ、パートナーや業務委託の方々の協力も得て成果を出している。イベントのようなマスマーケティング的な施策からナレッジの仕組み化まで、自ら推進しています。
斉藤:過去のデータを分析し、新しい施策と比較できるように整理したり、得た経験を仕組みとして残すことにも挑戦しています。幅広い領域に関わるのは簡単ではありませんが、その一つひとつが確かなスキルとして身についている実感があります。
清水:そうですね。マーケターとしてキャリアを積みたい人にとって、ここでの経験は大きな財産になると思います。負荷はもちろんそれなりにかかるけれど、チームでしっかりサポートしますし、挑戦を「学び」に変えていける環境です。
産業DX展の様子。客足には波があったが目標はほぼ達成できた
ーーこれまでの成果について、いくつか紹介してください。
斉藤:イベントによってはしっかり成功パターンが確立してきているものがあります。例えば「産業DX展」では初出展ながら商談化目標の約9割を達成できました。
一方で、Webまわりはこれからさらに伸ばしていける分野だと感じています。データ分析によりコンバージョンや離脱率など色々な課題が見えてきたので、より多くの方にサービスの魅力を伝えられるよう、サイトの見直しや新しいツールの導入を進めています。
清水:オフライン施策ではいったん成果を出せてきているので、オンラインの課題を片付けようとしているところですね。強みと弱みをしっかり分析しながら、次の一手を考えている段階ですね。
斉藤:はい。両方を比べることで、自分たちの得意な領域と改善すべき領域がはっきりしてきました。そこをどう伸ばしていくかが今後のポイントですね。
ーーふだん意識していること、工夫していることはありますか?
斉藤:全体像を見失わないようにしています。施策を単発で終わらせず、その後のナーチャリングや他の施策とのつながりを意識するようにしているんです。例えば展示会で獲得したリードを次の接点につなげるためにどうコンテンツを展開していくか、最初から考えるようにしています。直近ではお客さんの反響が良かった内容をコンテンツ化して、ウェビナーとして企画しているところです。
清水:ラウンドテーブルで好評だったテーマをウェビナーに展開したり、既存顧客向けにCS(カスタマーサクセス)で実施した施策をマーケにも活用したり、成果を横展開する仕組みづくりをしています。施策の全体像を把握しながら、マーケティングが主体で動けるようにしているんです。斉藤さんが単発で終わらせない、成果を次につなげるという視点があるからこそ、リード獲得からナーチャリングまでを一貫して設計できています。
斉藤:ABILIはSaaSですが、ただプロダクトを提供するのではなく、「伴走支援」「コンサル要素」が強い点が特徴です。マーケティング的には少し難しいところがあるので、色々な工夫をする中で、部門を超えた協力を得る必要があり、今のような形になっているとも言えます。
清水:属人的に近い形でお客様に伴走しますからね。一般的なSaaSとは違い、マンパワーも使いながら時にはアナログ的な支援もします。サービスのバリエーションも増えてきているので、マーケティングは少し複雑になりますが、工夫のしがいがあって面白さを感じるところです。
社内セッション中の清水
ーー新しくジョインするメンバーの人物像として、どんな方が活躍できそうでしょうか。
斉藤:スペシャリストよりもゼネラリスト志向の方が向いていると思います。全体最適を意識して、社内外を巻き込みながら形にできる人が理想ですね。あとは、個人の専門性だけではなく、組織を動かすという視点で挑戦を楽しめる人がいいのではないでしょうか。
清水:「いろいろなことに挑戦したい」という方が合っていると思います。総合的に経験を積みたいマーケターにとっては、大きな成長機会になるはずです。ぜひ一緒にABILIを盛り上げていきましょう!
部署横断で展示会に参加
最後までお読みいただきありがとうございました!
■マーケティング施策についてはこちらでもご紹介しています
■採用情報はこちら