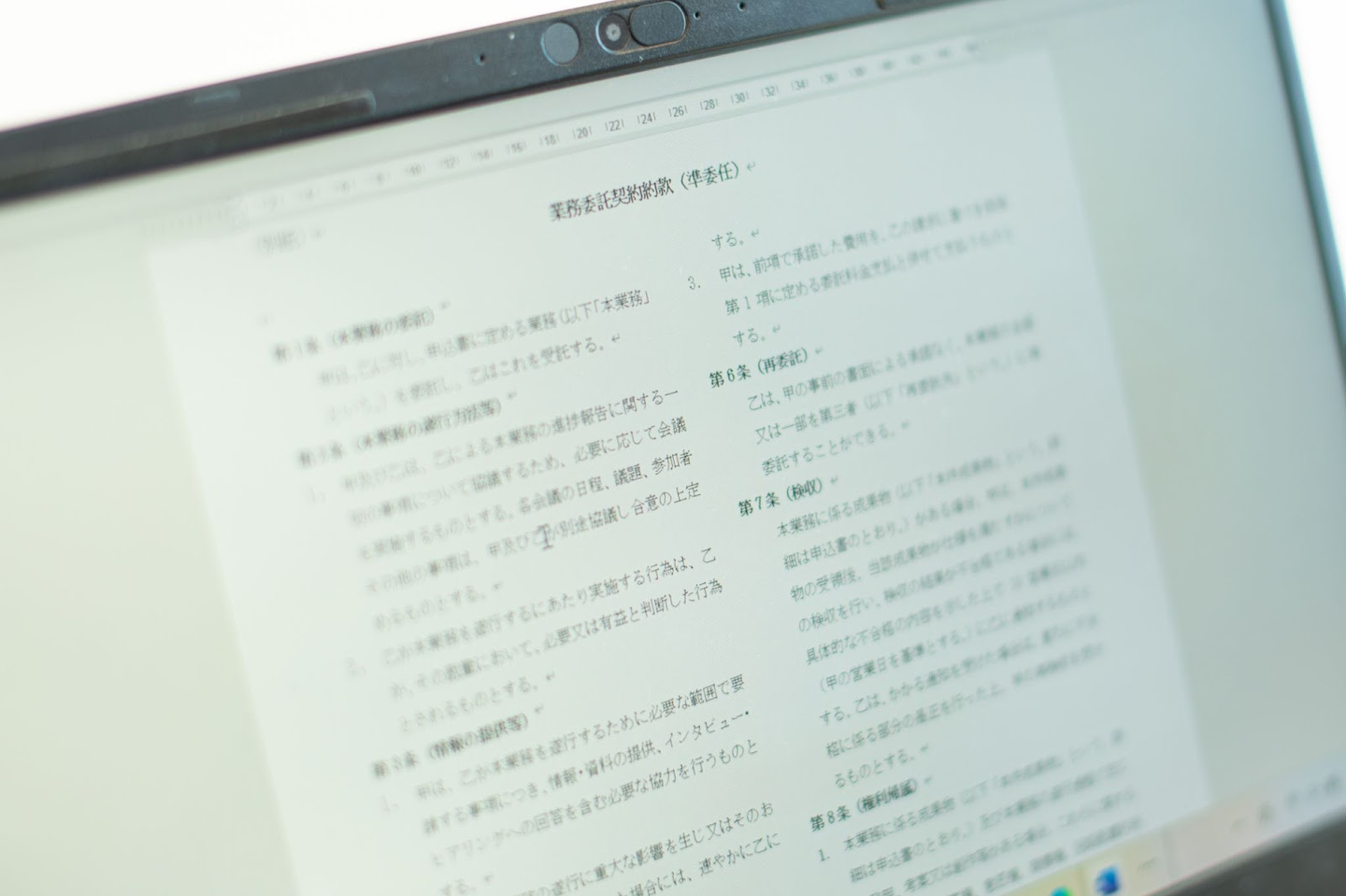- PMM
- Web Engineer
- エンタープライズ
- Other occupations (44)
- Development
- Business
- Other
企業の法務部は、契約書の作成・審査、社内規定の整備、コンプライアンス管理など、法的観点から事業で起こりうるリスクを除外する、「守り」のミッションを担っているケースが大半です。しかしアンドパッドの法務部が手掛けるのは、“守り”だけにとどまらず“攻め”の法務でもあります。ときには事業部の一員として事業推進やプロジェクト推進に直接関与することも求められます。今回は経営推進本部長である岡本と、法務部マネージャー 木下に、法務部が手掛ける業務内容や、アンドパッドの法務部で働く醍醐味について語ってもらいました。
岡本 杏莉 上級執行役員 経営推進本部長 (写真右)
西村あさひ法律事務所に入所し国内・クロスボーダーのM&A/Corporate 案件を担当。2015年3月に株式会社メルカリに入社。日本及び米国の法務を担当。2021年2月に株式会社アンドパッドに参画。2023年上級執行役員、2024年 経営推進本部長に就任。
法務部マネジャー 木下 圭一 (写真左)
大学卒業後、IT・外食・保育系の企業で法務を担当。様々な事業領域で、ビジネス法務を中心に、新規事業支援、組織再編、IPO準備などに従事。経営学修士(MBA)修了。アンドパッドに2022年7月入社。2025年6月現在、法務部マネジャーを務める。
成長スピードを緩めないための法務とは
――まず、現在アンドパッドが迎えているフェーズと、法務部での採用を強化している背景を教えてください。
岡本:アンドパッドは約3年前に大型の資金調達を行い、スタートアップとしては一定成熟したようなイメージを持たれているかもしれません。社員の規模は連結で800名を超え、グループ会社も増えている状況です。このように規模は拡大していますが、これからも成長スピードを緩めることなく、今後も継続的な成長を目指していく方針です。
その中で法務部では現在、これまでになかった多岐にわたる業務が発生しています。その理由は3点あります。1点目が、ビジネス領域の拡大です。現在当社では大手エンタープライズのお客さまが増え、個々に特殊な契約を締結する必要が増加しています。というのも、基本的にアンドパッドのプロダクトをご利用いただく際の契約は利用規約への承諾によりクイックにお申込みできる仕組みになっていますが、大手エンタープライズのお客さまの場合、プロダクトのご利用だけでなく、ニーズに合わせた機能の開発や共同開発、コンサルティングなど、プラスアルファのサービス提供が発生するケースもあり、別途契約を締結する必要が出てくる場合も増えると考えられるためです。
2点目が、新規事業の拡大です。アンドパッドは建設・建築業界に特化したSaaSを展開している企業です。しかし、私たちは建設・建築業を主軸とする企業へのSaaSの提供のみならず、建設・建築業態に関わる新規事業や新規サービスの展開も積極的に行っています。「ANDPAD」という施工管理サービスをベースにしながらも、「建設・建築業界の課題解決のために、あらゆる方向から挑む」という姿勢で、新プロダクトやBPO、コンサルティングサービスなど、新しいサービスや事業の検討が次から次へと会社の中で立ち上がっています。新規事業には複雑性もあり、法的検討事項が必要な場合も多くなっています。
3点目が、グループ会社の増加です。当社では去年初めてのM&Aを実施し、株式会社コンベックスにグループジョインいただきました。今後も積極的にM&Aを実施していきたいと考えています。さらに海外の子会社もあるため、法務としてカバーすべきPMI(Post Merger Integration)関連業務も増えています。グループ会社の中には、データ活用やAIといった領域の事業を手掛ける企業もあり、新しい分野の法的検討も必要となっています。こういった観点から、会社としても法務部としても、面白いフェーズを迎えていることは間違いありません。
――法的見解が問われる場面が増えてくるフェーズに入ったわけですね。そういった中で法務部が掲げるミッションや、経営陣から期待されていることとは何でしょうか?
木下:アンドパッドの法務部は、法的見解で会社を守るだけでなく、事業部の一員という立ち位置で、事業部を伴走していく姿勢が求められます。リスクを提示するだけでなく、リスクヘッジした上で、事業の成長スピードを保ちながらいかに推進できるか。その期待に応えられるように法務部としてどのように行動すべきかを常に考えながら、業務に取り組んでいます。
――事業部の一員とはどういったことでしょうか。
木下:ときには新事業における法的論点や相談への回答だけでなく、どのようなオペレーションを組むべきかまで一緒に考えることもあります。ある新規事業の立ち上げでは、定期的なミーティング、オフサイトミーティングへも参加し、貴重な経験をさせていただきました。
私はこれまで他社で、守りの立場で事業管理・監督する業務を中心に手掛けてきましたが、アンドパッドではそこから一歩飛び出した業務に携わることができています。事業を成長させるサポートができている、という実感が持てるのはアンドパッドならではだと思います。
自分で道筋を見つけながら進めていく面白さ
――続いて、詳しい業務内容について伺います。新規事業に関連する法務業務とはどのようなものですか?
木下:各事業部は、業界の新しい課題を解決するための手段として新たな事業スキームを立案します。その際、事業責任者や担当者から、事業を行う上での法規制、取るべき許認可の有無などの相談を受けます。事業開始日を踏まえ、法務としてどのような確認が必要か、どのようなスケジュールを組んで進めていくかを、事業部に提案していく必要があります。このような業務は、特に大企業の法務部などでは関われる機会も限定されると思いますし、自分でリードできるのは非常に面白いものです。
さらに、新規事業は、これまで提供してきた方法とは異なる視点で建設・建築業界における課題を解決していきます。よって、新規事業の大半は未知の領域です。経験のない中で、道筋を見つけながら進めていく手応えは何度味わっても面白いですし、刺激に溢れています。建設・建築業界の課題はまだまだ山積している中で、新規事業や新しいプロダクト・サービスに伴走して関わりながら、それらをひも解いていく。その実感は、やりがいでもありアンドパッドならではの面白さでもあります。
――社会問題を解決していく手応えも実感できる環境なんですね。法務部においても、建設・建築業界における課題解決に貢献している実感が味わえるんですね。
木下:恐らく、一般的には事業部から法務へ相談を受ける場合「この法規制について調べてほしい」「リスクについて調べてほしい」といった“点”での相談が来るケースが多いのではないでしょうか。「自分の回答した内容は、どのように事業と関係しているのか?」といったところまでは追うことができにくい。しかし当社法務部は、経営陣との距離が近く、本部長の岡本さんや取締役CFOの荻野さんと気軽に相談もでき、経営の目線でどのような事業が動いているのかを共有いただけるので、点が線につながり、しっかり理解しながら進められることも背景にあると思います。
――なるほど。さきほど、グループジョインのお話しがありましたが、木下さんはどのような業務を担っているのでしょうか?
木下:私がメインで携わっているのは、グループ会社の契約審査をはじめ、ガバナンスという観点から見た規程整備や職務権限の管理です。アンドパッドの体制と、グループジョインいただいた企業の体制を調整し、上手くバランスを取り、グループ会社が継続的に相談できる体制づくりを築くことが私のミッションです。
岡本:2024年に、住宅・不動産業界に特化したマーケティングオートメーションツール「Digima」を運営するコンベックス社にグループジョインいただき、木下さんはその法務PMIを担当しています。コンベックス社では、今まで法務の専任がいなかったので、アンドパッド側でいかに法務業務を受け入れるかについて、コンベックス社のメンバーとコミュニケーションを取りつつ進めてもらっています。グループジョイン後に重要なのは、いかにグループ全体として一緒に成長していくか。そういった重要なポジションを、木下さんに担っていただいています。
――PMI業務を行う上で、どのようなことを意識していますか?
岡本:グループジョインいただいた後に、会社の独立性は損なわないようにしながら、アンドパッドが持つ資産やノウハウをうまく活用して成長いただくため、グループジョイン企業には事業に集中できるような体制づくりに注力しています。そのため、相談できる関係性の構築、サポート体制などを築けるよう工夫しています。
業界の未来を担う実感が原動力に
――お話しを聞いていると、一般的な法務業務とは一線を画していますね。担当する業務が幅広い分、得られる体験や携わる意義も多いのではないかと想像しますが…。
木下:そうですね。仕事の面白みとしては、法務のポジションでありながらも、社会課題に挑んでいる実感を得られる点です。
岡本:日本では建設・建築業界の人手不足が深刻になっている今、社会資本の維持もままならなくなってきています。具体的には、自然災害の復興や道路、建物のメンテナンスに対応できない危機的状況に直面しています。さらに高齢化も進んでいる中で、建設・建築業界の担い手を急激に増やすという解決策は非現実的です。そうなると、やはりDXの力で効率化し、生産性を上げていくしかありません。建設・建築業界のDXに対する期待感は、年々高まっていると実感しています。業界からの期待を受けて、社会的な使命感、業界の未来の一端を担っている実感は仕事の原動力になっていると思います。
目の前のお客様のご苦労が、「ANDPAD」を使うことで解決されていく様子が日々シェアされるので、自分の会社の事業やサービスに誇りを持ちながら、日々の業務に携わることができます。そこはすごく恵まれている環境だと思います。
木下:また、得られるスキルや知見も広がりました。特にPMI業務は、プロジェクトを実行するにあたっての論点の洗い出しから、他管理部門へのタスク割り振りなどを担当することで、新たな経験につながったと思います。
さらに、自社やグループ会社の事業を通じて、SaaSの仕組みやAI技術について、深く理解できたのも新鮮でした。最新技術にまだ追いついていない法律、技術によって改正された法律などを学ぶ中で、この先どのような法律が生まれるのかといった予測をしながら事業の推進サポートができる。それは今まで経験したことのない新しいやり方だと思います。
――使命感を持って働きたい方、そして知的好奇心の高い方には最適な環境ですね。次に、法務部の風土について教えてください。
木下:これはアンドパッド全体に共通していると思いますが、一人ひとりが事業の主体者として行動できる風土が挙げられます。例えば、他の事業部に対して「ワークフローを改善したほうがより良くなるのでは?」と思っていても、いざ口を出してしまうと、関係がこじれてしまうケースがあるかもしれません。一方、アンドパッドの場合、「こういうプロセスにしたほうがいいのではないか?」と提案すると、そこからディスカッションが始まるように、意識が”コト”に向いています。自分の意見が会社の一メンバーとして尊重され、さらに社内のプロセスに落とし込まれていく。法務領域だけでなく、事業に関わる業務についても意見を求められますし、事業として出来上がっていく過程に関わることができるのは、本当に大きな経験かなと思います。
岡本:法務部の特徴としては、他のコーポレート部門とのつながりが深いということが挙げられます。法務だけ担当していればいいという発想はなく、管理やガバナンスという観点でワークフローをもう少し改善したほうがいいのではないか、支払いや請求のフローをスムーズにするために改善したいなど、他部署とも深く関わり合いながら、より良い管理体制を作っていこうという風土が根付いています。
――部署との横連携ですね。
木下:そうですね。事業部の一員として動く中で、法的な課題以外の支払いの課題、管理の課題に直面したとき、他のコーポレート部門に共有をしてみんなで事業サポートしていこうという動きもできるので、横の連携のしやすさは非常にスムーズだと思います。
岡本:法務部は経営陣と近い部門なので、「今、会社が何をしようとしているのか」「経営陣は今、どんなことが気になっているか」という新鮮な情報が頻繁かつタイムリーに入ってきます。経営との距離が近いからこそ、自分の見識もアップデートしていきたいという人にはすごく良い環境だと思います。
代表の稲田さんや荻野さんと日々会話を重ねる中で、アンドパッドの経営陣はコンプライアンスやガバナンスの意識が高いメンバーが集っていると感じます。ベンチャー企業ならではのスピード感を持って事業を進めていく気概を持ち合わせながらも、法令遵守の感度もしっかりと持ち合わせていると思います。
業界の発展を見据える、壮大なミッションに挑む
――最後に、法務部が目指す未来について教えてください。
岡本:組織の規模が大きくなればなるほど、スピードを保ったまま成長するのは困難がつきものです。しかし変化の激しい世の中で、事業が成長スピードを上げていくために、法務としてももっともっとスピードを追求していきたいと考えています。例えば、大手エンタープライズのお客さまが増えると、法的論点・コンプライアンスなどについて、正確性や細かい配慮が欠かせません。柔軟性を持ちながらベンチャーの特徴である機動力を保ち、いかに成長していくか。そのバランスを取るのがすごく難しい状況ではあると思います。
――時代の変化をいかに素早く察知し柔軟に対応できるか、ということですね。
岡本:短期間で色々な変化が起こり、新しいことが次々と生まれてくる環境なので、変化についていくのは大変だと思いますが、スピード感を持って会社の成長を支えたい、自分自身も密度の濃い時間を過ごして成長したいと思ってくださる方には非常に適していると思います。
会社自体や世の中の変化、そして社会貢献を働きながら実感できるのは貴重な体験ですし、非常に充実していると思います。私自身、アンドパッドがどのように建設業界の未来を変革していけるのか、楽しみでもあり、同時に業界からの大きな期待に応えなければという責任感も感じます。中長期的な視点で挑む必要がありますが、業界の発展に寄与し「幸せを築く人を、幸せに。」というミッションを実現する、壮大なチャレンジになると思います。このタイミングだからこそ得られる体験や経験は、代えがたいものになるのではないでしょうか。