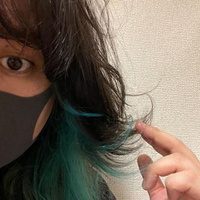カルチャーってなんだ?
会社において「カルチャー」なるものを大切にしていることが多いと思います。昨今は特にそれが目立つなぁと。
でも、私はこういう「わかるようで変わらない英単語」が怖かったりします。みんな当たり前にこの言葉を使ってて、なんか通じ合えている雰囲気出てて。でも、本当に分かり合えてるのか疑問に思ったこと、ありませんか?
「カルチャーとは何か説明してください」
この問いに自信を持って答えられて、且つ周囲と同じ回答できますかね?
私個人、人事キャリアを歩み初めてからずーーーーっと考え続けているんですが、例えば海外から日本に観光に来た方は、日本人がエスカレーターで左に寄るのを見て「それが日本のカルチャーだ」と言います。これは古来、お侍さんが左腰に刀を下げており、階段ですれ違い様に刀同士がぶつからないようにしてたことに由来する見たいです。
そうした「合理的な理由から生まれた習慣」こそが「文化=カルチャー」だと、私は理解しています。
その上で、ココナラのカルチャーブックに書かれていることを読むと非常に面白い。
読むと「あぁ、これあんま好きじゃないけど、これがココナラのカルチャーだから従わなきゃいけないんだ」と思うような項目は、少なくても私には無いんです。
例えば「オープンなコミュニケーション」というものがあり、そこでは「率直なコミュニケーション」と「オープンな情報共有」があります。
これだけ聞くと「風通しの良い組織なんだなぁ」と思われますし、実際転職軸に「風通しの良さ」を求める人も多いことから、採用における母集団形成のためのPRっぽくも見えます。
が、ココナラのカルチャーブックの面白いところは、「率直なコミュニケーション」について具体どういうことかを明記している点にあります。
「率直で開かれたコミュニケーションを自らが先んじて行い、本音で話し合える信頼ベースを築く。空気を読んで忖度するのではなく、意見を出す。」と。
目的と、その達成のために社員一人ひとりに何をして欲しいのかが具体的ですよね。そう、なぜか「風通しの良い組織」は社員にとって「与えられる環境」のような位置付けになっていることが多いと感じているのですが、働く環境を創る、特にカルチャーについてはその主体者は社員一人ひとりなんです。
さらに面白いのは、もしも働いていて「風通しが悪いなぁ」と感じたら"空気を読んで忖度するのではなく、意見を出す"ことをカルチャーブックで社員への期待として明記している点です。
これが一人ひとり、全員が合理的と感じ、習慣化して初めて「ココナラのカルチャー」となります。
なんとなぁく、オフィスのデザインにバリューが入っているとか、日常会話の中でバリューに含まれる言葉が使われてるとか、そういった表面的なことで「カルチャーが浸透してる」って思ってないですかね?
合理的な行動を誰かが示し理解を促すまでは重要ですが、それを社員一人ひとりが自分が主体であることを理解し習慣化していく、その習慣が成果を生み出して初めてカルチャーが醸成した、と言えるんだと思ってます。
そして、ここならはまだまだカルチャー面では課題があります。つまり、ここで書いたことを踏まえると「風通しが良いとは言えない部分がある」ということになります。でも、みんな風通しが良い会社で働きたいですよね?としたら、一緒に働きませんか?こういうのにワクワク出来る人をココナラの人事企画で待ってます!
https://open.talentio.com/r/1/c/coconala/pages/80622