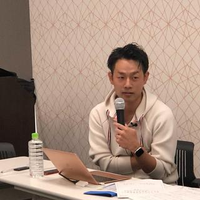なぜ、応募100件でも採用ゼロなのか?3つの失敗事例から学ぶ採用の本質
「応募はたくさん来るのに、誰も採用できない...」
もしあなたがこんな状況に陥っているなら、それは決してあなたの会社が悪いわけではありません。むしろ、多くの経営者が同じ罠に陥っています。
今回は、僕がこれまで見てきた採用の失敗事例を3つご紹介します。そして、なぜその失敗が起きたのか、どうすれば防げたのかを解説します。
失敗事例1:条件を上げたのに、応募の質が下がった製造業A社
年商3億円の製造業A社は、慢性的な人手不足に悩んでいました。
社長は決断しました。 「給与を月5万円アップしよう。そうすれば良い人材が来るはずだ」
結果、応募は3倍に増えました。 しかし...
面接に来たのは、給与の話しかしない人ばかり。 「残業代は?」「賞与は?」「有給は?」
A社が求めていたのは、モノづくりに情熱を持ち、技術を磨きたいと思う人材でした。でも、来たのは「条件」で選んだ人ばかり。
結局、100名以上の応募があったにもかかわらず、採用はゼロでした。
何が問題だったのか?
条件を上げると、「条件で選ぶ人」が集まります。彼らは他社がもっと良い条件を出せば、すぐに転職します。
A社に必要だったのは、条件アップではなく「モノづくりへの情熱を持つ人だけが応募する仕組み」でした。
失敗事例2:人材紹介に年間500万円使ったIT企業B社
年商5億円のIT企業B社は、エンジニア不足に悩んでいました。
そこで、大手人材紹介会社3社と契約。 年間で約500万円を投資しました。
紹介された人材は10名。 そのうち採用できたのは2名。
しかし、その2名も... 1名は3ヶ月で退職。 もう1名も半年で退職しました。
採用単価は250万円。 しかも誰も残らない。
何が問題だったのか?
人材紹介会社の担当者は、B社で働いたことがありません。会社の雰囲気も、開発の面白さも、チームの関係性も知りません。
だから、「スキル」だけでマッチングしてしまう。 「Python経験3年」「GitHub実績あり」といった表面的な条件だけで。
でも、B社が本当に欲しかったのは「チームで協力して開発を楽しめる人」でした。
スキルがあっても、文化が合わなければ辞めてしまう。これが現実です。
失敗事例3:「とりあえず人が欲しい」で妥協採用した介護施設C社
年商2億円の介護施設C社は、スタッフが1名退職し、急遽募集をかけました。
「とりあえず誰でもいいから、すぐに人が欲しい」
面接で違和感はありましたが、「人がいないよりマシ」と採用。
しかし、入社後すぐに問題が発生。 利用者への対応が雑。同僚とのコミュニケーションも取れない。
結局、3ヶ月で退職してもらうことに。
その後、残ったスタッフのモチベーションも下がり、さらに2名が退職。負のスパイラルに陥りました。
何が問題だったのか?
「人数を埋めること」が目的になってしまった。
でも、介護の現場で大切なのは「人間性」です。利用者に寄り添える心、チームで協力できるコミュニケーション能力。
妥協採用は、短期的には人数を埋められますが、長期的には組織全体を壊します。
3つの失敗に共通する本質的な問題
これら3つの失敗事例には、ある共通点があります。
それは、「人数を集めること」が目的になってしまったということ。
- A社は「応募数を増やす」ことに注力
- B社は「紹介数を増やす」ことに期待
- C社は「とりあえず埋める」ことを優先
でも、採用の本質は「人数を集める」ことではありません。
「自社にピッタリな人材と出会う」ことです。
応募100件で採用ゼロより、応募5件で採用3件の方が圧倒的に価値があります。
では、どうすればいいのか?
僕が10年間のマーケティング支援で学んだことがあります。
それは、「仕組み」がすべてだということ。
集客も採用も、本質は同じです。
お客様を集める仕組みがあれば、見込み客が自然と集まります。 人材を集める仕組みがあれば、ピッタリな人材が自然と応募してきます。
その仕組みとは:
- 自社の文化や価値観を明確に発信する
- 仕事の実態をリアルに伝える
- ミスマッチな人が自然と応募しなくなる設計
これが「求人マーケティングシステム」の本質です。
あなたの会社も、同じ失敗を繰り返していませんか?
もし少しでも心当たりがあるなら、一度「採用の仕組み」を見直してみてください。