「一人前のデザイニストになるとはこういうことなんだ!」を届けたい
若手クリエイターの奮闘レポート!一人前のデザイニストになることを目指し、前に突き進む過程をお届けする企画「デザイニスト道場」が始動!!
クリエイターの指南書とも言えるアンティー・ファクトリーの理念ブックを中心に据え、業界の最前線で活躍している先輩や同僚たちの門をたたいていきます。
理念ブックをより深く理解するためのサポート教材として、マネージャー陣に推薦図書も聞いて回ります。
時には先輩を突撃、時には同期や後輩と切磋琢磨しながら、道場で体験できたことを自分なりの理解におとし、理念ブックが指南してくれている内容とリンクさせながら、全ての方に届く言葉でお伝えしていきます。
私たちのリアルな体験を通して「一人前のデザイニストになるとはこういうことなんだ!」を指し示し、届けられたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
たのもう!!第四の門・小田島さん編
![]()
前回は、「第三の門・星山さん編」をお届けしました。
前回の記事はこちらから
今回突撃するのは、盛岡支社長兼アートディレクターの「小田島 佑太さん」です。支社長として、デザイン部門の指揮官として、アンティーならではのデザインに対する考え方『アンティー流』の原点を大切にしながら、日々、新たなクリエイティブを届けています。
■ 小田島さんの紹介
【名前】小田島 佑太
【所属】盛岡支社
【役職】支社長
【職能】アートディレクター
小田島さんが推薦する
理念ブックを読み解くための推薦図書とは……!?
早速、突撃していきたいと思います!
■ 推薦図書の紹介
中川政七商店のメソッドを初めて全公開!!日本初・ものづくり企業のための「ブランディング×デザイン×経営」の教科書とも言える1冊
推薦図書「経営とデザインの幸せな関係 中川 淳(著)」
経営とデザインは、どのように手を取り合えば「幸せな関係」になれるのか?
メインメッセージ「経営者とクリエイターが”共通言語”を持てば企業とブランドは強くなる!」を掲げ、互いに研鑽し合い「ブランディング×デザイン×経営」の力を高めていくことの重要性が説かれています。
筆者が実際に行ったものづくり企業の再生支援を通して得られた「ノウハウ」「方法論」が体系化されているので、とても理解しやすく、無理なく自然の流れで自分ゴトとして捉えていくことができます。
最も印象に残ったのは、第1章「ブランディングは、”会社のことを正しく知る”ことからはじまる」の部分です。アンティーの理念ブックにある「デザイニスト(*1)はかくあるべき」の像に近づくための大きなヒントをもらったようにも思います。この点からも一気に読み進めることができました。
アンティーのメンバーは勿論、ものづくりに関わる全ての人にぜひ読んでいただきたい1冊です。
*1.デザイニスト
アンティーでは、デザインはデザイナーだけが行う作業だとは考えません。実際に手を動かし造形的なデザインを行うのはデザイナーですが、デザインという言葉を広義に捉えれば、課題を解決し新たな価値を創造する行為は全てデザインと定義することができます。
産業革命以来の変革の時代を迎えた今、社会は新しい価値創造を必要としています。目の前の課題をただ解決するだけではなく、左脳と右脳、知性と感性をハイブリッドに活用し、知的美的デザインを生み出す力が求められているのです。
そしてその能力をもつプロフェッショナルをデザイニストと呼び、私たちは一流のデザイニストになり、一流のデザイニストを育成するために日々邁進していきます。
“デザイニスト“と”知的美的デザイン“は、PAOS 中西元男氏が主宰する、STRAMD戦略経営デザイン論で謳われている言葉を引用し、私たちなりの経験や考えを合わせて咀嚼、活用しています。
■ インタビュー
小田島さん、推薦図書をご紹介いただきありがとうございます!
ここからは、私たちからいろいろ伺いたいと思います!!
片山
事前ヒアリングシートで、「デザイニスト(*1)になることを目指しているアンティーの若手に伝えたいこと」として「守破離」をあげていらっしゃいました。
小田島さんが、盛岡支社長兼アートディレクターとしてお仕事をされてきた中での「守破離の瞬間」、「今まさにステージを上がったと感じた瞬間」のエピソードがあればお伺いしたいです。
小田島
「守破離」は、瞬間的なものではなく案件毎に行うべきこと
毎回、守破離の「離」まで行っていないといけない
私の考える守破離では、
- 最初の思いつきや多くの人が考えられるアイデアは「守」
- 自分で考え抜いたアイデアは「破」
- 頭ひとつ突き抜けて、自信を持って世の中に作品として出せたら「離」
ここまでやり抜くのはとても難しいこと 高いハードルがある
やり抜いたという事実は後からついてくる
直感を信じ、「自分で判断する力」を養うことが大事
- 制作の過程で「最初に感じたことが正しかった、間違ってなかった」と分かることもある 理屈じゃない
- 自分で判断する力「世の中に出しても大丈夫か?」「世の中と戦えるか?」を養うことを大事にしている
- アンティーに入ったばかりの頃は、これができていなかった
- 中川社長や先輩のアートディレクター、プロデューサーの力を借りていた
- 世の中に出ている良いものを見て洞察力を鍛えながら、自分目線を育てていくことが大事
片山
なるほど、今まで小田島さんが積み重ねてこられた実績に裏付けされた極意ですね!
私も、これまで以上に「守破離」の「離」までやり抜くことを意識していきたいと思います。
推薦図書の第1章に、顧客理解を深めるためのメソッドが綴られていました。
顧客理解を深めるにあたって小田島さんご自身が大切にし、実践されていることはありますか?
小田島
顧客理解を深めるために「とにかく調べる!」「想像力を働かせる!」
- クライアントは長い時間をかけて自身の課題と向き合っている 浅い理解では太刀打ちできない
- 現地に足を運び、記事やデータを読み込み、徹底的に情報を収集する必要がある
「デザインとは好きな人に花束を贈ること」(イタリアのデザイナーエットーレ・ソットサスの言葉)
相手の立場に立ち、考えを巡らすことが、デザインという行為の第一歩となる
- 相手の言葉の奥にある「思惑」「本当の悩み」を汲み取る
- その上で「もし自分が贈るならどんな花束を選ぶか」と想像するように、相手の立場に立って考えることが大事
- 相手が喜ぶものやタイミング、見せ方まで、とことん想像力を働かせる
顧客思考で考えることの大切さは、アンティーの理念ブックの「行動規範3. 顧客満足」にある「まず相手の話を聞くこと」にもつながってくる
- 自分の都合や要求よりも先に相手の想いを理解する
- 寄り添って想いを巡らすことが、満足の種を育て、顧客の成果や幸福に寄与するデザインを生み出す
- デザイニスト(*1)の要件「課題解決」「新たな価値創造」にも直結し、社会に求められる存在へと近づいていく
片山
私たちは、「アンティーからクライアントに贈る花」「クライアントから消費者に贈る花」、この2つの視点で想像するのですね!!
推薦図書では、一貫して、「経営者と消費者の視点の違い」「消費者が本当に必要としているものは何か?」というテーマで話がされていました。ここにつながっていくお話だと思います。
消費者の立場に立って想像を深めたあと、案件に立ち返ってみると、「経営者の視点」と「消費者の視点」とで折り合いがつかなくなることはありませんか?
そういった時、どう折り合いをつけていますか?
小田島
やはり、顧客の目的を達成することが第一
迷ったら「顧客が何をしたいのか?」「何を達成しようとしているのか?」に立ち返る
- 先ほどの花束の話で言うと、「そもそも贈るのは本当に花束でいいのか?」一番大きな目的に立ち返る
- 総合的に考えて、「顧客が得られる結果がベストかどうか」が最優先の目的になる
- ここを基盤に、正しい/正しくないの線引きをしていけば、間違った判断には至らないと思う
片山
アートディレクターとしての小田島さんについてもお伺いしたいです。
一般消費者の目線で物を見ようとしても、どうしてもデザイナーの視点が入ってくると思います。
どのように対処されているのかお聞かせください。
小田島
常に「一般消費者」「デザイナー」この両方の視点を持って物を見るようにしている
- コンビニに並んだ商品の中から一つを選ぶときは、自分の気分や気持ちを優先し直感で選ぶ
- その後、「なぜこれを選んだのか?」「気分?」「条件?」「パッケージの見せ方?」と因数分解していくと、その中に詰まっている要素が分かりやすくなり、本質が見えてきて、デザインのヒントにつながることもある
片山
推薦図書の第3章に、「商品政策」が綴られていました。「商品の構成要素の本質を見抜き、新たな選択肢を発見する」とある部分から、とても大きな気づきをもらいました。
アンティーのビジネスに置き換えると、「クライアントからいただいたオーダーをそのまま形にするのではなく、その奥に隠れた真の課題を見つけ出して形にしていくことが重要」と理解しています。理念ブックにある「知的美的デザイン(*2)」そのものだと思いました。
実際、小田島さんは、どのような工夫をされていますでしょうか?
*2. 知的美的デザイン
私たちが行うデザイン行為は以下の2つを満たしているべきと考えます。
このデザイン行為から生まれた成果物は、機能性と審美性を兼ね備えたものであるべきと考え、この行為と成果物を含めた総称として知的美的デザインと呼びます。
小田島
クライアントに寄り添い、徹底してヒアリングを行う
- クライアント自身、真の課題に気づいていないことがある
- 相談が来た時は、まず、与件を疑ってかかる
- 何に悩んでいて、何を解決するべきか、相手に寄り添い、想いを巡らせる
- そうすることで、自然とヒアリングすべきことが見えてくる
- 本質にたどり着くことができる
究極のところ「人間力」が一番
- 相手の懐にどんどん入り込んで話す この能力は、仕事をしていく中で最大の強みになる
- クライアントの担当者も一人の人間 問題の本質を引き出すには、「この人なら分かってくれる」「頼れる」と思ってもらい、信頼関係を築くことが一番
片山
小田島さん、ありがとうございます。
「守破離」から「人間力」まで、言葉の一つひとつに、実践から培われた重みと優しさを感じました。
「デザインとは好きな人に花束を贈ること」という言葉がとても印象的でした。改めて、私たちの仕事の本質に立ち返るきっかけをいただいたように思います。
デザイニスト(*1)を目指す私たちにとって、大切にしたい視点と姿勢をたくさんいただきました。
本日は貴重なお話を本当にありがとうございました!
■ 本日の学び!!
✓「徹底調査」「想像力」この両輪が知的美的デザイン(*2)を生む
- 顧客理解を深めるために、「とにかく調べる!」「想像力を働かせる!」
- これが、「知的美的デザイン(*2)」を生み出す第一歩となる
- 真の課題を見抜き、「課題解決」「新たな価値創造」へとげつなていく
✓ 判断の軸を明確に持ち、最終目的を見失わない!迷ったら立ち返る!
- 相手の言葉の奥にある「思惑」「真の悩み」を汲み取り、判断の軸を明確に持つ
- この軸があれば、迷った時も自然と正しいゴールに導かれる
- 真の成果「顧客が求めているゴール」「顧客の幸福に寄与するデザイン」を見失わない
✓ 自身が選択したことを客観的に振り返り、分析する習慣を持つ!
- 直感と因数分解の蓄積が、デザインをするときの財産になる
- 感覚的に判断したことに理由を与えることで、再現性と説得力が高まる
- 目まぐるしく変化する時代や社会にも対応でき、デザイニストとしての普遍的価値を高めることができる
✓ 隠れた真の課題を見つけ出して形にしていくためには、人間力が欠かせない
- クライアント自身、真の課題に気づいていないことがある
- 相手の懐に入り込み、本質を引き出し、形にしていく力が求められる
- そのためにも「この人なら分かってくれる」「頼れる」と思ってもらえるよう信頼関係を築くことが欠かせない
- デザイニスト(*1)に求められる人間力そのものと言える
デザインとは単なる課題解決ではなく、相手への深い理解と本質への探求から生まれる「信頼のかたち」だということを心に留めてこれからも仕事に向き合いたいと思います!
小田島さん、ありがとうございました!
次回は、また新たなマネージャーに突撃します。お楽しみに!!
記事作成: 片山 小巻(UCML(アンティークリエイティブメディアラボ)/VIDEO Development Group)
インスタグラム
![]()
@unt_factory_official
un-T factory | アンティー・ファクトリー【公式】
渋谷に本社を置くクリエティブ&デザインエージェンシー
アンティーファクトリーの“今”を発信するアカウント
ㅤㅤㅤ
・全国7拠点3法人のグループ
・戦略企画立案、制作、動画等の提供
・メンバー紹介や最新トピックス、採用情報、カルチャーを発信
関連エピソード
その他の情報


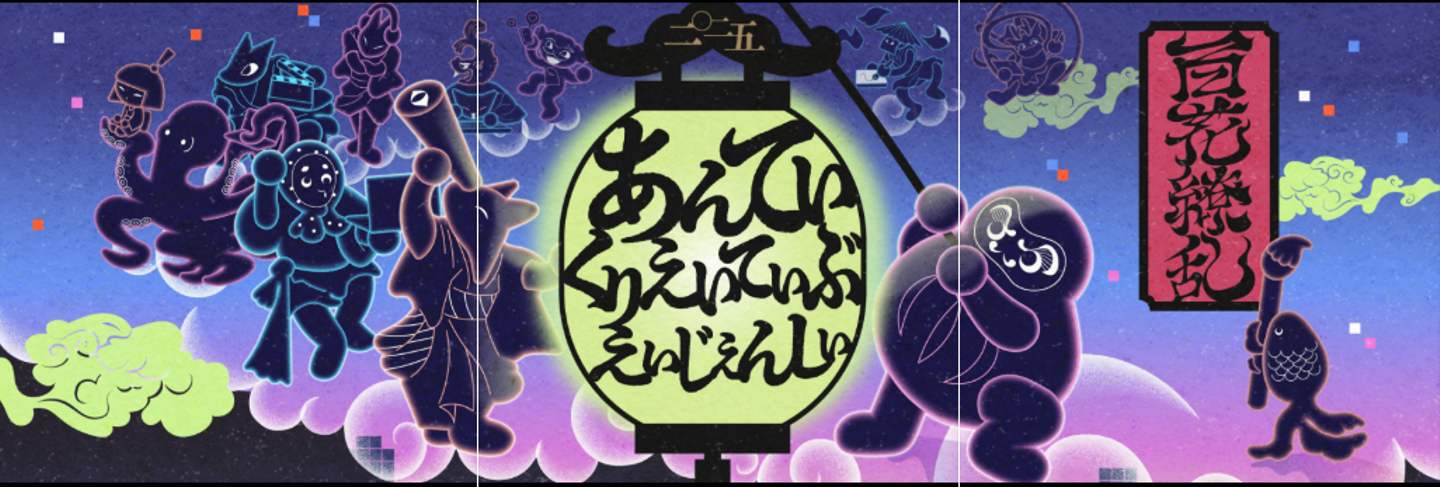
/assets/images/360499/original/34231fe6-30cf-4deb-a6a7-b6ee028af9f0.png?1460973864)


アンティー・ファクトリー)/assets/images/360499/original/34231fe6-30cf-4deb-a6a7-b6ee028af9f0.png?1460973864)
/assets/images/18214431/original/34231fe6-30cf-4deb-a6a7-b6ee028af9f0.png?1718243228)

