"ホームページには素敵な理念が書いてあるけど、本当に大切にしてる?"
"同じような価値観を持った人と一緒に働きたい"
"入社するからには、困難なことがあっても乗り越えられるほど共感できる事業に関わりたい"
・・・
転職活動の目的は人それぞれですが、次の職場では【やりがいを感じながら、できるだけ長く、楽しく、働きたい】と感じることはありませんか?
そのような"あたりまえの思い"を実現するには、入社後のミスマッチを防止するために少しでもリアルな情報に触れることが大切だと思います。
【Member Stories|Startline】では、既に入社して活躍されている様々な社員の様子をインタビュー形式でありのままにまとめています。今回は、2017年9月に入社した福島さんに、スタートラインへの入社の決め手と仕事のやりがいについてインタビューいたしました!
ぜひ、最後までご覧ください!
——作業療法士からスタートラインへ。福島さんが歩んだキャリアとこれから
|福島さん、今日はよろしくお願いします!まず、スタートラインにはいつ入社されたんですか?
2017年の9月です。もうすぐ8年になりますね。
|以前は、作業療法士として活躍されていたと伺いました。
はい、6年半ほど、病院で作業療法士をしていました。高校生で進路を考えた時、保育や介護の仕事を検討していました。ただ高齢者と子供どちらに関わりたいか、なかなか決め切れずにいたんです。
そこで作業療法士であればどの年代においても、『その人らしさ』を大切にしながら生活を豊かにする支援をすることができると考え、この道に進むことに決めました。
|“その人らしさ”というとこを大切にされていたんですね。
はい。また私は、もともと”遊び心”が好きなんです。リハビリは訓練ですが、作業療法では遊びを取り入れながら進めていく側面もあり、その人が楽しみながらリハビリできるように“設計”するというのが、すごく面白いなと思っています。
|リハビリを苦しくて大変なものだけに留めず、遊びを通して楽しいものと思える工夫をされていたんですね。作業療法士として順調にキャリアを積まれていたように感じますが、なぜスタートラインに転職することを決めたんでしょうか?
病院の回復期病棟で働く期間が長かったのですが、その立場では退院後の社会生活までのサポートは難しいと感じていました。働き盛りの高次脳機能障害の方の退院・復職支援を担当することもありましたが、そもそも、入院中は社会との関わりや刺激が少なく、社会に出てから支障が表面化することも少なくありません。リハビリテーションセンターに繋ぐ等はしましたが、社会復帰したときにちゃんとその人が生活できるのか不安に感じていました。その様な背景から、だんだん「退院後の人生の方が長いのに、自分はそこに関われていない」という思いが強くなりました。
もっと生活に近いところで支援したいと思っていたときに、作業療法士の集まりでスタートラインの社員に出会ったことをきっかけに、見学・選考に進みました。

|病院でのご経験を経て、よりその先の支援に興味が出てきたんですね。生活支援を行う企業はいくつかありますが、その中でもスタートラインに惹かれたポイントはなんでしたか?
スタートラインの事業が”福祉”ではなく、ビジネスとしてしっかりと“社会への価値提供”を軸にしているところですね。また、やってきたことの延長として就労フェーズの方の自己理解や定着支援に関われ、自分の視野も広がりそうだと思い、飛び込んでみました。
|作業療法士から民間企業への転職は大きな決断でしたよね。では実際にスタートラインに飛び込んでみてからはどうですか?
最初は、INCLUのサポーター職に応募をしていましたが、採用面接で私が【クライント社内で雇用されている(社内雇用)方の就労支援をやりたい】と伝えていた思いを踏まえ、当時近しい取り組みを始めていた障害者雇用研究室(現在のCBSヒューマンサポート研究所)へ配属を打診され、配属となりました。入社から今まで部署の形は変わっていきましたが、一貫して【社内雇用の支援】に携わらせてもらい感謝しています。最初は高次脳機能障害の方に関わりたいと思っていたものの、精神・発達障害の対象者が多く、そこから学習を深めました。
半年間研究所に在籍し、その後は新規事業に携わりました。新規事業では、定着支援における一気通貫のサービス開発に尽力しました。一般企業での就業経験がなかったので、市場分析やテレアポにし苦戦しました。 一方でビジネスとしての知見や法人折衝の経験を得ることができたので、視野が広がりとても貴重な経験だったと思っています。
|なんでも完璧にこなされる印象の強い福島さんですが、苦戦されることもあったんですね!具体的にどのようなことが大変でしたか?
この領域で働くのが初めてだったため、事前に分析やリサーチをしておかないと共通言語でお話ができなかったり、お客様のトレンドや課題感にマッチする提案をすることが難しいと感じていました。はじめは、企業の方と関わり経験もなかったために「人事部長」という顧客の肩書に一歩引いてしまうこともありました。
ただ、経験を積む中で「人事部長」も「(同じ)人」だと思うことで、心理的な距離が縮まり、顧客との関わり方のハードルを下げることが出来たと思っています。

|確かに、相手の方のことを肩書で見るのではなく、「人」としてみるというのはどの業務でも大事になってきますよね。福島さんが仕事において大事にしていることはありますか?
「話を聞いて、なりたい姿に向かう支援をする」というスタイルは、作業療法士のときからずっと変わっていないです。個人か組織かという違いはありますが、「悩みは一体何なのか?」という根本的な課題解決に伴走するためのコミュニケーションを実践していました。
例えば、提案していた案件が失注になったとしても、そこまでのプロセスを大事にすることでお客様との関係性は構築できると思います。関係性さえできていれば、数年後に、改めてお声がけいただきご一緒できることもあります。そのため、結果だけを見るのではなくどういったアプローチをしていくかが重要だと思います。
長期的な視点で見たときに、会社として価値提供ができているなと思えることが大事ですし、お客様のニーズを明確に満たしていくことがその先に繋がると考えています。
|受注をゴールにするのではなく、そのプロセスやその先にあるものもしっかり見据えていらっしゃるんですね。福島さんは、実際の課題解決(カスタマーサクセス)にも携わっていらっしゃいますよね。
サポーターとして個人への支援から始まり、現在は顧客の組織全体の支援にチャレンジしています。関わる組織の規模が大きくなる分、私自身も様々な角度からのアプローチのノウハウを得ることができていると実感しています。
|視点が広がった分、支援の深さも増しているんですね。
そう思います。いろんな階層の“らしさ”や課題を整理して、支援できる手札を得たことが今の自分の強みかなと思います。
|様々な立場を経験されてきた福島さんですが、この3年間は運営責任者としてチーム運営をされていますよね。何か意識していることはありますか?
一番は、チーム全員が意見を言いやすい環境づくりです。答えのない仕事ですので共に最適解を探すことで、よりよい価値提供ができる仕組み作りを実現していくことが大事だと考えています。(今はProsocialも取り入れています)
例えば、入社間もない社員だからこそ感じる感覚に大切なヒントがあったりします。経験が長い自分自身にも苦手なことがあるので、そこはチームに頼らせてもらっています。チームワークの良さを、日々感じることができています。
|福島さんの仕事観や熱意など詳しくお伺いできました。入社して8年目となりますが、今後のキャリアビジョンはありますか?
実は、自分の5年後10年後先の目指したい姿をあまり具体的に考えられないタイプなんです。なので、キャリアビジョンはありません。(笑)ただ、自分の価値である”価値提供・出来ることを増やす”に実直に向き合うことで、次に深めたいことが自然に見えてくる気がします。
今までもその時に興味があることに熱量を注ぐというキャリア形成をしてきたので、まず今やるべきことをやりつつ、見えてきたものを深めていくことになるかなと思っています。
|最後に、この記事を読んでいる方にメッセージをお願いします!
スタートラインは、やりたいことを「やりたい!」と口に出して言える方であれば、周囲がバックアップしますので活躍できる環境だと考えています!もちろん、全部が叶うわけではないですが、伝えることでまずは“種まき”ができ、少しずつ実現に近づいていくと思います。
あとは、「苦手なことはそれぞれ誰しもあるので、それを素直に認めてチームを頼れる」ことも大事かなと思います。(私はとっても道に迷うのでいつもフォローしてもらっています。)相互に協力し合って、何かを成し遂げる楽しさを実感したいと思える方と一緒に働けたらとても嬉しいです!
--------------------------------------------------------------------------------
最後までお読みいただきありがとうございました!
・どんな人と一緒に働くの?
・採用プロセスでは会社の良い面ばかりの話で、言いづらい話はしないでしょ?
・志望動機が明確じゃないし、少し気になっている程度だけど応募していいの?
など、転職活動を進めていく中で感じる疑問や悩みはたくさんあると思います。
採用に携わるメンバーが共通して大切にしていることは、双方にとって入社後のミスマッチを発生させないことです。面談や面接の場では、皆様が気にされている点についてしっかり開示し、双方納得した上で握手ができればと思っています。
また、志望動機はコミュニケーションを経て初めて固まるものだと思っています。面談の場では、どんな疑問も解消できるよう努めてまいりますので、少しでも気になった方はぜひ【話を聞きに行きたい】をクリックしていただければと思います!
/assets/images/181771/original/bb0a5983-8aab-4e1f-8cb7-fc45b7667cbc.jpeg?1441073811)
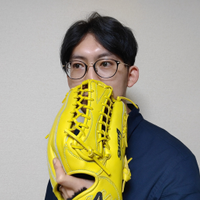

/assets/images/181771/original/bb0a5983-8aab-4e1f-8cb7-fc45b7667cbc.jpeg?1441073811)


/assets/images/181771/original/bb0a5983-8aab-4e1f-8cb7-fc45b7667cbc.jpeg?1441073811)

/assets/images/15336306/original/MepU2Qr?1697358347)

