要件定義書を読もう。仕様変更や「ちゃぶ台返し」に備えるために
Photo by Alexander Nrjwolf on Unsplash
こんにちは。和田です。
私は56歳、ソフトウェア開発歴26年になります。長年の経験から断言できることがあります。それは「要件定義書を理解しているかどうかで、仕様変更への対応力やスケジュール管理の精度が大きく変わる」ということです。若手のころは「設計さえできれば実装はできる」と思い込み、要件定義書を軽視していました。しかし、現場で繰り返される仕様変更やプロジェクトの“ちゃぶ台返し”に直面するうちに、その考えは大きな誤解だと痛感しました。
ソフトウェア開発の現場で、若手エンジニアが最初にぶつかる壁のひとつは「設計より前の仕事の理解」です。日常的に触れるのはソースコードや詳細設計書ですが、その背後にある「要件定義書」を意識している人は少ないかもしれません。しかし、ここにこそプロジェクト全体の方向性や顧客の真意が詰まっています。
要件定義とは何か
要件定義書は、顧客が実現したいことやプロジェクトの目的を整理した文書です。「これだけ読めばすぐコーディングできる」というものではありませんが、ソフトウェアが果たすべき役割、業務フロー、制約条件、顧客の思いなど、プロジェクト全体の羅針盤となる情報が詰まっています。
現場では、若手エンジニアがこう思いがちです:
「設計さえできればコードは書ける。要件定義は素人がまとめたキャプチャの切り貼りでしょ?」
確かに、要件定義書だけではそのままコーディングできるケースは少ないです。しかし、それを理由に軽視すると、後で膨大な仕様変更に振り回されることになります。顧客の意図を理解しておくことで、設計チームやプライム企業に頼るだけでなく、自分で判断してスムーズに対応できる場面が増えます。
ソースコードからさかのぼる設計の理解
エンジニアの心理として、「難しいコードを書くこと」「高度なロジックを実装すること」が重要に見えたり、カッコよく感じたりすることがあります。しかし、実際に価値を生むのは「設計が正しいこと」です。設計がしっかりしていれば、実装は比較的スムーズに進みますし、後から仕様変更があっても対応しやすくなります。
設計が不十分な場合、若手は「設計チームや上流工程の落ち度」と考えがちです。しかし、要件定義書を理解していれば、設計の意図や変更の背景を自分で把握できることが多く、ただコードを書くだけでなく、設計全体を見渡す力を養えます。
具体例:ECサイト開発
ここで、実際の開発プロジェクトを例に考えてみます。あるECサイト開発でエンジニアが依頼された作業は以下の通りとします:
- IDを入力ボックスで追加
- 取引データにIDを追加
この時点では「要件定義を読まずにコーディングできる」と思うかもしれません。しかし、プロジェクトが進むにつれ次々と仕様変更が発生します:
- 帳票の変更が必要になった
- 会計システムとの連携が必要になった
最終的に要件定義書を確認すると、顧客の本当の意図は「インボイス対応」。インボイス対応には、取引情報に必要な追加項目や会計連携の要件が含まれます。もし初めから要件定義書を読んでいれば、個別の変更に振り回されることなく、全体像を把握した設計が可能でした。
この例からわかるのは、表面的な実装内容だけを追うのではなく、顧客の「やりたいこと」を理解することが重要だということです。対象の変更が全体にどう影響するかを考えられるようになり、抜け漏れや後戻りを減らせます。
要件定義を活用するためのポイント
- プロジェクトの共有フォルダを探す
要件定義書はプロジェクトフォルダの端っこに置かれていることがあります。まずはそれを見つけ、内容に目を通しましょう。 - 顧客の意図を意識する
単に機能や仕様を追うのではなく、「なぜその機能が必要か」を理解します。目的を意識することで、追加や変更の判断が早くなります。 - ソースコードとの紐付けを意識する
実装中のソースコードを見ながら、要件定義のどの部分を実現しているのかを対応付けると、設計や実装の意図が明確になります。これにより、コードの修正や機能追加の際も、全体を見渡しながら作業できます。この対応付けを「トレーサビリティ」と言います。 - 全体像を把握する
要件定義書を理解することで、プロジェクトのスケジュールや優先順位も全体感で組みやすくなります。小さな仕様変更が他の部分にどう影響するかを事前に見通すことができ、無駄な手戻りを防げます。 - 仕様変更に強くなる
顧客の意図を理解していれば、表面的な変更だけに対応するのではなく、全体を最適化する視点で実装や設計を考えられます。結果として、プロジェクトの信頼性が上がり、エンジニアとしての価値も高まります。
まとめ
要件定義書は「素人がまとめたキャプチャ集」ではありません。顧客の思いや業務の本質が詰まった、開発の羅針盤です。若手エンジニアがこれを読むかどうかで、プロジェクト全体の見通しや、仕様変更への柔軟性は大きく変わります。
まずはフォルダの端っこにある要件定義書を開き、顧客が本当にやりたいことを把握してみましょう。それが、設計力や実装力をさらに伸ばす第一歩です。
また、要件定義書を読む習慣をつけることで、上流工程とのコミュニケーションも円滑になります。「設計チームの落ち度」と思っていた問題も、実は顧客の意図や制約条件を理解していなかっただけ、というケースは少なくありません。エンジニア自身が要件定義を理解することで、問題の本質を捉え、より良い設計・実装が可能になります。
結局、ソフトウェア開発で最も大事なのは、単にコードを書くことではなく、「顧客が何を実現したいのか」を理解し、それを全体像として設計・実装に落とし込む力です。要件定義書は、その力を養うための貴重な教材です。


/assets/images/11010934/original/654c912d-792c-43e7-8c6e-0bced2263011?1667182788)


/assets/images/11010934/original/654c912d-792c-43e7-8c6e-0bced2263011?1667182788)

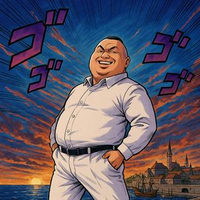


/assets/images/20408409/original/654c912d-792c-43e7-8c6e-0bced2263011?1739429121)

