NTT東日本で14年間、総額10億円の案件創出、年間ARR10億円規模の新規事業立ち上げを成功させた男がなぜベンチャーへの転職を決断したのか。現在、株式会社openpage事業開発部長として活躍する北森雅雄さんが、転職の決断プロセスから転職後わずか数ヶ月で実現した成果まで、営業変革を通じた地方創生への想いを語る。
14年間で築いた現場力 - 3つのフェーズで培った顧客視点
ライター:北森さん、本日はお時間をいただきありがとうございます。NTT東日本での14年間は、どのようなキャリアだったのでしょうか?
北森さん:大きく3つのフェーズに分かれていました。それぞれの経験が、今の私を作っていると思います。
第1フェーズ:自治体SE時代(2011-2016年)- 現場での顧客理解
東日本大震災の年に入社し、最初の5年間は自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションのコンサルティングに従事していました。
「自治体の現場で、職員の方々が抱える課題を間近で見てきました。どうすれば、もっと市民サービスを向上させられるのか。どうすれば、職員の方々の業務を効率化できるのか。常に顧客の立場に立って考える姿勢は、この時期に培われました」
ライター:その時期の具体的な成果を教えてください。
北森さん:千葉で2年間自治体のセールスをしていた際は、総額で10億円以上の案件創出を実現しました。自治体内のネットワークや小中学校のネットワークを作る案件が中心でした。自治体さんには無料公衆Wi-Fi(無線LAN)の設置なども提案し、とにかく現場に向き合う仕事でしたね。

第2フェーズ:新規事業開発時代(2016-2020年)- プロダクトの力を知る
ライター:その後はどのような業務に?
北森さん:その経験を踏まえてビジネス開発本部の新サービス開発の部隊へ異動し、AI-OCR(※紙の文書をデジタル化する技術)とRPA(※定型業務を自動化するツール)の新規事業を立ち上げました。
この新規事業は年間ARR(※年間売上高)5億円まで成長させることができました。
その後、中小企業・自治体の業務効率化に向けた複数のサービスを事業開発していき、最終的には10以上のサービスを所掌し、全事業合計で年間ARR10億円以上の規模にまで拡大することができました。
「プロダクト開発では、お客様の声を直接聞き、それを形にしていく。自治体SEとして培った『顧客視点』が、ここでも活きていました」
第3フェーズ:デジタルマーケティング時代(2020-2024年)- ゼロから始めた挑戦
ライター:デジタルマーケティングでも大きな成果を上げられたそうですね。
北森さん:2020年、新型コロナウイルスの感染拡大が、私に大きな気づきをもたらしました。
「コロナ禍で、今までとは違う働き方を余儀なくされました。でも、それは同時に『考える時間』を与えてくれたんです。世の中ではどんなマーケティング手法が使われているのか。デジタルマーケティングで、どれだけ多くの人に価値を届けられるのか」
リモートワークで生まれた時間を活用し、私は様々な情報を収集。世の中の先進的なデジタルマーケティング事例を研究し始めました。
北森さん:当初はマーケティング専任者がいない中でのスタートでした。もともとプロダクト開発企画やセールスイネーブルメントを担う部門に所属していたので、マーケティングは未経験です。デザインツールの使用経験もなく、独学で身に付けました。
しかし、組織として取り組むべき重要な領域だと確信し、データに基づいた論拠のある施策を設計しながら、段階的に社内の理解と協力を得ていきました。
長年SEとして直接お客様と向き合ってきた経験を活かし、お客様の顔と求める情報をイメージしながら、関係部署と連携して取り組みを推進しました。特に意識したのは、サービス提供側が「伝えたい」情報ではなく、お客様が「知りたい」情報を発信することでした。

一人から始めたマーケティングが生んだ驚異的な成果
ライター:具体的にはどのような成果が出たのでしょうか?
北森さん:予想を超える成果として結実しました。
主な実績:
- オウンドメディア「ワークデジタルラボ」:最大で26万UU達成
- 資料ダウンロード:月間170件以上(2023年9月実績)
- メールマガジン:最大800件超のダウンロード
- ホワイトペーパー:10種類以上のバリエーションを制作
- 組織の成長:2023年にメンバーが3名体制に拡大
「最初は月に5〜10件の資料ダウンロードがせいぜいでした。それが10倍以上のコンバージョンを生むまでに成長しました。顧客視点でコンテンツを作り続けた結果です」
「共感」が生む価値 - 事例の力
北森さん:導入事例の制作には特に注力し、民間企業から自治体まで数多くのユースケースを作成していきました。お客様が新しいサービスの導入を検討するにあたって、「共感」はとても重要な要素です。導入事例があることで『自社も同じように課題解決ができるだろう』と感じてもらえる。
特に自治体向けには、自治体通信と連携して「自治体DXのホンネ」という企画を立ち上げました。これは、自治体職員の方々の生の声を収集し、その取り組みや課題、成功事例を全国の自治体に届ける取り組みです。私自身、自治体SEとして現場を知っているからこそ、現場の職員が本当に知りたい情報、共感できるストーリーを届けられました。
実際、メールマガジン施策でも、コラムや汎用的なコンテンツより、具体的なお客様の社名が掲載された導入事例の方が、総じて反応率(開封率)が高くなりました。
「全国各地でがんばっている現場の方々にスポットライトを当て、その取り組みを可視化する。民間・自治体問わず、現場の声を形にすることで、同じ課題を抱える組織に解決の道筋を示す。それが私のミッションでした」

転機となったopenpageとの出会い - 営業の本質を言語化する
ライター:順調なキャリアを歩まれていた中で、なぜ転職を考えられたのですか?
北森さん:2022年、デジタルマーケティングで一定の成果を出していた頃、社内での実績と並行して、自分のキャリアの可能性を社外でも試してみたいという思いが強くなっていました。NTT東日本での仕事は充実していましたが、自分が培ってきたスキルや知見が、より広い世界でどのような価値を生み出せるのか探求したかったんです。そんな時に出会ったのがopenpageでした。
「営業の本質とは何か。なぜ優秀な営業パーソンは成果を出せるのか。その暗黙知を言語化し、誰もが実践できるようにする。openpageのビジョンに、私が探していた次のミッションを見つけました」
ライター:openpageの何に具体的に惹かれたのでしょうか?
北森さん:2022年から副業として関わり始め、藤島さんとカスタマーサクセスや営業の形を一緒に作っていく中で、今までやってきたことを言語化していく作業に深く共感したのです。こういう言語化したものを世の中に浸透させることが、残りの社会人生活で自分が注力したほうが社会に還元できることが多いのではないかと思いました。
openpageが掲げる「営業とは顧客との共同作業である」「相手の意思決定や行動を促すために必要な情報と道筋を示すもの」という哲学に、私は深く共感しました。
2年間の副業期間は、まさに自分のキャリアの可能性を確かめる期間でした。マーケティングコンテンツの制作や営業資料の企画を手がけるなかで、営業という仕事の本質が言語化されていく過程を体験し、NTT東日本での経験とopenpageでの新しい視点が融合していくのを実感できました。
「openpageでは、営業という仕事の本質を言語化し、それを世の中に広めようとしていました。私自身、長年営業の現場を支援してきて感じていたモヤモヤが、ここでは明確な言葉になっていった」
転職の決断 - 半年間の葛藤とメンタリングの力
ライター:openpageからオファーをもらった時の心境はいかがでしたか?
北森さん:正直、半年間悩みました。大手からベンチャーに行って通用するのか、仕事本当にできるのか...そんな不安でいっぱいでした。そこでメンターの方にメンタリングしてもらったんです。5〜10年、20年先のキャリアを現職とopenpageとでどう歩むかを並べるワークをしました。
メンタリングで描いた未来像
転職後の数年間:
- 大手メーカー企業との協業を成功させ、執行役員への道をつなげる
- パートナービジネスの立ち上げを通じて、openpageのソリューションを広く展開
- セールス分野での第一人者として、アカデミックな取り組みも推進
5〜10年後:
- 特許取得や大学との共同研究を通じて、営業の科学的アプローチを確立
- 大学の客員教授として、次世代に知見を伝える
- 地域スタートアップの発見・投資を通じて、地方創生に貢献
20〜30年後:
- 複数企業の顧問として、経験と知見を社会に還元
- 講演会などを通じて、営業の本質を広く伝える
- 地域を再定義するような社会貢献活動に従事
ライター:キャリア分析ではどのような結果が見えたのですか?
北森さん:NTT東日本でも地域創生に関わり、組織の中で着実にキャリアを積んでいく道もありました。ただ、大企業では幅広い地域に対して総合的なアプローチを取ることが多い。一方でopenpageなら、営業変革という明確な軸で、より深く集中的に社会課題に取り組めるんです。
特定の領域に特化して深く関わることで、より本質的な変革を起こせる。今まで暗黙知だった営業の言語化を徹底的に追求し、その研究で大学との産学連携なども視野に入ってきます。
社会に対して意味のある営業の言語化を発信し、その分野の第一人者になれる可能性が見えました。openpageなら、自分の専門性を最大限に活かしながら、より直接的で深いインパクトを社会に与えられる、それが見えて意思決定したんです。

家族との対話を通じて確信した決断
ライター:ご家族の反応はいかがでしたか?
北森さん:メンタリングを通じて明確になったキャリアの道筋について、半年間じっくりと家族と対話を重ねました。私が描いた将来のビジョンや、なぜopenpageでのキャリアが自分にとって必要なのか、その論理的な根拠を丁寧に説明していきました。
家族も私の考えのロジックを理解し、「それだけ明確な道筋が見えているなら、もう行くべきなのでは」という結論に至りました。私の決断を肯定し、応援してくれたことで、最後の迷いが消えたんです。
クロージングでは年収面の調整はもちろん、執行役員を目指していくキャリアの合意形成も取れました。
ライター:実際に転職してみて、当初の不安はどうでしたか?
北森さん:行ってみたら全然やっていることが通用して、新しいアイデアも進められたので杞憂でした。大手で培ったスキルは、思っていた以上にベンチャーでも活かせることが分かったんです。
条件面のリアル、それでも転職を決めた理由
ライター:転職による条件面の変化はいかがでしたか?
北森さん:正直、大手企業と比べると福利厚生などは大手企業とベンチャーの違いがあります。退職金や企業年金などは確かに大手の充実度には及びませんが、それを理解した上で納得のいく条件で転職できています。
ライター:それでも転職を決断された理由は?
北森さん:2〜3年後の成長の展望が明確だったからです。そこで成果を出し新しいマーケットを開拓できれば、自分のキャリアバリューができて市場に必要な人材になれると考えました。経営人材になっていくキャリアパスを見据えて、自由度をもって新しいキャリアを築けると判断したのです。
「これは『挑戦』というより『自身のフェーズアップ』だと考えています。NTT東日本では特定の顧客に深く貢献してきましたが、openpageならそのナレッジを日本中の企業に展開できる。社会への貢献度を高めるための必然的な選択でした」
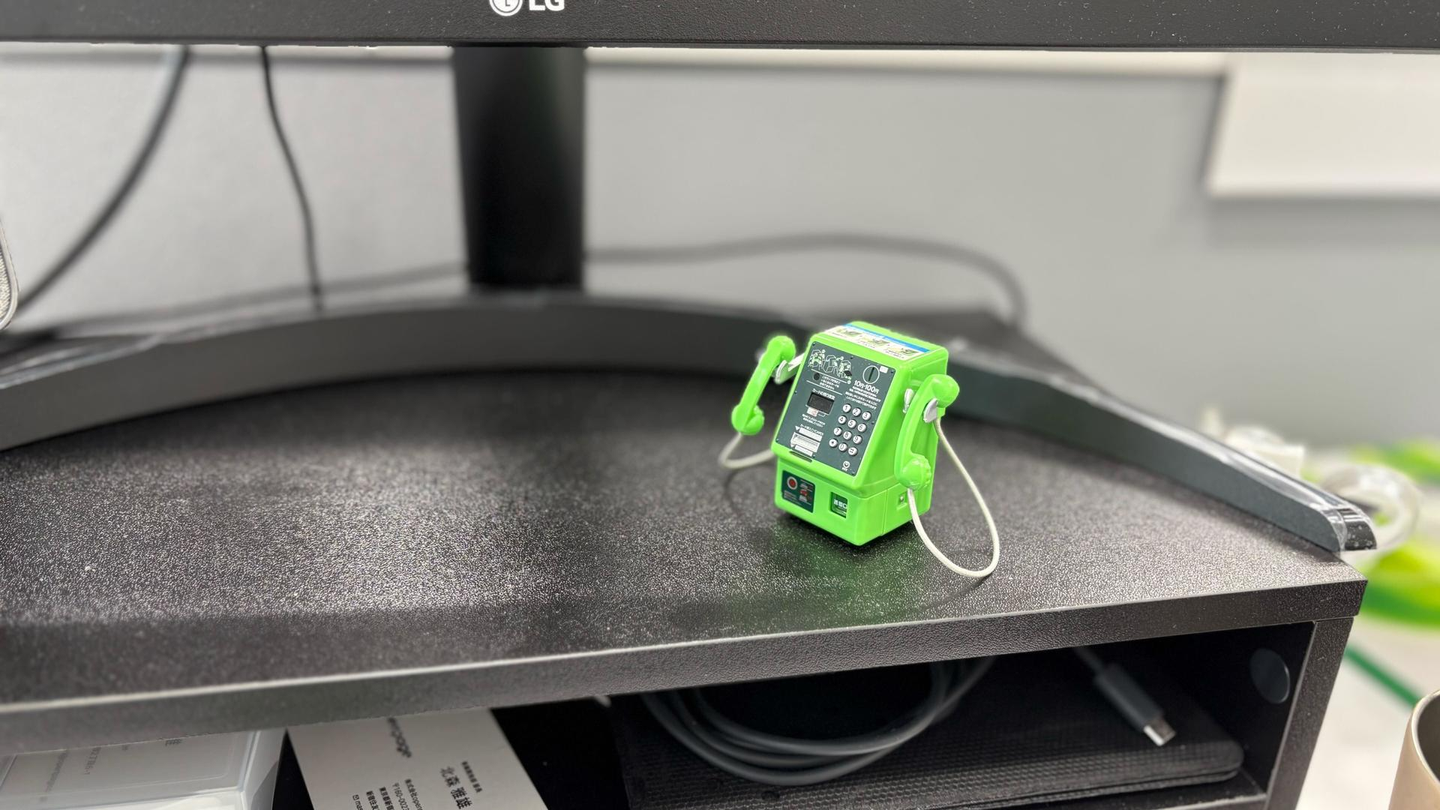
ベンチャーならではの魅力 - 仲間との関係性
ライター:実際にopenpageで働いてみて、どのような点に魅力を感じていますか?
北森さん:一つのテーマを深く、解像度高く追求し合える仲間がいることですね。営業の本質について、表面的ではなく徹底的に議論し、お互いの視点を重ね合わせながら前に進められる。この深い対話ができる環境が、最大の福利厚生だと思っています。
ライター:具体的にはどのような?
北森さん:仲間としてプライベートも含めて夜に食事に行ったり、合宿に行ったり、バーベキューに行ったり、ワーケーションに行ったりしています。そこでも営業変革について熱く語り合い、新しいアイデアが生まれることも多いです。
入社して2ヶ月くらいで自分のやりたいことが実現できる環境だと感じました。同じビジョンに向かって、細部まで妥協せずに追求できる仲間がいるのは本当にいいですね。
openpageのメンバーは、Salesforce、三菱UFJ銀行、ビズリーチなど、各業界のトップ企業出身者で構成されています。それぞれが専門性を持ちながら、営業の本質を科学するという一点に集中して、深く探求している。みんな、自分の経験を社会に還元したいという思いで集まっています。
転職後わずか数ヶ月での実績 - 大手企業との協業の加速
ライター:現在はどのような業務を担当されているのですか?
北森さん:事業開発として、openpageの事業の拡張性を高めるための施策全般に取り組んでいます。具体的には、大手企業とのアライアンス構築、営業ナレッジの体系化とドキュメント化、社内運営の仕組み化を進めています。
特に重要なのは、実際にお客様のところへ足を運んでコンサルティングを行うことです。現場で直接対話することで顧客の解像度を深め、そこから新たな事業領域の種を見つけています。顧客の本質的な課題を理解することが、次の事業展開につながるんです。
ライター:転職後の具体的な成果はいかがですか?
北森さん:新規事業の実証実験から来年度の予算化まで進めることができました。新規開拓先とのアポイントは月20件以上実施し、そこで得た知見を事業開発に活かしています。
単なる営業活動ではなく、それぞれの企業が抱える営業課題の本質を探り、openpageのソリューションをどう拡張すれば解決できるかを考える。この積み重ねが、新しいパートナーシップや連携の仕組みづくりにつながっています。
大きな成果:キヤノンマーケティングジャパン様との協業の加速
ライター:大手企業との連携はいかがですか?
北森さん:入社してわずか数ヶ月で、キヤノンマーケティングジャパン様(以下キヤノンMJ)との協業を大きく前進させることができました。資本業務提携を結んでいるキヤノンMJとの関係において、私は入社後すぐに営業組織への展開を加速させるため、具体的な展開方法について深い議論を行い、スピード感を持って実践に移しています。
このような大手企業との協業を通じて得られる知見も含め、社内では日々の業務から生まれる貴重なナレッジを確実に蓄積する仕組みづくりに注力しています。メンバーが感じる違和感も含めて言語化し、納得できる形に昇華させていく。ただ、こうした知見は放っておくと流れていってしまう。だからこそ、ナレッジをしっかりと止めて蓄積することが重要なんです。
その一環として、Notionを活用したナレッジマネジメントポータルの立ち上げを社内に提案しました。目的を明確に伝え、全社の合意を取り付けて、現在は全社基盤として運用を開始しています。営業の暗黙知を形式知に変えるopenpageだからこそ、社内のナレッジマネジメントも徹底的にやっています。

地方創生への想い - 営業変革が生む社会的価値
ライター:新規事業で、どのような手応えを感じていますか?
北森さん:私たちopenpageの営業の価値観や言語化しているものは、中小企業や様々な組織の人たちが気づいてなかったが実は苦労していることを解決できる手助けのきっかけになります。
「これは実はやってたけど属人的だったんだ」
「当たり前にやってたが、これは確かに重要」
お客様からこんな気づきの声をいただきます。openpageが推奨するアジェンダ作りや議事録での認識合わせといった内容は、実は多くの営業組織の考えと合っている普遍的なものです。共感をすごく得られやすいですね。
ライター:それが解決されると、どのような未来が描けるのでしょうか?
北森さん:事業の伸び悩みや収益を上げられない、経済が進められなかったものをopenpageは後押しができるのです。
地方に行くと収入が下がる、東京より経済が回らない現状がありますが、どの地方でも東京のように経済循環し、地方で働くことを誇りに思えるような未来をopenpageは作れるようになるはずです。
現場視点から生まれる営業変革 - 日本の営業文化を変える
ライター:大手企業からも評価されている理由をどう分析されていますか?
北森さん:よくあるのはトップダウンでツールを入れようとマネジメントしていく構図ですが、openpageは逆のアプローチなのです。現場で何が起こっているかを整理しながら全体設計をしています。
ライター:現場視点とは具体的に?
北森さん:現場視点の営業のプロセス設計です。重要なのは、既存の営業オペレーションを壊さないこと。むしろ、今ある営業活動の中で自然に顧客理解が深まる仕組みを設計しています。
新しい作業を増やすのではなく、日々の営業活動を効率化しながら、同時に顧客の解像度を高められる。例えば、商談の準備や振り返りの時間が短縮される一方で、顧客のニーズや意思決定プロセスがより明確に見えるようになる。結果として、現場の営業担当者が自然に質の高い提案ができるようになっているんです。
これが今まで施策を考える企画の人達がやりたくてもできなかった営業現場の改革をopenpageが実現できている理由です。営業担当が実際にどううまくいくのかの型化、再現性といった営業現場の強い課題意識に対し、現場に負担をかけずに解決策を提示できるのがopenpageの強みです。
日本の営業生産性向上への使命
「日本の営業のあり方を根本から変え、社会全体の生産性向上に貢献することです。これまでの営業は残念ながら属人的すぎました。トップセールスが『なぜ成果を出せるのか』を説明できない。その暗黙知を形式知に変換し、誰もが成果を出せる仕組みを作ることが社会への大きな貢献になるはずです」
openpageの「デジタルセールスルーム」は、営業活動を可視化・標準化し、顧客とのコミュニケーションを最適化します。日本の営業生産性は先進国の中でも低いと言われていますが、それは個人の能力の問題ではなく仕組みの問題です。

プロダクトとナレッジの両輪 - openpageの独自性
ライター:openpageの独自性について教えてください。
北森さん:openpageの独自性は、営業プロセス全体を「顧客との共同作業」として捉え、その実現方法を徹底的に体系化している点にあります。
私たちのカスタマーサクセスでは、お客様の目的を明確に言語化し、その達成までの道筋を設計することを重視しています。お客様が何を達成したいのか、そのためにはどんなステップを踏めばいいのか。次のアクションを具体的に設計してつなげていき、最終的な目的達成まで伴走する。このプロセスが徹底的に体系化されています。
大手から中小企業まで、この考え方に基づいた実践ナレッジがスライドに細かく落とし込まれ、私達も日々学習してお客様へ適切にフィードバックしています。
ライター:プロダクト面での工夫は?
北森さん:プロダクト設計の根底にあるのは「現場が最適に運用できること」です。現場で真に必要とされる機能に集中し、シンプルで直感的な操作性を実現しています。誰もが迷わずに目的地にたどり着ける設計を徹底しているんです。
これはプロダクト本体だけではありません。操作方法を説明する動画、マニュアル、デモサイトに至るまで、すべてに「迷わせない設計思想」が染み込んでいます。製品を使う具体的なユースケースごとに、どんな流れで操作すれば自然に運用に乗せられるか。プロダクトとその周辺のサポートツール全体が、一貫した思想で設計されているんです。
ナレッジの解像度の高さ
ライター:ナレッジの解像度の高さとは?
北森さん:営業の初回商談からクロージング、その後の支援工程まで、どのような流れで、どういうポイントを押さえて話を進めていくか、すべてが体系化されています。
特に私たちが「眼前可視化」と呼んでいる手法があります。商談中にその場で文字を起こしながら、お客様と認識を合わせていく技術です。お客様がふと言った一言を適当に流さず、「それはどういう意味ですか?」と深掘りし、真のニーズを理解した上で最適な提案をしていく。
さらに重要なのは、前向きに導入を検討してくださっている担当者様が、社内で孤立しないようにサポートすることです。担当者様が社内で「いらない」「うちには合わない」「今は必要ない」と言われてしまい、導入意欲が折れてしまわないよう、どのような資料を提供すべきか、どんな論点で社内説得をサポートすべきか。こうした顧客の社内承認プロセスを成功に導くためのナレッジが、openpageには驚くほど細かく言語化されているんです。
すべての仕事に通じるスキル - キャリアの汎用性
ライター:openpageでのキャリアの意味をどう捉えていますか?
北森さん:私たちがやっていることは、どんな業界・職種でも応用できる普遍的なビジネススキルを身につけられるよう設計されています。例えば営業は単に商品を売るだけでなく、相手のニーズを深く理解し、Win-Winの関係を構築し、複雑な利害関係を調整しながらプロジェクトを前進させる仕事です。これはマーケティングでも、カスタマーサクセスでも、アライアンスでも、どんな仕事でも必要とされる本質的なスキルです。
ライター:具体的にはどのようなスキルが身につくのでしょうか?
北森さん:openpageでキャリアを積むことで、ステークホルダーマネジメント、課題の構造化と解決策の提案、データに基づいた意思決定、チームでの協働など、ビジネスパーソンとして必須のスキルセットが高いレベルで身につきます。特に異なる立場の人々の利害を調整し、全体最適を実現する力は、将来どんなポジションに就いても活きる財産になります。
これらはキャリアの基軸となり、さらに新しいことに挑戦する際の強固な基盤になる。それがopenpageで働く大きなメリットだと考えています。
大企業経験者へのメッセージ - 経験を社会に還元する選択
ライター:最後に、この記事を読んでいる大企業の方々にメッセージをお願いします。
北森さん:大企業での経験は、社会にとって貴重な財産です。その経験を、より多くの人に還元できる立場で活かしませんか。
大手で働いていることは他の会社で通用できないと言われがちですが、そんなことはありません。大手で培った「人と共通認識を作り話し合い、協力体制を作ってチームを作り進める」仕事の進め方は、ベンチャーでも非常に役立ちます。むしろ武器になる強みなんです。
ライター:ベンチャーでその経験をどう活かせるのでしょうか?
北森さん:新しい製品、新しい取り組みと大手での経験を組み合わせると、自分の価値は増大します。自分がやってきたことを含めて価値を高め、社会に意味のあるものを作りたい人には、openpageをおすすめします。
私の場合、一人でデジタルマーケティングを立ち上げ、顧客視点でコンテンツを作り続けてきました。その経験があるからこそ、次のステージで社会により大きく貢献できると確信しています。

転職を検討している方へのアドバイス
ライター:この記事を読んでいる方に、具体的にどのような行動をとってほしいですか?
北森さん:まず紙に書き出してみてください。これまでのキャリアで培ってきたスキルや経験、そして今後10〜20年で実現したいことを。いわば社会人としての自己分析です。
今までやってきたことを振り返り、それを踏まえて未来の自分にとっての「Must(やらなければならないこと)」「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」がどこにあるのか。それを言語化していくプロセスは、社会人生の後半をどう生きるかの意味付けをする上で間違いなく役立ちます。
その結果、今の会社でさらに頑張るという選択肢もあるでしょうし、新しい環境に飛び込むという選択肢も見えてくるはずです。もしその中で、openpageが選択肢の一つに入るなら、ぜひ一緒に仕事をしたいと思っています。
今後の展望 - 営業変革で日本を変える
ライター:最後に、今後の展望について教えてください。
北森さん:10年後、『日本の営業が変わった』と言われる時、その変化の一端を私たちが担っていたい。それが、私の新たなミッションです。
入社前は営業の変革だけに目を向けていたのですが、入社すると地方創生の取り組み、地方の中小企業の支援など新しい事業が広がっていて、自分のキャリアがopenpageで活躍できるようになって嬉しいです。
ライター:どのような未来を描いていますか?
北森さん:NTT東日本で培った14年間のすべてが、今につながっています。自治体SEとして現場を知り、新規プロダクト開発で顧客の課題を理解し、デジタルマーケティングで多くの人に価値を届ける方法を学んだ。これらすべての経験を、今度は日本の営業文化の変革に活かします。
openpageで培う営業変革のナレッジを通じて、地方の中小企業が本来持っている力を最大限に発揮できるような支援を続けていきたいです。それが結果的に地方創生につながり、どこで働いても誇りを持てる社会を作ることができると信じています。
そして、この経験を通じて自分自身も経営人材として成長し、さらに大きなインパクトを社会に与えられるような人材になっていきたいと思っています。
北森雅雄さんプロフィール
基本情報
- 1987年東京都生まれ、理系国公立大学院卒業
- 2011年 NTT東日本入社(14年間勤務)
- 2025年 株式会社openpage入社、執行役員候補・事業開発部長
主な実績
- 自治体向けセールス:総額10億円以上の案件創出
- 新規事業開発:AI-OCR・RPA事業で年間ARR5億円達成、10以上のサービスを所掌しARR10億円以上を達成
- デジタルマーケティング:一人から立ち上げ、月26万UU・800件超のリード獲得実現
- 転職後:新規事業予算化、キヤノンマーケティングジャパンとの資本業務提携をリード
株式会社openpageについて
デジタルセールスプラットフォーム「openpage」を提供。「営業とは顧客との共同作業である」という理念のもと、営業の暗黙知を形式知に変換し、日本の営業生産性向上を通じて社会全体の生産性向上に貢献することをミッションとする。
2024年8月にキヤノンマーケティングジャパンと資本業務提携を締結。現在、事業開発、フィールドセールス、カスタマーサクセス、エンジニアなど各ポジションで積極採用中。

/assets/images/21165365/original/3ff4f912-5858-4406-b3ee-8f29caf7faf7?1747810835)


/assets/images/21165365/original/3ff4f912-5858-4406-b3ee-8f29caf7faf7?1747810835)




/assets/images/21165365/original/3ff4f912-5858-4406-b3ee-8f29caf7faf7?1747810835)

