こんにちは。人事課の西山です。
念願だった会長インタビューのリリースがついに叶いました!
前編・後編で『創業当時の想い』から『求める人物像』にまで迫っておりますので、是非ご覧ください。
■創業当初から現在までを振り返って
――事業を立ち上げようと思われたきっかけや当時の心境を、お聞かせください。

幼い頃から農業をなんとかしたいという思いは幼い頃からなんとなくありました。その根幹には無口であまり弱音を吐かない父が「いやあ、農業はしんどかったよ」とよく話していたからです。同様に祖父と話していても辛い生活が続いているように見え、その様子を見て、食べ物を作っている人たちがなんでこんなに苦労をしないといけないのかと考えていました。
このもやもや感をきっかけに東京農業大学へ進学。
明確に農業をなんとかしたいと思うようになったのも大学時代です。
卒業論文の準備で5年後・10年後・100年後日本の農業がどうなるかという予測を、当時の数字データから調べてはじき出した結果、農業をやる人がどんどん減っていき、高齢化率が年々増加し、耕作放棄地が増加し、そして食糧自給率が下がって行くというデータになりました。今まさに農業について言われているのと同じ結果がでたというわけです。
このままでは本当に農業は良くない方向に進むと思い、何とかするためには、ただ農家の数を増やすとか、生産量を増やすということではなく、農業を構造的に変える必要があると思うようになりました。
大学卒業時の就職活動では、農業や食品関係の企業に関心がありましたが、就職氷河期であったことからお声はかからず、一般企業に就職し、約6年間楽しく勤めていましたが、いつかは農業の仕事をやりたいという思いが残っていたため、結婚を機に農業をしようと思い、当時では珍しい男で寿退社をしました。
農業は仕組みが悪いから衰退していると思っていましたが、当時28歳の東京出身の兄ちゃんが田舎で「農業の仕組みが悪い!」と声を上げても聞いてもらえない。まずは現場で農業を実践することが重要だと思い、東京から和歌山へ移り住み義父が営むきゅうり農家に弟子入りしました。

仕事をした正直な感想は「つまらない」。
今まではお客さまや先輩・上司から「ありがとう」と言っていただき、褒められていたので「よし、頑張ろう」と思えていたが、出荷と引き換えに受け取った伝票には「曲がったきゅうり50本、真っすぐなきゅうり50本、合計100本」のみ。「おいしかったよ」「ありがとう」なんて書かれておらず、誰が僕のきゅうりを食べているか分かりませんでした。改めて、感謝されることでモチベーションが上がり、また仕事を頑張る、このサイクルが、仕事の楽しさだと感じました。
2年目からは独立することを考え、ハウスを借りて自分で農業をすることにしました。
しかし、全くうまくいかない。作るのも売るのも半人前の状況では、良い品質の作物ができず、曲がったきゅうりを販売するため、スーパー50件に飛び込み営業をしました。
結果、月収は数万円。しかもこの時期に子どもができてしまい、生活は苦しい状況になりました。
3年目に入り、これでは食べて行くことすら難しそうだったので、東京に戻りまたサラリーマンをやろうかと思っていましたが、その年には、去年注文してくれた人がリピーターになり、自動的に注文が入るようになりました。そして、他の野菜や、漬物、サラダなどの加工品の需要も増え、様々な販売手段が増加。
結果、地元の農家さんより数倍収益が上がりました。相手が欲しているものを出荷する、付加価値をつけるなど、お客様の要望に応えて的確な商品を持っていくことで「ありがとう」が生まれ、成果に繋がり、農業の面白さを実感するようになりました。

――生産から販売に転身した経緯を、お聞かせください。
私の農業に携わるきっかけは、農家で儲けたいからという理由ではなく農業の仕組みを変えたいと思っていたからでした。その第一歩として、スーパーマーケットに自分で営業に行き、要望に応えた商品を持っていくというマーケットインの発想を普及させるなど、自分の考えた仕組みを、和歌山から情報発信したいと考えていました。
しかし農家からすれば、作ることに専念しておけばいい、流通は管轄外という考えです。地方では自分が考えた農業の仕組みを変える工夫を理解してくれるけれども、様々な絡みもあり、なかなか新しいことができる素地がないということを実感しました。これではいくらいい仕組みを考えても、農家という中で仕事をしていたら情報発信はできないと悩むようになりました。
その時、あるご縁で野菜ソムリエ協会から農業経験を活かして、会社を手伝ってみないかと誘われ、大阪の千里中央で八百屋に転身しました。

そこで驚いたのは生産者側と販売者側ではまったく考えが異なることを知ったことです。生産者側は1円でも高く売ろうとしていたのに、逆に販売者側では利益率を考えて農家から安く買い叩いているということでした。
その状況を見て、やはり生産者と販売者を両方関わった人でないと、この水と油の関係を調和させることはできないということ感じました。また、生産するのも販売するのも大変ということを実感しました。
これ以降、生産と販売をつなげることが大事だと考えるようになり、そのような仕事がなかったことから自分でやるしかないと思い、自己資金をかき集めてつくった現金50万円をもって、2007年、株式会社農業総合研究所を立ち上げました。
――起業当初はどのような事業で稼いでいたのですか?
生産者に代わって高級スーパーや百貨店などに農産物を売り込む農業の営業代行コンサルティングのような事業を行いました。具体的には私が農家の方々を訪問して、より買付価格の高い売り先を紹介して関係を構築し、商流ができたらコンサル料を農家の方々から頂くというものでしたが、コンサルティングという目に見えないサービスにお金を支払うという概念がなく、大失敗に終わりました。
困った末に考えたのが、お金の代わりに野菜・果物を頂くという方法でした。そしてそのもらったみかんを大阪や和歌山の駅前でゴザを広げてみかんを売ることで、お金を稼ぐことができるようになりました。農家からお金ではなく農産物を引き取っていくうちに直売所について相談を受けるようになり、それをきっかけに現在の主力ビジネス「農家の直売所」がスタートしました。
「ファーマーズマーケットや道の駅、農産物直売所はいっぱいある。確かにたくさん売れるし儲かるけど土日じゃないと売れないし、車がないとお客さんも来れない。これを何とかコーディネートできないのか。」という意見が数多くの農家から言われるようになりました。それを聞いて私は都会にファーマーズマーケットを出すことを考えたのですが、そのコストを算出したら1億円弱になりました。
しかし資本金は50万円しかない。いろいろなビジネスモデルを考えた結果、スーパーの中に直売所を作って、農家の方が作った野菜、果物、花、お米を、農家が値段を決めて自由に販売し、売上を農家とスーパーと農業総合研究所で分け合うというビジネスモデルを構築しました。
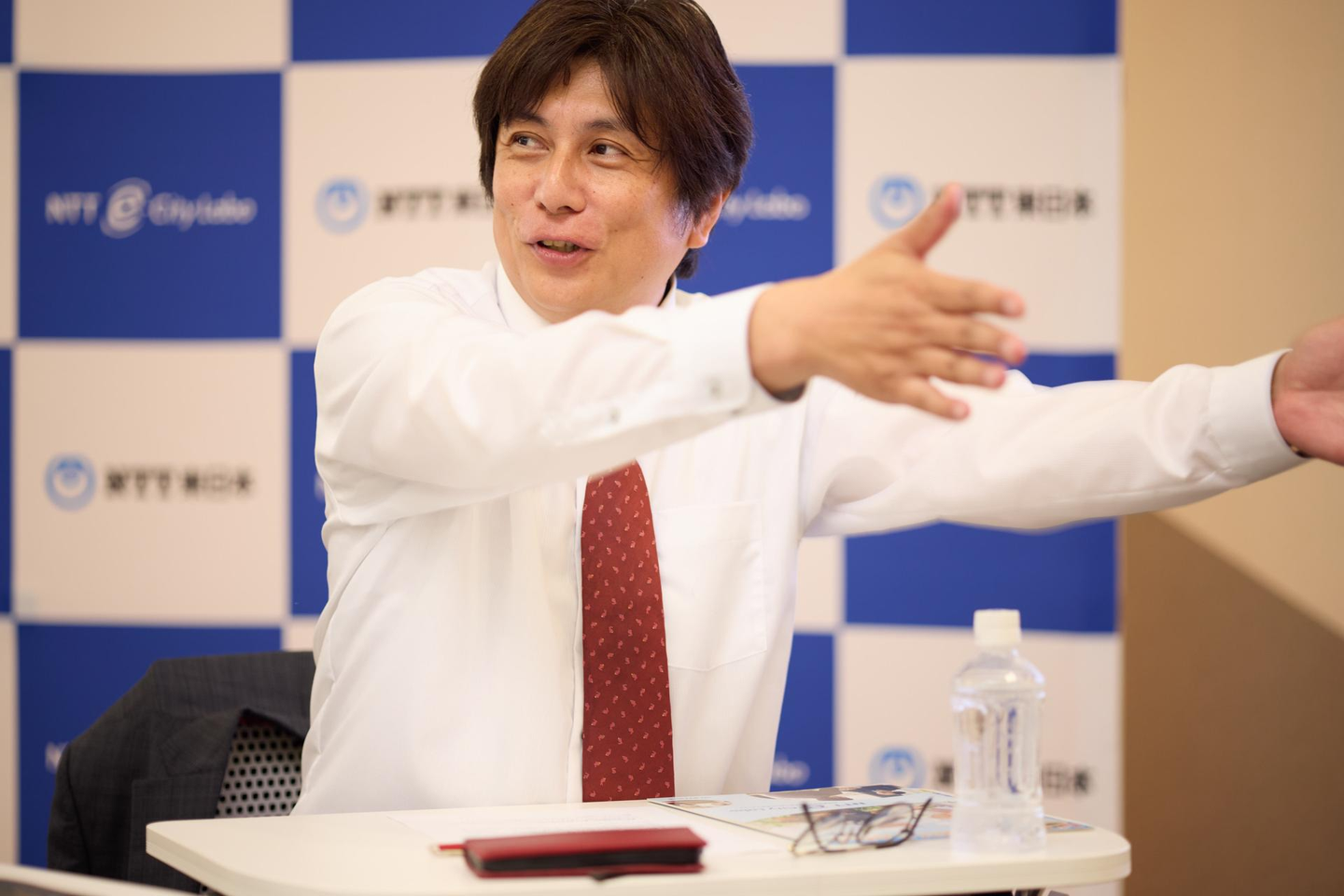
――「農家の直売所」のビジネスモデルをお知らせください。
簡単に言うと、うちのプラットフォームは面白くて、全国に1万人の生産者がおりまして、スーパー2000店舗、これをITと物流で繋いでおります。うちの会社の面白い特徴は、生産者がスーパーで販売したい金額を決められます。多分、こんなことやっているのはうちだけだと思ですけども。本当ですよ!
例えば、生産者が100円で売りたいと思ったら、100円シールを自分で作って、バーコードを自分の商品に貼り付ける。で、もう一つは出荷したスーパーを生産者が好きに選べるんですよ。各スーパーの店舗ごとにコンテナを準備してありますので、その中に商品を入れていただければトラックで運んで売ってあげるという方法です。そんなプラットフォームを構築しました。
そして、委託販売方式というものをとっておりますので、売れないと生産者にお金が入ってこないんです。その代わり、生産者に値付けの決定権を与えている。それで、売れたら、ざっくり言うと売上の70%を生産者に返して、残りの30%を我々とスーパーが分ける。
農産物直売所とJAの流通のちょうど中間ぐらいの流通を作っているというようなイメージです。生産者から見るとJAよりはたくさん売れないけど、JAよりは手取りがいいです。道の駅農産物直売所から比べると、手通りは悪いけど手間が少なくてたくさんあります。ちょうどこの中間、ラインの流通形態を作っているというような、そんな会社でございます。
ビジョンである「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」を実現するためには、このような形で従来の限られた流通形態だけでなく、様々な流通チャネルを形成し、農業者が自立・選択できる仕組みを構築することで、「ビジネスとして魅力ある農産業」を確立して行くことが不可欠と考えております。
農家自身が経営感覚を持ち、主体的に出荷を行うことで豊作貧乏から豊作裕福へと変革させ、未来永劫日本から、世界から農業が無くならない仕組みを作る。これが我々のビジョンであり、私の人生のビジョンです。
~後編に続く~



/assets/images/841342/original/762c014a-16f4-4fa3-9489-2db6fa4ee303.png?1480124270)




/assets/images/21437782/original/762c014a-16f4-4fa3-9489-2db6fa4ee303.png?1750835766)

