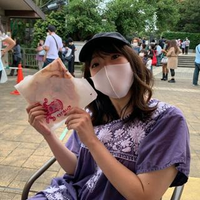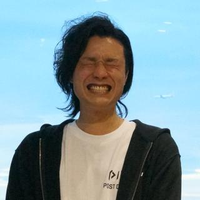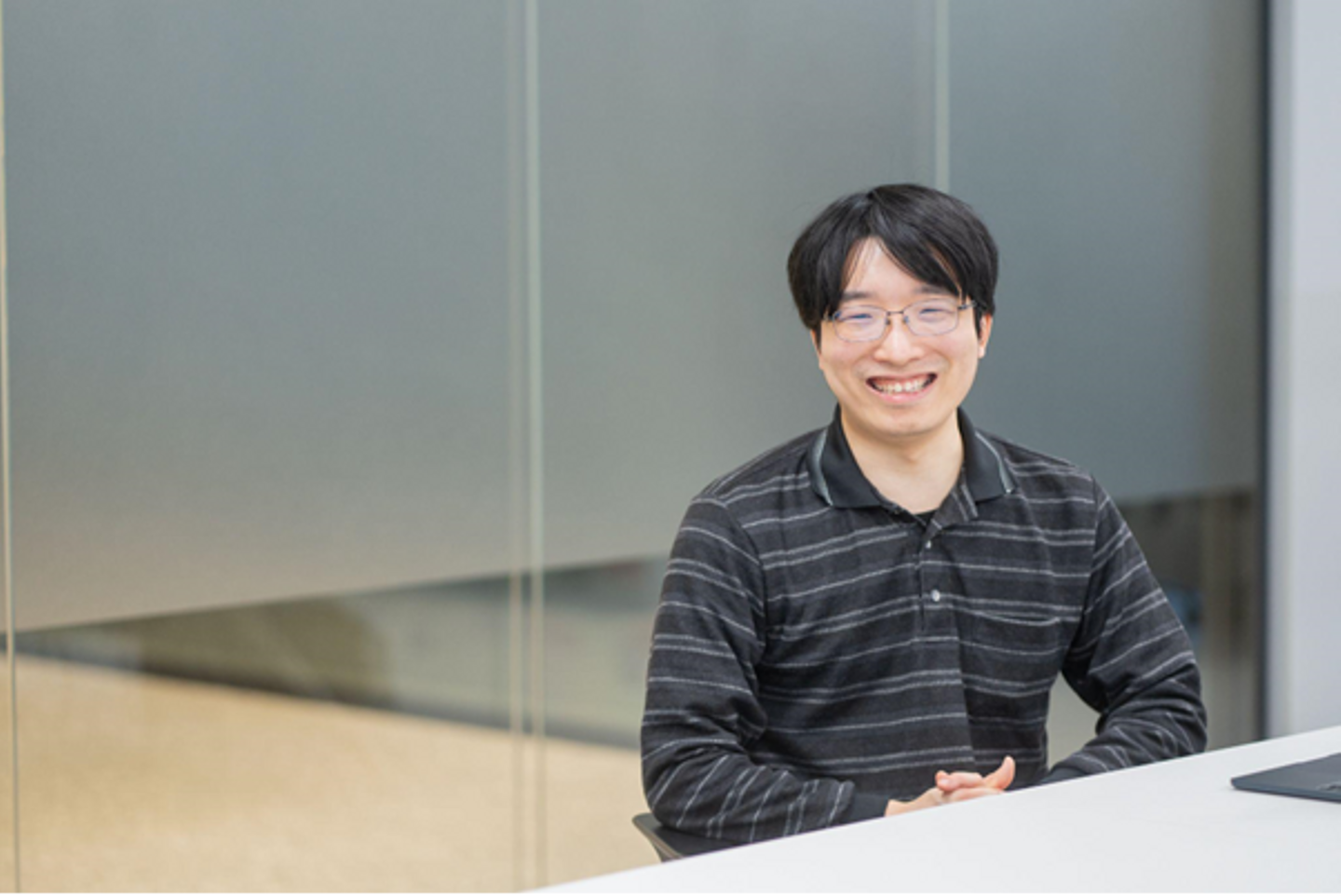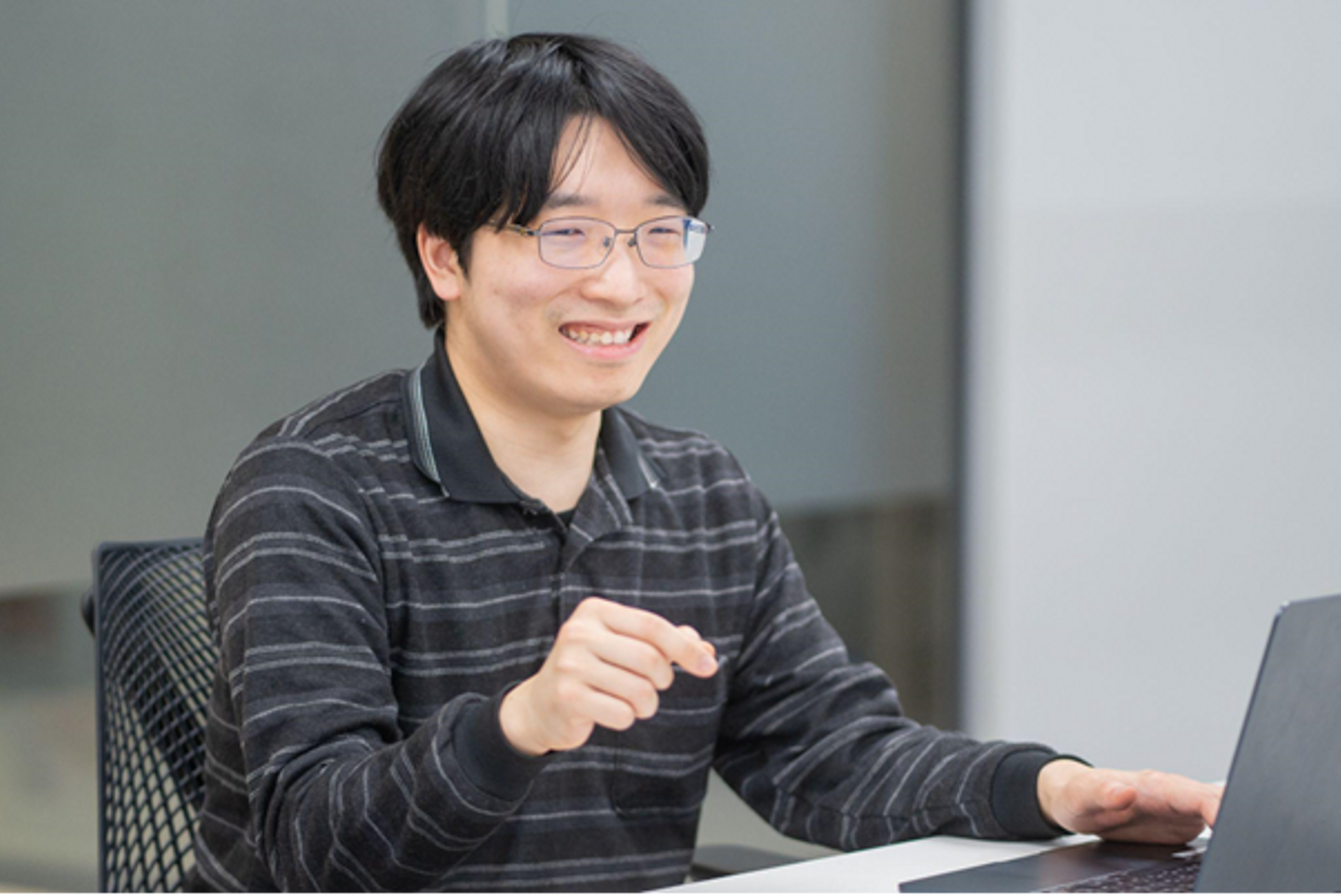- プロダクトグロースエンジニア
- 開発ディレクター
- BIエンジニア
- Other occupations (1)
- Development
- Business
ニジボックスにおける主力事業の一つ「リクルート共創」。その中でも注力するのはリクルートグループのデータ利活用の取り組みへの参画です。今回はデータ利活用を裏側で支える、横断データプロダクト『Crois(クロイス)』の開発運用に携わるPGE(プロダクトグロースエンジニア)の南川さんに、学習意欲の高いエンジニアにとって最先端技術を駆使したプロダクトに携わる醍醐味について語っていただきました。
モダンな技術を実務を通して習得したい
-- まずは南川さんが現在携わっている業務について教えてください
リクルートグループのデータ利活用における、データ処理基盤『Crois』の運用・開発に携わっています。事業をまたいでデータの利活用を可能とする横断データプロダクト として、リクルートのさまざまな事業領域のデータ利活用施策を文字通り裏側で支えているシステムなんです。
-- 南川さんが担当されている開発領域は?
インフラをはじめ、バック・フロントエンドに至るまで幅広くカバーしています。メインはバックエンドで、必要に応じてAWS(Amazon Web Services)などのクラウド周りにも手を出しています。
前職もバックエンド寄りのエンジニアだったのとAWSに触れる機会も多少あったので過去の経験を生かすことができています。ちなみに、入社後はCroisの開発を通して新たに、GCP(Google Cloud Platform)や Kubernetes、TerraformなどのIaC ツールに業務としてはじめて触れたんです。
フロントエンド開発ではVue.jsを、バックエンド開発ではPythonを、フレームワークはDjango REST Frameworkを使っています。インフラ周りはAWSとGCPですね。AWSのサービスではLambda、Step Functions、ECS、CodeBuildなどを主に利用しています。他にも関連する新しい技術はいくらでもあると思っていて、個人的に調べながら知識を深めることも楽しんでいます。
-- エンジニアとしての経験は何年ですか? なぜ転職を?
今年(2025年)で6年目になります。前職は事業会社でバックエンドを中心にスキルを磨き、その後レガシーなシステムの刷新などにも携わっていました。
前職でも一定の学習機会はありましたし、勉強会で学んだことを実務を通してシステムに落とし込む場面もあり充実してはいたのですが、ある程度の経験を積んだ時点でそれまでに得てきた技術や知識が他の会社でどれぐらい生かせるものか試してみたくなったんですよね。
また、転職にあたってはさらに、前職と同等かそれ以上に学ぶ機会がほしいという気持ちもありました。できたらモダンな技術を実務を通して習得できたら理想的だなと。
難易度の高いプロダクトにこそ感じるやりがい
-- ニジボックスを知ったときの印象はどのようなものでしたか?
リクルートの多様な事業のデータ利活用の取り組みに関われることに惹かれましたね。なんといってもスケールが大きい。事業規模や社会へのインパクトなどからプロダクト運営の現場を想像するだけでワクワクしました。
働く環境に求めていたのは新しい技術や知識をエンジニア同士で共有して、スキルを高め合いながらプロダクトの開発や改善に努めていく、といったカルチャーです。求人情報や従業員のインタビュー記事などを拝見し、それがニジボックスならかなえられるんじゃないかという期待をもって入社しました。
-- はじめてCroisを見たときの感想はどんなものでしたか?
素直に驚きました。システムとしてのレベルも完成度も極めて高く、特にジョブの実行ロジックが優れていて、ユーザーにとってかなり使いやすいように作り込まれているなと思いました。多くのユーザーが使う基本機能の Web UI の最適化をはじめ、コアなユーザー向けにWeb API やワークフローの設定を管理できるように IaC ツールも用意するなど、使い勝手を重視した細かな配慮の数々には本当に驚かされました。
-- 利用者の体験価値と生産性が向上しそうですね
よく使われる処理はあらかじめモジュール化されているので、リクルートの従業員はすぐにCroisを使い始めることができます。もちろんカスタム処理が必要な場合はユーザー自身でモジュールを作成することも可能。さらに、コンテナのログやメトリクスがAmazon CloudWatch と連携している点も開発や運用のしやすさに寄与していると思います。
プラットフォームエンジニアリングへの取り組みは運用コストの増加を抑えるだけでなく、いわゆる持続可能な価値の提供を実現していると思います。
こういったプロダクトをつくるのは非常に難しいのですが、一エンジニアとしてとても魅力に感じます。
-- 難しいプロダクトだからこそ魅力を感じると
そうですね。触れるほどに興味が深まるとともにワクワクしてきます。私もまだまだ全容を把握できているわけではありません。どこをどれだけ掘っても飽きがこないプロダクトだと感じています。
-- 現場に入ったのは入社後かなり早いタイミングだとか?
配属は入社翌日で、そこから2週間ほどはオンボーディングでした。内容としてはCroisのドキュメントを見ながらチュートリアルをこなしていくものが中心。メンターから最初にどこをメインに触っていきたいかを聞かれたんですね。私は全体をまんべんなく触りたかったのでその旨を希望したら、フロントからバックエンド、インフラまでひと通り経験させていただけることになったんです。
タスクそのものは割ととっつきやすいものばかりでしたが、実装からリリースに至るまで開発全体の流れを体験できました。これはありがたかったですね。そのままオンボーディングと同時並行で現場にジョインしました。
-- 豊富な開発経験のある南川さんなら比較的スムーズに慣れていったのでは?
入社当初は少なからずプレッシャーを感じており、良い意味での緊張感を持って業務に取り組んでいました。ひと息つけたのは2ヶ月目ぐらいにメンターからタスク処理の正確さと速さを褒めていただいたときですね。これなら大丈夫、やっていけそうだと確信を持つことができました。
レベルの高いエンジニアに追いつき、追い越せ
-- 学ぶスタイルはニジボックスで変化しましたか?
あくまで主体的に学んでいこうという姿勢は変わっていません。実際のソースコードを追いながら、ちょっと分かりにくいところがあればドキュメントとひもづけて理解するよう努めています。Croisチーム内で開発者用のドキュメントが整備されていてロジックもまとまっているんです。
もともとニジボックスは学ぶ機会に恵まれていますが、個人的には実務そのものにも学びの場が豊富にあると感じています。作業の上で新たに習得しなければならない技術が次々と出てくるんですが、その都度ドキュメントを参照しながら学びを深めています。
-- 周囲のサポートといった面についてはどうですか?
前述の通り基本的に自分で調べて自分で解決するスタイルではありますが、それでも不明な点があれば毎週開催される「よもやま」という、担当の方とフラットに何でも話せるミーティングを有効活用しています。そこではリソースをチェックしたり進捗を共有するとともに、困ったことの相談もできるんです。また、「よもやま」で伝えきれなかったことや緊急で対応が必要なことはSlackでも相談するんですが、レスポンスがかなり早くてどのような問題でも割とスムーズに解決しています。
その他にも輪読会をはじめLT会や各種ワークショップ、開発合宿など学ぶ機会が豊富にあることは向上心や学ぶ意欲が旺盛なエンジニアにとって非常に魅力的です。ニジボックスの学習環境はかなり充実していると思います。
-- 同じチームのエンジニアにはどのような印象を?
かなりレベルの高い方がそろっています。はじめてGCPを触ったときにつまずいた箇所があったのですが、そのことをSlackで相談するとすぐに有識者の方から回答いただきました。またメンションを付けていない方からも親身で詳細なアドバイスをいただけることもあります。エンジニア同士という観点で、垣根なくフレンドリーにコミュニケーションをとれる雰囲気がとてもいいですね。
-- 南川さんにとってニジボックスへの転職はキャリアに大きなプラスとなったようですね
難易度の高いプロダクトを手掛けることで技術力や知識に磨きをかけたいエンジニアにとってチャレンジする価値はあると思います。
一つ新しい知識を得たら二つ未知の世界が増える。そんな飽きることのない環境でこれからもエンジニアとしての腕をアップデートしていきたいと思います。
□Croisについて詳しい紹介がされている参考記事:Recruit Data Blog『AWS Innovate にて内製データ基盤 Crois のプラットフォームエンジニアリングの取り組みを発表しました』