DEI担当執行役員の永井さんと学生インターン須田さんの対談【後編】です。
前編ではイベント登壇を振り返りましたが、今回はより実践的なテーマでの対談です!「多様性」の視点を、日々のデザインプロセスにどう組み込んでいくのかを深掘りします。
誰もが取り残されないサービスを生み出すためのヒントが詰まっています。ぜひ最後までご覧ください!
▶︎前編をまだお読みでない方はこちらから
※この記事はSERVICE DESIGN BLOGの転載です
ニューロマジックのDEIの中核を担う、DEI担当執行役員の永井菜月さんへのインタビュー。前編では学生インターンの私、須田桜子が、2024年9月に虎ノ門ヒルズで行われたトークイベント「Hills Breakfast」に永井さんが登壇された際の内容を振り返りながら永井さんに「多様性」についてインタビューしました。
デザインにおいても多様性が注目されるようになった一方で、実際のデザインプロセスに多様性をどう取り入れるかについては、現場では試行錯誤が続いています。
後編では、共創の場作りやターゲット設定における視点の持ち方、そして多様性を実践するデザイナーとして持っておきたい心がけについて、話を伺っていきます。
■永井 菜月(ながい なつき)
上智大学院グローバルスタディーズ研究科卒業。2018年当社入社。サービスデザイナーとしてユーザーインタビューなどの企画・実施から、調査結果を基にしたサービスの体験設計やブランドデザインを担当。 2020年よりチームリーダーとして育成や同グループの事業づくりにも携わる。また学生時代から多様性やEquity(公平性)について関心を持ち、修士課程では米国のマイノリティコミュニティを研究。2022年よりDEI担当執行役員。2024年5月より現職。
共創の場をつくるサービスデザイナーの役割
近年では、従来のデザインプロセスで除外されてきた人々を取り入れ、製品やサービスをより良くすることを目的とした『インクルーシブデザイン』という領域も登場しています。このように、デザインが社会に対して適切に機能するためには「誰のためにデザインするのか」を考えることが非常に重要です。デザインの力を活かして社会をより良くするために、サービスデザイナーはどのような役割を担っているのでしょうか。
須田:従来のデザインプロセスで除外されてきた人々について、私たちの普段の生活のなかでその実態や、彼らに対して社会が抱える課題に目を向けるきっかけを見つけるのはなかなか難しいですよね。
永井:特定の人々が不都合を感じているような社会課題の認知を広めること、そして行動に移し、解決に結びつけていくということは人類の永遠の課題だと感じます。
サービスデザインが特に発展している欧州のデザインプロセスで参考にしたいと思うのは、産官学のプロジェクトがとても多いということです。欧州では地域の課題などに対して企業や地域住民、自治体、大学等が一緒に解決するために新しいプロジェクトが立ち上がり、そこにデザイン会社も参画していて、デザインの力で社会課題を解決しながら上手くマネタイズしている事例もあるんです。
日本においてもこのような潮流が徐々に高まってきていて、ニューロマジックと同業界のデザイン会社が社会課題に向き合うような産官学のプロジェクトも実施されているケースがすでにあります。サービスデザインのアプローチにおける「ユーザー視点で何をすべきか」を紐解いていくという思考法は、社会課題に対しても有効的な方法でもありますし、全体として社会課題の解決に関心の高い人が多い業界でもあると思います。
須田:デザインを考えるうえで、視点の中心となるユーザーも社会の枠組みのなかで生きる人だからこそ、ユーザーに考慮するために社会課題に目を向けることは必然的なことなんですね。当事者だけで考えるのではなく、それぞれ異なる得意分野を持つ人を巻き込みながら考えられると、巻き込まれる側も社会課題について考えるきっかけにもなりそうです。
永井:多様な視点を持った人々で共創することで、優れたアイデアに最短距離で近づけるとよく言われていますが、産官学のプロジェクトをやるとしても、例えば研究所の人たちの観点とエンジニアや市民の観点は、お互い専門領域も知識量も違うから、なかなか意思の疎通ができないみたいなことってあるあるだと思うんです。
私の先輩のサービスデザイナーがよく話していたのは、「サービスデザイナーはその共通言語をつくる人になれる」ということです。
例えば、ペルソナやカスタマージャーニーマップなどのサービスデザインのツールは視覚的に優れたツールですし、共創する過程で知識も共有されていきますよね。何か課題を解決しようとして多様なステークホルダーが集まる共創の場を円滑にできる存在として、サービスデザイナーは媒介者になれるのだと思います。
株式会社ニューロマジック「DESIGN SPRINT SEMINAR」より
デザインプロセスでの「当たり前を疑う思考」
サービスデザイナーが共創の場を円滑にする媒介者として、社会課題の解決に貢献するプロセスを振り返ってきましたが、デザインプロセスの中核ともいえるターゲット設定においてはどのような視点が求められるのでしょうか。そこでは「当たり前を疑う思考」が鍵となるようです。
須田:商品やサービスを生み出すビジネスでは、明確なターゲット設定が求められます。しかし、よりインクルーシブなデザインが重視されるなかで、ターゲットを定める際にはどのようにバランスを取れば良いのでしょうか?
永井:商品やサービスを必要とするであろう人に「こういうものがあるよ!」ときちんと伝わらないと意味がないので、ターゲットを定めることが排除に繋がるかというと、必ずしもそうじゃないと思うんです。
ターゲットを特定する場面で、サービスデザイナーの手腕が問われるところだなと思うのは、ターゲットを策定する際に何らかのステレオタイプ的なものに引っ張られてしまうことがないように、「当たり前を疑う思考」をワンクッション持っておくことです。
須田:確かに…! 伝えるべき人に正しくメッセージが届くことがとても重要で、そのアプローチは実はいろいろありますよね。私自身もはっとさせられました。ここでも「当たり前を疑う思考」がキーポイントになるのですね!
永井:商品やサービスによって、その領域の当事者のことについてリサーチするにはある程度ターゲットを絞らないといけないですし、当事者に十分に共感するためにも絞ることは全く悪ではないと思います。でも、一義的な価値観や時代的にアップデートされてない価値観をもとにターゲットが絞られないように、策定する側が意識することが大事ですね!
柔軟なチーム編成で当事者の思いを形にする
課題に応じて適切なソリューションを組み立てていくためには、その意思決定に関わるチームの編成も重要です。影響を受けている当事者の思いを汲み取り、デザインに反映させるためには、どのような共創が有効的なのでしょうか?
須田:先ほどの話とも重なりますが、何らかのデザインプロセスにおいて多様な視点を持った人々で共創することは、アイデアの偏りを減らすという点でもとても魅力的だと思います。
私が大学でとある制作プロジェクトを行ったときに、同年代の女性メンバーだけのチームを組んだことがあるのですが、このようなチーム編成だとメンバー同士の共感は得やすい反面、ターゲットも自然と同年代の女性に限定されたりと、制作の初期段階で自分たちのアイデアの偏りを感じる瞬間がありました。
永井:デザインする側が多様な視点を持った人々で構成されることはとても大事なことですが、一方で何らかのセンシティブな課題を持っている人に向けたソリューションを創るときは、当事者が安心できる環境で課題について語り合えた方が良いと思うし、そういうときは不必要に多様性を取り入れる必要はないと考えています。
例えば私の興味領域になりますが、「フェムテック」という女性の健康課題をテクノロジーで解決する産業領域があるんです。女性特有の健康課題によって女性の生活自体に苦労が多いように、特定の属性の人が困っているけど永遠に解決されない課題って社会に多く存在していると思います。
そういう課題はある意味イノベーションの源泉だったりして。その場合は当事者同士で語ったり発散してもらったからこそ、特定のセグメントでの課題が解決されるっていうパターンもあるんです。
須田:私自身、多様性とデザインを結びつけて考えようとすると、デザインする側は多様な視点を持つメンバーで構成されていた方が良いのではないかと考えてしまいがちでした。
永井:課題のソリューションについて考える際は「誰の困りごとを解決したいか」や「どういう課題に向き合いたいのか」といった場面ごとに、多様なメンバーを組むべきか、それとも特定の属性に当てはまったメンバーを集めるべきかが変わってくると思います。
須田:課題を取り巻く状況に応じてアサインするメンバーを調整することで、当事者の健康や幸せに最短距離で到達できるようなソリューションを考えることができるのですね。
多様性を実践するためのコンテクストの理解
ここまで「多様性の実践」をデザインに反映させるプロセスのあり方について永井さんとお話ししてきましたが、そもそも「多様性」という言葉の捉え方が人それぞれであるからこそ、そのプロセスを踏むうえでは気をつけなければならないこともあります。
永井:私は「多様性の実践」に向けた施策を考えるうえで、「歴史的、社会的なコンテクストを踏まえて筋が通っているか」ということをいつも心がけています。こういったことがきちんと踏まえられていないと、変えるべき社会問題を無意識に継承してしまったり、または特定の属性の人々のための施策が逆差別に繋がってしまったりすることもあります。
今後、須田さんも課題に対するソリューションを考える場面があるかもしれないけれど、そのときには定めたターゲットが置かれた歴史的、社会的な課題をできるだけ理解しようとすることがとても重要になると思います。
須田:歴史的、社会的なコンテクストを踏まえるということは、永井さんが大学院で文化人類学を専攻されたように人文科学系の学びもサービスデザインの重要な要素になるのですね。
永井:そうなんです!クライアントにニューロマジックの強みをプレゼンするときには、ニューロマジックには人文科学系に興味関心があったり、長くそれらを勉強してきたメンバーがいたりすることも挙げています。
社会に対してサービスがどうあるべきかを考えるときには、目の前にいるユーザーに一義的に目を向けるだけではなくて、歴史的、社会的なコンテキストとしてその人たちがどういう状況に置かれているかまで考えることが、サービスデザイナーに限らず、デザイナーの本当の価値だと信じています。
須田:私もインターンを通してサービスデザインに携わることで、人と社会の関係性を捉える視点から、大学で専攻している社会学との関連性をしみじみと感じていました。
学びを深めることで、ユーザーが抱える本質的な問題に気づき、適切なソリューションを提案できる力を養っていきたいです!
おわりに
後編では主にデザインにおける「多様性の実践」について取り上げてきました。
デザインという領域自体に正解がないように、デザインにおける「多様性の実践」にも一律のアプローチがないなかで、デザイナーは何か不便を感じている当事者の意見を汲み取り、デザインの力で課題を解決するという使命を持っています。
今回の対談を通して、デザインの現場に多様性をもたらすうえで、課題を取り巻く状況に応じてデザインの手法や参画する人を調整するといった「柔軟な思考」と、より多くの人にそのデザインに共感してもらうための「明確な根拠」を持ち合わせる必要があると実感しました。これらはデザインに携わる人だけでなく、加速度的に変化を遂げる現代社会を生きるすべての人に今求められていることではないでしょうか。
前編と後編を通して永井さんと対談させていただきましたが、「多様性」という言葉が話題に挙げられる昨今、私は社会の一員として何をすべきかを明確に掴めずにいた状態から、対談を通して「多様性の実践」を紐解いていき、少しずつ自分が起こせそうなアクションを見つけられたように思います。
永井さん、ありがとうございました!
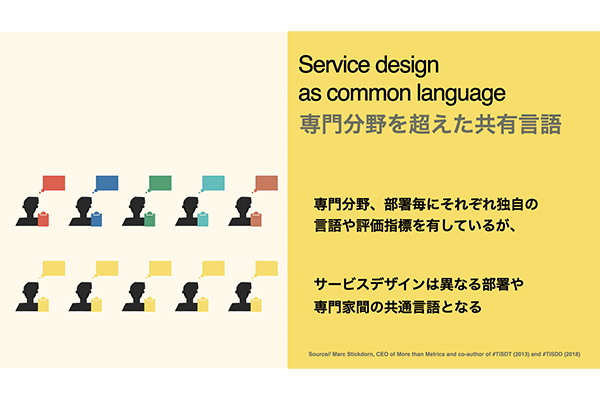

/assets/images/5579099/original/a999b3a9-39a0-4405-b18c-e53691d6e95a?1601289726)

/assets/images/5579099/original/a999b3a9-39a0-4405-b18c-e53691d6e95a?1601289726)
