目次
――まずは自己紹介をお願いします。
――neoAIに入るきっかけを教えてください。
――入社前のイメージと実際に入ってみてのギャップはありましたか?
――これまでどんなプロジェクトを経験してきましたか?
――今までで一番成長したと感じた瞬間はなんですか?
――どんな時にやりがいを感じますか?
――neoAIのカルチャーや魅力について教えてください。
――どんな人がneoAIで活躍できると思いますか?
――今後の展望を教えてください。
――AI業界で働く魅力について聞かせてください。
――最後に読者に向けて一言お願いします。
――まずは自己紹介をお願いします。
東京工業大学改め東京科学大学の修士1年の糸陸哉です。来年留学に行く予定なので、来年も修士1年なんですけど(笑)。
情報理工学院の情報工学科知能情報コースに所属しています。neoAIには2023年12月に入社しており、だいぶ古参メンバーになってきましたね。

――neoAIに入るきっかけを教えてください。
大学2年生の夏頃にX(旧Twitter)でMidjourneyの記事が流れてきたんです。深津さんのnoteで「悪魔の実がメルカリで買えるくらいすごい」って表現されてたんですよ。ほんとにワンピースの第1000話を読んでるくらいめちゃくちゃ興奮した記憶があります(笑)。
その時くらいからAIの勉強を始めて、学部3年の夏頃には「せっかく勉強したし、実際に活かす機会が欲しいな」と思うようになりました。AI軸でインターンを探していたところ、WatedlyでneoAIを見つけ「まずカジュアル面談で話だけでもしてみよう!」と思い応募してみました。カジュアル面談の中で雰囲気がすごく良くて、学生に大きな裁量を与えてくれる環境だと聞いて、「ここだ!」と思い、入社を決めました。
実は後から聞いて知ったんですが、僕はWantedly経由での初めての採用メンバーだったみたいです。最初は知り合いがいなくてちょっと緊張していたんですが、気づいたらすぐにみんな仲良くなっていました。ご飯に行ったり、仕事の話をしたり、気さくで優しいメンバーばかりで、すぐに馴染めました!
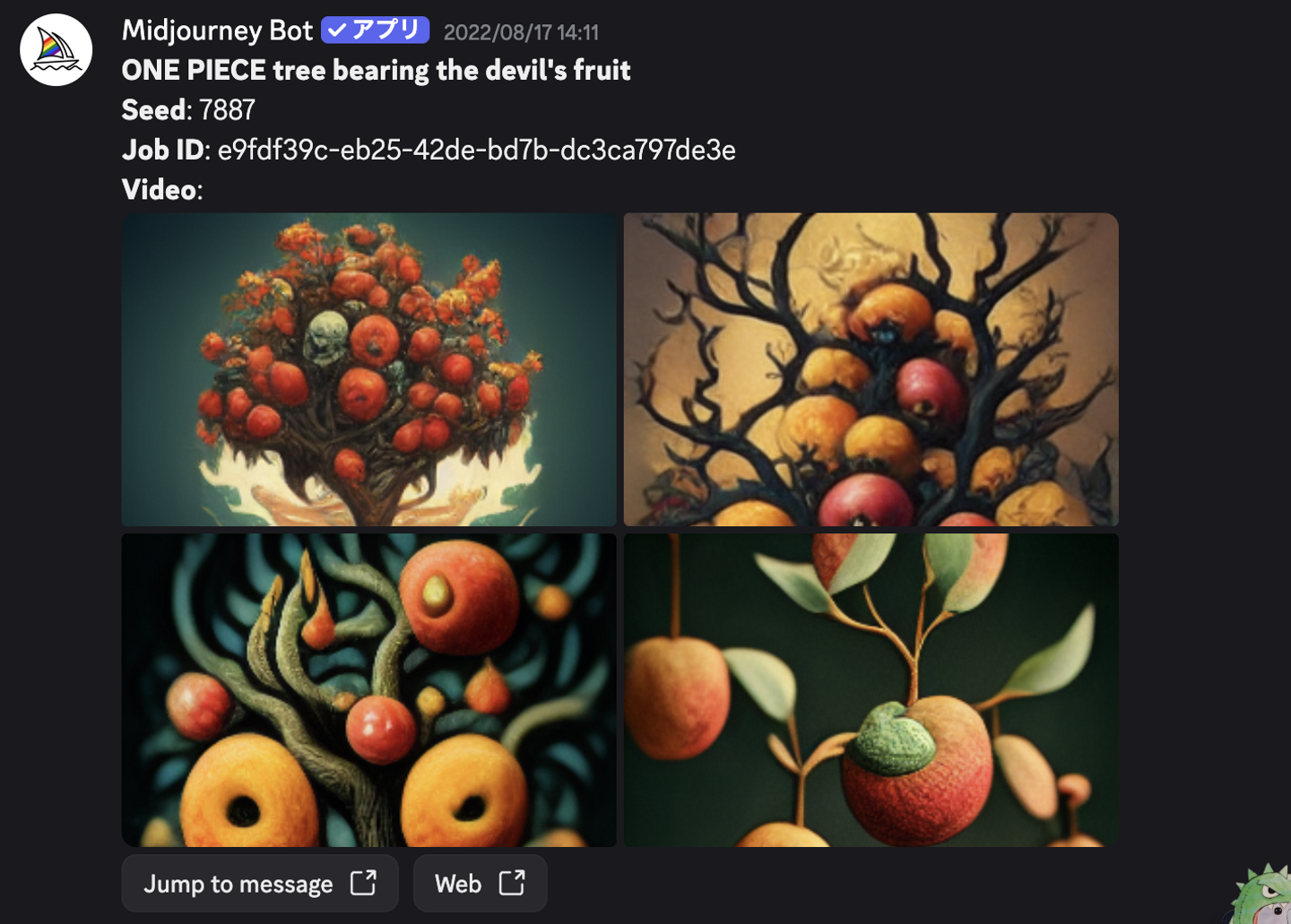
※糸が2022年に実際にMidjourneyを使って生成した画像
――入社前のイメージと実際に入ってみてのギャップはありましたか?
正直、学生の裁量の大きさには本当に驚きました!エンジニアインターンって、データクレンジングみたいな地味な作業をやらされるイメージだったんですけど、neoAIではそういった細かい作業のところだけじゃなくて、プロジェクトのコアになるような検証・実装を任せてもらえるのがすごく魅力的でした。さらに、そういった技術面のところだけではなく、学生がマネージャーまでやってるんですよね。
「これやりませんか!」と提案すると、「じゃあやろうか」って言ってもらえる風通しの良さがあるんです。一人一人が会社作りをしていこうというカルチャーもあるので、バックオフィス系の業務も任せてもらえます。僕は資格取得の支援制度や学生向けの長期休暇制度の運用に携わったりしました。
――これまでどんなプロジェクトを経験してきましたか?
一番印象深いのは、neoAI Chat(自社プロダクト)をお客様向けにカスタマイズ開発するといった、システム開発を一から行うプロジェクトでした。
プロジェクトの前半は要件定義書の作成がメインで、後半は先方とのコミュニケーションを僕がメインで任せてもらえることになって。システム開発を一からやるのは僕にとっては初めての経験で、「要件定義書って何?」「総合テストって何?」という状態からのスタートでした。
でも、この経験を通じて「未知のタスクに取り組む力」が身についたんです。1年前は知らないタスクが来ると思考が固まって動けなくなっていたんですけど、今は「とりあえずAIを使って調べて、手を動かしてみよう」って前に進められるようになりました。
特にAIの使い方が格段に上手くなったと感じています。例えば、要件定義書を書いていて「非機能要件の可用性要件」とか「セキュリティ要件」みたいな知らない専門用語が出てきたとき、AIと対話しながら理解を深めていくんです。「この用語の意味は?」「具体的にはどんな例がある?」「今回のプロジェクトだとどう適用すべき?」って、段階的に質問を重ねていくことで、表面的じゃない本質的な理解ができるようになりました。
要件定義書を作成するときも、まずneoAI Chatに一般的なテンプレートを聞いて、そこに今回のプロジェクトのコンテキスト、例えばお客様の業界特性とか、既存システムとの繋ぎ込みなどを詳しく入力して、プロジェクトに最適化された情報を引き出すようにしています。AIをただの検索ツールじゃなくて、思考のパートナーとして使えるようになったことが、未知のタスクでも怖がらずに取り組める自信につながっています。
neoAIにはAIを使いこなしている人が多いので、その使い方を見て学べる環境があるのも大きかったです!周りの上手い人たちの仕事のやり方を見て真似したり、自分の働き方を常にアップデートし続けることの大切さを学びました。
――今までで一番成長したと感じた瞬間はなんですか?
実は最初に所属したプロジェクトで、自分でも少しずつAIエンジニアとして活躍できるかも!?と思っていたタイミングで新しいプロジェクトにアサインしてもらったんです。ただ新しいプロジェクトでは、今までと使っている技術やプロジェクトの進め方が全く別物だったため今まで培ってきた自分の力が通用しないことに気づいてしまったんです...
でも先述したプロジェクトでの活動を通じて、自分の能力がいろんなプロジェクトにどんどん汎用化していったのを実感しています。今では基本的にどんなタスクを振られても「大丈夫だな」って思えるようになりました。
技術的な面では、AzureやGCPみたいなインフラを触れたのは大きかったです。一般の学生だとなかなか触る機会がないと思うんですけど、プロジェクトを通して実践的に学べました。 最初は「とりあえずデプロイできればいいや」くらいの感覚だったんですけど、実際にインフラを構築していくうちに、サービスがどうやって動いているのか、その裏側の仕組みまで理解できるようになりました。テックブログとかで読んだ知識が、実際に手を動かすことで「あ、こういうことだったのか!」って腑に落ちる瞬間がたくさんありました。 そうやってインフラの知識が深まると、今度はSaaS全般の仕組みが見えてくるようになったんです。点だった知識が線でつながって、最終的にはシステム全体をアーキテクチャレベルで考えられるようになりました。大学の授業だけでは絶対に得られない、実践的な理解が身についたと感じています。

――どんな時にやりがいを感じますか?
一番やりがいを感じるのは、自分たちの仕事が実際に世の中で役立っている瞬間です。先日、ANA様のプロジェクトのプレスリリースが日経新聞に載ったんですけど、自分が必死に取り組んできたシステムが、実際にお客様の業務を劇的に改善しているんだって実感できた時は、本当に嬉しかったです。

あと、自分の成長を実感できる瞬間も最高です!朝出社したら必ずその日のタスクを全部書き出して、終わったものから一つずつチェックをつけていくルーティンがあるんです。で、たまに過去のタスクリストを見返すと、やれること、できることが増えたなと感じます。 以前は1日かけてやっていたタスクが今では半日で終わったり、当時は手も足も出なかった技術的な課題が今では当たり前にこなせていたり。量的にも質的にも、明らかにレベルアップしているのが目に見えて分かるんです。この「昨日の自分を超えた」っていう実感が、毎日のモチベーションになっています。
プロジェクトが無事に終わって、お客様と会食する時も特別な瞬間ですね。「お互い大変だったけど、本当にいいものが作れましたね」ってお客様から言葉をもらえた時の達成感は格別です。なんていうか、文化祭の打ち上げみたいな感じなんですよ(笑)。みんなで一つのものを作り上げて、それが成功して、喜び合える。そういう瞬間があるから、また次も頑張ろうって思えるんです。

――neoAIのカルチャーや魅力について教えてください。
一番好きなのはShout-outとワーケーションですね!Shout-outは、この一週間頑張った人に対してneoAIの行動指針(※1)に則って感謝の気持ちをSlackのメッセージで伝えるカルチャーです。直接感謝を伝えるのって気恥ずかしいじゃないですか。でも制度があるから、恥ずかしがらずに自然に言えるんです。特に自分がロールモデルにしている人や上長から「ANA Buildのパフォーマンスが素晴らしすぎて毎週驚いてます!糸くんなしでは考えられないプロジェクトなので引き続き頑張りましょう!」って言われた時は、本当に嬉しかったです。
あと、一人一人が持つプロジェクトの裁量、ひいては社会への影響が大きいことが大きな魅力ですね。 大企業だと大人数プロジェクトの一部しか関われないことが多いと思いますけど、neoAIならプロジェクト人数が少人数なので、自分の仕事が直接価値に繋がっている実感があります。 また、クライアントが日本を代表するようなエンタープライズ企業なので、僕たちの日々の活動が社会に大きなインパクトを与えているのを日々実感しています。学生でありながらこのような経験を積めることは貴重なことだと感じています。
会社自体も急成長していて、僕が入った時は20人もいなかったのが、今や100人規模になっています。来年はどうなってるんだろうってワクワクしますね!

――どんな人がneoAIで活躍できると思いますか?
シンプルに言うと「ポテンシャル」ですね。実務経験はなくても問題ないです。AIがすごく賢くなっているので、実務経験よりもポテンシャルの方が重要なんです。
具体的には、新たなものに対する吸収力とか、プロジェクトの背景を理解する力、ミーティングで相手の意図を汲み取る力。そして、そうしたInputを整理して自分の考えを構造的に伝える力。そういった情報を出し入れする能力が大事なんじゃないかと思います。
ロールモデルで言うと、大坂洋豊さんが本当にすごいです。学業・研究・インターンの“三足の草鞋”を履きながら、全部で結果を出しているんですよ。現在はプロジェクトオーナーとして6つの案件を率いながらも、研究では論文を査読通過に導き、学業も疎かにしない。それでいて人との交流も大切にしていて、週に3回はメンバーと飲みに行くというタフさ。「本当に同い年なのか?」って思うくらい、尊敬しています。
他にもすごい人はたくさんいて、同年代の中でトップオブトップが集まっている環境は、neoAIの大きな魅力だと思います。
――今後の展望を教えてください。
究極のジェネラリストになりたいです。AIエンジニアの能力には、AI技術、ソフトウェアエンジニアリング、コンサルティング、マネジメントなど様々な領域があると思うのですが、そのすべてにおいて一定以上のレベルに達し、「全部すごいじゃん、こいつ」と言われる存在になりたいです。
AIエンジニアとして一通りのコーディング力を身につけ、今では他の人が書いたコードをレビューするまで成長できました。ただ、ソフトウェアエンジニアほどの、設計思想を持ったエンジニアリング力が全般的に弱いと感じています。今はこの力を特に伸ばしたいと考えています。
まず個人的には、将来の選択肢を広げたいという思いがあります。正直、ある程度深くやってみないと、自分がその道に向いているかどうかって分からないじゃないですか。最近、プロダクト設計思想を求められるコーディングをしていて「これ楽しいな」と感じることが増えてきたんです。アーキテクチャや設計パターンを学んで、実際にコードに落とし込んでいく過程が面白くて。一度しっかりやってみて、将来的にソフトウェアエンジニアの道に進む可能性があるのか、自分に向いているのかを見極めたいんです。たとえその道に進まなかったとしても、AIエンジニアとして活動する上で、絶対的な強みになると思っています。少なくとも、その入り口に立てるレベルまでは到達したいですね。
会社的にもこういった人材って重宝されるんですよね。AIの実装はできてもコードの設計が作れない状態では、結局ボトルネックになってしまいます。僕が身につけることで、そのボトルネックを解消できる存在になりたいと考えています。
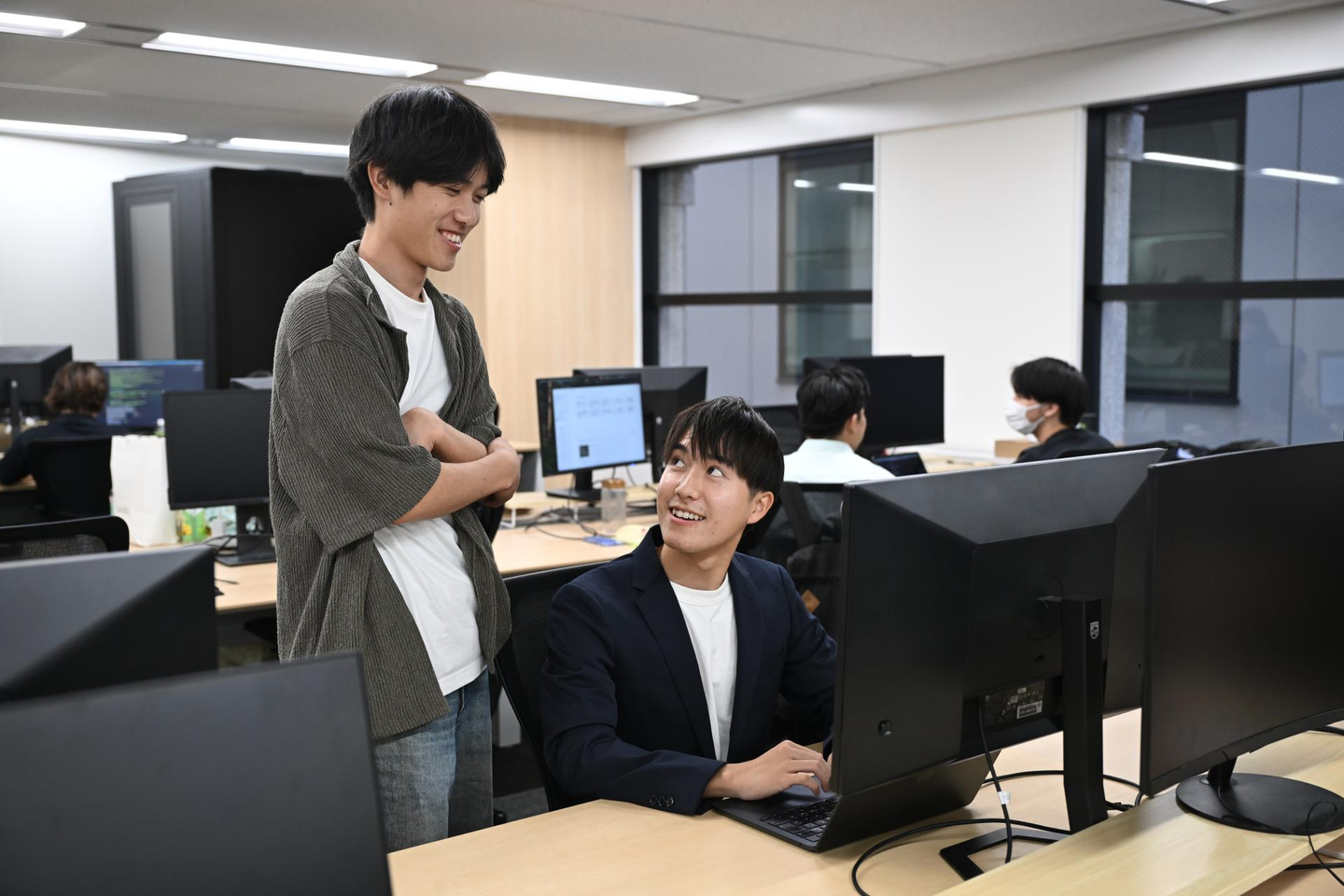
――AI業界で働く魅力について聞かせてください。
AI業界って今めちゃくちゃ熱いじゃないですか!毎週のように新しいモデルが出たり、アップデートが入ったり。まるで進撃の巨人の展開をリアルタイムで追っているみたいな、そのライブ感、ワクワク感がたまらないんです。
またneoAIのオフィスはワンフロアでCEOの千葉さんとの距離もかなり近いので、直接会社の成長や方向性についてのディスカッションが日頃からできるという特殊な環境です。「neoAIがどうあるべきか」「どんな社会にしたいか」っていう視座をもって働くのもなかなかない経験だと思っています。
――最後に読者に向けて一言お願いします。
将来やりたいことが見つからない人って多いと思います。僕もそうでした。
でも、とりあえずインターンに参加して、一生懸命取り組んでみるのは本当におすすめです。最初は「応募するの、ちょっと気が引けるな」と思うかもしれませんが、実際にやってみるとすごく楽しいですし、将来やりたいことの輪郭が少し見えてくる気がします。
neoAIには爆伸びできる環境があります。優秀な仲間に囲まれて、最先端の技術に触れながら、大きな裁量を持って仕事ができる。こんな環境で挑戦してみたいと思ったら、ぜひ飛び込んでみてください。きっと今の自分が想像もつかないくらい成長している自分の姿に出会えるはずです!
※1. 行動指針:メンバーが大切にしている「行動する上でのOS(=Operating System)」のこと。10個の項目からなる。


/assets/images/20374514/original/d1e525c3-e155-4c2a-ad81-433b096db315?1738997625)




