- フルスタックエンジニア
- 営業責任者
- エンジニアリングマネージャー
- Other occupations (2)
- Development
- Business
こんにちは、medimo採用担当です。
今回は、エンジニアの柳田さんに、これまでの経歴やストーリーについてインタビューを行いました。
ぜひ最後までお楽しみください!
ー まずは簡単に自己紹介をお願いします。
柳田:はじめまして、medimoでエンジニアをしています、柳田大我です。
慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、新卒でmedimoにジョインしました。
medimoではプロダクトマネージャーやエンジニア組織のマネジメント、また、開発そのものも担当しています。
エンジニアリングを始めたきっかけ
ー 柳田さんと言えば本当にコードを書くのが好きだとか。プログラミングとはいつ出会われたのですか?
柳田:プログラミングとの出会いは、小学3年生のときです。幼少期からものづくりが好きだった私を見て、母が近所にあったロボット教室に通わせてくれました。小学生の頃の僕は、いつも①ボールを投げるか②ロボットを作っているかのどちらかであった記憶があります。笑
その後、中学・高校ではロボット部に所属し、毎日ロボットに熱中し、作る日々を送りました。高校時代には、なんとロボットの世界大会の一部門で優勝することもできました。
高校で世界大会に優勝したことで、「ロボット作りはひと段落ついた」と感じ、大学では全く異なる分野に挑戦。経済学を専攻し、特にデータ分析に強い関心を持ちました。主に計量経済学を学びながら、データを片っ端から集め、可能な限りバイアスのない因果推論を追求する、そのような作業に魅了され、日々熱心に取り組んでいました。
一方で、経済学の勉強を進めながらも、「やはりコードを書くのが好きだ」と再認識するようになりました。そこで、リクルートやプレイドといった大企業やスタートアップでインターンを経験し、エンジニアリングを並行していました。
その中でアサインされたプロジェクトは複雑なシステムや最新技術が多く、学業との両立はなかなかキツイものでしたが、その経験を通じて自分自身が大きく鍛えられ、今に間違いなく生かされていると感じています。
株式会社medimoとの出会い
ーmedimoにはどのような形で参加することになったのですか?
柳田:もともと共同代表の中原くんとは知り合いで、彼とはこれまで一緒にいろいろな“ガラクタ”を作ってきました。そんな中、新しく会社を立ち上げて「medimo」というアプリを作るって話を聞いて、「それ面白そう!」と思い、参画することになりました。
特に印象に残っているのは、ニューログラフィーという脳波を使ったガラクタです。きっかけは、馬くんと中原くんが「NFTがすごい流行ってるらしい!これを脳波から作ったらめっちゃ面白くない?アートにしちゃう?」なんて盛り上がったことでした。そこからもう、どんどんすごい方向に進んでいきました。笑
毎週末に「撮影会」ならぬ「撮脳会」を開いて、いろんな人の脳波データを使ってNFTアートを作っていました。そのうち日本を飛び出して、有名人の脳波までデータを取るように……。あれはもうビジネスっていうより、ただただ面白い経験でした。笑
最終的には「とてもいいガラクタ」でしたね。笑
ー様々な選択があった中で、medimoに踏み切った理由は?
柳田:入社を決めた理由は、ただただ「楽しそうだったから」です。ピザパーティの最中に「medimoに入社しない?」と聞かれて、「うん、いいよ。」と返事を。「え、いいの?本当に?」って感じですよね。笑
それでも、自分の中ではもう答えが出ていました。
スタートアップと大企業を比べたとき、どっちが成長できるかを考えてみたら、間違いなくスタートアップだろうと思ったんです。大企業って、基本的に縦割りで役割がはっきりしていて、やるべき作業や仕事内容がほぼ決まっています。一方で、スタートアップはみんなが「これをやらなきゃ」「あれをどうする?」という感じで、毎日試行錯誤の連続です。
しかも裁量権が大きいので、自分の行動次第で会社全体が大きく動く。そんな環境に飛び込めば、10年スパンで見たときに絶対に成長できるだろうと思いました。
だから、「いいよ。」と答えた自分の選択に、今も満足しています。
音声認識カルテ作成アプリ「medimo」開発の面白さ
ー開発をしていて、柳田さんが楽しいなと思う瞬間はどんな時ですか?
柳田:やはり自分は根っからのエンジニアなので、難しい実装に挑戦して、それが思った通りに動いたときは、本当にたまらなく嬉しいです。medimoのエンジニアとして一番挑戦的だったのは、書き起こしの機能をすべて自社で実装したことだと思います。
medimoの顧客は主に病院やクリニックですが、医療機関ってネットワーク環境があまり良くないことが多いんです。しかも、扱う情報は超重要で、データが流出したり消失したりするなんて絶対に許されない。そんな制約の中で、ウェブアプリとしてどう実現するかを考えるのは、まさにエンジニアの腕が試される部分でした。技術的に面白いだけじゃなくて、色々と考えさせられる部分も多かったですね。
ーでは、柳田さんが思う、大企業では経験できないけれどmedimoだからこそ経験できることとは何でしょうか?
柳田:自分が今の環境で魅力的だと感じるポイントは、大きく2つあります。
1つ目は、上流から携われることです。medimoのようなスタートアップでは、プロダクトの方向性がまだ固まりきっておらず、「どの道を選ぶか」「何を優先するか」といった決断に関わることができます。完成された状態ではないからこそ、このステージでしか得られない貴重な経験ができると思っています。
2つ目は、LLM(大規模言語モデル)まわりに触れられることです。次の時代の大きなトレンドを実際に経験しながら学べるのは、本当に魅力的だと感じます。とはいえ、まだまだ未知の領域なので、僕たちも手探り状態で試行錯誤しながら進めているところです。
それでも、エンジニアリングの力を活かして少しずつ新しいことを試していけるプロセスがとても楽しいですね。
ーmedimoというアプリケーションの開発の面白さとは?
柳田:medimoは見た目はシンプルなアプリに見えるかもしれません。でも実際に開発に関わると、かなり複雑なんです。その「複雑さ」というのは、要件が難しいだけじゃなく、それをどう解決するかという手段自体も複雑になりがちなところにあります。たとえば、挑戦的な技術スタックを採用していたり、ブラウザ特有のややこしい部分に手を入れる必要があったりと、ストレートにはいかないことが多いです。
さらに、medimoは録音がメインなので扱うデータ量が大きくなりがちです。ネットワークの環境が弱い環境でどうやってスムーズに動かすか、常に工夫が求められます。
また、文字を転送するハードウェアとの連携が必要だったり、アプリケーション開発だけじゃなくAI開発も含まれていたりと、様々な領域をまたいで取り組む必要があります。こうした「簡単にはいかない」部分が多いからこそ、エンジニアとして挑戦しがいがあり、開発していて楽しいと感じます。
開発チームについて
ーどのようなチームで開発をおこなっているのですか?
柳田:一言で言えば「自分の考えをしっかり持った人が多いチーム」です。一つの機能を作るときでも、まずは丁寧にドキュメントを作り込みます。そして、それをもとにお互いにレビューを行い、鋭いフィードバックを出し合いながらディスカッションを繰り返して、改善を重ねていく形です。こうしたプロセスを通じて、より良いものを作ることに全員が真剣に向き合っている、レベルの高いチームだと思います。
最近はバグの修正やリファクタリングが多かったのですが、今後は新機能の開発がメインになっていくと思います。ユーザーも増え、要望も多くなり、それに合わせた新機能をどんどん実装し、より付加価値のあるアプリにしていきたいです。
ー使用している技術スタックについて教えてください。
開発で使用している技術スタックについてですが、以下のような構成になっています。
- フロントエンド:React
- バックエンド:FastAPI
- インフラ:AWSをTerraformで管理
meidmoへの入社を考えている人へ
ーどのような人と一緒に働きたいですか?
柳田:まずは、自分の考えを持ち、責任感がある人、そしてエンジニアリングに関するディスカッションを楽しめる人です。です。一つの機能を作る上でアプローチの方法はいくつかあるのではないかと思います。
自分はこれがいいと思っていても、例えば人に流されて「あれ、自分のアイデアのほうがよかったじゃん」となりかねないのがエンジニアリング。自分の考えをしっかりと持ち、かつ、仲間の考えに耳を方向け、話し合いを楽しめることが重要なのではないかと考えています。
まさに今、非常に楽しいタイミングだと思います。
ー今、medimoを考えてくださっている方へ一言お願いします。
新しい技術やレベルの高いメンバーと働きたい方はぜひ、medimoへ来てください。
/assets/images/21567635/original/da0223bc-1302-4b26-909a-36d4f9d5101b?1752217294)

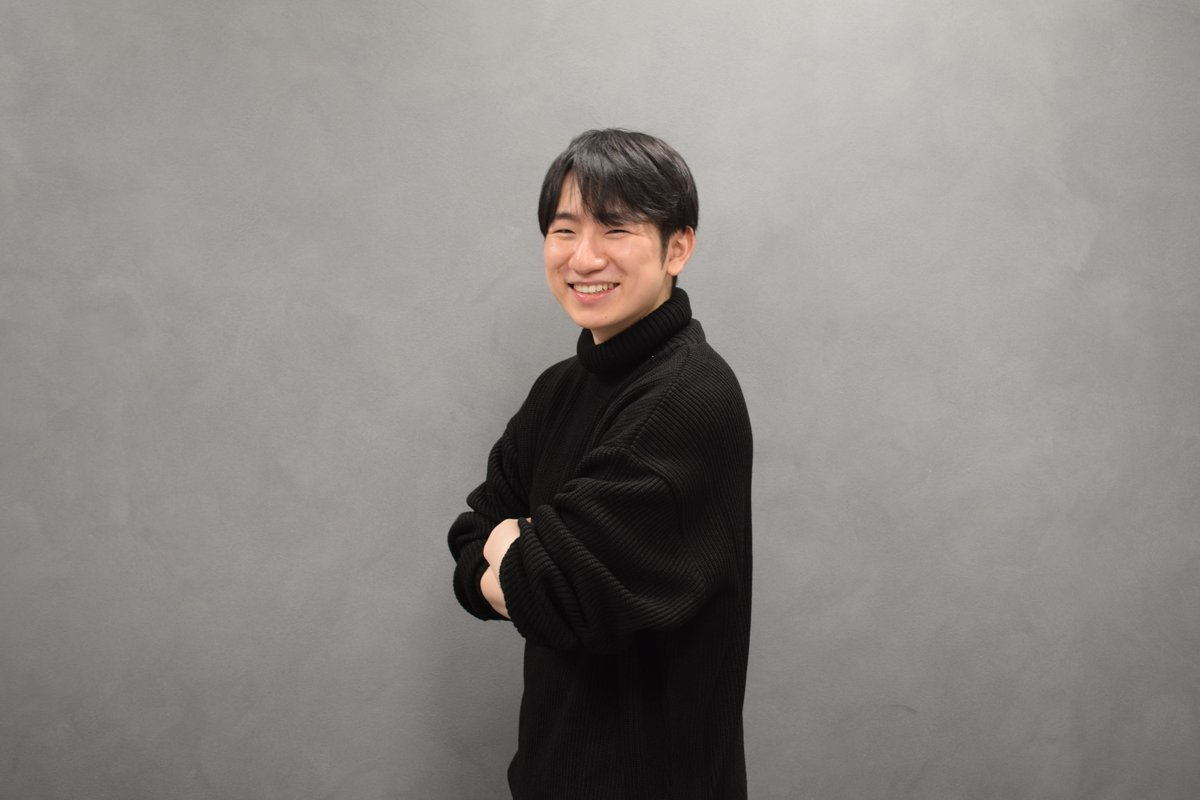




/assets/images/21543675/original/b9fa3666-42b5-4047-9645-80fa9c96da40?1752031643)
/assets/images/21543675/original/b9fa3666-42b5-4047-9645-80fa9c96da40?1752031643)

